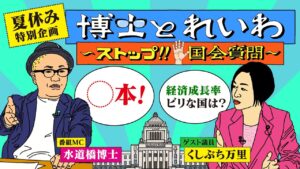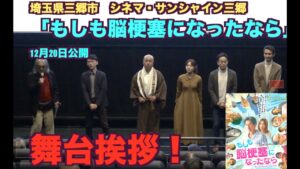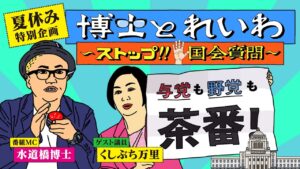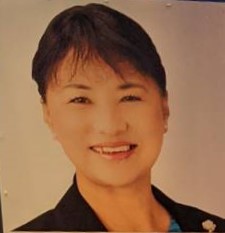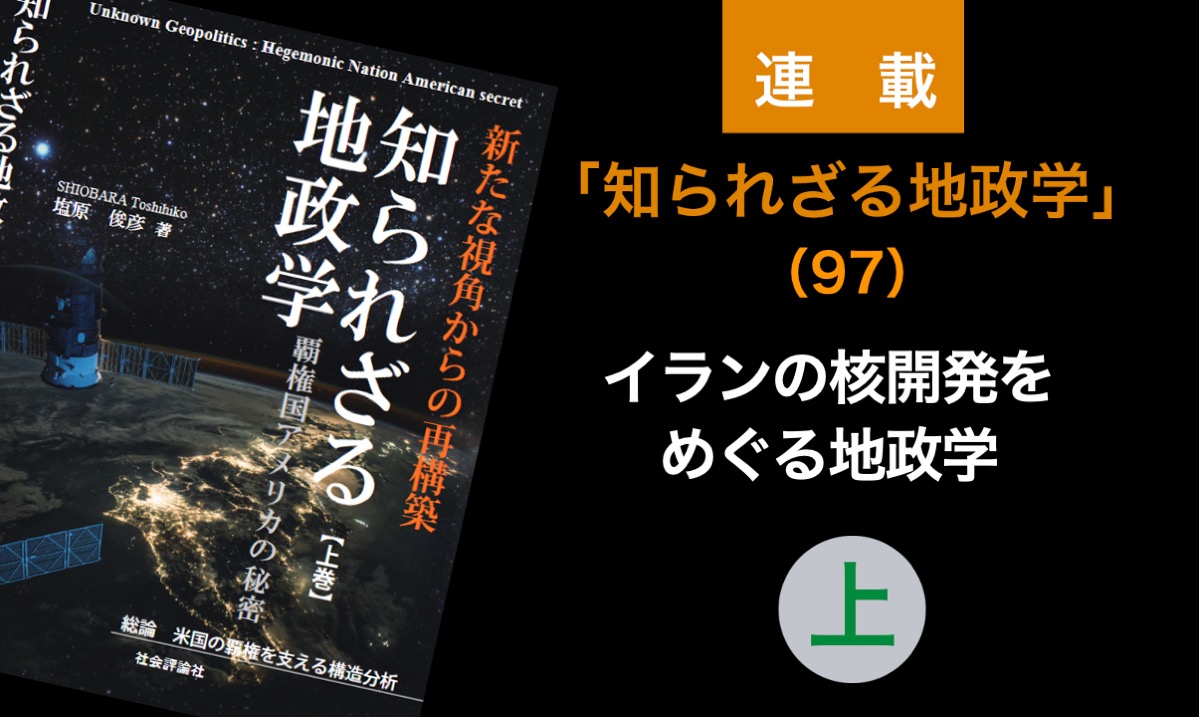
「知られざる地政学」連載(97):イランの核開発をめぐる地政学(上)
国際
エネルギーは地政学・地経学上の大問題である。ゆえに、1年ほど前に、本連載(39)「ウランをめぐる地政学」(上、下)において、核発電や核兵器にかかわるウランについて考察した。2023年4月には、拙稿「ロシアの核エネルギー産業と制裁:地政学上の意味」もこのサイトで公開した。核開発は核発電と核兵器開発の二つにかかわっているために、エネルギー関連分野でもっとも重要な論点を提供する。そこで、今回は、イランにおける核開発の歴史を紹介し、この国の長い苦悩について考察したい。これを読めば、中東地域における地政学上の駆け引きが長くつづいてきた歴史がわかるだろう。
核エネルギーをめぐる基礎知識
核エネルギーは「分裂」(fission)または「融合」(fusion)によって生まれる。分裂型核エネルギーは核爆弾となり、その分裂をゆっくりと制御することで核発電を可能とした。核融合については、いわゆる水素爆弾として実用化されたが、核融合型発電については、いまなお実現できていない(最新の状況を知りたければ、2025年6月23日付の「ワシントンポスト」の記事「核融合発電はまだだれも実現できていない。 なぜ大企業は何十億ドルも投資するのか?」が役に立つだろう)。
イランの核開発問題を考察する際に必要なのは、核発電による利用と、核爆弾の開発という二つである。前者については、覇権国アメリカが核発電技術を世界に輸出しようとしてきた以上、反対する国家はなかったし、いまでも基本的に変わっていない。後者については、1968年7月1日に署名開放され、1970年3月5日に発効した核兵器不拡散条約(NPT)のもとで、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国である、米、ロ、英、仏、中の5カ国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止してきた。ゆえに、NPT体制下にあるイランが秘密裏に核兵器開発に取り組めば、大きな問題となる。
ここで重要なのは、一般に、ウラン235の含有率は天然ウラン鉱石で0.3~0.4%程度、核発電用低濃縮ウランになると、4~5%、核爆弾向けには、90%以上の高濃縮ウランが必要とされていることである。つまり、核発電所で利用される低濃縮ウランをさらに高濃度に濃縮すれば核爆弾を製造できる。これは、little boyとして知られる広島に投下された「原子爆弾」と同じ型ということになる。
核発電所の原子炉の運転中にU-238が中性子を吸収すると、核分裂性物質であるプルトニウム239(Pu-239)に変化することも重要だ。炉心での核分裂反応の自然な副産物としてプルトニウムができてしまうのである。つまり、プルトニウム型核兵器が製造可能となる。長崎に投下されたfat manというニックネームの原爆はプルトニウム型であった。
この二つの理由から、核発電所の利用は核兵器開発につながりかねないと懸念される。だからこそ、イランの核開発問題は複雑な様相を呈していると考えられる。
イランの核開発の歴史
拙著『知られざる地政学』〈上〉の99~100頁において、 ドワイト・アイゼンハワー大統領が1954 年8 月、原子力法に署名し、米国企業が外国に核発電所を輸出する条件が整備された歴史について紹介したことがある。これは、潜水艦の原子力推進システムで培った技術をベースに、本格的な核発電所時代が到来することを意味していた。
アイゼンハワーは、「アトムズ・フォー・ピース」(平和のための原子)構想を通じて、核科学の平和的探求に取り組むよう各国に働きかけたのである。その結果、イランは1957年、アイゼンハワー政権と初めて民間核協力協定を結んだ。
1967年には、米国の援助を受けて、イランはテヘランに現在も存在する小型の研究用原子炉(テヘラン原子力研究センター)を建設した。米国はこのセンターに、GAテクノロジーズ社製の最初の5MW原子炉と、約6kgのウラン、112gのプルトニウムを供給した。その1年後、イランは核拡散防止条約(NPT)に調印する。これにより、イランは核兵器開発を自主的に自制した。
NYTによれば、西側諸国の仲間入りを望んだモハンマド・レザー・シャー・パフラヴィー国王は、1973年の石油ショックによって潤沢な資金を得て、イランの民生用核プログラムの急速な拡大を選択する。イラン人学生数十人をマサチューセッツ工科大学に送り込み、核エンジニアリングを学ばせた。1974年には、イランは国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置協定に調印し、平和的原子のみに関与することを再確認した。同年、テヘランは初めて原子力開発計画を発表する。それによると、イランは合計約20GWの原子炉を22基建設する計画であった。
ロシアの情報によると、1974年、イランはトリカスタン(フランス)にあるウラン濃縮工場の株式10%を10億ドルで購入した。この工場は国際コンソーシアム「ユーロディフ」が所有していた。ドイツのクラフトワーク・ユニオン社とフランスのフラマトーム社の専門家が、最初の発電ユニットに取り組んだ。米国はイランに6~8基、ドイツは4基程度、フランスは約8基の原子炉を建設する計画だった。
イラン革命
1979年、イランでは国王(シャー)の政権が打倒されるイラン革命が起きる。その結果、イランから欧米の物理学者や技術者が去り、核開発計画は中断された。1975年にドイツの企業によってイラン南部に建設が開始されたブシェール核発電所の工事はすでに約85%完了していたが、革命後、プロジェクトは中断され、未完成のままとなる。
1992年になって、イランはロシアと建設再開に関する協定を締結する。2011年9月、ブシェール核発電所の1号機が送電を開始した(図1を参照)。2014年11月、両国は、ロシア加圧水型(VVER-1000型)原子炉を備えた2号機と3号機の建設に関する新たな契約を締結した。

図1 米国が攻撃した核施設(赤丸で囲まれた部分、上からフォルドゥ、ナタンズ、イスファハン)および核発電所( 、上から建設中の原子炉があるアラク、ロシアとの契約に基づいて建設された核発電所のあるブシェール)の場所
(出所)https://www.kommersant.ru/doc/7831991
イラン・イラク戦争
他方で、1980年代、イランはパキスタンと中国からの技術援助を受けて、核開発計画を再開する。これは、1980年から1988年にかけてのイラン・イラク戦争の途上での複雑な国際関係や宗教関係のもたらしたものだった。そこで、普段は語られることの少ないイラン・イラク戦争について概説しておこう。1932年にイラクがイギリスから独立して以来、イラクとイランとの関係は複雑化する。シャットアルアラブ川(ティグリス川とユーフラテス川がクルナal-Qurnaで合流してからペルシア湾にいたるまでの185kmの川の名)がその理由の一つだ。この川は、バスラから数km下流の地点からイラン・イラク国境線と重なるが、1937年の条約で従来の協定が変更されて国境線が川の中央線から東岸に移されたため,これが両国の紛争のたねとなったのである。これは、イラクがシャットアルアラブ川を完全に支配することを意味していた。
1970年代になると、イランはイラク領内でクルド人の反乱を組織し、隣国を弱体化させようとし、最終的には1975年のアルジェ協定が結ばれる。このアルジェ協定により、イラク北部のクルド族の反乱に対するイランの支援停止と交換に国境線は再び中央線に戻される。
1979年1月から2月に、イランの大混乱、すなわち、イスラム革命による国王モハンマド・レザー・パフラヴィーの打倒、ホメイニ師による政権奪取が起きる。当時のイラクの大統領兼首相、アフマド・ハサン・アル=バクルはホメイニ政権を歓迎したが、イスラム革命の「輸出」をめざす一部は、イラクのクルド人への支援を再開し、イラクのシーア派をバグダッドの政府に敵対させようとした。これに対して、アル=バクルはバランスを保とうとしたが、やがて権力闘争に自ら敗れ、1979年7月16日、当時、治安機関のトップであったサダム・フセインにすべてのポストを譲ることを余儀なくされるのである。
他方、イランでは、「輸出」支持派がついに優勢となり、イラク、サウジアラビア、バーレーン、クウェートで反政府グループを率いる特別組織「イスラム革命最高評議会」を設立する。厄介だったのは、米ソ対立の時代にあって、ソ連は長くイラクの「社会主義」当局と友好関係にある一方、米国はイラン国王を支持していたことである。
パフラヴィー国王政権が崩壊したことで、新しいイラン・イスラム政権に近づいたのは、フセインをアラブ世界のライバルとみなしていたシリアのハーフィズ・アル=アサド、リビアのムアンマル・アル=カッザーフィー(カダフィ)だけであった。当時、中国もソ連に支援されたイラクを嫌っていた。
1980年になって、親イラン派がサダムの関係者を狙った暗殺未遂事件を数回起こす。これを受けて10万人のペルシア人がイラクから追放された。同時に、小さな紛争もはじまる。イランのイスラム主義者が1980年前半に200回以上イラク国境を侵犯したのだ。7月には、旧国王側近の軍部がホメイニ打倒を企てたが、失敗に終わる。イラクは、この騒乱の組織には関与しなかったものの、その勝利に貢献しようとした。そうしたなかで、9月17日、サダムはテレビの生中継でアルジェ協定を破棄し、その無効を宣言した。その5日後、イラク軍はイランへの攻撃を開始した。
しかし1980年、イランは断固として立ち向かい、領土の大きな損失を許さず、ホメイニは外部からの侵略に反対するというテーマで権力を強力に強化した。しかもイランはすぐに反攻に転じ、いくつかの領土を解放する。だが、イラクとイランは勝利を望みながら、何年もの間、和平に合意することができなかった。そして、1988年になって、ようやく相手が疲れ果てたときに初めて休戦協定が結ばれた。戦争は開戦時とほぼ同じ国境線で終結したのである。
レーガン政権下で起きたこと
1981年1月20日、米国のロナルド・レーガン新大統領の就任式が行われた。同日、イランのイスラム主義者はテヘランの米国大使館を出て、人質を全員解放する。これに対して、ホワイトハウスの新政権は政策を180度転換し、イランへの軍事支援を開始する。それは、ソ連に近いイラクにイランを対抗させて、ソ連の同盟国の弱体化をねらったものだった。
この米国の大転換は、イスラエルの立場を変えさせる。同年6月7日、米国のF15とF16で構成されたイスラエル空軍は、イラクの原子炉(オシラク)を空爆する。その1カ月後、イスラエルがイランに武器と予備部品を送っていることが世界に知れ渡る。 7月18日、イスラエルの輸送機がソ連領内に飛来し、撃墜される。
1982年4月8日、イランの要請を受けたシリアのアサド大統領は、イラクの主要輸出幹線である「キルクーク-バニヤース」間の石油パイプラインの閉鎖を発表する。これはイラク経済に大きな打撃を与えたが、わずか3年後、サウジアラビアの助けによって、この国への石油パイプラインの建設が共同で行われ、イラクからの石油輸出の仲介役となる。
それでも、2~3年の間、イラクは脆弱になる。イラクに残されたのは、占領した領土のわずか10%程度だった。ただし、イランも苦境に立たされていた。1981年、イランの大統領と首相、その他数十人の高官が一連のテロ攻撃で殺害されたからである。
1982年6月6日、イスラエルはレバノンに侵攻する。この状況に乗じて、サダムは停戦を宣言し、自らを侵略者と認め、イランの全領土から軍隊を撤退させ、レバノン人を助けるために派遣する用意があると宣言した。その主張を裏づけるように、バグダッドは6月20日、シャットアルアラブ川を支配するために必要なわずかな地域を除いて、占領した土地のほとんどを更地にした。サウジアラビアも仲介に乗り出す。しかし、ホメイニは拒否し、激怒したサウジアラビアのファハド国王は、米国製精密ミサイルの膨大な備蓄をイラクに移送するよう命じる。イラクはそれを使ってペルシア湾でイランの石油を積んだタンカーを砲撃する。
米国とイスラエル、イランと決別
イランのイスラム原理主義者の姿勢に対して、1983年初頭、米国とイスラエルはイランへの武器と予備部品の供給を停止するようになる。さらに、その数カ月後には米国はイラクとの秘密交渉を開始する。その結果、1967年の6日間戦争以来なかった在イラク米国大使館が1984年に開設される。 イラクへの武器供給も再開される。
このような状況下で、イランが戦争に勝利する見込みはなくなった。1983年の攻撃はごく限られた成功に終わり、1984年にはすべての試みが失敗に終わる。 1984年晩春までに戦線は安定し、両軍は消耗戦、つまり敵の都市を爆撃する作戦に切り替えた。この戦争でも、イラクはソ連から航空機と予備部品の両方を調達し、優位に立った。イランは、少なくとも部分的に自国の空軍を戦闘可能な状態に保つため、軍備の「闇市場」に参入しなければならなくなる。
ニカラグアの反政府武装組織「コントラ」
レーガンの2期目の1986年は、国家安全保障担当補佐官ジョン・ポインデクスターがレバノンの米国人人質と引き換えにイランに武器を密かに売却し、その代金をニカラグアの反共ゲリラに違法に流していたというスキャンダルに明け暮れた(なお、この時、米国のイランとコントラの双方の交渉窓口は、レーガン政権において副大統領だったジョージ・H・W・ブッシュ[父ブッシュ]であった)。これは、CIAがホワイトハウスの指示を受けながら、秘密裏にイランに武器を売り(公式にはイラクに売り)、その代金をニカラグアのゲリラ(「コントラ」)に送っていたものだ。米国人の人質をとった、イランからの支援を受けているレバノンのヒズボラの言いなりになりながら、反共ゲリラ、コントラを支援するという、さまざまな意味で、不誠実かつ国民を欺く取引であった。
この年2月、イラン軍は戦略的に重要なイラクのファオ半島を占領し、バスラからの海路をすべて封鎖したことが一度だけあった。1986年末、イラン軍はバスラへの総攻撃を試み、包囲さえしたが、イラクは化学兵器を使用し、最終的に敵を撤退させた。
こうした事態を重くみた米ソはホメイニに圧力をかける一方で、イラクへの武器供給を増やす。1988年4月、イラク軍の奇襲攻撃などから、イランは同半島から撤退せざるを得なくなる。これは1987年に対イラク包囲網が強まった結果であった。1985年のミハイル・ゴルバチョフ政権誕生後、1986年に中ソ関係が改善しはじめる。それに気づいたイラクが米国に接近するようになる。こうして、イランへの風当たりが強まり、1987年9月21日、アメリカ軍はバーレーン沖で機雷を敷設していたイラン船を攻撃し、拿捕、撃沈した。数日後、イスラム革命防衛隊(IRGC)の部隊が英国のタンカーを攻撃し、英国は自国のイラン大使館を閉鎖して対応した。10月19日、米海軍はイランの石油基地を砲撃した。
「知られざる地政学」連載(97):イランの核開発をめぐる地政学(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)