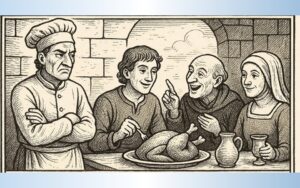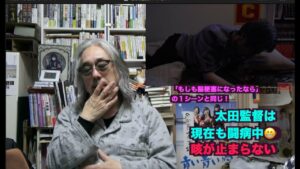7月5日のウクライナ情報
国際7月5日のウクライナ情報
安斎育
❶【米国がウクライナ向けの武器供与を停止、米国の利益を最優先】(内容既報、2025年7月2日)
米国は精密ミサイルの在庫が減少していることから、予定していたウクライナ向けの供与を停止した。NBCが国防総省と議会関係者の証言を引用して報じた。
具体的にはパトリオット用迎撃ミサイル数十発、155ミリ榴弾数千発、ヘルファイア・ミサイル100発超、精密誘導弾250発超、地対空ミサイル「スティンガー」数十発、空対空ミサイルAIM、グレネードランチャー数十発となっている。
ホワイトハウスの報道官によると、「米国の利益を優先するため」ウクライナ向けの武器供与を停止したという。
https://x.com/sputnik_jp/status/1940216585224151380
❷「そばに離れない人がいてくれることが重要だ」:地域の子どもの権利擁護官が家族を支援する方法(2025年7月2日)
プスコフ州で、障害のある子どもの母親は3年間、療養所への入所許可を待っていました。女性は地域の子どもの権利擁護官ナタリア・ソコロワに相談しました。
「市内の小児クリニックと州立精神科・薬物依存症治療センターの医師たちと一緒に、書類を適切に集めて作成することができた。そして、その家族はついに海辺で休暇を過ごすことができた」とナタリア・ヴィクトロヴナは語る。
ブリャンスク州の児童権利担当官、インナ・ムヒナ氏は、「親の居間」の後で起こった出来事に感動しました。
「ある少年が、会合の後で私に電話をしてきました。その日、彼は母親に近づき、「愛してる」と言ったのです。母親は驚いて、「大学を退学になるの?少年は笑いながら答えました:『大丈夫だよ。ただ、ずっと言っていなかっただけさ』このような小さな変化でも、関係に大きな価値をもたらすのです!」と、インナ・ニコラエヴナは語ります。
カルーザ州の児童権利担当官イリーナ・アゲエワは、特別教育施設を訪れた少年たちの変化に感動しました。
「彼ら一人ひとりに複雑な過去があります。しかし、1年前は全く違う少年たちでした。今では家族について語り、将来の計画を立て、学業やスポーツでの成果を共有し、メダルまで見せ合っています。こんなに変わった少年たちを見るのは本当に嬉しく思います!」とイリーナ・アナトリーエヴナは述べています。
ザポリージャ州の子供人権擁護官ユリア・サジャエワは、困難な状況で支援した8人の子供の母親について温かく語ります。2023年、女性は親権を制限されました。彼女は12回の裁判を経て諦めず、最終的に子供たちを取り戻すことができました。
「家族全員がようやく家に帰ってきた時、母親は私に、私たちが彼女を信じていたからこそ耐え抜くことができたと語りました。そばに、決して見捨てない人がいることが重要です」とユリア・ニコラエヴナは結論付けました。
ロシア連邦大統領府子ども権利担当特使。マリア・リボワ・ベロワ
リンクはこちら
❸ ウクライナ問題は二の次、戦禍拡大でも西側の一部で優先順位低下(2025年7月3日)
(ブルームバーグ): ロシアの全面侵攻から4年目の夏を迎えるウクライナは、激しさを増すミサイルやドローンの攻撃に苦しんでいる。だが、支援国の一部は関心を別の問題へと向けている。
米国のトランプ政権はウクライナへの砲弾や防空システムの供与を停止した。備蓄状況を確認した結果だとし、米国が重要な支援を継続するとの期待を打ち砕いた。
フランスではマクロン大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談を行い、他の欧州首脳を困惑させた。主な議題はイランだったとしているが、ロシアを孤立させる団結した取り組みを二の次とし、他の地政学的な問題を優先させたことは明らかだ。
戦争終結を目指したトランプ氏の外交攻勢は不発に終わり、ウクライナ問題への米国の関与低下は著しい。米上院はロシアに対して強硬姿勢を維持しているものの、「骨の髄まで砕くほどの制裁」が成立する見込みは立っていない。
今年に入りロシアはウクライナに対する空襲を大幅に強化し、大量のドローンとミサイルでインフラや住宅を破壊している。ウクライナ防空部隊によると、6月29日の攻撃だけで537のドローンと弾道・巡航ミサイルが使われた。
国連が1日公表した報告書によると、今年1-5月に戦争被害で死亡したウクライナの民間人は約1000人に上り、前年同月に比べ37%増加した。
不意打ち
米国の兵器供与停止に、ウクライナ当局者は詳細確認と影響把握を急いでいる。トランプ氏は先週、ハーグで行われた北大西洋条約機構(NATO)首脳会議に合わせたウクライナのゼレンスキー大統領との会談を「良かった」とし、ウクライナへの地対空ミサイルシステム「パトリオット」の追加供給を検討すると述べたばかりだった。
ウクライナ国防省は2日、米国から供与停止に関する公式な通知は受けておらず、納入予定にも変更は見られないと発表した。同国外務省は同日、駐キーウ米国大使館の臨時代理大使ジョン・ギンケル氏を招き、同日中に協力について協議したと明らかにした。
「ウクライナの防衛能力支援におけるいかなる遅延やちゅうちょも、侵略者の戦争とテロ継続を後押しするだけで、平和を導くことはない」と、外務省は声明で主張した。
NATO首脳会議でのトランプ氏の発言を聞いていただけに、米国の供与停止の決定に欧州首脳は不意を突かれたと、当局者は述べた。欧州首脳は細る米国の支援を補う計画を進めているところだという。当局者は非公表の協議内容だとして、匿名を要請した。
当局者によると、欧州の同盟国はホワイトハウスに決定の詳細な説明を求めており、決定が緩和される、あるいは一部撤回される可能性に期待を持つ向きもいる。
電話外交
欧州連合(EU)の有志国は年内にウクライナに弾薬200万発を提供すると約束するなど支援を強化しているが、その取り組みは十分速いとは言えないと、ウクライナのポドリャク大統領顧問は指摘。同氏はウクライナの放送局に対し、欧州の軍用品生産拡大は「遅い」と語った。
マクロン氏とプーチン氏の電話会談も、意識の低下を印象づけた。両者の電話会談は2022年以来で、フランス側が申し入れた。
フランスの働きかけはイランの核開発を巡る危険が強まる中で、西側首脳の中でトランプ氏だけがプーチン氏に接触する状況を避けるために行われたものだと、マクロン氏の意向に詳しい当局者は説明した。
マクロン氏は、イラン問題について国連安全保障理事会の常任理事国5カ国共通のアプローチを構築しようとする自身の取り組みについて、欧州各国の首脳およびゼレンスキー氏にも説明したと、電話会談の内容に詳しい関係者は語った。フランスがウクライナ防衛支援を続けていくことも、ウクライナ側に伝えたという。
当局者によると、それでも欧州首脳の間でロシアとの対話ルートを開くことの有用性は疑われている。
一方、この電話会談は勝利としてモスクワでは受け止められている。モスクワを拠点とする中東問題専門家エレナ・スポニナ氏は、「欧州主導の動き」だと評価し、米国の兵器供与停止と重なったのは「偶然ではない」との見方を示した。
原題:Key Ukrainian Allies Are Shifting Focus to Other Priorities(抜粋)
–取材協力:Henry Meyer、Arne Delfs、Alberto Nardelli、Aliaksandr Kudrytski、Olesia Safronova、Daryna Krasnolutska、Ania Nussbaum. (c)2025 Bloomberg L.P.
リンクはこちら
❹ウクライナ・中東・アメリカ…「リベラルな国際秩序」の危機と再構築をめぐる対話(Newsweek, 2025年7月2日)
<3年間で大きく変わった世界各地の情勢、そして今後の国際秩序の行方について。『アステイオン』102号──「自由主義国際秩序の再建と日本の役割」より3回に分けて転載。本編は前編>【池内 恵+廣瀬陽子+森 聡+北岡伸一】
2021年から2024年9月まで行われた「自由主義国際秩序の再建と日本の役割」研究会を振り返り、メンバーの廣瀬陽子・慶應義塾大学総合政策学部教授と森聡・慶應義塾大学法学部教授、ゲストの池内恵・東京大学先端科学技術研究センター教授に本研究会主査の北岡伸一・国際協力機構顧問が聞く(座談会開催は本年1月19日)。
◇ ◇ ◇
【北岡】 戦後維持されてきた自由主義的な国際秩序が危機に瀕しています。この研究会を立ち上げたのは2021年11月でしたが、同年2月にはミャンマーのクーデター、8月にはアフガニスタンの崩壊があり、翌2022年2月にはロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。
こうした状況において、自由主義国際秩序を再建、あるいは維持できる方法はあるのか、というのがこの研究会の課題でした。まずはこの間の主な出来事を、その節目に着目しながら振り返っていきたいと思います。はじめにウクライナについて、廣瀬先生、いかがでしょうか。
■ウクライナ情勢
【廣瀬】 世界にとって、2つの驚きがあったと思います。1つは、言うまでもなくロシアが侵攻したという事実です。2つ目は、ウクライナがあれほどまでに勇敢に戦ってきたということです。
ロシアの侵攻開始直後には、戦争はすぐ終わるだろうと考える向きが多かったのですが、ウクライナが一国で怯まずに戦ったこと、またウクライナのこの戦争は民主主義を守る戦いだという主張も多くの人々の心を掴み、侵攻開始3カ月くらいから、欧米も熱心にウクライナに対して軍事支援を行うようになりました。
最初は重火器の差などから、ロシアがかなり優勢でしたが、2022年9月頃からウクライナの反転攻勢が始まりました。そこでロシアは「部分的動員令」を出したものの、国内で相当の反発を生み、多くの若者が国外流出したことから、動員の難しさを認識しました。その後は、戦いが泥沼化していきます。
なかでもドイツが「レオパルト2(戦車)」の供与を決めた2023年1月は1つの節目といえます。ドイツが戦車を出さないとヨーロッパ諸国も出せないというところで、ドイツが供与を決め、多数の戦車をウクライナが受け取れるようになりました。それでも戦闘はだらだらと続いていくことになるのですが……。
同年8月以降の戦闘機の供与決定も大きな節目といえますが、パイロットの訓練が容易ではなく、また戦闘機の機数もまだまだ少ないことから、戦況にはあまり影響が出ていないといって良いでしょう。
【北岡】一時期、ウクライナの反転攻勢といわれましたが、結局あまりうまくいきませんでした。その後、昨年2024年8月には、ウクライナは国境を越え、ロシア西部の都市クルスクで攻撃を始めます。一方ロシアは、北朝鮮の兵隊まで使うようになりました。
【廣瀬】ウクライナの反転攻勢がうまくいかず、ロシアは攻勢を強めようとしていました。そんな中でウクライナがクルスクに奇襲攻撃を行ったことで、ロシアも世界も非常に驚きました。
ロシアはウクライナ東部での戦いを優先し、クルスクの軍備はかなり手薄になっていたのですが、何の対処もしないわけにもいかない。そのため訓練が不十分な徴兵者などを含む部隊が送られましたが、依然、苦境に陥っていたところに追加増員されたのが北朝鮮兵です。
2024年6月のプーチン訪朝時の「包括的戦略パートナーシップ条約」によって、堂々と参戦による協力も得られるようになったわけです。
もう少し具体的にお話しすると、部分的動員令も不評で兵員確保に苦悩しているロシアは、地方の少数民族や囚人を動員したものの、それでも十分な数には及びませんでした。そこでロシアが目をつけたのが外国兵(*)です。
キューバやシリア、ネパール、アフリカ諸国や中央アジア諸国の人々が、特に多く使われたと言われています。
しかしながら、当然ですが、今日の国際秩序の下において外国兵を使うと、必ずその国の政府と問題になるわけです。でも、ロシアもどうにか兵員を確保しなければならない。そこで生まれたのが、北朝鮮との包括的戦略パートナーシップ条約になります。
【北岡】 なるほど。また、ウクライナでは政治的腐敗が一部で言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか。
【廣瀬】 今も非常に腐敗しているようです。前線に送られた兵器や支援物資は、途中でかなり抜かれているようで、事前に送られてくるリストの中身と異なり、政府の高官が相当私腹を肥やしていると現地の方から聞きました。
ウクライナの一般の方から度々聞いた「誰のための戦争なのか」という声はとても重く響きました。
【北岡】 政府を引き締めなければ、外からの援助が得られないわけですから、これはゼレンスキー政権にとってはかなり痛いですよね。どのような手を打っているのでしょうか。
【廣瀬】 腐敗を防がなければならないことはゼレンスキー大統領もわかっているので、閣僚の左遷などを度々行っています。ただ、あくまでもそれは氷山の一角に手をつけているに過ぎないというのが実情です。
【北岡】 それは厳しい状況ですね。では、次に池内先生から特にイスラエルとパレスチナの話を中心に中東問題を振り返っていただけますか。
■中東情勢
【池内】 自由主義国際秩序の揺らぎという文脈の中で画期となる日をいくつか挙げるとすると、例えば、アブラハム合意が発表された2020年8月13日、そしてイスラエル・ガザ紛争が勃発した2023年10月7日、さらには、シリアのアサド政権が崩壊した2024年12月8日になります。
これまで中東には、3つのトレンドがありました。
1つ目は、かなり長期的なもので、非国家主体が強力で、主権国家を内側から揺るがすような動きがあることです。2つ目は地域の中でいくつかの有力な国々、地域大国が台頭していること。そして3つ目がアメリカの覇権です。中東においてアメリカが圧倒的な軍事力によって覇権を確立し、それを背景とした政治力を行使して秩序を形成してきました。
その3つ目が揺らいでいます。アメリカの軍事力は依然として圧倒的に大きいにしても、それを背景にした政治力を世界の各地域で行使する意思や、その持続性・安定性に対して、行使を受ける地域の側から疑いの目が向けられています。
この疑念が顕著に現れることになったのが、2024年の多くの期間にわたって、アメリカがレームダックに陥っていると広く認識された事象です。
【北岡】 そのアメリカのレームダックというのは、中東、とりわけイスラエルをコントロールする能力におけるレームダックということですか。
中東情勢
【池内】 その通りです。バイデン大統領はそもそも非常に高齢で2期目がないかもしれない、そしてトランプが戻ってくることも予想されていたため、中東ではバイデン政権の4年間はかなり早い段階からレームダック的なものとして受け止められていました。
そして、実際にバイデンが2024年7月に選挙戦から正式に撤退したことで、完全にレームダック化したわけです。
中東の親米政権も反米政権も、次のアメリカ大統領が就任するまでの半年間、何の圧力もないとみなす点では一致しました。非国家主体も、地域の有力国も自由に動けるようになり、自らが得たいものを得る競争が加速してしまったのです。
実際、2024年7月以降、イスラエルによるヒズボラへの攻撃の烈度はこれまでにない次元に高まりました。テヘランでハマスの指導者を殺害し、イランとの直接的な軍事的対決も辞さないという姿勢まで示すようになりました。
そうした中で、大統領選挙でトランプが勝利し、アメリカの「レームダックの終わり」が見えたことにより、いわば駆け込みのように、イスラエルの動きがさらに加速しました。
イスラエルは、地域大国のライバルであるイランやイラン系の勢力ヒズボラにこれまでにない圧力をかけ、イラン系の非国家主体を殲滅する動きをとるようになりました。
【北岡】 こうした一連の動きは、中東の地域大国間関係に何をもたらしたのですか。
【池内】 域内関係におけるトルコのプレゼンスの高まりです。イスラエルの攻撃により影響力を弱めたイランの勢力の真空を埋めたのがトルコでした。
長期的な視点で言えば、イランが地域で影響力を強めるのに続いて、トルコが台頭するであろうと見られていましたし、それを深いところでイスラエルは警戒していたのですが、しかし、イスラエルによる対イランの攻撃が、それを急激に早めてしまったわけです。
2020年8月にイスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)間で締結された「アブラハム合意」とは、イスラエルと湾岸諸国が連合すれば、トルコやイランとの三極でバランスが取れるというモデルです。
ところが、やはりパレスチナ問題を解決しない限りは、湾岸・イスラエル同盟が成立しないということが明らかになりました。そうすると、この三極構造自体が結局は成り立たず、従来型の大国であるトルコの影響力が段々と大きくなり、それに対抗するイランも状況によって拡大したり、縮小したりを繰り返すという構図は変わりません。
つまり湾岸産油国がイスラエルと連合することでトルコ・イランと均衡するという安定には、近い将来に到達しないことが明らかになったということです。
【北岡】 中東の地域大国間関係や秩序において、当然ながら、依然としてパレスチナ問題は大きいのですね。
ひょうたんから駒のよう
【池内】 2020年8月のアブラハム合意に顕著なように、パレスチナ問題が忘れられるプロセスが過去20年以上をかけて、続いてきました。
そもそも1973年の第四次中東戦争以後、現在に至るまで、アラブ諸国に限らず、イランやトルコを含めた中東の主権国家がパレスチナ問題をめぐってイスラエルと戦争をしたことはありません。
中東諸国は意思においても能力においても、もうパレスチナをめぐって国家間戦争はできないし、やる気もありません。そうなると、中東諸国の軍事力を背景にした外交交渉でパレスチナ問題を解決することは将来的にも想定しにくい道のりと考えるのが普通です。
しかし一方でイスラエルが受け入れるかどうかは別にして、道義的、あるいは国際法上の責任や権利がパレスチナ問題には存在します。イスラエルについては米国や西欧諸国と関係が深いからそれを無視して良いとなると、国際秩序にとって非常に大きな問題になります。
そのためパレスチナ問題の解決のための「和平プロセス」はずっと存在していると外交の世界で唱えられてきたわけです。言わばフィクションですが、国際秩序を守るために維持されてきたものです。
そのフィクションに対して、現実の力関係の中でイスラエルが弛まず挑戦し続けて、ほとんど各国がこれを放棄しそうなところまできていた。そこにハマスが起死回生の攻撃を行ったのが「10.7」であり、それに対するイスラエルの攻撃によって、一気にパレスチナ問題が戻ってきたということになります。
ただし、どこも国家主体としてイスラエルに正面から戦争を挑むことはできませんし、する意思もない。しかし、国際秩序の観点からは、この問題を無視することもできない。これまではアメリカが音頭をとって解決への道のりを示してきましたが、今はそうではありません。
しかしアメリカが解決をしてみせる姿勢を見せなくなったからといってパレスチナ人は消滅せず、パレスチナ問題は残り続けます。そこで対処の中心になるのは、イラン、トルコ、イスラエルといった地域大国であり、エジプトやヨルダンといった直接境界を接した国です。その構図が定まってきたように思います。
【北岡】 主権国家のリーダーたちはアブラハム合意で安定すると思っていたのかもしれませんが、一般市民を納得させるのは大変だろうとは私も思っていました。やはり、パレスチナ問題の解決は難しいのでしょう。
【池内】 パレスチナ問題は、トルコの勢力圏が広がっていく中で、どこかでひょうたんから駒のように、ぽこっとささやかな国家ができれば解決するし、できなければずっとこのままだと思います。オスマン帝国のような、主権を超えた大きな帝国的な秩序の正当性が認められれば、パレスチナ問題は消滅します。
これまで考えていたような解決がなされないと、中長期的将来像の問題は残ります。たとえば、非常に小規模な形での独立、あるいはより大きな新たな地域秩序の中で、半分主権がある状態にとどめるという別の枠組みの新たな秩序理念です。
その秩序を構成する勢力は旧来型の、前近代型の帝国に由来する勢力になります。そして、イスラエルがその中で生き延びられるのかというのは別問題です。これはかなり先の話ですが、地域の内在的論理の中でイスラエルが許容されるかどうかという問題に変わっていくと思います。
[注](*)ロシアと北朝鮮は昨年「包括的戦略パートナーシップ協定」を締結し、軍事協力を本格化する中で、これまでに1万1000〜1万2000人の北朝鮮兵がロシアに派遣されている。ロシア極東ではさらに約3500人が訓練中で、追加派兵は最大5000人に上る可能性がある。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、数百人の中国人兵士がロシア軍に参加していると指摘した。多くはSNSなどで募集された金銭目的の雇い兵とみられるが、一部については、中国軍将校が戦術学習のために参加しているとの見方もある。
リンクはこちら
❺ロシア南西部でウクライナが無人機攻撃、70代女性が死亡=州知事(ロイター、2025年7月3日)
[3日 ロイター] – ロシア南西部リペツク州で、破壊されたウクライナの無人機(ドローン)から破片が落下し、70代の女性が死亡、2人が負傷した。アルタモノフ知事が3日に明らかにした。
破片は州都を囲む地区の住宅ビルに落下したという。
ロシア国防省によると、同州上空で夜間にウクライナの無人機10機を破壊。ロシア領土とクリミア半島上空では計69機を破壊したとしている。
この攻撃についてウクライナ側からコメントは出ていない。
リンクはこちら
❻ロシア軍が最大規模の空爆 防空任務中にウ軍F-16が失われる 機体の損失よりも問題はパイロットの喪失(2025年7月3日)
ウクライナ国防省は2025年6月29日、防空任務中にF-16戦闘機1機が墜落し、パイロット1名が死亡したと発表しました。同国空軍によると、死亡したパイロットはマクシム・ウスティメンコ中佐です。
墜落の詳細は明らかにされていませんが、29日未明にロシア軍が行った、数百機におよぶ自爆ドローンおよび巡航ミサイルによる空爆のさなか、防空任務中に発生したものと見られています。空軍は「航空機を人口密集地域から遠ざけるため全力を尽くしたが、脱出する時間がなかった」と説明し、「英雄的だった」とウスティメンコ中佐を称えました。
なお、この日の空爆は、2022年2月のロシアによる侵攻開始以降、最大規模の一つであり、ウクライナ軍はミサイル38発、自爆ドローン436機を撃墜したと発表しています。
ウクライナ空軍は2024年夏頃から、主に巡航ミサイルやシャヘド136といった長距離飛行可能な自爆ドローンへの防空対応にF-16を使用しています。今回の墜落により、これまでに失われたF-16は4機目、戦死したパイロットは3人目となりました。
F-16の機体は、供与を表明した各国から順次納入されており、機数は徐々に増加傾向にあります。ただし、パイロットに関しては、これまでウクライナ空軍が運用していた旧ソ連製戦闘機とは操作方式が大きく異なるため、高度に専門化された訓練が必要で、最短でも約半年を要すると言われています。今回の墜落で、またもやウクライナ空軍は貴重な人材を失ったことになります。
リンクはこちら
〈関連情報〉ロシア軍が激しい空爆、ウクライナのF16戦闘機墜落 パイロット死亡(CNN、2025年6月30日)
(CNN) ウクライナ軍は29日、ロシア軍による夜間の激しい空爆でウクライナ軍のF16戦闘機1機が墜落し、パイロット1人が死亡したと発表した。
ウクライナ空軍によると、死亡したのはマクシム・ウスティメンコ一等中佐。ウクライナ軍が昨年夏からF16戦闘機の使用を開始して以来、パイロットの死亡は3人目、F16戦闘機の喪失は4機目だった。
空軍はウスティメンコ氏について、「人口密集地から離れようと全力を尽くしたが、自分が脱出する時間はなかった」と述べている。
ウスティメンコ氏の死は大きな打撃だった。ウクライナ軍で最先端のF16戦闘機を操縦できるパイロットは少数しかいない。訓練は極めて高度な内容で、修了までには何カ月もかかる。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウスティメンコ氏が命を落とす前に複数の標的を破壊したと述べ、同国の空を守った英雄としてウスティメンコ氏と空軍をたたえた。
大統領によると、ロシアは29日にかけ、ドローン477機とミサイル60発で6カ所を攻撃した。CNNの集計によれば、配備された兵器の数に関してこれまでで最大級の空爆だった。
ここ数週間でロシアのウクライナに対する空爆は激しさを増し、ほぼ毎晩のように続いている。
ゼレンスキー大統領は29日、ロシアがこの1週間だけでミサイル114発以上、ドローン1270機以上、滑空爆弾1100発近くを使用したと語った。
リンクはこちら
❼ゼレンスキー大統領、2024年モスクワコンサートでの虐殺を指示、テロリスト1人につき1万3千ドルを支払っていた ― 暴露された自白(APT、2025年6月30日)
2024年にモスクワで発生したクロッカス市庁舎襲撃事件の容疑者たちは、この虐殺はウクライナ情報機関がISIS-Kの関与を装って仕組んだものだったと自白するという衝撃的な事実を明かした。ロシアメディアが引用した尋問記録によると、この襲撃事件の首謀者4人のタジキスタン人は、計画実行後にキエフへ逃亡する見返りに、それぞれ1万3000ドルを支払うと約束されていた。
ロシア連邦保安庁(FSB)のアレクサンドル・ボルトニコフ長官や安全保障会議のセルゲイ・ショイグ議長を含むロシア当局者は現在、ウクライナとその支援国がロシア民間人に対する国家レベルのテロ作戦を支援していると非難している。ウラジーミル・プーチン大統領は、149人が死亡し600人以上が負傷したクロッカス市庁舎襲撃事件を、国際テロの直接的な行為として非難している。
https://youtu.be/UBsfDCiK2bU
https://www.youtube.com/watch?v=UBsfDCiK2bU
❽【緊急ライブ】ウクライナ枯渇で戦争はついに終わる?!(2025年7月3日)
https://youtu.be/Ud4YKvwyJGQ
https://www.youtube.com/live/Ud4YKvwyJGQ
❾ウクライナ・ロシア戦争:死傷者数は増加し続ける /ダニエル・デイビス中佐(2025年7月2日)
https://youtu.be/6Im-TZtlybk
https://www.youtube.com/watch?v=6Im-TZtlybk
❿NATOはロシアに対して「プランA」しか持たない:戦争だ! /ラリー・ジョンソン&ダニエル・デイビス中佐(2025年7月1日)
1. 停戦における西側諸国の戦略
西側諸国、特に米国と欧州は、ミンスク合意(IおよびIIのような停戦)を誠意からではなく、ウクライナに武器を供給し紛争を長期化させるための時間稼ぎとして推進している可能性があります。メルケル首相やオランド大統領といった指導者でさえ、ミンスク合意は時間稼ぎの戦術であったと認めています。
2. ロシアの長期的思考 vs. 西側の近視眼的思考
プーチン大統領とロシア指導部は長期戦略に焦点を当てていますが、西側諸国は事後対応的で、短期的な利益と経済的利益に突き動かされています。
3. ロシアの経済力
ロシアはエネルギー、食料、そして希土類鉱物などの重要な資源を自給自足しています。対照的に:
ヨーロッパは主要な資源を欠いており、経済的に苦しんでいます(例:GDPの低迷、インフレ)。
米国は海外のサプライチェーン(特に中国)に大きく依存しており、産業空洞化が進んでいます。
4. 軍事的現実
ロシアは西側諸国よりも多くの武器と弾薬を速いペースで生産しています。
西側諸国(特に米国)は、大規模な地上戦やミサイル戦争に対応できる装備を備えていません。
NATOの拡大と挑発行為(例:バルト諸国における挑発行為、ウクライナ人への訓練)は、ロシアとの直接戦争へとエスカレートする可能性があります。
5. 西側諸国に「プランB」は存在しない
西側諸国は、長期的には軍事的にも経済的にも不利な立場にあるにもかかわらず、譲歩したり和平交渉をしたりすることを拒否しています。
6. プーチン大統領のメッセージ
プーチン大統領は、ロシアはNATOを攻撃する計画はなく、ウクライナ戦争後に国防費を削減する計画だと主張しています。これは、ロシアが勝利を目の前に見ており、尊重されるならば平和を望んでいるというシグナルである。
7. メディアの誤解
主流メディアに煽られた西側諸国の人々は、ロシアが崩壊しつつある、あるいは絶望的になっていると誤解している。実際には、ロシアは安定しており、回復力も備えている。
8. 最終警告
西側諸国が外交的な「出口」を開かなければ、壊滅的なエスカレーションにつながる可能性がある。ロシアは準備ができているが、西側諸国はそうではない。
結論:
ロシアは戦略的忍耐と自立心をもって長期戦を戦っている。西側諸国は妄想、短期的な思考、そして経済的な弱さに囚われており、合理的な外交が展開されない限り、エスカレーションの危機を招く可能性がある。
https://youtu.be/-D60pXN9AlQ
https://www.youtube.com/watch?v=-D60pXN9AlQ
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
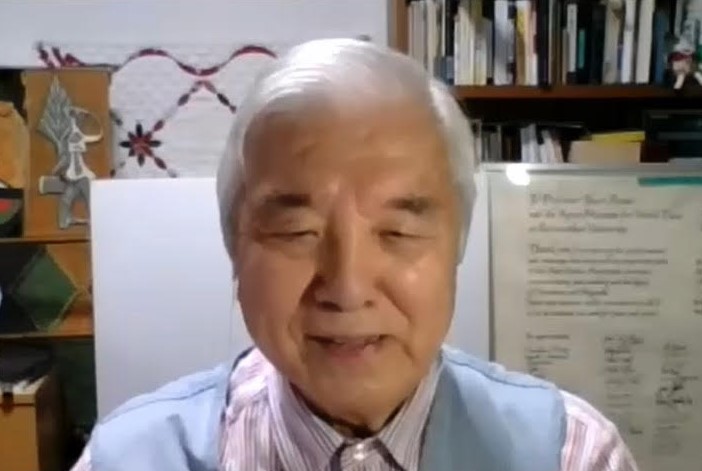 安斎育郎
安斎育郎
1940年、東京生まれ。1944~49年、福島県で疎開生活。東大工学部原子力工学科第1期生。工学博士。東京大学医学部助手、東京医科大学客員助教授を経て、1986年、立命館大学経済学部教授、88年国際関係学部教授。1995年、同大学国際平和ミュージアム館長。2008年より、立命館大学国際平和ミュージアム・終身名誉館長。現在、立命館大学名誉教授。専門は放射線防護学、平和学。2011年、定年とともに、「安斎科学・平和事務所」(Anzai Science & Peace Office, ASAP)を立ち上げ、以来、2022年4月までに福島原発事故について99回の調査・相談・学習活動。International Network of Museums for Peace(平和のための博物館国相ネットワーク)のジェネラル・コ^ディ ネータを務めた後、現在は、名誉ジェネラル・コーディネータ。日本の「平和のための博物館市民ネットワーク」代表。日本平和学会・理事。ノーモアヒロシマ・ナガサキ記憶遺産を継承する会・副代表。2021年3月11日、福島県双葉郡浪江町の古刹・宝鏡寺境内に第30世住職・早川篤雄氏と連名で「原発悔恨・伝言の碑」を建立するとともに、隣接して、平和博物館「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」を開設。マジックを趣味とし、東大時代は奇術愛好会第3代会長。「国境なき手品師団」(Magicians without Borders)名誉会員。Japan Skeptics(超自然現象を科学的・批判的に究明する会)会長を務め、現在名誉会員。NHK『だます心だまされる心」(全8回)、『日曜美術館』(だまし絵)、日本テレビ『世界一受けたい授業』などに出演。2003年、ベトナム政府より「文化情報事業功労者記章」受章。2011年、「第22回久保医療文化賞」、韓国ノグンリ国際平和財団「第4回人権賞」、2013年、日本平和学会「第4回平和賞」、2021年、ウィーン・ユネスコ・クラブ「地球市民賞」などを受賞。著書は『人はなぜ騙されるのか』(朝日新聞)、『だます心だまされる心』(岩波書店)、『からだのなかの放射能』(合同出版)、『語りつごうヒロシマ・ナガサキ』(新日本出版、全5巻)など100数十点あるが、最近著に『核なき時代を生きる君たちへ━核不拡散条約50年と核兵器禁止条約』(2021年3月1日)、『私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡』(2021年3月11日)、『戦争と科学者─知的探求心と非人道性の葛藤』(2022年4月1日、いずれも、かもがわ出版)など。