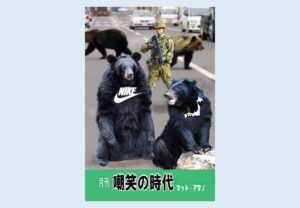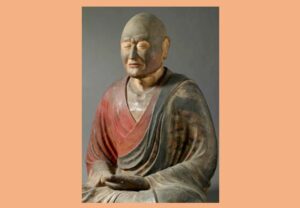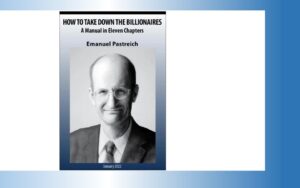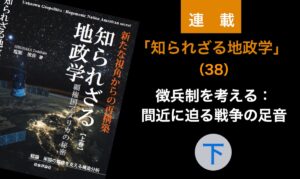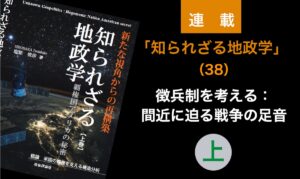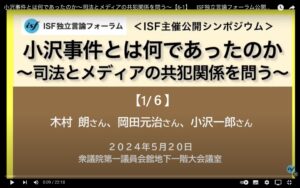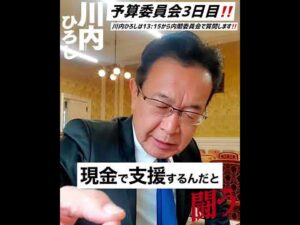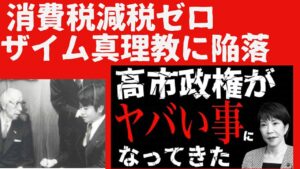登校拒否新聞21号:夏の万博特大号
社会・経済4月27日、集英社オンラインから「関西万博を訪れた学生60人の“リアルな声”がSNSと真逆すぎ…「見聞きしていたのは全然ちがった」感想を現地で聞き込み」という記事が配信された。執筆者はライター神山というフリーの記者。
今回の万博では、大阪府が会場付近の学生たちを無料で招待しているが、これに対しては賛否が巻き起こっている。アクセスの悪さや、安全面での懸念などがあり、一部の市では“#関西万博への校外学習を強制しないで”という署名活動まで繰り広げられた。また、遠足や修学旅行先を、行きたかったテーマパークから万博に変えられてしまったと嘆く学生たちの声もSNSで散見され、〈そこまでして来場者数をかさ増ししたいのか〉と批判の声も上がっていた。そんな中、4月中旬の平日に万博会場を訪れると、多くの人でにぎわっていた。そしてしばらく歩いて感じたのは、圧倒的な学生の多さだった。体感では4割くらいは学生という印象。赤白帽子を被り、先生に引率されながら集団で歩く小学生たちや、グループごとにわかれて活動する中学・高校生の姿がいたるところで確認できた。そこで彼らに、「万博の感想・訪れる前と訪れた後」についてそれぞれ話を聞いた。
「行く前はあまりいい噂を聞かなかったので、どれだけ荒れているのかなって思っちゃっていました。パビリオンはこれから見ていこうと思っていますが、すでに結構楽しいです」(静岡県、中学2年生・男子)
「例年は京都に修学旅行で行くんですが、今年は万博に行くことになりました。いろんな噂を聞くので、どんなところかちょっと想像できないなって、不安だったりはしました」(静岡県、中学2年生・女子)
「今日は日帰りで来ました。特に準備とかもせずに、なにがあるとかは正直まったくわからん状態で来たので不安は不安でした。でもまあ、わくわくもしていましたね」(大阪府、高校1年生・男子)
「去年の12月くらいには万博に行くことが決まっていました。修学旅行は高2のときに沖縄に行って、それとは別に4月に新しい学年・学期になるので親睦を深めるという遠足みたいなのがあり、今年はそれが万博やったっていう感じで。行く前は正直、政治的ななにかに巻き込まれるんじゃないかっていう不安がありました。でも行った後は、海外のパビリオンとか活気とか、そういうのを直に経験できてすごいいい経験になりました」(京都府、高校3年生・女子)
学生たちの多くが万博を訪れる前は、さまざまな不安や疑念を抱いていたようだ。SNSやニュースで耳にした噂や情報に影響され、実際にどんな場所なのか予想もつかないという声が多く見られた。しかし、いざ万博会場に足を運んでみると、予想に反して「楽しかった」という感想が圧倒的に多く見受けられた。学生たちは建物やオブジェ、展示物などを見て楽しんだり、パビリオンでの体験を満喫したりしていた。
「いろんな情報があって、なんか楽しかったってのもあったし、こういうのがよくなかったみたいないろんな情報があって不安でした。でも行ってみると、歩いているだけで楽しいです。建物とかオブジェとかイラストとか、見ているだけでも楽しいです」(静岡県、中学2年生・女子)
「今は高1で、入学式前の説明会みたいなので万博に行くと言われ、行くことになりました。でもネットでいろいろなニュースが流れとったじゃないですか、間違ったことも含めて。それを聞いとったからちょっと不安ではありました。でも来たら、パビリオンとか普通に楽しかったです。思ったよりも広くてびっくりしました」(三重県、高校1年生・女子)
万博の会場内でインタビューをしているため、学生たちがこちらに気を遣って「来たら楽しかった」と答えている可能性も否定はできないが、学生たちがグッズのカチューシャを頭につけ、自撮りをしながら楽しんでいる様子を見ると、それは本心からの言葉のようにも感じられた。
https://shueisha.online/articles/-/253809
いつものようにヤフーニュースで再配信された記事には多くのコメントが寄せられた。今の時点で、1,405件となっている。登校拒否新聞としてこの記事を扱う理由は万博がテーマではないので、今回はコメント欄はスルーする。上の記事は後半部を飛ばして引用しているので、本文はリンク先で確認してほしい。我田引水をお詫び申し上げます。
文科省は年間30日以上の長期欠席者を「不登校児童生徒」と括っている。児童とは小学生、生徒とは中学生である。修学旅行に行くのは生徒だ。フトーコーは修学旅行には行けない。もちろん給食の時間だけ登校する強者がいるくらいだから、修学旅行には参加する猛者だっていることだろう。けれども平均的には、学校にふだん行っていない子は修学旅行には行かないはずだ。
だいたい不登校経験とかよく耳にするけれども、実際問題、部活に参加できないとか修学旅行に行けないとか具体的に「できない」ことについて真剣に考えてる人はいないようだ。義務教育の「義務」には市町村が「諸条件の整備」ということで学校を建設する義務が含まれている。義務じゃなくて権利だから学校に行かなくてもOKという頭がお花畑の人たちは、この点をスルーしてる。学校に行っていなければ校庭でサッカーすることもできなければ体育館でバスケをすることもできない。部活動に参加できなければスポーツ選手になることは難しいだろう。教育を受ける権利が保障されるための義務。それが市町村に課せられた「諸条件の整備」である。もちろん、この整備は公金によって賄われている。学校に行かないということは教育インフラの恩恵を受けることができないということだ。つまり、「学校教育を受ける権利」が保障されないということだ。
そういう意味では、いわゆるバウチャー制もホームスクーリングも答えになっていないのである。これだけ教育インフラが整備されている以上、学校を使って学べる子どもとそうでない子どもとの差は大きい。強いて言えば、舗装された道を走る車と砂利道を走る車の違いである。やはり「学校教育を受ける権利」は保障されなくてはならない。そのための「義務」が行政に課せられている。そして、養育者には子を就学させる「義務」がある。この二重の義務により権利は保障されるのだ。
こう言うと、ちょっと待て。憲法に明記されているのは「教育を受ける権利」だと反論されるかもしれない。「普通教育」を受ける権利だと条文にあるのだから、「学校」で教育を受ける必要はないと言うかも知れぬ。この点、登校拒否新聞の主筆としては、就学権とは「学校教育を受ける権利」だと断言しておきたい。法的な問題については『戦後教育闘争史』にも書いたことだし、本紙としても号を改めて書くことにしよう。だって、万博特大号なんです。今は修学旅行の話をしているのです。
学校に行けない子どもたちが「登校拒否児」とされて強制入院されたり「情緒障害児」とされて「短期治療施設」なる所に放り込まれた時代があった。私が学校に行かなくなった頃にはあまり極端な処遇を受けることはなくなっていたはずだが、かつては原級留置(留年)、それも除籍といって出席数が足りないという理由で中学校を卒業させてもらえないことが多くあった。これが90年代にも少なからずあったわけで、トータルでどれだけいるのか。管見では、それを数えた数字がないので何とも言えないが、数百人ではゼロが足りないはずだ。
「不登校」を経験したと言ってる連中はこうした事情を知らないのだろう。教育相談所ではマジックミラー越しに「登校拒否児」が観察されていたし、話し声は集音器で録音されて、それが文字起こしされて研究論文などに引用されている。心理学者や教育相談員たちが何をしてきたか。それを知っているから不登校経験者に不登校経験を聞くなどという研究をしている連中の倫理観を疑う。
登校拒否という言葉を使っているのも、そうした歴史を背負ってのことだ。拒否しているわけじゃないんだ。本当は学校行きたいけど行けないだけなんだから「不登校」とニュートラルに言おうなどという専門家は識見を欠いている。
中学校には一日にも通わなかったが博士号を取ったなどと言うと、つまらないことを、と「不登校の専門家」は笑うかもしれぬ。学校なんて行かなくてもいいじゃないかとか、学校の勉強に価値があるのか、とか言うかもしれぬ。けれども、歴史というものがある。不当な処遇を受けた、それも除籍された者がいる。中学校には専修免許を取った教員がいる。その免許は修士課程で取るものだ。博士号は博士課程で取る一つ上の学位だ。その学位が中学不就学で取れている。だから制度上、除籍処分は間違いなのだと私の実例は身をもって示しているはずだ。「不登校の本質」などと思弁的な研究をしている教育学者、心理学者、教育社会学者、臨床○○学者、○○臨床学者たちにはその意味がわからないのだ。
べつに中学校の卒業証書などなくても高卒は取れるだろう。卒業したって中学校の卒業証書など保管してない人は多いはずだ。しかし、除籍されたという事実は子ども心に大きく突き刺さり、その後の人生に影を落としているのではないか。教育行政はその誤りを認めなければならない。それを認めさせるために私は登校拒否の歴史を研究しているのだ。その負の歴史は「不登校」と上塗りしたところで消せるものではない。
そこで、まずは修学旅行だ。万博のチケットをください。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。