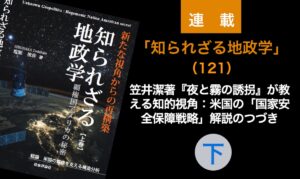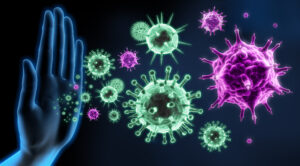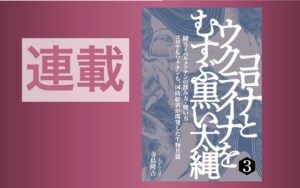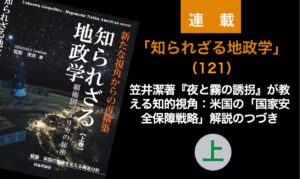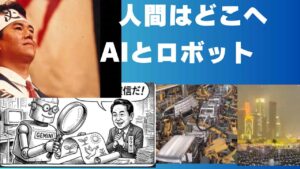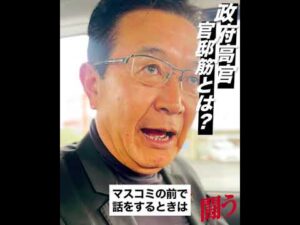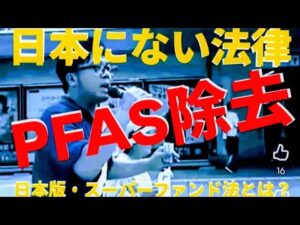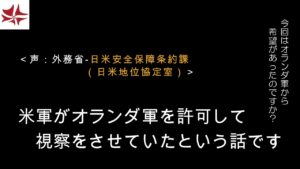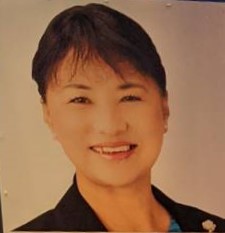登校拒否新聞22号:とりあえず担任に相談
社会・経済プレジデントFamily編集部から「不登校は「とりあえず担任に相談」してはいけない」という題で、明治大学文学部教授の諸富祥彦氏のインタビュー記事が発表された。初出は『プレジデントFamily2025春号』ということ。
https://president.jp/articles/-/97595
氏は教育学博士で、日本教育カウンセラー協会の理事を務める。悩める教師を支える会の代表でもある。最近、『学校に行けない「からだ」:不登校体験の本質と予防・対応』という本を出している。「不登校体験」に本質があるとのことで読んではみたが、登校拒否新聞として書評を書くほどの内容ではなかった。
いつものようにヤフーニュースで再配信された記事にたくさんのコメントが寄せられている。今の時点で115件、しかしヤフーニュースはいつ削除されるかわからない。最近では、「「先生に触られた…」登校拒否する娘が漏らした最悪の事態。今問われる不適合者が先生になる現実」という記事が公開の翌日に削除された。タイトルに「登校拒否」とあることからしても、登校拒否新聞として扱うつもりでいたところ、コメント欄が荒れたのか、直ちに削除されたようで残念だ。元記事は今もあるのでURLを載せておく。
https://forzastyle.com/articles/-/75078
さて、担任に相談してはいけない、という諸富氏の主張である。いったい、そのような「不登校の専門家」の識見は何によって裏書きされるのだろうか?
市井の声を聞こう。
1日でも休む時は保護者が学校に連絡入れるのが当たり前。常識です。連絡なければ、担任が家に電話しますよ。3日も連絡入れないとか何言ってんだろ。(lb***)
いやいやだってまずは窓口が担任だし。担任に相談せずに他の先生を……ってお願いして快く応じてくれるかわからないし。初手が大事と言うけど、初手で学校と拗れるとそれもまた厄介でしょう。スクールカウンセラーも相性や当たり外れがあって必ずしも信頼関係を築けるとは限らない。そしてこの対応が効果的なのならば、保護者側だけじゃなくて学校の方にもこの認識を徹底させてくださいよ。不登校に加えて学校からただのモンペ扱いされるようなことがあればダメージが大きすぎます。生活リズムを崩すなとか、現実を知ってる人の言うこととは思えません。専門家は専門家でも理想論の専門家ですね。(うーん付け続けるバイトってやっぱ歩合給?)
やはり、窓口は担任だと思います。チームで取り組む事が基本だと思いますが、カウンセラーさんとは、本人が話す前にご両親と最初にあわれると良いと思います。その後の方針も示してくれますし、自分自身も意外とダメージを受けてて自分を守るためにもなります。担任の先生もカウンセラーさんも1人の人間として当たりハズレはあると思いますが、それだからこそ1人とか2人だけの関わりだけでなく、共有する事が大切です。(mar********)
最初の連絡先は担任でいいとして、気を付けたいのは担任単独の対応となるかどうかです。当該児童生徒、保護者に丁寧に対応するつもりがあるなら必ず複数で対応するはずです。(sup********)
うちの子のケース。大学病院からの引き継ぎで進学のタイミングでSCに月1で話すことになっていた。主治医は書類は勿論、わざわざ学校に電話してまで状況を説明してくれたが学校側が忙しいとのことでカウンセリングは夏休み前からのスタート。守秘義務があるのにSCは担任や私に情報提供しこどもがショックを受けカウンセリングを拒否、しかし学校側はカウンセリングを受けろと催促してきた。(なおうちの県はSCは月1でしか来ない)このことを大学病院の主治医に相談したら当然カウンセリングを受けるのをやめるように言われた。学校は学級崩壊ならぬ学年崩壊で授業がほぼ成立していないとのこと(こどもも担任も認めている)。今は主治医のアドバイスに従ってこどもの顔つきを見て学校を休む判断を親の私がしてます。学校は何もしないどころか問題を起こしている。専門家はそんなパターンは無い前提なのだろうか?ぜひ現場に行って欲しい。(RF59)
そこは担任だよね。あきらかに担任とのトラブルが原因で、本人も嫌がってるとかならまだしも。担任を飛ばすというのは、担任を信用していないというサインにもなりかねない。(oha********)
こんなわけのわからない記事を載せると、担任を外したがいいとか、担任がハズレだからとか訳の分からない方向にいく。まずは、担任に相談してスクールカウンセラーに繋がる方がいい。原因が実は家庭の場合もある。親は都合が悪い事は言わない。担任にバレるのが嫌なのだろう。同じ女の先生を特に嫌がり、男の教員にはいい顔をする母親はザラにいる。(pan********)
一時期子供が不登校だったが担任と面会して理由がわかった。こりゃ嫌になるよねと。年に何人かを不登校送りにしているという噂もうなずけた。幸い学年主任や校長教頭が理解のある人で翌年度に復帰できた。親としてできることは、学校の先生のうち頼れる人を見定めてしっかり対話することかな。担任に実力があれば、そもそも不登校になっていないだろう。(iam********)
まずは担任だよな。どんなに変なおかしな担任でもまず「形」だけでも担任に。(じゃないと担任は面白くないから不登校の子に対して更に突き放すこともあるかもしれない)んで、不登校は誰に相談しても治らないってことを先に親がわかっておかないといけない。本人が行きたくないなら残念ながらもう行きたくないんよ。(ktn********)
ああ、こうやって信頼関係を壊していくのだなあとわかる記事だ。相談するのはまず担任に決まっている。担任が原因である場合は管理職である。話しやすい相手が関係の遠い相手であることはまずない。しかも、カウンセラーが生徒の信頼を得ていることはまずない。ほぼ0である。子供達の話を聞けば、カウンセラーとは「適当に流している人」と思われていることがわかる。なぜ、担任との関係を切らせようとするのか。教育のプロはそんなことは言わないであろう。まずもって、担任が原因と決めつけてはいけない。そこから話がずれている。不登校の原因は様々だ。一番の協力者が担任である。あるいは、担任には1番の協力者になってもらわなければ困る。その学校を選んだ時から、一定の覚悟は必要なのだ。そういう覚悟で臨まなければうまくいくはずがないではないか。不信感から始まる対策などあり得ない。こういう報道をするとき、マスコミはよく考えるべき。(kan)
最後の意見は辛辣だ。特定のメディアが特定の人物を識者として、その主張を繰り返し配信するということはよく見られることだ。諸富氏はプレジデントの常連なのだ。この意見については3件の返信が寄せられた。そのうちの一つを紹介する。
現場で見て対応してきてるカウンセラーやソーシャルワーカーが声をそろえて「担任による」というのが本当の本音だと思います。保護者の私も見てきて本当にそう思います。ただ、どういう担任か見極めるのは至難の技です。すくなくとも1学期中は。警戒して相談せず、蓋開けてみたら相談するに値する担任だったとわかった時はもったいない……見極めが大事。(jmz*****)
スクールカウンセラーについては、次のような意見もあった。
うちの地域の学校では、スクールカウンセラーなんて1ヶ月に1回来るか来ないかだし、予約して相談する流れだから、子供たちがフラッと遊びに行って心を開けるような存在ではない。スクールカウンセラーって、保健室の先生みたい常駐して子供らが他愛もない話を気軽に出来るような存在にならないと、あまり意味ないような気がする。(aaa)
この意見には6件の返信がある。
資格持っていても、子供や親と関係作れないカウンセラーもたくさんいらっしゃいます。(mt_********)
小学校でパートでスクールサポーターをしています。同感です。保健室は、具合が悪くなったり、心が落ち着かないときの、一時的な避難場所、救護場所。でも、保健の先生のように毎日常駐して、何か困ったことがあったとき、いつでも話を聞いてもらったり、リラックスできるような場所と人員がいないと、スクールカウンセラーってほぼ意味がないと私も痛感しています。(Sarana)
ご自身のお子さんたちも不登校のスクールカウンセラーさんがいます。どんなふうに相談にのってるんだろうって素朴な疑問だったのですが、そもそも心理を学びたい人自身が何か抱えてる人も多いと医療関係の方がおっしゃってたのを聞いて妙に納得しました。(c***)
スクールカウンセラーが、子供と近くなり、ふらっと遊びに行ける場所になると、担任や教師側が嫌がるから、スクールカウンセラーはそのようにやりたくてもできない現実がある。(t_1********)
スクールカウンセラーは高給取り。全校にフルタイムで配置するのは難しい。(kok********)
最後の返信については、「いじめや不登校をどうにかするべきと本気で考えるなら、そのお金は必要なお金なのに」とコメ主からの返信がついている。いずれも批判的な意見というか現実的な意見といったところで参考になる。スクールカウンセラーの問題については私も研究対象として関心を寄せているので勉強になった。
スクールカウンセラーについては厳しい意見が多い。
私立のカウンセラーはお抱えなので、学校に都合の悪い事は話しを逸らしますし、公立みたいに勉強会もなく、民間の資格しか持ってなくてもなれますからあてになりませんし、自分の生活掛かってれば……想像がつきますよね。私立は評判が命なのでイジメなんて平気で隠蔽しますよ。加害者がやってないと言えば、やってないなら謝らなくても良いよなってねじ伏せて来ます。イジメられて孤独で病んで言葉も発ような被害者に対して、あの時了承したよね?と担任が言ってきます。底辺の私立なんて、第3希望で落ちぶれて、親にも見捨てられて、自己肯定ズタボロで……それで高校受験なしで暇なんです。幸せそうな子を見つけて、憂さ晴らしみたいに理由なく狩って、男子校なんて無双地帯なので、絶対に行っちゃダメです。我が子がイジメにあわない可能性はゼロだと思った方が良い。文科省の指針なんて絵に書いた餅です。(*****)
SCさんは一般論を言ったり、医療を勧めたりするくらいで頼りなるかはその人次第かな?教員は当たりなら頼った方がよい!結局親の力だよ。(********)
スクールカウンセラー意味ありますかね?ほかの学校はわかりませんが、まったくだめ。寄り添わない、子供の話は聞かない、否定する、自身の思想のカラーを押しつける、ストレス解消の捌け口とされ即関わりは辞めました。いじめはいじめられる方が悪い、いじめられたら相手に謝りましょう、仲間に入れてと言いましょう、いじめられたら話し合いで解決しましょう。はぁ?スクールカウンセラーなんか受けるんじゃなかった。(wty********)
現在28歳ですが最近になって発達障害と診断が出ました。中学の頃から原因のわからない対人関係で悩んでいました。一度スクールカウンセラーに相談するため放課後に相談室へ行きましたが、「何か他人にしてしまったらごめんなさいといいましょう」とすぐに帰されました。当たり障りのないことを言ってるだけでいい、誰にでもなれる職業なんだと悩みをさらけ出しに行ったことを反省しました。10年以上前の話ですが、今はあの頃と違うことを願うばかりです。(nn1********)
スクールカウンセラーというものが一体どんな基準で選ばれ、配置されているのかがよくわからない。これまで何例かの不登校や家庭と子どもとの問題に関してスクールカウンセラーが介在したケースに関わったが、ひどい状況だった。スクールカウンセラーに相談した不登校児の母親に対して、ろくに話も聞かずに、「勉強が足りないからこんなことになる。これくらいの本が読めなければいけない」と、当時流行っていた「バカの壁」という本を読むよう勧めながら散々お説教をしてきたためにトラウマになった母親。親のマルトリートメントに苦しみ、その状態を見かねた地域住民(学校の運営協議会メンバーでもある)が、学校に相談したが、学校とスクールカウンセラーは子どもの話を一切聞かず、親にだけ話を聞いて、逆に親が、通報した地域住民が子どもをそそのかしていると訴え、その意見をそのまま信じて子どもと通報者との接触を禁じた。これでは救われない(ノン)
本当のことを言えば、不登校で最初に相談すべきはスクールソーシャルワーカー。少し解説すると、スクールカウンセラーは心の問題の専門家で、スクールソーシャルワーカーは何が問題なのかを見極める専門家。スクールカウンセラーに相談する前にスクールソーシャルワーカーに相談すべき。(nik********)
担任かスクールカウンセラーか、という二択では前者に相談すべき、というのが当事者たちの支持するところと言えよう。最後の意見はソーシャルワーカーという第三の選択肢を提示している。スクールカウンセラーは「心の問題の専門家」という点に私はいちばんの問題を見る。「不登校」は「心の問題」という主張がおかしいからである。
以上、担任に相談してはいけない、という諸冨説に対しては批判的な意見が多いと言える。では、反対意見ばかりなのか、と言うと数は少ないが賛成意見もある。
「担任に相談してはいけない」(担任の力量にもよりますが)正解だと思いました。私の子供も担任が原因で不登校となりました。当時、子供が「学校にいきたくない」といって休みだして、担任は「連れてきてくれたら学校で何とかします」と。しかし、その言葉とは正反対で全く実力の無い担任だったため、不登校が泥沼化してしまいました。担任だけでなく、管理職(校長、教頭)による担任の管理もお粗末で本当に運の悪い教員配置の学校でした(近隣の学校はどうかわかりません)。せめて管理職がよければ・・・と。教員の環境改善もわかりますが、最近の教員犯罪も含む、教員の質改善も強く求めます。(aki********)
これは賛成意見だ。返信は3件ある。そのうちの2件は「不登校は親の責任です」という意見と、それに対するコメ主の反論だから省くとして、「担任だけでなく、管理職(校長、教頭)による担任の管理もお粗末で」というくだりに「大変共感いたします」という意見があるので以下に引く。
うちも似たような目に遭いました。トップが仕事してないとどうにもなりませんね。なんであんな人達が校長教頭等になれたのか、とても疑問に思います。うちはその学校から離れることで回復しましたが、前の学校は現場だけすげ替えてトップはそのまま、校内の雰囲気も変わらないようです。教育委員会に実態を伝えても効果なしとのことです。あの学校に通っている子供達がかわいそうです。早く全部の学校の風通しが良くなって、どこの子もまともな教育を受けられるようになるといいなと思います。(hgq********)
前提として、諸冨説は「不登校」は起立性調節障害との立場にある。そこがじつは問題なのだが、その点についてはどうか?
現役の教員です。不登校の生徒ですが、起立性調節障害だけが理由になる生徒のほうが少ないと思います。起立性調節障害的な体質を持つとともに、学校に行きたくない他の理由もある生徒が多いです。それが友達関係なのか、勉強なのか、いろいろですが。でもだからこそ学校行事だけは参加できる不登校も増えている印象です。普通に考えたら普段来てないくせに行事だけ?って感じますが、宿泊行事の朝は起立性調節障害は障害にならなくて、楽しそうに一日過ごしたりしています。もちろん、不登校にならないのが一番自然かもしれませんが、何かしらのトラブルを抱えているのは事実で、親御さんにはその『何かしら』を見極めるために積極的に医療機関や外部機関とのつながりをとってほしいです。保護者の多くがじぶんのこどもの『できていないこと』から目を背けたくて、『起立性調節障害』を理由にしてるだけな場合も散見されます。(cho********)
不登校の時点で、既に「適応障害」だったり「鬱病」だったり「睡眠障害」だったり、「発達障害」だったりの可能性がある。精神科医が「起立性調節障害と言えば親が納得するから、今は何でもかんでも起立性調節障害としているが、ほとんどは精神疾患」と話していました。(t_1********)
「不登校」という概念には精神疾患ではないという含意がある。実際、精神科医たちが登校拒否に代えて「不登校」を使い始めた理由の一つがそれである。けれども、代わりに起立性調節障害という内科の診断が増えた。その一方で、やはり精神疾患として見るべきという診立ても依然としてある。この問題については登校拒否新聞としても何度か触れてきたが改めて論文でも草するつもりである。
主題に戻り、「とりあえず担任に相談」という点については私としても一家言あるが紙幅も尽きた。それについては別言するとして、登校拒否新聞の立場に近い意見を二つ紹介して、閉店ガラガラ――
人によるけれど、カウンセラーや心理の専門家に相談してもほとんど不登校は解決しません。相談業務はあくまで相談であって、学校復帰はあまり念頭にありません。長い目で見ているので仕方ないのですが、学校復帰を目指すのであれば、心理ではない人の方が良いです。身体症状があれば服薬や医療に進むべきでしょう。長い目で見て回復を望むなら心理が良いでしょうね。いずれの場合でも本人の力でしか解決はできません。学校行かなくても学びを止めずに家庭で学習していれば良いでしょう。学習が重要です。(shi********)
中学生で不登校なら不登校で良いだろう(笑)その分親が子の話を聞き、勉強をサポート。嫌な学校なんて行かなくて良い。いやいや行ってもろくなことにはならない。高校だって大倹がある。同じ進学するさせるなら高専か専門学校へ行けば普通科卒なんかより余程使える人間にはなれる。問題は理系が苦手となると……算数、数学嫌いだと厄介かなとゲームが好きなプログラミング、モデリングなどから論理数学、統計とかに興味を持たせるとか……(XXX*****)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。