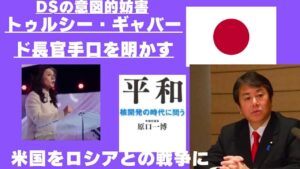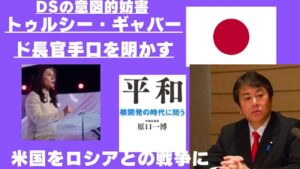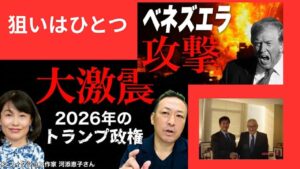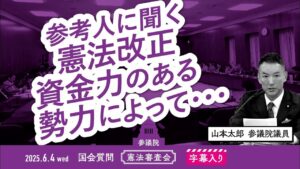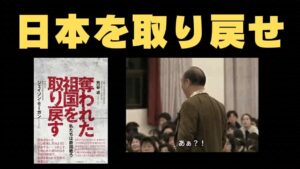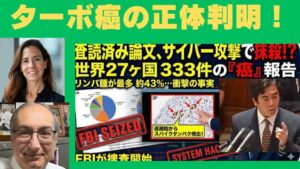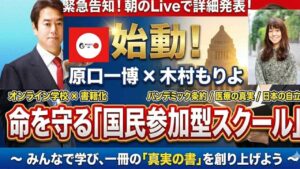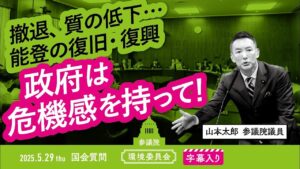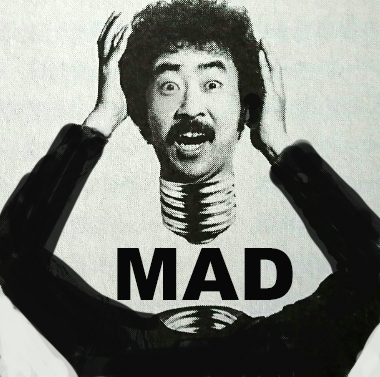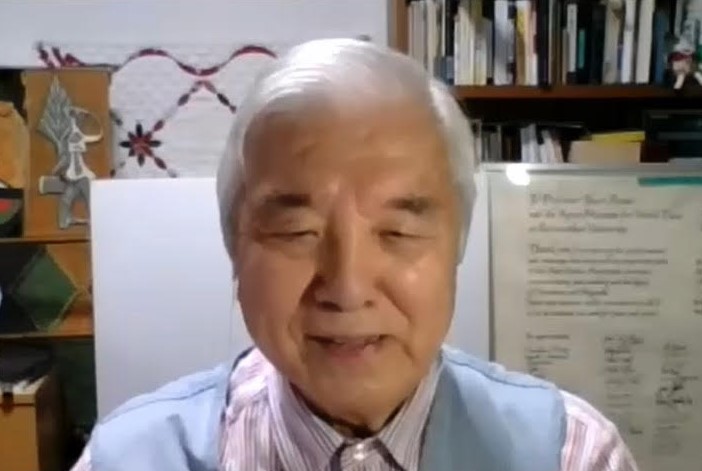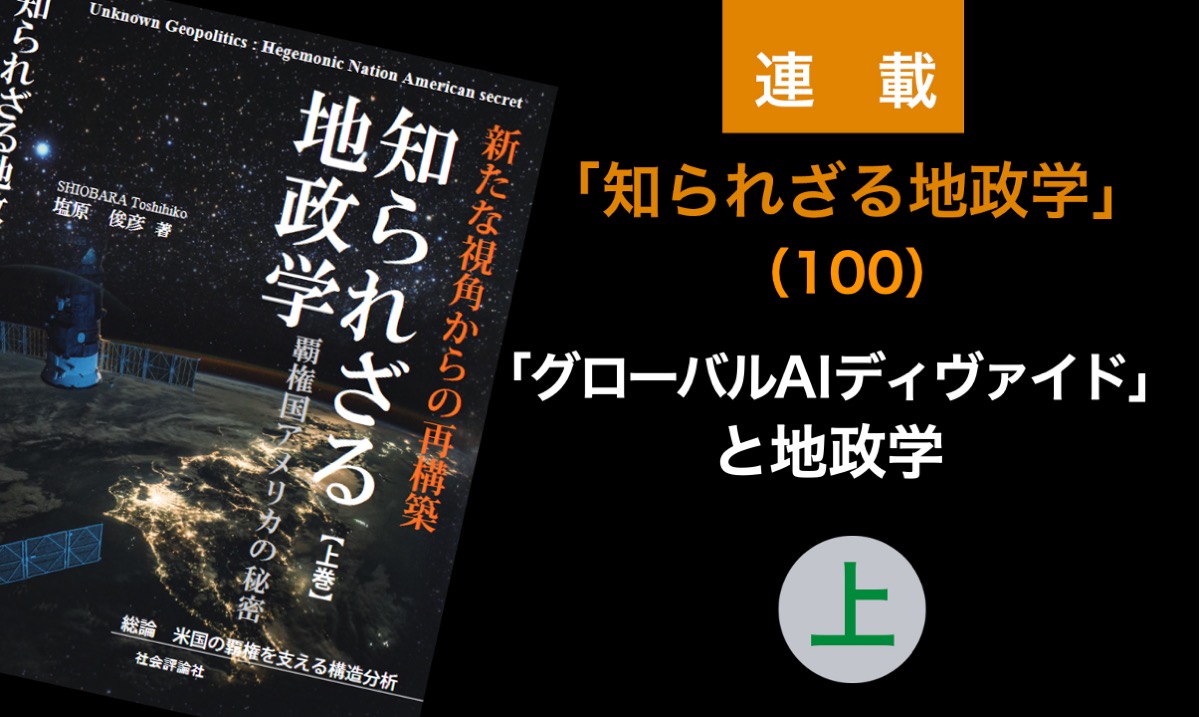
「知られざる地政学」連載(100):「グローバルAIディヴァイド」と地政学(上)
国際
拙著『知られざる地政学』〈上〉において、「「科学技術の推進」⇒「安全性の軽視」⇒「米国の影響力拡大」という過程こそ、米国の覇権の源泉であることになる」(8頁)と書いておいた。そうであるならば、いまもっとも重大な科学技術の一つである「生成AI」、それにつぐ「AIエージェント」に注目しなければならない。前回、この連載で「生成AIをめぐる諸問題」をとりあげたのもこのためだ。いずれにしても、これは、地政学にかかわる大問題だから、連載100回目の今回、詳しく考察することにした。
ただし、残念ながら、この生成AIやAIエージェントに関する知識をしっかりと身につけた日本人はほとんどいないのではないか。ある時点において社会の一部で流行しているにもかかわらず、テレビや新聞といったマスメディアが不勉強であるために、こうしたポップカルチャーを報道しない結果、多くの人々はこの最先端の動きを知らないのだ。
その典型例は、生成AIを利用した動画情報にあるかもしれない。意図的にポップカルチャーを取り込もうとしている「ニューヨークタイムズ」は2025年7月18日付の記事でまず、YouTubeで1600万回以上の再生回数を記録して波紋を呼んだ、AIを使ってドナルド・トランプ大統領やカマラ・ハリス前副大統領らを登場させた動画を紹介した後、ニューヨークのリンカーン・センターで開催された今年の第3回映画祭受賞作を取り上げている。映像からナレーションまで、すべてがAIによってつくられている作品「Total Pixel Space」(下を参照)である。

Total Pixel Space
(出所)https://www.youtube.com/watch?v=zpAeygE4d1A
日本のオールドメディアをこうした努力を怠っている。たとえば、もうすぐ上梓される拙著『ネオ・トランプ革命の深層』の注(139頁)において、私は、「DeepSeek と同じような衝撃を世界に与えたのが2025年3月5日に発表された汎用AIエージェント「マヌス」(Manus)である。開発したのは、武漢を拠点とするスタートアップ企業「蝴蝶効応」(Butterfly Effect)」だ(MIT Tech Review を参照)。ほかにも、アリババは3月6日、DeepSeek と同等の性能をもつという新しい推論モデルを発表した」と書いておいた。
だが、2025年7月21日時点で、朝日新聞のサイトで「マヌス」を検索しても、該当項目はゼロだ。日本経済新聞のサイトでは、さすがに五つの項目が存在する。つまり、朝日新聞はポップカルチャーを取り込み、読者に世界で何が起きているかを報道するという点で読むに値しないことになる。まあ、日経くらいは多少とも読む価値がありそうだが。
生成AIの重要性
前回の連載を書き上げて以降、生成AIをめぐる興味深い記事にめぐりあった。生成AIが重大問題であることを理解してもらうために、ここで三つの記事を紹介したい。
第一は、The Economistが公開した“AI is killing the web. Can anything save it? The rise of ChatGPT and its rivals is undermining the economic bargain of the internet”という記事である。
この記事の核心は、「人工知能(AI)は、人々がウェブをナビゲートする方法を変えつつある」という指摘にある。 ユーザーが従来の検索エンジンではなくチャットボットに問い合わせをすると、リンクをたどるのではなく、答えが返ってくるというのだ。その結果、ニュース・プロバイダーやオンライン・フォーラムからウィキペディアのような参考サイトまで、「コンテンツ」パブリッシャーのトラフィックは「驚くほど減少している」という。
これまで、人々は検索エンジンで単語を入力し、出てきた答え、すなわち個別サイトをクリックして、細かい情報を入手してきた。ところが、生成AIを使って尋ねると、直接、答えが返ってくるために、人は情報を得るために個別のウェブサイトを訪問しなくなる傾向があるということだ。もちろん、生成AIの答えのなかに、関連するウェブサイト情報も含まれているが、それを改めてクリックして確認したり、詳細を知ったりする努力をしない人が多く、結局、個別ウェブへのアクセスが減ってしまうというのである。
これが意味しているのは、オンライン広告を使った収益化の困難だ。そのため、「コンテンツ制作者は、AI企業に情報の対価を支払わせるための新たな方法を早急に見つけようとしている」、とThe Economistは指摘している。
記事によると、「1億以上のウェブドメインへのトラフィックを測定するSimilarwebは、6月までの1年間で、(人間による)全世界の検索トラフィックが約15%減少したと推定している」、と記している。もっとも影響を受けたサイトの多くは、検索に対して一般的に回答しているようなサイトであり、科学と教育のサイトは訪問者の10%を失い、レファレンス・サイトは15%を失ったという。さらに、 「健康サイトは31%を失った」と書いている。
さらに、ニュースについては、もっと恐ろしい事態に陥っている。AIによるオーバービューを開始して以来、ニュース関連の検索でクリックされない割合が56%から69%に上昇したとSimilarwebは推定している。 「つまり、10人に7人が、その答えを提供したページを訪問することなく、答えを得ているのだ」という現状を知ると、もう絶望感しかない。
バカが増える懸念
もう一つの記事は、同じくThe Economistの「AIはあなたをバカにする?」という記事である。実は、拙著『バカ学生よ すべてを疑いなさい』(Kindle版)のなかで、つぎのように書いたことがある。
「ニコラス・カー著『ネット・バカ』という本がある。ぼくは、The Shallowsという、「浅瀬」を意味する、翻訳前の英語の本しか読んでいないけど、たしかに電子情報化はバカを大増殖させるのに一役買っているように思われる。とくに、検索エンジンの発達で、検索を安易に行うようになった結果、研究者の参考文献の参照範囲が狭まる結果をもたらしているという指摘は興味深い。みんな安易になってしまって、ピンポイントで検索しようとするから、検索にかからなくても興味深い関連事項に出会う機会が失われてしまっている。」
これと同じように、MITの研究結果によると、生成AIを利用すると、どうやらバカになるらしい。ChatGPTを使用する学生と使用しない学生を対象に、一連の小論文作成セッションの間、脳波計(EEG)につないで脳活動を測定してみると、創造的な機能や注意力に関連する脳の部位の神経活動が、AIを使用した生徒の方が全体的に著しく低かったというのだ。さらに、チャットボットの助けを借りて執筆した学生は、作成したばかりの論文から正確な引用を行うのが非常に困難であったという。
ほかにも、生成AIを使うと、「頭を使わなくなる」こともわかっている。マイクロソフト・リサーチの研究者が少なくとも週に1回は生成AIを使用している319人の知識労働者を調査したところ、回答者は、長い文書の要約からマーケティング・キャンペーンの設計まで、900以上のタスクをAIの助けを借りて行ったとのべている。
どうやら、ChatGPT、Google Gemini、マイクロソフト独自のAIアシスタントCopilot、Perplexity AI、Jasper Chatのような生成AIツールを多用していると、「浅瀬」で「ちゃぽちゃぽ」するだけの「脳」になってしまいかねないようだ。
生成AIの利用分野
三つ目の記事は、7月14日の「ワシントンポスト」の記事「政府はAIに戦争と税務調査をさせようとしている」である。まず、「米国防総省は今年、AIの開発に邁進している」という。国防総省の中核的なAIプログラムのひとつであるNGA メイヴン(Maven)を使用する軍人と民間人の数は、1月以来2倍以上に増えており、2017年に開始されたこのシステムにおいて、人工衛星や無人偵察機などからの画像を処理し、人間が評価するための潜在的な目標を検知・特定する作業に、現在、世界中の2万5000人以上の米軍および民間人がNGAメイブンを使用している。
5月、国防総省は、「メイブン・スマート・システム」と呼ばれるNGAメイブンの一部であるコアAIシステムへの支出計画を、2倍以上の7億9500万ドル追加すると発表した。
内国歳入庁は、様々な内部用途のためのチャットボットに加え、職員が内部マニュアルを照会するためのAIプログラムをもっている。だが、同局は現在、より重要な業務をAIツールに委ねようとしている。「最終的な目標は、IT、人事などを財務省に一本化し、AIにすべてを任せることだ」と紹介されている。
他方で、米連邦航空局は、AIソフトウェアが管制官を確実に支援できるかどうかをテストしている。また、米国特許商標庁は、特許審査官(特許出願を審査し、その有効性を判断する)の仕事の一部をAIに置き換えられるかどうかをテストしたいと考えている。運輸保安庁(TSA)は空港の検問所での作業の自動化を進めて警備員の数を減そうと、AIの利用をはかっている。
AIスマートフォンの最前線をご存じか
日本のオールドメディアは、ポップカルチャーを無視し、昭和時代から抜け出そうしない姿勢をつづけている。その結果、少なくとも私のような老人のなかで、AIスマートフォンの最新情報を知る者はほとんどいないのではないか。オールドメディアが報道しないからである。
ところが、ポップカルチャーを意図的に取り込もうとしているNYTは7月17日付の記事「アップルのiOS 26とグーグルのアンドロイド16は我々の電話をどう変えるか」のなかで、最先端の動きを報じている。詳しくはこの記事を参照してほしい(なお、かつてこの連載にあるURLにアクセスしても、有料会員でないと記事全体が読めないと苦情を言ってきた読者がいると聞く。そんな読者にいいたい。「タダほど怖いものはない」のであり、「重要な情報に対価を払うのは当然である」と。そして、私がこの連載を100回書くためにどれほど勉強を重ねてきたかを想像してほしい。「善意に基づいて無償で書いている私の連載につまらぬ文句を言うな」と書いておきたい)。
AIエージェントについて
前回の連載で説明しなかったAIエージェントについて、ここで簡単に説明しておこう。AIエージェントは、人間の介入なしにタスクを実行できる自律的な認知システムである。従来のチャットボットとは異なり、タスクを割り当てられた人工エージェントは、リアルタイムで情報を収集・分析し、ソリューションを提供し、作業結果を調整することができる。AIエージェントは、たとえば、金融、物流、セキュリティ、教育など、幅広い分野で活用できる。
「初の自律型汎用AIエージェント」とよべるのが先に紹介したManus AIである(「ノーヴァヤガゼータ・ヨーロッパ」を参照)。たとえば、つぎのようなリクエストをしてみる。
リクエスト:「4月15日から23日までの7日間の日本旅行の旅程をシアトルから手配してほしい。予算は2500ドルから5000ドルで、女性と2人で行く。史跡や隠れた名所、そして日本の文化(剣道、茶道、禅の瞑想)が大好きだ。奈良で鹿を見たり、街を歩いて探索したりしたい。この旅行中にプロポーズするつもりなので、特別な場所の推薦も必要だ。詳細な旅程と、地図、名所、基本的な日本語のフレーズ、旅行中に役立つヒントを記載したシンプルなHTMLガイドを提供してほしい。」
すると、Manus AIは、プロンプトで入力されたすべての希望を考慮して作成された、旅行の日時ごとの詳細なスケジュールを出力する。さらに、宿泊先や公共交通機関の最も有利なオプションの推奨も行われる。これこそが、AIエージェントである。
グーグルの場合、2024年12月11日に「Gemini 2.0」を基にしたAIエージェントのプロトタイプ「マリナー」(Mariner)を発表した(NYTを参照)。基本的に、ユーザーはウェブブラウザにリクエストを入力し、Marinerがユーザーに代わって対応する。2025年2月2日になって、OpenAIは、ワシントンDCの議員や政策立案者、その他の関係者にYouTubeでデモンストレーションを行い、「Deep Research」と呼ばれるAIエージェントを発表した(NYTを参照)。
実は、AIエージェントの主な目的は、企業の業務を最適化すること(結果としてビジネスコストを削減すること)である。このため、バックオフィスの業務を最適化するAIエージェント(「スマート秘書」)、顧客サポートとサービス(「バーチャルアシスタント」)、心理的支援サービス、事前質問と患者予約(「AIレジストリ」)、緊急対応システム(自然災害の被災者となったユーザーの地理的位置を特定するAIエージェント)などで、AIエージェントの活用が想定されている。
ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長は7月16日、法人向け年次イベントでOpenAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)と対談した。その際、孫は自社グループで「10億のAIエージェントをつくる」と表明したが、これは前述のような事情を知っていれば、驚くに当たらない。2024年11月段階の情報で、Virtuals Protocol、MyShell、Theoriq、GaiaNet、Bitte、io.net、Zero1 LabsなどがAIエージェント開発で凌ぎを削っていたことを知っている私のような者からみると、孫の発言は「著しく古い」かつ「遅れている」。
ただし、「AIがビジネスを変えるのは予想よりもずっと遅い。アメリカの国勢調査局による質の高い調査によると、AIを有意義に活用している企業はわずか10%に過ぎない」と、The Economistが報じていることも書いておこう。米国でさえ、ポップカルチャーを取り込もうとするマスメディアがNYTくらいしかない結果、オールドメディア情報に安閑として事態の深刻さを報道してこなかった結果だ。これを考えると、日本のマスメディア報道の「愚劣さ」が国民全体をバカ、マヌケ、アホにしている事情を理解してもらえるはずだ。
それでも、AIが著作権を侵害しつづけるという事態は深刻化の一途をたどっている。ゆえに、米国では、上院議員が著者の訴えを聴き、訴訟が法廷を駆け巡るなか、法案を検討している(「ワシントンポスト」を参照)。日本の国会議員は、日本のオールドメディアの愚劣さのために、問題の所在さえ知らないのだろう。
ついでに、今回の参院選の結果をみて痛感するのは、SNSを知らないオールドメディアに毒されている連中(自民党、公明党、立憲民主党、日本共産党、社会民主党など)の「圧敗」である。2~3年前から、SNS利用というポップカルチャーに関心を払い、内部に取り入れる努力を真剣に進めていれば、こんな結果にはならなかっただろう。
「知られざる地政学」連載(100):「グローバルAIディヴァイド」と地政学(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)