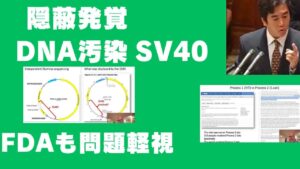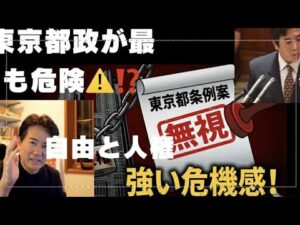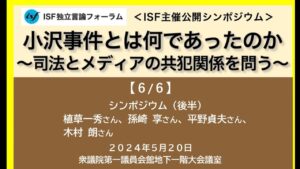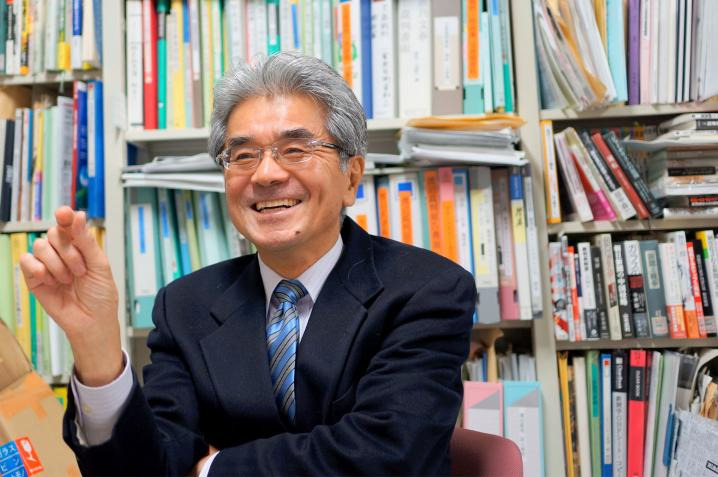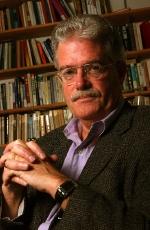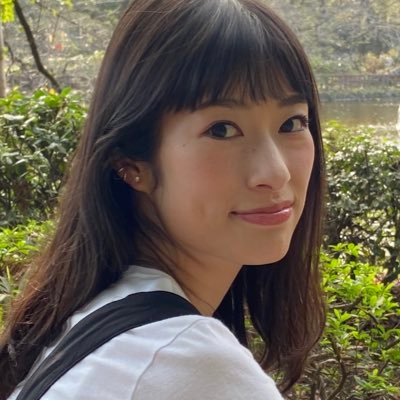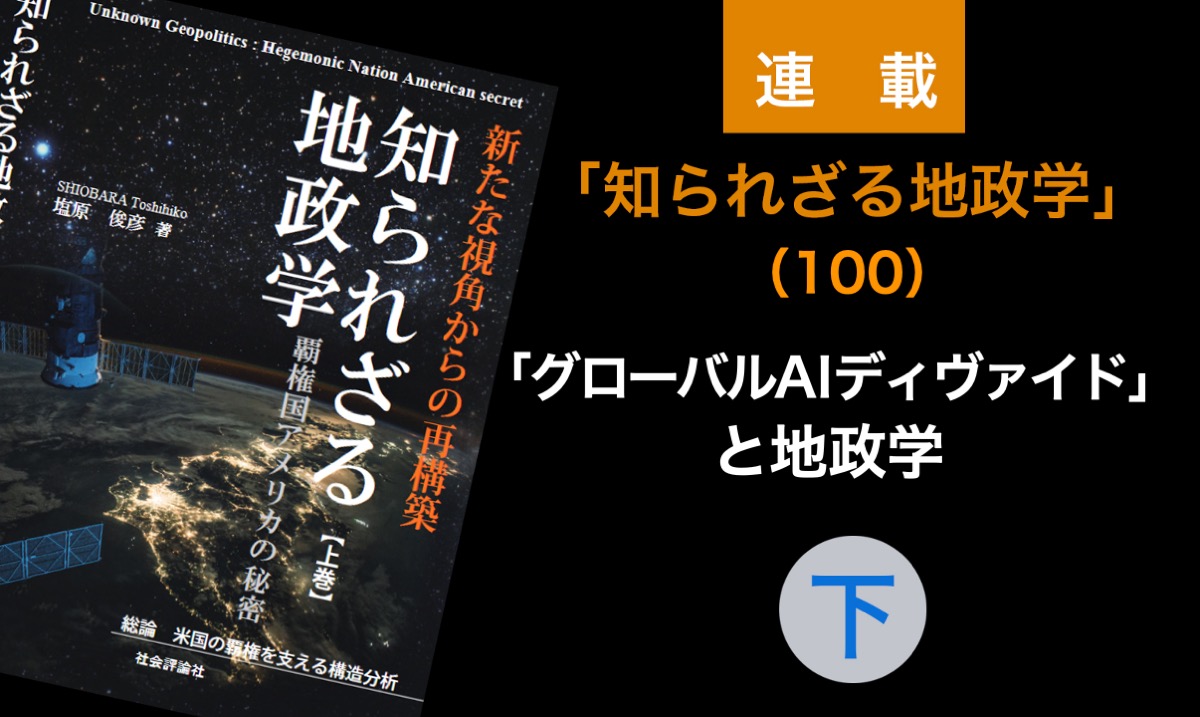
「知られざる地政学」連載(100):「グローバルAIディヴァイド」と地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(100):「グローバルAIディヴァイド」と地政学(上)はこちら
「グローバルAIディヴァイド」
このように、今後、世界は生成AIやAIエージェントの影響を避けることはできない。逆に言えば、この最先端の科学技術をリードできる国家や企業は世界中にその影響力を広げることで一定の力をおよぼすことが可能となる。なお、これは「いいとか」「悪い」といった問題ではない。資本主義はテクノロジーによって企業や人を金儲けに駆り立てるものなのだ。もちろん、それをどう制御するべきかという大問題が残されている(いずれ、この連載でも議論する予定だ)。
別言すれば、「AIは、電力を、想像しうる限りもっとも価値のある生産物、すなわちインテリジェンスに変換する」のであり、「AIのリーダーとして世界的な競争を制する国は、イノベーション、経済生産性、国防の未来を形づくることになる」というThe Economistの記事の指摘はきわめて重要である。もちろん、AIを支配するには、世界トップクラスの科学的専門知識だけでなく、膨大で継続的な電力が必要となる(注1)。
このように考えると、「AIは新たなデジタルディヴァイド(情報格差)を生み出し、最先端のAIシステムを構築できる計算能力をもつ国とそうでない国との間で世界を分断している」というNYTの記事の指摘は正しい。「この分裂は地政学と世界経済に影響を及ぼし、新たな依存関係を生み出し、テクノロジー競争から排除されまいと慌てふためかせている」というのだ。とくに、このテクノロジー競争は、経済を再編成し、科学的発見を促し、人々の生活や仕事のあり方を変える可能性があるだけに、まさに死活問題となっている。そうであるならば、日本もまた、最先端のAIシステム事情を熟知し、その対応策を検討しなければならないはずだ。しかし、私のみるところ、オールドメディアの愚劣さと、能天気な政治家や学者が権威主義的である結果、若者の叡智を抑圧し、日本国としての対応を遅らせている。
なお、これから解説する内容をより深く理解するには、「連載(31)「デジタル帝国」をめぐる地政学」(上、下)を読むことを勧めておきたい。
AIデータセンター
前述したNYTの記事でいう「グローバルAIディヴァイド」(Global AI Divide)は、AIデータセンターの設置によって決定づけられていると主張している。このデータセンターには、最先端のAIモデルを作成・提供するためのコンピューティング・パワーを提供する「グラフィック・プロセッシング・ユニット」(GPU)として知られるマイクロチップを利用できる環境が必要になる。AIの計算処理を高速化するために設計されたハードウェアであるAIアクセラレーターを米国の会社エヌヴィディア(Nvidia)製のGPUが支えている。これにより、従来のCPUやGPUよりも高速にAIの計算を行い、AIアプリケーションにおけるコストを大幅に縮小できる。
いまのところ、現代のAIモデルは、相互接続された多数のGPUとメモリーチップ上で動作する。これらの間でデータを素早く移動させることが、パフォーマンスの中心となっている。実際には、AIアクセラレーター・チップをデータセンターに配備し、開発者やユーザーがアクセスできるようにするハイパースケール・クラウド・プロバイダーがAI利用の鍵を握っているケースが多い。
2025年6月に公表されたオックスフォード大学の研究者らが公表した論文「AIコンピュート主権」によると、AI アクセラレーターは半導体材料からつくられるため、その供給は半導体のサプライチェーンに大きく依存しており、単純化すると、主な工程は設計、製造、流通となる。設計会社Nvidiaは半導体(チップ)の80~95%を設計しており、インテルとAMDは強力なライバルとは言えない。
一方、チップ製造の90%は台湾セミコンダクター社(TSMC)が台湾で行っており、TSMCはオランダのASML社が供給するリソグラフィ装置に全面的に依存している。チップはNvidiaを通じて、世界のクラウド・コンピューティング市場の70%以上を占めるAWS、グーグル、マイクロソフト・アジュールなどのコンピュート・プロバイダに配布される。チップ製造の大部分はTSMCのようなチップ製造請負業者に委託されているが、設計側はライセンス権を保持し、サプライチェーン契約に輸出制限を盛り込むことが多い。さらに、TSMCは設計能力をもたないため、Nvidiaの母国である米国がサプライチェーンを顕著に支配しているとも言える。
クラウド・コンピューティング市場
そこで、世界最大のクラウドサービス・プロバイダー9社の顧客ウェブサイトを調べ、昨年末時点でどのような計算能力があり、どこに拠点があるのかを確認したのが先の論文「AIコンピュート主権」ということになる。対象企業は、米国のアマゾン、グーグル、マイクロソフト、中国のテンセント、アリババ、ファーウェイ、ヨーロッパのエクソスケール、ヘッツナー、OVHcloudである。
論文によると、世界のクラウド市場は、六つのハイパースケール・クラウド・プロバイダー(米国企業のAWS、Google Cloud、Microsoft Azure、中国企業のAlibaba Cloud、Huawei Cloud、Tencent Cloud)に支配され、非常に集中している。
問題は、AIの将来性を重視する見方が広がるなかで、AIコンピューティングリソースへのアクセスおよびそのガバナンスが国家安全保障問題と関連づけられるようになっている点にある。単に、民間企業が米国系のAIコンピューティング・クラウド・プロバイダーあるいは中国系AIコンピューティング・クラウド・プロバイダーを選ぶというわけにはゆかなくなっている。世界各国の法律や政策が企業行動を大幅に制約するという事態になっているとも言える。
Nvidiaの戦略
話題となっているのは、最近のNvidiaの戦略である。Nvidiaは米国政府の規制に対応した、最先端ではない、特別に設計したH20 GPUを対中輸出してきたが、2025年4月、トランプ政権は4月にその販売を停止した。H20には複雑な要求を処理できるメモリが搭載されており、それが中国を利するとみる向きに従った措置だった。
しかし、大統領科学技術諮問委員会委員長で、ホワイトハウスAI・暗号担当長官でもあるデイヴィッド・サックスはAIチップを海外で販売することは米国にとって悪いことだというワシントンのコンセンサスに疑問を呈した(NYTを参照)。さらに、4月にファーウェイが新しいAIアクセラレーター、CloudMatrix 384を発表し、いくつかの指標ではNvidiaの一部商品よりも進んでいるとの評価を受けたことから、サックスはH20の対中輸出停止に反対するようになる。こうして、7月14日、Nvidiaは、同社のH20 の中国での販売が再び許可されると発表するに至る。禁止措置が解除されれば、Nvidiaの今年の売上高は100億~150億ドル、純利益は60億~90億ドル増加する可能性があるという(The Economistを参照)。さらに、サックスは、Nvidiaがサウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)にチップを販売する道を開いた、とNYTは指摘している。
熾烈なテック・ジャイアンツ間競争
もう一つの重要な論点として、いわゆるテック・ジャイアンツ間の熾烈なAI開発競争の展開に留意する必要があると指摘しておきたい。
まず、2025年6月12日、メタがAIシステムを訓練するためにデータを扱う新興企業Scale AIに143億ドルを投資する予定であると発表したことを思い出す必要がある。メタにとっては、約11年前にメッセージングアプリのWhatsAppを190億ドルで買収したのに次ぐ、2番目に大きな取引となる。
同日付のNYTは、取引の条件として、Scale AIの28歳の最高経営責任者であるアレクサンドル・ワンが、メタのスーパーインテリジェンス研究所と呼ばれる新部門のトップリーダーとしてメタに加わる予定だと報じている。ワンはメタ社内で先見の明のあるリーダーと呼ばれており、スケールAIの従業員チームもメタ社で働くことになるという。
この買収劇は、メタ社がグーグル、マイクロソフト、OpenAI、AnthropicといったAIの競合他社に追いつこうと躍起になっている姿を浮き彫りにしている。
6月27日付のNYTの記事「神のような技術を追い求め、マーク・ザッカーバーグはAI競争を激化させる」は、その厳しい状況を物語っている。具体的には、優秀な人材の獲得競争に発展している。グーグルの最高経営責任者であるスンダル・ピチャイとそのAIトップの部下であるデミス・ハサビス、マイクロソフトとOpenAIの最高経営責任者であるサティア・ナデラとサム・アルトマンも、ともに個人的に研究者のリクルートに関与しているという。
これがいま起きている世界の「現実」だ。だが、日本のオールドメディアはこうした「現実」を報道しない。その結果、日本はますます世界の潮流から周回遅れ状態に陥っている。
地政学的視線
ここまでの話を前提にして、実際にどんなことが起きたかを東南アジアや中東についてみてみよう。紹介したNYTの記事「グローバルAIディヴァイド」によると、2010年代、中国企業は米国の重要なパートナーであるサウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)の技術インフラに、公式訪問と手厚い融資によって進出した。これに対して、米国はAIのリードを利用して反撃を試み、バイデン政権とのある取引で、UAEのある企業がNvidiaとマイクロソフトのAI技術を利用する代わりに、中国の技術を排除することを約束した。さらに、トランプ大統領は2025年5月、サウジアラビアとUAEに米国製チップへのアクセスをさらに増やす追加取引に署名した。
他方で、東南アジアをみると、アマゾン、アリババ、Nvidia、グーグル、そしてTikTokのオーナーであるByteDanceといった中国と米国の企業は、アジア全域にサービスを提供するためにシンガポールとマレーシアにデータセンターを建設している。
国家主導のAI開発
こうした「グローバルAIディヴァイド」を是正するために、国家主導で巻き返しを動きが注目されるようになっている。
NYTの記事「グローバルAIディヴァイド」によれば、たとえば、インドでは、政府が計算能力を補助し、その国の言語に堪能なAIモデルをつくろうとしている。アフリカでは、各国政府が地域的なコンピューター利用可能な「ハブ」の協力について話し合っている。
欧州でも、米国企業がデータセンターの大半を支配していることへの懸念が高まっている。欧州連合(EU)は今年2月、27カ国にまたがる新しいデータセンターを含むAIプロジェクトに2000億ユーロを投資する計画を発表した。
さらに、ブラジルはAIプロジェクトに40億ドルを拠出することを約束している。
中国政府の動き
中国では、データセンター、大容量サーバー、チップなどのAIインフラやハードウェアの資金調達に大きな役割を果たしているのは政府である。中国政府はまた、国内のエンジニアの才能を集中させるため、最先端のAI研究の多くが行われる研究所のネットワークに資金を提供し、しばしばアリババやバイトダンスなどの大手テック企業と共同で研究を行っている。
北京はまた、銀行や地方政府に融資を行うよう指示し、何百もの新興企業に資金を供給した。2014年以来、政府は半導体産業を成長させるための基金に1000億ドル近くを費やしており、2025年4月には若いAIスタートアップ企業に85億ドルを割り当てると発表した(NYTを参照)。
アリババやディープシークの本拠地であり、AI人材のホットスポットとして知られる中国南部の都市、杭州の「ドリームタウン」のように、地方政府はスタートアップのインキュベーターとして機能する都市づくりもしている。
懸念される日本の低能化
私が連載100回目のテーマとして、「グローバルAIディヴァイド」を選んだ理由は、ここで紹介したような情報をまったく報道しようとしないオールドメディアのひどさに気づいてほしいからであった。
連載(99)で指摘したように、オールドメディアであっても、ポップカルチャーを取り込む努力をすれば、活性化する可能性がある。周縁にある得体の知れないものであっても、それを中心に持ち込むことで、中心部を活気づかせる契機になりうる。その意味で、NYTのように、意図的に努力して、周縁の文化を読者に紹介することが何よりも求められていると確信している。
こうした努力をしなければ、オールドメディアはますます古臭くなり、相手にされなくなるだろう。そうなれば、すでにさまざまな分野で現れている「日本の低能化」がますます深刻化するだろう。私が書いているこの連載は、まさに「日本の低能化」を食い止めるための「悪あがき」なのかもしれない。
それでも、周縁から中心を眺めることで、中心部の腐敗を炙り出しつづけてゆきたい。ほんの一握りの熱心な読者がいてくれるのであれば。
【注】
(注1)2025年6月24日付のNYTの記事「アマゾン最大のデータセンターでは、すべてがAIのために超大型化されている」からわかるように、AIの利用は大量の電力消費を伴う(といっても、だからこそAI利用の電力省力化がはかられており、日本の電力見通しのような安直な電力需要の拡大が予想通りに起きるかどうかはまったく未知数だ)。ゆえに、Facebook、Instagram、WhatsAppを所有するメタ社は、ルイジアナ州に2ギガワットのデータセンターを建設している。OpenAIはテキサス州に1.2ギガワットの施設を、アラブ首長国連邦(UAE)にもほぼ同規模の施設を建設中だ。アンソロピック(Anthropic)社に80億ドルを投資したアマゾンは、新施設のコンピューティング用電力を新興企業パートナーに貸し出す予定だ。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)