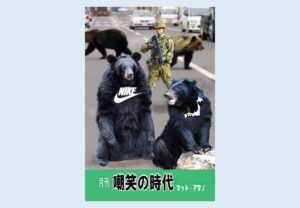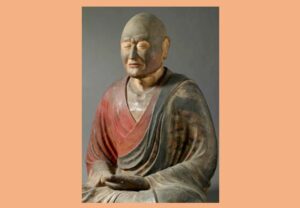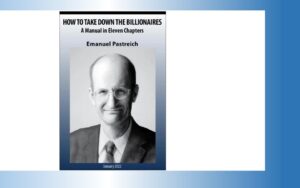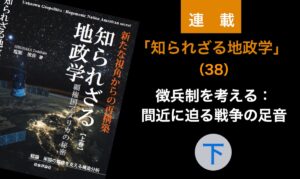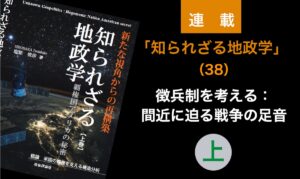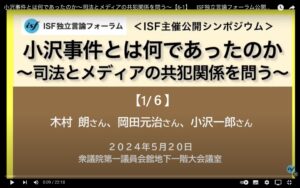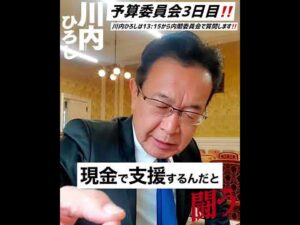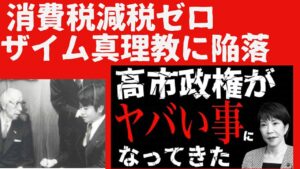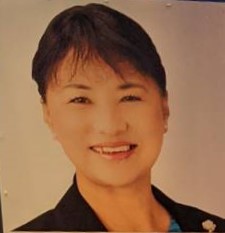登校拒否新聞23号:取り残し
社会・経済6月14日、「誰一人取り残さない」という題で、南日本新聞の記事が発表された。サブタイトルとして「県内初、不登校特例校を設置へ 中学生対象、対人関係のスキル向上めざす さつま町」とある。
鹿児島県さつま町教育委員会は2026年度の開設を予定する宮之城中学校の「学びの多様化学校」(不登校特例校)について、町内の山崎小学校敷地への設置に向けて準備を進めている。独自の教育課程で生徒の社会生活や対人関係のスキル向上などを目指しながら、学びを保障する。多様化学校は増加する不登校児童・生徒の実態に合わせ、柔軟に授業の時数や内容を調整できるのが特徴。文部科学省が全国に設置を促している。県内には現在、中学生が通う多様化学校はない。計画するのは、中学校とは別の敷地に一部の教室を置く「分教室型」。山崎小の特別教室棟内に「山崎分教室(仮称)」を設置し、教職員を配置する予定。何らかの理由で年間30日以上欠席している町内在住の中学生を対象にする。児童との動線は分ける。計画中の教育課程では国語や数学の時数を減らす一方、探究学習が中心の総合的な学習の時間を充実させたり、社会生活技能訓練の教科を新設したりする。町教委学校教育課の井手口勉課長は「誰一人取り残さない学びの保障をベースにしながら、社会的に自立する力を身に付ける場にしていきたい」と話した。これまで不登校の生徒らの居場所になってきた教育支援センターの「ふれあい教室」(宮之城中学校内)、「さつまる~ム」(屋地楽習館内)は継続する。
https://373news.com/news/local/detail/215382/
ヤフーニュースで再配信された記事にはコメントがついている。20件ほどと少ないが、参考になる意見もある。
不登校って、病気で行けないのはどうするのかな?(vbp********)
記事に「何らかの理由で年間30日以上欠席している町内在住の中学生」とあるのは長期欠席の定義だ。いつも言っているように、「不登校」はその理由別分類の一つである。そこで「不登校」とは恣意的に「病気」とは区別されたところに成り立つ概念だ。「発達障害」や「起立性調節障害」といった診断を受ける例が多いことは事実である。もちろん、そういう診断を疑う向きもあるけれども、診断を受けた例を「病気」とは区別して「不登校」と概念化することはムリがある。安定剤を処方してもらうために精神科に通院しているのなら欠席理由は「病気」でもいいわけである。うつ病による教員の休職は認めるくせに不定愁訴による子どもの長期欠席は認めないというダブルスタンダードが「不登校」という問題をでっち上げている。
その概念の恣意性が「国語や数学の時数を減らす」ことを当然とするのだ。つまり、「不登校」の子が通学する「学びの多様化学校」(旧不登校特例校)では勉強時間を減らすことが通例となっている。「学び」の保障は勉学の削減を代償とする。
記事には「分教室型」とある。制度上、分教室というのは昔からある。戦後も、いわゆる僻地校などが分教室という仕方で存在していた。それも統廃合などにより数を減らした。それが今になって、「不登校特例校」改め「学びの多様化学校」として復権している。
けれども――、
良い取り組みと思われますが鹿児島は教員の数が充実しているのでしょうか?(ken********)
教育内容と教員の質を担保できないフリースクールへ税金投入するのは反対ですが、こういう取組みは良いと思います。今や、中学生15人の1人が不登校らしいですから、全国で必要なんじゃないでしょうか?(kig********)
こういうの流行りで「善」とされるから夜間中学なんかも含め全国で展開されてきている。厳しいこと言うけど、こうやって後手後手でどこまで支援続ければいいわけ?「教職員を配置し」?どこにそんな教職員いるの?現場が超過酷だからそれは嫌なペーパーティーチャーを掘り起こすわけ?いいね!って思ってる人、こうやってどんどん税金が流れ込んでいって自分たちの生活はますます苦しくなるからね?「フツーのこども」(大人も)だけがますます我慢を強いられていくんだよ?1クラス40人も突っ込まれてる国、こんなの「教育水準が低い国」か「子供を成績でしか評価しない詰め込み教育の点数主義の国」だけだよ?日本はいつまでこれを続ける?予算があるならまず1クラスの子供数を減らし、先生を増やし、苦しんでいる子供を発見しやすくし、社会性と適度な学力を身につける学校生活を全こどもが遅れる教育を目指すべきでしょう?(sh******)
実際のところ、南日本新聞でも「先生のなり手不足、どうすれば解決?受験年齢引き上げた、試験前倒した…それでも倍率は右肩下がり」という記事が配信されている。6月8日付だから、上の記事の1週間前のことだ。
https://373news.com/news/local/detail/214823/
地教委の学校教育課の課長は「誰一人取り残さない学びの保障をベースにしながら、社会的に自立する力を身に付ける場にしていきたい」と言っていた。「誰一人取り残さない」という記事の題もここから取ったのだろう。しかし――、
誰一人取り残さない。きれいな言葉だけれど、どういった意味として考えればいいのだろう?「取り残す」ってどういうこと?やる気のない者と能力のない者を同じように扱うということ?能力のない者はいいよ。かけ算ができない…という感じだろうから。むしろ、やる気のない者の対応だよ。やる気のない者のために、やる気のある者が我慢をするのはそれこそやる気のある者たちが「取り残されて」いないのだろうか。(mhp********)
やや、うがった見方だが、学校哲学を謳う登校拒否新聞の読者投稿欄にはふさわしい意見だ。かつて、「落ちこぼれ」は「落ちこぼし」という標語が流行った。教育という営みは教育者を主語とする論理がまかり通る。「取り残さない」というのも主語は教育者だ。この意見が問題にしているのは「取り残し」とでも言うべきか、そこで取り残される者は誰か、ということだ。それが「やる気のない者」なのかは別として、「取り残さない」という教育者の論理において客体とされる子の存在は問うてみる必要がある。
うちは娘二人共、中学校に行かず家でYouTubeを見てる。最初は自分から隠れてたけど、「行きたくないなら行かなくていい、気が向いたら行きなさい。」と言ったら、もう隠れなくなった。やはり親としては対人関係や勉学が気になるが、後々後悔するような事があるくらいなら、家に居てほしいと思う。情けない親なのかもしれない。そういう子供達と向き合ってくれる学校が全国に出来てくれたら嬉しい。(njh********)
ここに「勉学が気になる」とあるのが気になる。「不登校支援」なる営みは「多様な学び」を圧しつけてくる。「勉強」はおろか「勉学」などという言葉は禁句だ。その結果、取り残されるのではないか。
ちなみに、南日本新聞では「県が初の実態調査、年内にも支援策の方向提示」という記事が5月3日に公開されている。
鹿児島県は2日、不登校の子の居場所に関する初の実態調査結果を公表した。回答した県内の児童生徒555人のうち、フリースクールなどに「行っている」と答えたのは23.4%で、いずれの施設にも行っていないのは21.4%だった。調査は支援ニーズを把握するため昨年12月〜今年2月に実施。対象は小中学校、義務教育学校、高校、特別支援学校に在籍する長期欠席者(30日以上)と、その保護者、フリースクールなど居場所になっている施設。回収率は児童生徒10.5%、保護者12.7%、施設28%だった。児童生徒は中学2年生が20.7%を占め最多だった。不登校の間、フリースクールや放課後等デイサービスに「よく行っている」が13.8%、「ときどき行っている」10.1%だった。
https://373news.com/news/local/detail/213251/
この後、8日に公開された「GW明けに増える不登校」という記事には「鹿児島県教育委員会によると、2023年度に不登校になった県内公立小中高校の児童生徒は計5,432人。いずれも前年度を上回り、6年続けて最多を更新した」とあるので、たしかに555人という数字は回収率にして約10%だ。もちろん「行っている」と答えるタイプのほうが回答者の中には多いはずだから、現実には「いずれの施設にも行っていない」というタイプのほうがずっと多いはずだ。
https://373news.com/news/local/detail/213522/
いつも言っているように、「居場所」という概念は塾を含まない。あくまでフリースクールが原型であるから、塾は排除されている。そこに最近ではデイサービスが加わった。この調査では高校生も対象としているのだから、予備校も含めて調査対象とすべきであろう。なぜ学校に行かずに塾に通っていてはダメなのか、その問いをスルーしたところに「不登校」という問い立ては成り立っている。「取り残さない」という教育者の論理のメタ論理として塾は学校にあらずという前提がある。「長期欠席者(30日以上)」という数量的に定義される子の存在と「不登校の子の居場所」という場合の子の存在とは概念的に異なっている。そこを一跨ぎに跳ぶ力が「不登校」というコトバにはある。
調べて見ると、鹿児島県には村立の義務教育学校が多い。これも僻地校の現代的な形態だろうか。その半分が鹿児島郡の島にある。この記事では区別されていないが小中一貫校も2校ある。学校統廃合の結果、地方ではこのような学校が増えることが予想される。「中1ギャップ」の解消というような都市部のそれと違って、教職員の定数削減がそうさせる。僻地校を義務教育学校・小中一貫校として、分教室を「学びの多様化学校」として、上は一貫教育、下は「居場所」と学校間格差は広がる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。