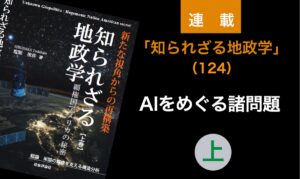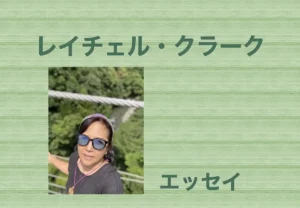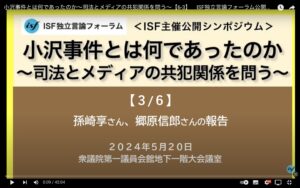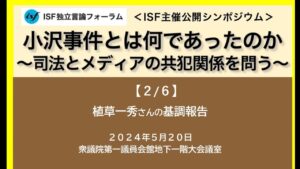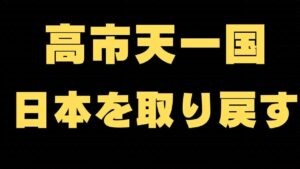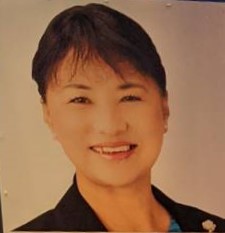米国政府による「気候危機」批判の報告書 松田 智(市民記者)
社会・経済7月23日に、米国エネルギー長官の指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が出された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー」である(https://www.energy.gov/topics/climate)。
日本などで支配的な論説は「人類起源のCO2が地球温暖化を招き、それが暴走して気候危機に陥るから、2050年までにCO2排出をゼロにすべし!」と言った内容だった。しかし、これまで私も指摘してきたが、実はこの説には科学的な根拠がない。そのことをこの報告書は各種データに基づいて説得的に述べている。つまりこれは、気候危機論者に対する、米国政府による公式の挑戦状とも言える文書なのである。
著者はスティーブン・クーニン、ロイ・スペンサーら5人の科学者で、私は彼らの仕事を紹介・引用したことがあるが、いずれも大勢に抗して敢然と気候危機説に異を唱え続けてきた人たちである。こう言う人たちに政府の公式報告書を書かせるあたりが、米国と言う国の「懐の深さ」というべきかも知れない。日本では、まず考えられない事態だ。
実は、キャノングローバル戦略研究所の杉山大志氏によって、本報告書の詳細な内容紹介が既になされつつある(https://agora-web.jp/archives/250803021714.html)。本稿はその後追いではあるが、ISF読者の便を考えて、敢えて簡略化した紹介を試みる。
まず、本報告書は内容的には全13章に分かれており、気候危機説に関する問題点がほぼ全部網羅されている。以下、各章の概要を記す。
第1章では、CO2はいわゆる汚染物質ではないこと、それには植物の生育を促進するなどの直接的な効果と、温室効果ガスとしてふるまうという間接効果があることを説明している。実は米国環境保護庁(EPA:日本の環境省に相当)が以前に「CO2危険性認定」なる文書を発表していたが、本報告書の発表と同時に、トランプ政権はこのEPA認定を撤回する提案を発表している。なおこの件に関しては「CO2を悪者扱いすることの愚かしさ」との論説を私はISFにも載せたので参照されたい(https://isfweb.org/post-47348/)。
第2章では、大気中CO2の直接的な効果として「地球緑色化」に焦点を当てている。すなわち大気中CO2の増大は、光合成を高めるという「施肥効果」によって、地球上の植物を繁栄させてきた。このCO2がもたらす生態系への便益は大きなものだが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)などの既往の報告では扱いが極めて乏しかった。しかし衛星観測によって地球表面を植物が覆う割合を定量的に測定できるようになり、現在ではその効果が明確に実証できている。その詳しいデータが紹介されている。
第3章では、CO2 のもう一つの直接的効果として「海洋酸性化」を論じている。用語として「海洋酸性化」は不適切で、むしろ「海洋中性化」というべきである。というのは、海水は弱アルカリ性であり、CO2はそれをやや弱くするだけだからだ。実際の数字で示すと、1985年には8.11だった海洋pHは2022年までに8.03まで低下した。37年間で0.08の低下に過ぎないし、このまま進んで海水が酸性(pH7.0未満)になるとは予想されていない。さらに、仮に海水が酸性になったとしても、海洋の生命はpH6.5から7.0のやや酸性な環境で進化したと考えられている。要するに、この海洋中性化に大きな問題があるとは考えにくい(IPCCの2100年予測でも、海洋pHは7.8程度までしか下がらない)。
第4章では、人間活動による温室効果ガス(とエアロゾル)が地球の気温上昇を司る支配的な要因であるというIPCCの説に有力な疑問を投げかける。太陽活動の変化や大気・海洋などの内部変動の寄与は無視できないほど多いという論文が紹介される。またIPCCが環境影響評価に用いるシナリオの排出量が非現実的に多すぎるため、環境影響が過大に評価されていることも指摘する。
第5章では、CO2がどの程度気温を押し上げるか――いわゆる気候感度(ECS/TCR)が議論される。IPCCが示す範囲よりも気候感度は低い、つまりCO2が排出されてもそれほど気温は上昇しない、という論文が紹介されている。
第6章では、IPCCが用いる気候モデルの性能検証を行う。気候モデルは過去の再現にも大きく失敗している。観測データに比べて全般的に気温が上昇しすぎる傾向が顕著であり、また、南北半球の反射率が大きく異なるなど、観測データに合わない出力になっている。これでは将来予測も信頼に足らず、政策決定のツールとして使い物にならない。
第7章では、「災害の激甚化」は統計的に何ら確認されないことが示される。すなわち、暴風雨や干ばつなどの長期トレンドに有意な増加はない。既往の米国政府報告では、気温上昇について、都市熱の影響を除いていない、といった問題点があったことも指摘する。
第8章では、海面上昇について述べている。海面水準は19世紀末から直線的に上昇しており、潮位計のデータは「海面上昇の加速」を示していない。また、局所的に海面上昇が速い地点はあるが、それは主に地盤沈下の影響によるもので、CO2に起因する地球規模の海面上昇の影響は小さい。日本では、南の島ツバルが沈むのは温暖化のせいだと信じている人がまだ多数いるようであるが、ツバルの海水面変化の実際を知らないのである。
第9章では、猛暑や大雨などの個々の異常気象を「CO2のせい」と断定する「事象帰属研究(イベント・アトリビューション研究:EA)の誤りについて論じている。米国での熱波を「CO2排出が無ければ起こりえなかった」とした研究発表は、その後完全に誤りだったという事例も紹介されている。
第10章では、CO2濃度上昇が光合成を促す「施肥効果」によって食料増産をもたらしてきた歴史的実績を紹介する。米国主要穀物の収量は1940年代以降、50~80%押し上げられたと推計されている。今後についても、CO2濃度上昇は、それがかなりの気候変動を起こすとしても、食料生産にとって純便益になるとされている。
第11章では、人命や経済の災害リスクは、気候変動で悪化するどころか、時間とともに減少してきたことを紹介している。GDPあたりの災害損失は技術革新とインフラ整備のお陰で大幅に軽減した。暑さによる死亡数も、住宅の改善とエアコンの普及で激減してきた。安価な電気を供給することが、今後、貧困者の暑さによる死亡リスクの軽減に重要であると論じる。
第12章では、炭素の社会的費用(SCC)は、費用と便益の評価や割引率の設定などにおいて、不確実性が高く、政策決定に用いるべきではない指標であることを詳述する。
第13章では、CO2は従来型の大気汚染対策とは本質的に異なる問題であり、米国単独で排出を削減しても全球平均のCO2濃度には測定不能なほどしか影響しない、と結論づける。
最後に、13章のラストのパラグラフを翻訳しておこう。この報告書全体についての、良いまとめになっている。
“この報告書は、不確実性を明示的に認めた、より精緻で証拠に基づいたアプローチで気候政策に対する知見を提供します。自然要因と人間活動の両方による気候変動のリスクと便益は、信頼性が高く手頃な価格のエネルギーの確保と地域汚染の最小化という国家のニーズを考慮した上で、あらゆる「気候行動」の費用、効果、付随的影響と天秤にかける必要があります。地球の気候システムに対して精密で継続的な観測をすることに加えて、将来の排出量に関する現実的な仮定を立て、気候モデルの偏りや不確実性について再評価を行い、極端な気象の帰属研究の限界について明確に公表することが重要です。CO2の潜在的なリスクと便益の両方を認めるアプローチは、欠陥のあるモデルや極端なシナリオに依存するのではなく、情報に基づいた効果的な意思決定に不可欠です。”
日本でも、このような科学的知見に基づいた議論が交わされることが望ましいが、現状の学界・マスコミ状況では望みが薄い。物事を正確に見ようとしないで固定観念にしがみつく人間が多すぎるからだ。国会で今のところ、脱炭素に批判的なのは参政党しかいないが、気候危機説批判が参政党の専売特許になってもらっては困る。本来なら、すべての会派が率先して「科学的」に気候危機説を批判すべきであるから。
私は2021年5月に「2050年までの脱炭素社会の実現」を明記した改正地球温暖化対策推進法が全会一致で可決、成立した際に、「『50年脱炭素法』に意味はあるのか」と題した論説を書き(https://agora-web.jp/archives/2051659.html)、その中で「国会議員諸氏は、これらの問題をどの程度真剣に検討して「脱炭素社会法」に賛成したのか、ぜひお考えを伺いたい。まさか「皆がそう言っているから・・」とは言わないですよね?」と書いたのであるが、返事をくれた国会議員はむろんただの一人もいなかった。あれから4年以上経ち、世の中は変転して、米国政府が率先して人為的地球温暖化説に批判的な報告書を出す時代になった。さて、日本の国会では、どんな議論がなされるのであろうか?
☆ISF主催トーク茶話会:松田智さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 松田 智(市民記者)
松田 智(市民記者)
まつだ・さとし 1954年生まれ。元静岡大学工学部教員。京都大学工学部卒、東京工業大学(現:東京科学大学)大学院博士課程(化学環境工学専攻)修了。ISF独立言論フォーラム会員。最近の著書に「SDGsエコバブルの終焉(分担執筆)」(宝島社。2024年6月)。記事内容は全て私個人の見解。主な論文等は、以下を参照。https://researchmap.jp/read0101407。なお、言論サイト「アゴラ」に載せた論考は以下を参照。https://agora-web.jp/archives/author/matsuda-satoshi