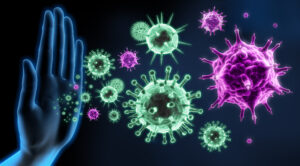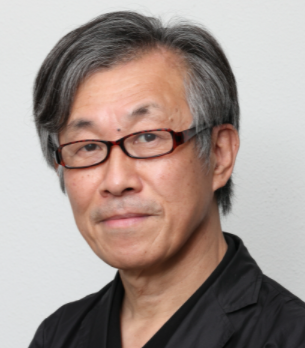故意か不勉強か、酷すぎる日航123便関連のマスコミ報道
社会・経済メディア批評&事件検証8月11日の朝日新聞に載った日航123便に関する「ファクトチェック」は、その名に値しないものだった。それは単に、一方の意見だけを取り上げ、客観的証拠と反証の提示もないまま「誤り」と断定しているからだ。早速、青山透子氏のブログ(https://tenku123.hateblo.jp/)で取り上げられ、抗議文が掲載された。また読売新聞も13日の記事で周回遅れの情報収集に基づく偏向報道を行っており、同ブログで再びやり玉に挙げられている。また新聞だけでなくTV報道も酷いものだった。私が視聴したのはTBSの「News23」とNHKの「時論公論」の二つだが、これらについて論評したい。
まず「News23」では、当時、茨城県の百里基地から発進した自衛隊機に乗っていたとするパイロット2名が出てきた。その日の19時15分には墜落現場付近に到着していて、19時20分には現場から火が出ているのを見たと言い、当時の写真まで見せていた。つまり19時20分には墜落現場の確定が出来ていたということだ。それならば、当日、墜落現場に関する報道が二転三転し、結局は夜が明けてから現場が確定されたのは何故だったのかを問わないといけないはずだ。少なくとも、当時の報道ぶりの実態を振り返り、検証する必要があるはずだろうに、番組の小川彩佳キャスターらは何も問わない。この辺で、すでに私の中では違和感だらけだった。
それにこの番組に限ったことではないが、墜落原因が圧力隔壁破壊だと決めつけ、それに対する異論を「陰謀論」と呼んで憚らない。これもまた、偏狭で一方的な見方と言わざるを得ない。
圧力隔壁に関しては、ボーイング社の修理ミス問題ばかりが取り上げられているが、これはそもそもピントがずれている。理由は大きく3つあり、1)圧力隔壁の破壊自体、起きた証拠がない、2)圧力隔壁の破壊で垂直尾翼の破壊は起きない、3)垂直尾翼破壊は123便墜落の直接的な原因ではない、の3点である。
まず理由1)。もし高度7000mで圧力隔壁が壊れたら、機内との差圧は0.3気圧に達するから、機内は急激な気圧低下が起こり猛烈な風が吹く。地上の最強台風でも中心気圧が900hPaを割ることは稀だから、差圧はせいぜい0.1気圧だ。それでも、とんでもない強風が吹く。0.3気圧と言えばその3倍だから、想像を絶する強風が機内を吹き荒れる。乗員乗客は、とても無事ではいられない。しかし機内の写真を見ると、全員平静で、降りてきた酸素マスクに手を伸ばしたりしている。また4人の生存者たちにも、鼓膜の損傷などは確認されていない。つまり、圧力隔壁が壊れてその時に発生した強風で垂直尾翼が壊れたとする説は、状況証拠的に、どうにも成り立たない。
それに、理由2)、垂直尾翼は密閉構造でないから空気が自由に出入りでき、たとえ強風が吹いたとしてもそれが原因で壊れることはあり得ない。
また理由3)。垂直尾翼破壊が起きたのは18時24分35秒のことだが、123便が墜落したのは同56分10秒頃、つまり異常事態発生後32分間も同機は飛び続けている。そして18時55分45秒に重大な異常事態が起きて、機長らが「アーッ」という絶叫を残している。フライトレコーダー記録でも、この時に突然強い横揺れ衝撃を受けたことが分かっている。その後機体はバランスを崩して急降下し、1分も経たないうちに墜落している。つまり、直接の墜落原因は18時55分45秒に起きた「異常事態」である。この時、第4エンジンが脱落し水平尾翼も落ちてしまったことが判明しているが、この時に何が起きたのかは解明されていない。突然の強い横揺れなので、何かが機体の外からぶつかった可能性が最も強く考えられるのであるが。
しかも念の入ったことに、その圧力隔壁は墜落現場で数個に「切り分けられて」いたと言う衝撃の事実がある。現場で最初に発見されたとき、この部品は「五体満足」の姿だった写真が残っているからだ。自衛隊は、事故原因の本命とされた部品をわざわざ切り裂くと言う「蛮行」をしているわけだし、警察や事故調査委員会がそれをなぜ許したのか理解困難だ。航空事故に限らず、事故があった場合は現場や部品の確保が最優先される筈なのに。
結局TBSのNews23は、こうした重大問題を扱うこともせず、ただ「陰謀論」に負けないようにしたい、みたいなことだけで済ませてしまった。情けない報道と言うしかない。小川キャスターは「正確な情報に立脚して報道したい」などと言っていたが、それならまず勉強することがもっと沢山あるはずだ。彼らは本来知っていなければならないことに対して無知すぎる。その「無知」が、意図的なものかどうかは分からないが。それは実際には日航113便関連に限らず、温暖化・脱炭素やウクライナ、コロナ、消費税関連など、一連の報道統制問題と関わるのである。
NHKの「時論公論」でも123便事故を取り上げていたが、これまた圧力隔壁説しか取り上げておらず、さらにはパイロットの訓練が必要などというピンボケ話をしていた。その前提には、123便は操縦不能になって、パイロットたちは何もできずに迷走の末に墜落したとの思い込みがあるからだ。恐らくこのNHK解説委員は、事故調査報告書に「機体は操縦不能の状態に陥り、乗員たちは何も出来なかったから無事な生還は困難だった」と書かれているのを鵜呑みしている。しかし、実際は違う。
乗員たちはエンジン出力の調整と手動操舵(電気で動かす)だけで機体を操り、32分間も飛んで横田基地に着陸寸前だったのだから、操縦不能であったはずがない。亡くなった乗客の遺書にも「機体は、今は静かだ」との記述がある。異常事態が起きた当初はダッチロールしていた機体を、後には制御できるようにクルーは努力してそれに成功したからだ。実際に123便の飛行経路を見ても、大月市上空で旋回しながら高度を下げて着陸態勢に入ろうとしたことが分かっている。彼らは不自由ながらも機体を何とか操っていた。
そして18時55分45秒に起きた「異常事態」によって機体がバランスを崩し絶望的な状況になってもクルーは最後まで全力を尽くして機体の立て直しを図った形跡がある。そのまま山の斜面に直角に激突したら全員即死は確実だったが、機長らは機首を持ち上げて斜面とできるだけ平行になるように墜落直前まで努力した。その結果、機体は山の斜面に斜めにぶつかり、機体の胴体は大きく5つに分かれて、前半部分は大きく損傷したが、後半部、特に最後尾部分はちぎれて山の斜面を滑り落ち、スゲの沢と呼ばれる地点で止まった。生存者4名は全員そこで発見されている。後の検死結果でも、墜落直後ならば生存者がもっと多かったはずだとの見解が示されている。つまり、機長らの努力は無駄でなかったことになる。彼らの努力はもっと強く讃えられるべきだ。
もう一つ重要な事実は、事故調査委員会が2013年9月に公表した資料に「異常外力の着力」が明記されているのに、報道では全く触れられていないことだ。具体的には、「62-2-JA8119(航空事故調査報告書付録)(JA8119に関する試験研究資料)(https://jtsb.mlit.go.jp/aircraft/download/62-2-JA8119-huroku.pdf)と言う文書だ。ここに「異常外力着力」が明記されている。123便の外から11トンもの異常な外力が着力したと書かれ、機体のどこに着力したかも図示されている。それは垂直尾翼の、まさに「ど真ん中」である。これこそ、圧力隔壁破損説を覆す、重要な科学的根拠であるのに、マスコミは完全無視を決め込んでいる。これはどうしたわけなのだ?新事実が発見されたなら、それを大きく報道し、墜落原因の再調査を求めるのがジャーナリストの当然の務めではないのか?一体、誰に「忖度」しているのやら。
私の見立てでは、要するに大手マスコミはこぞって日航・国交省の言いなりの報道をしているのだ。一種の報道統制と言って良い。事実に基づいた指摘は何もない。政府の事故調査報告書だけを間違いのない事実と受け止め、それに対する批判的な検討をしようとしない。戦前の大本営発表に対する翼賛報道と、少しも違わない。日本のジャーナリズムは、これへの反省から出発したのではなかったか?戦後80年経つと「何事も学ばず、何事も忘れず」の旧貴族たちと同じになってしまうのだろうか?
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 松田 智(市民記者)
松田 智(市民記者)
まつだ・さとし 1954年生まれ。元静岡大学工学部教員。京都大学工学部卒、東京工業大学(現:東京科学大学)大学院博士課程(化学環境工学専攻)修了。ISF独立言論フォーラム会員。最近の著書に「SDGsエコバブルの終焉(分担執筆)」(宝島社。2024年6月)。記事内容は全て私個人の見解。主な論文等は、以下を参照。https://researchmap.jp/read0101407。なお、言論サイト「アゴラ」に載せた論考は以下を参照。https://agora-web.jp/archives/author/matsuda-satoshi