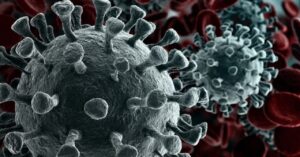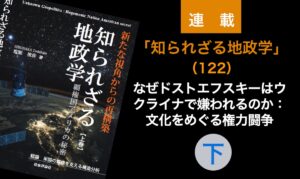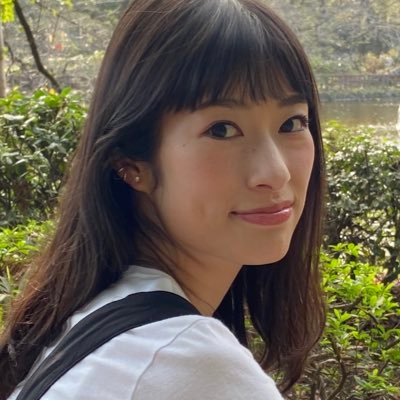ニッポン核武装モウソウの脳天気―ウクライナ戦争でウカレたウソつきどもが吠(ほ)える―
政治
図1:阿米住血吸虫
2022年2月下旬、ロシアのウクライナ軍事侵攻が勃発(ぼっぱつ)するや、日本ではその週末に、1年半ばかり前に政権を投げ出して遁走(トンズラ)した安倍晋三がフジテレビ日曜朝の政権宣伝番組で(米軍の核兵器を日本に配備する)「核兵器の分担保有(シェアリング)を検討すべし」と声高(こわだか)に吠(ほ)えて“ニッポン核武装”を唱えた。
しかし現実的な核武装の可能性を考えれば、現在の“ニッポン國體(こくたい)”では不可能で“改憲”必須であるのは無論のこと、それこそアベのような民族主義者を粛清(しゅくせい)して、欧米並みの“民主主義国”に国家改造しなきゃ“核兵器共有”なんぞ米国が許さないだろうし、日本が“核武装”したところで最悪の場合は“米国挑発による核戦争”の砂袋(サンドバッグ)にされるのが落ちである。日本はホントに核武装が必要なのか?
「核シェアリング」論は国家の安全保障を破壊する罠である。
・近代国家ニッポンの歴史は、ロシアを無闇(むやみ)に恐れて憎悪する不条理な歴史だった
2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻した。
ふだんはウクライナが世界地図のどこにあるのかすら知らない島国ニッポンの“マスコミ漬(づ)け国民”が、「巨大熊のように獰猛(どうもう)なロシアが、小さなウクライナにいきなり戦争を仕掛(しか)けたのは許せない!」と条件反射的に憤慨(ふんがい)したのは、呆(あき)れるほどに、ありふれた、恍(とぼ)けた反応なのであるが、実際には、これは愚かで悲惨な感情的反応に他ならない。だが良くも悪くも“平和ボケ”したニッポン国民大衆が、ロシアを“歌舞伎芝居の悪役”、ウクライナを“悲劇の主人公”と見立てて、「ロシア憎し!がんばれウクライナ!」と黄色い声援を上げたとしても、アメリカに洗脳された島国根性ゆえに、こんな愚劣な反応しか、せざるを得なかったわけだ……。
大多数のニッポン人は、徳川江戸幕府が経験した「開国」に至る西洋列強との外交の実情なんぞ知らないから、「中国人に行なったのと同様に、日本人に対しても、恐怖に訴える方が、友好に訴えるより多くの利点があるのだ」という“外交方針”で日本に来航したマシュー・ペリー提督率(ひき)いる米国海軍・東インド艦隊が(ちなみに浦賀来航は1853年7月8日、すなわち今からキッカリ169年前だ)大砲をドンパチ打ち鳴らし、地方の陣地には砲撃して徳川日本側をパニック状態に追い込むなど、“強姦(ごうかん)”まがいのやり方で日本を「開国」させたアメリカ合衆国よりも、むしろ日本の(シナ由来の)伝統文化のなかで“鬼門”として迷信的に恐れられてきた“艮(うしとら)”の方角から、ノッソリと姿を現わしたロシアを兎角(とかく)怖(こわ)がるという、歴史的文化的に歪曲した“民族感情”を持ち続けてきた。
今から130年ばかりまえ(1891年5月11日)、ロシアのニコライ皇太子が訪日して滋賀県大津を行啓(ぎょうけい)した際には、護衛の地元警察官が皇太子を斬(き)りつけて重傷を負わせるという“不敬の極み”の襲撃事件、「大津事件」が起きた。
1904~05年の「日露戦争」では、両軍ともども継戦困難なドン詰まりの状況に追い込まれて、米国政府の仲介で講和会議を行なった結果、ともかくも日本が「勝利」した形で話がまとまったけれども、政府とマスコミの民心宣撫(パブリックリレーション)にスッカリ騙(だま)されて「日本軍が大勝している」と信じ込んできたニッポンの民衆は「対露講和(ポーツマス)条約」での日本側の“収獲”が予想外に少ないことに憤慨(ふんがい)し、東京日比谷で開かれた「講和条約」反対集会での警官隊の不当介入をきっかけに、東京の各所を広域的に破壊してまわる都市暴動、すなわち1905年9月5~6日の「日比谷焼き打ち事件」を起こした。組織的暴力と刀剣(サーベル)による威嚇(いかく)で抗議集会を解散させようとした警官隊の横暴に、怒った群集は、交番や、会場ちかくの内務大臣官邸を焼き打ちして路上電車をひっくり返し、それまでは調子のいい“イケイケ軍報”で「戦況は絶好調!」だとウソをつき続けて「敵国ロシア憎し!」と憎悪感情を煽(あお)ってきた政府系の御用新聞社――すなわち「日清戦争」以前は「平民主義」だったが、その後は“帝国主義”的な“対外拡張主義”を煽動していた、徳富蘇峰(とくとみ・そほう)の発行による『国民新聞』であるが――を焼き打ちにしたのち、都内あちこちの交番の襲撃に及んだのである。
皮肉なことに、日露戦争の因果で、ロシアでは民衆が“帝政”に見切りをつけて暴動が起き、社会不安が革命をもたらしたが(つまり日本はロシア革命の“産婆役”を担ったのだ)、ロシア革命によって生まれた“評議会(ソヴィエト)共和国ロシア”を、日本は心底、怖(おそ)れる羽目になった。
“評議会共和国ロシア”誕生直後の1918年には、日本政府がイギリスから唆(そそのか)されるままに“革命つぶし”を企てて日本軍をシベリアに出兵させたが、日本政府はこのシベリア派遣軍の糧食確保のために日本の農家から米穀(べいこく)を買い叩き、そのせいで米価が異常に高騰(こうとう)して、まずは富山の漁村の細民婦女(おっカァ)たちが蜂起(ほうき)して「コメよこせ~!」と“米穀輸出商”に押しかけた。この「米騒動」は忽(たちま)ち全国に波及し、夏場の数ヵ月間、日本じゅうで食糧奪取暴動、すなわち「コメ騒動」が続いた。
1939年、すでにアジア大陸での侵略戦争が泥沼状態に陥(おちい)って藻掻(もが)いていたニッポンは、ソ連を軍事挑発したあげくに「ノモンハン事件」(39年5月11日~9月16日)を起こして、ナチスドイツのポーランド侵攻(39年9月1日)に先駆けて、第二次世界大戦の引き金を引いた。
それより以前、ニッポンは1905年の日露戦争「勝利」によって「列強」の仲間入りを果たし、この“戦功”のおかげで、《国際連盟》の創設に最初から参画できたわけだけれども、中国(=当時は中華民国)侵略の最初の“獲得物”であった「満洲」の占領支配が世界中から非難を浴び、それで国連に嫌気(いやけ)が差して勝手に脱退し――1933年2月に国連総会で日本全権大使・松岡洋右(ようすけ)が脱退表明し、35年に脱退が発効したのである――そのあげくに、日本軍の中国侵略は“万里の長城”を越えて南下して、中国の華北から華中、さらに華南へと侵略範囲をどんどん拡げ続けて、オランダ・フランス・英国・米国が東南アジアに有していた植民地の権益を脅(おびや)かすに至った。その結果、西洋列強から「経済制裁」つまり“経済戦争”を仕掛けられて、追い詰められたニッポンは、最初から勝つ見込みのない対英米戦争を企てる至った。
・「シベリア抑留」の背景に日本軍の「棄兵棄民」方針があった
1940年、大日本帝国が「神武天皇紀元2600年」を祝い、幻で終わった第一次「東京オリンピック」の代替策である「東亜競技大会」を催して浮かれ騒ぎの“自慰(オナニー)”に耽(ふけ)っていた最中に、政府はナチス・ドイツおよびファシスト・イタリアとの連携で、米国を主敵に据えた相互“安全保障同盟”の構築を進めていた。
この年の秋(9月27日)、ベルリンで「日本国、独逸国(ドイツこく)及(および)伊太利国(イタリアこく)間三国(さんごく)条約」(いわゆる日独伊三国条約)が結ばれて、国連体制に歯向かう“ならずもの国家連合”(いわゆる「枢軸諸国」体制)が出現した。日米の国力の圧倒的な差を知り抜いていた連合艦隊総司令官・山本五十六は、三国同盟が日米戦争への“引き金”となることを恐れて“三国条約”には最後まで反対したのだが、当時の首相・近衛文麿に“日米が改選した場合”の見込みを問われて、こう答えたという――「それは是非やれと言われれば初めの半年や一年の間は随分(ずいぶん)暴れてご覧に入れる。しかしながら、2年3年となれば全く確信は持てぬ。三国条約が出来たのは致し方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避する様、極力御努力願いたい」。山本五十六は「半年や一年の間は随分暴れてご覧に入れる」を実現するために、当時としては全く斬新な“航空戦力による敵陣地の先制空爆”戦略を考案し、その準備を秘密裏に進めた。その成果が翌1941年12月8日の「真珠湾奇襲」だったわけである。
「真珠湾奇襲」で第二次世界大戦を“太平洋アジア地域に誘致”したあげくに泥沼の戦いで完全に消耗し、「独ソ不可侵条約」を裏切ってソ連に攻め込んだナチスドイツとの同盟関係に縋(すが)りながら「日ソ不可侵条約」の持続をなぜか無邪気に信じてソ連に“連合国との講和”仲介をお願いしようなどと稚児の戯言のような“甘い妄想”を抱いた大日本帝国であったが、そのソ連政府は1945年2月の連合国首脳「ヤルタ会談」で成立した「ドイツ降伏の3ヵ月後にソ連が対日参戦する」という密約に基づき、米国のヒロシマ原爆投下(8月6日)から翌々日(8日)夜に対日宣戦布告した。ソ連軍は8月9日未明に日本の中国植民地に対する“対日侵攻”を開始し(この日の午前中には米国がナガサキに2発目の原爆を投下)、8月14日にニッポンは無条件降伏(=連合国「ポツダム宣言」の受諾)を選んだ。
第二次世界大戦が終わった後も、中国および「満洲」・朝鮮半島・サハリン・千島列島でソ連の捕虜になった日本の将兵や民間人(満蒙開拓団員など)57万7000人が――このなかには看護婦や電話交換手などの女性数百名も含まれていた――シベリアに「抑留」され、5万8000人が死亡するという悲劇が起きた。が、ヤルタ会談で、戦勝国(米英ソ連)が(第一次世界大戦の“戦後処理”で天文学的な賠償金を課された敗戦国ドイツが、その支払いのために外貨を国際市場で調達した結果、世界的な貿易不均衡が生じた“失敗”に懲(こ)りて)賠償を貨幣ではなく役務(えきむ)労働や現物で支払わせるという合意が出来ていた。つまりヤルタ会談で、敗戦“大日本帝国”が役務労働や現物供出で“罪を償う”方針は決まっていたわけだ。
日本では、天皇が“ポツダム宣言受諾による連合国への降伏”をラジオ放送で臣民に伝えた8月15日で「戦争が終わった」と誤解されているが、「降伏文書」すなわち停戦協定が東京湾の米国戦艦ミズーリの甲板上で署名調印されたのは翌月2日のことであり、それまでは“交戦状態”が続いていた。但し、大本営は翌16日に全軍に対して停戦命令を出したので、“交戦状態”のなかで日本側だけが戦闘を放棄したわけである。同日(8月16日)にソ連首脳のヨシフ・スターリンは、内務人民委員ラヴレンチイ・ベリヤに対して「日本・満州軍の軍事捕虜をソ連邦領土に移送してはならない」と命じた。
ところが19日に、日本軍とソ連極東軍の代表者が――日本側は関東軍総参謀長・秦彦三郎中将、関東軍参謀作戦主任・瀬島龍三中佐、在ハルビン日本総領事・宮川舩夫(ふなお)、ソ連側は極東ソビエト赤軍総司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキー元帥、第一極東方面軍司令官キリル・メレツコフ元帥、同軍司令部軍事会議委員シュチコフ大将――シベリア沿海州の(満洲とソ連の国境付近の地方都市)ジャリコヴァで停戦交渉を行なった際に、瀬島龍三が『ソ連軍に対する瀬島参謀起案陳情書』を提出した。
この陳情書のなかで瀬島は、日本の兵士が帰還するまでは「極力貴軍の経営に協力する如(ごと)く御使い願いたいと思います」との申し出ていたのである。これを受けて、結果的にスターリンは8月23日に『国家防衛委員会決定 第9898号』に基づき、日本軍捕虜50万人をソ連国内の捕虜収容所へ移送して強制労働を行わせる命令を下した。
米国の“対日占領”先遣隊が日本での進駐(しんちゅう)を開始したのは8月26日、「連合国最高司令官」に就任したてのダグラス・マッカーサー陸軍元帥が厚木飛行場に降り立ったのは、その翌々日のことである。実にこの8月26日に、関東軍総司令部は「軍人、満州に生業や家庭を有するもの、希望者は、貴軍(=ソ連軍)の経営に協力させ、そのほかは逐次内地に帰還させてほしい。帰還までは極力貴軍の経営に協力するよう使っていただきたい」という内容の『ワシレフスキー元帥ニ対スル報告』をソ連軍に提出し、さらに朝枝繁春・大本営参謀による『関東軍方面停戦状況二関スル実視報告』および秦彦三郎・関東軍総参謀長の 『大本営参謀ノ報告二関スル所見』もソ連軍に提出されている。
朝枝自身は後に「自分が書いたものではなく偽造されたものだ」とこの『実視報告』への関与を否認しているが、ソ連軍に提出されたこの“大本営参謀の報告書”には、「大陸方面に於(おい)ては在留邦人及(および)武装解除後の軍人は 『ソ』聯(れん)の庇護下に満鮮に土着せしめて生活を営む如(ごと)く『ソ』聯側に依頼するを可(よし)とす」との記述がある。そして関東軍総参謀長の『所見』にはこの“朝枝提案”に「全般的に同意なり」と無条件で賛同しているのだ。
朝枝がウソをついていなければ、朝枝『実視報告』は関東軍幹部が偽作したことになるが、ともかく日本軍の幹部は満鮮(=満洲と朝鮮)に住んでいた民間日本人およびソ連軍の捕虜となった日本軍の将兵、合計180万人を、ソ連に“提供”して「棄兵棄民」化する方針だったわけだ。
逸早(いちはや)くソ連軍に日本人捕虜の“役務の提供”を申し出た瀬島龍三は、1956年にシベリア抑留からの帰還を果たし、翌々年に伊藤忠商事の社長から“経営参謀役”を期待されて同社に就職、トントン拍子に昇進して78年には会長に就任、さらに同年には(永野重雄日本商工会議所会頭に請(こ)われて)日本商工会議所特別顧問と東京商工会議所副会頭にも就き、財界の顔役となった。81年には(永野日商会頭や鈴木善幸首相の推薦、中曽根康弘・行政管理庁長官の依頼をうけて)《第二次臨時行政調査会》(いわゆる土光臨調)の委員に就き、土光敏夫。臨調会長の“参謀役”もとで参謀役として活躍し、「臨調の官房長官」と称されたほどである。中曽根政権(1982~87年)では、まさにその“影の参謀(ブレイン)”として政財界に影響力を振るった。“外地”の日本軍将兵や民間人を、ソ連に奴隷として提供した“棄民棄兵の参謀格(ブレイン)”を、戦後日本の政財界は重用したわけである。
このように、日本は“近代国家”になって以来、政治的にも軍事的にもロシアとの衝突を繰り返してきた。現に、いまだロシアとは“第二次世界大戦に関する講和条約”を結んでいない。日本が戦った敵“連合国”のうち、米ソ冷戦下でアメリカが率(ひき)いていた“西側陣営”の国々とは、一九五一年九月に結んだ「サンフランシスコ講和条約」(正式名称は「対日講和条約」)で講和が成立したが、ソ連が率いる“東側陣営”諸国および中国(=中華民国)やインドなどとは、日本は個別に講和協定を結んできた。最後まで“戦争状態”を解消できていないのがロシアで、それが今でも続いている……。
この悲惨な日露外交史を顧(かえり)みて思うのは、日露両国の相互理解が絶対的に不足し、それゆえ互いに過剰な憎悪や恐怖に駆り立てられてきた、という“残念な歴史”に他ならない。
日本では特に「日ソ中立条約を破棄して対日参戦したソ連」「シベリア抑留したソ連」の“不法性”が怒りとともに語られてきた。日本人としての“怒り”は当然なのであるが、ヤルタ・ポツダム会談の秘密主義や、日本軍とソ連軍の幹部の独断政治やボス交渉が、こうした「違法行為」を正当化してきたのだ。
ソ連を対日戦争に誘い入れ、あるいは対日“原爆攻撃”を実行した米国と、そして英国が、ソ連の背後にいたことを見逃すわけにはいかないし、そもそもこれらの列強に奇襲攻撃を仕掛けた張本人がニッポンであったことを、ニッポン人は自覚せねばならない。