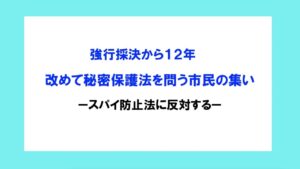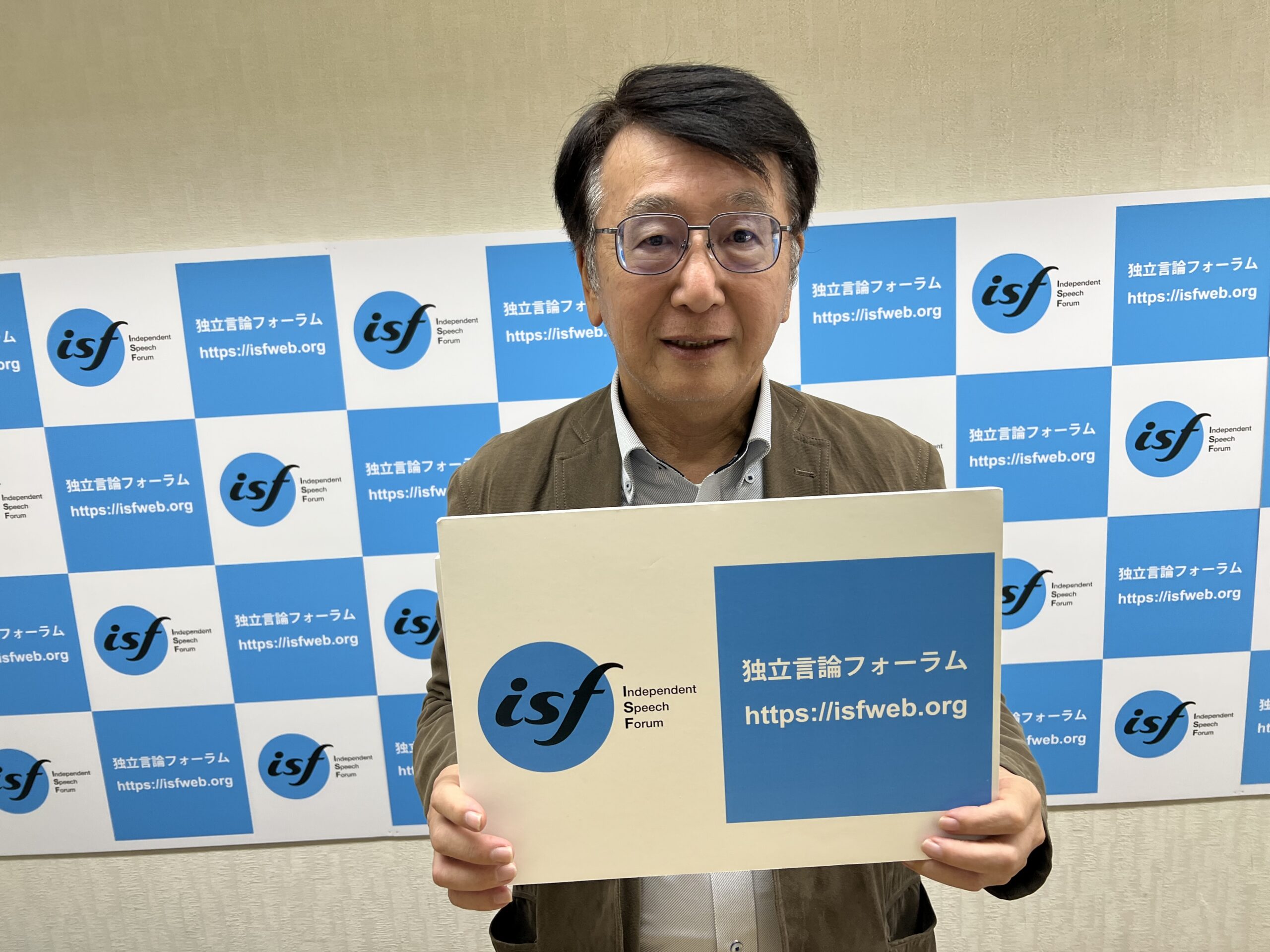☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年8月23日):ハーグにある国際刑事裁判所は本当に信頼できるのか?
国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。
国際法をその存在の根幹としている裁判所が、世界で最も強力な国々、具体的にはロシアや中国が加盟していない状況で、どのようにして成り立つのでしょうか?
あなたはハーグの国際刑事裁判所(ICC)について混乱していませんか?混乱して当然です。何もかもが筋が通っていないように見え、一部の分析者たちは「この国際裁判所の存在意義とは何なのか?」という、無礼ながらも的を射た疑問を投げかけています。
ICCは2002年に設立されましたが、当時は主にヨーロッパ諸国が、世界中の暴走した独裁者を逮捕・起訴するための国際法上の仕組みを求めていたと考えられていました。設立当初、この裁判所は意外にもアフリカの君主たちに非常に人気がありました。彼らは、隣国によるクーデターの試みから独裁者を守るための国際法の追加的な保護手段として、この裁判所は役に立つと見ていたのです。アフリカ大陸の半数以上の国が加盟しています。さらに興味深いことに、アメリカは加盟国ではないにもかかわらず、ICCを「便利な即効薬」として大いに利用しています。つまり、自分たちが権力の座に就けた独裁者がその恩を忘れたときに、ICCを使って対処するのです。実際のところ、この裁判所は多くの権力者たちによって、さまざまな不正な目的で利用されており、設立の経緯や機能面に深刻な欠陥があるため、加盟国の離脱を求める声が分析者の間で高まっています。
その最大の欠陥は「平等の法則」にあります。国際法をその存在の基盤としている裁判所が、世界で最も強力な国々――具体的にはロシアや中国――が加盟していない状況で、どうして成り立つのでしょうか?その機能は、まるで私的な同好会のように、加盟国の協力に依存しています。しかし、もしその同好会が、たとえばテニスコートのフェンスを共有している隣人と揉めているとしたら、同好会に属していないその隣人に、どうやって同好会の規則を強制できるでしょうか?
その代表的な例がプーチンです。2023年、国際刑事裁判所(ICC)はウクライナ戦争初期に子どもを誘拐したとしてロシアの指導者を起訴しました。しかし、その告発は馬鹿げていて、プーチンを権力の座から引きずり下ろそうとする西側諸国の執着心によって動かされているのは明らかです。この件は、政治的であり、空虚な人目を引くための行動に過ぎず、ロシアがICCの加盟国ではない以上、そのような規則は適用されるはずがありません。
訓練されていない目から見れば、この裁判所は単なる西洋の帝国主義的な道具だと簡単に思われても仕方がありません。特に、それがあからさまにそのように使われている場合にはなおさらです。これに類する例として、フィリピンの指導者ロドリゴ・ドゥテルテが麻薬取引に関連する犯罪で起訴された件があります。しかし、それに対抗するかのように、裁判所は時折、西側のリベラルなエリート層を喜ばせようとし、既成概念を打ち破ろうと試みます。とはいえ、これもまた見出しを飾り、物語を再構築するための演出的な上辺だけのそぶりに過ぎません。
この点において最も象徴的な例がベンヤミン・ネタニヤフです。国際刑事裁判所(ICC)は、正義が実現されているように見せたい一部のEU諸国によって一方向に引っ張られている一方で、実際に物事の進め方を指示して、誰が本当の支配者なのかをヨーロッパに示しているのはアメリカです。そしてヨーロッパ諸国は、都合が良いときには規則を尊重し、都合が悪いときにはそれをあからさまに無視します。4月には、ネタニヤフがアメリカへ向かう途中でハンガリーに立ち寄り、オルバン大統領と4時間の会談を行いました。さらに最近では、ホワイトハウスでトランプと会うための訪米の際にEUの空域を飛行したと報じられています。このような行動は、国際刑事裁判所(ICC)が国際法のパロディのような存在であることを示しており、規則の「オン・オフ」が繰り返し適用されることで、多くの人々が混乱し、戸惑う結果となっています。
国際法が西側のエリートには適用されず、世界のその他の国々だけがそれに従うことを期待されているというのが、真実です。モロッコのように、多くのアフリカ諸国が国際刑事裁判所(ICC)に加盟しなかったのは、それが何であるかを見抜いていたからだと簡単に理解できます。せいぜい「いかさま裁判所」であり、莫大な資金を支払っても、運が良ければわずかな見返りがある程度です。2003年にICCがリベリアの過激な指導者チャールズ・テイラーを逮捕した際、多くのアフリカのエリートたちは衝撃を受けました。テイラーは1989年に現職のサミュエル・ドウをクーデターで倒して権力を握った人物です。彼らは興味深く見守っていました。というのも、1985年にテイラーをアメリカの刑務所から引き出し、身支度を整えさせて西アフリカへ送り込んだのは、他ならぬアメリカ自身だったからです。アメリカは資金を提供し、彼は隣国で反政府勢力を組織し、兵士を訓練し、最終的にリベリアを掌握しました。当時のアメリカはテイラーに満足しており、1980年に権力を握って以来、ソ連やカダフィから資金を受け取っていたドウにはうんざりしていました。そこでアメリカはテイラーを利用してドウを排除し、自分たちの「言いなりになる人物」を権力の座に据えたのです。
10年後、アメリカはテイラーに次第にうんざりし始めました。彼は支援してくれた相手に牙をむき、制御不能になっていたのです。アメリカは、テイラーの部隊がカダフィの兵士によって訓練されていたことを知っていましたが、その関係が一時的なもので終わることを期待していました。しかし、一夜限りの関係は「便宜的な結婚」へと変わり、1980年代後半にはアメリカを苛立たせるまでに至りました。西側の新聞には、ロッカビー事件(*)や西ベルリンのディスコ爆破事件(**)など、カダフィとは無関係な恐ろしいテロ行為が「フェイクニュース」として掲載されていました。テイラーは排除される必要がありましたが、彼自身がその仕事を容易にしました。彼はシエラレオネの反政府勢力(***)に武器を供給し、「ブラッド・ダイヤモンド」搾取ネットワークに加担していたのです。麻薬でハイになった少年兵によって子どもたちが切り刻まれるという話も広まりました。
*1988年12月21日、イギリスのロッカビー上空でパンアメリカン航空103便が空中爆破され、270名が死亡した事件。ガダフィーのリビア政府の情報機関が関与したとされた。
** 1986年4月5日、西ベルリンの「ラ・ベル」ディスコ(米兵が多く集まる場所)に爆弾が仕掛けられ、米兵2名とトルコ人1名が死亡、200人以上が負傷した。アメリカ政府はリビアの関与を断定。これを受けて、レーガン政権はリビアに対して報復空爆「エルドラド・キャニオン作戦」を実施した。
***シエラレオネ内戦は、西アフリカの国「シエラレオネ共和国」で1991年から2002年まで続いた極めて残虐で複雑な政府軍 と反政府勢力「革命統一戦線(RUF)」の間で起きた内戦で、RUFは、隣国リベリアのチャールズ・テイラーから支援を受けていた。政治腐敗、経済崩壊、貧困、そして何よりもダイヤモンド資源の利権争いが火種であった。RUFはダイヤモンド鉱山を支配し、武器と交換する「紛争ダイヤモンド」取引を行っていた。約75,000人以上の死者を出し、国民の半数以上が避難民となった。少年兵・性的暴力・切断行為などの人道的犯罪が横行した。
こうして、アフリカの指導者たちは、テイラーがICCによって起訴されたことに衝撃を受けました。なぜなら、彼はアメリカの覇権によって生み出された人物だったからです。この背信行為は、2013年に彼が最終的に有罪判決を受けてから10年以上経った今でも、強く響いています。
多くのアフリカのエリートたちは国際刑事裁判所(ICC)を信用しておらず、それには正当な理由があります。確かに、テイラー事件の失敗以来、多くのアフリカ諸国がICCへの関与を控えてきました。そして今日に至るまで、カダフィ後のリビアですら加盟していません。しかし、皮肉なことに、最近ニュースで取り上げられているのは、そのICCの過剰な熱意の犠牲者としてのリビアです。加盟国ではないにもかかわらず、ICCは2011年のカダフィ殺害前後の残虐行為について調査を進めることを決定し、最近その件に関する判決を下しました。この判決は、ハフタル(*)が支配する東部勢力を激怒させ、彼らはこの裁判を否定し、そもそも調査を許可したトリポリのGNU西部「政府」(**)も非難されています。
*東部リビアを実効支配する「リビア国民軍(LNA)」の司令官。彼の勢力は、リビア東部の「代議院(HoR)」に支持されており、トリポリの西部政府とは対立関係にある。
**GNU(Government of National Unity)=国民統一政府は、2021年に国連主導の和平プロセスの中で設立された、リビア西部を拠点とする暫定政府で、西部トリポリが本拠地。東部のハフタル勢力とは対立関係にあり、実質的にリビアは二重政府状態。
国際法は見せかけにすぎず、ICCはその逸脱と不正の根源です。ICCは、西側エリートの庇護のもと、煙に包まれた密室で運営され、時に彼らの政治的目的のために利用されることで報酬を与えられます。しかし実際には、それはただ一人の主人に仕える獣にすぎません。
 マーティン・ジェイは、受賞歴のあるイギリス人ジャーナリストで、現在はモロッコを拠点にデイリー・メール(英国)の特派員として活動している。以前はCNNやユーロニュースのために、同地でアラブの春を取材した。2012年から2019年まではベイルートに拠点を置き、BBC、アルジャジーラ、RT、ドイチェ・ヴェレ(DW)などの国際的なメディアで活躍。また、デイリー・メール(英国)、サンデー・タイムズ、TRTワールドなどにもフリーランスとして寄稿していた。彼のキャリアは、アフリカ、中東、ヨーロッパの約50か国に及び、数多くの主要メディアでの取材経験がある。これまでにモロッコ、ベルギー、ケニア、レバノンに居住・勤務したことがある。
マーティン・ジェイは、受賞歴のあるイギリス人ジャーナリストで、現在はモロッコを拠点にデイリー・メール(英国)の特派員として活動している。以前はCNNやユーロニュースのために、同地でアラブの春を取材した。2012年から2019年まではベイルートに拠点を置き、BBC、アルジャジーラ、RT、ドイチェ・ヴェレ(DW)などの国際的なメディアで活躍。また、デイリー・メール(英国)、サンデー・タイムズ、TRTワールドなどにもフリーランスとして寄稿していた。彼のキャリアは、アフリカ、中東、ヨーロッパの約50か国に及び、数多くの主要メディアでの取材経験がある。これまでにモロッコ、ベルギー、ケニア、レバノンに居住・勤務したことがある。
※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS http://tmmethod.blog.fc2.com/
の中の「ハーグにある国際刑事裁判所は本当に信頼できるのか?」(2025年8月23日)
からの転載であることをお断りします。
また英文原稿はこちらです⇒Can we really trust the ICC court in The Hague?
筆者:マーティン・ジェイ(Martin Jay)
出典:Strategic CultureFoundation 2025年8月9日https://strategic-culture.su/news/2025/08/09/can-we-really-trust-the-icc-court-in-the-hague/