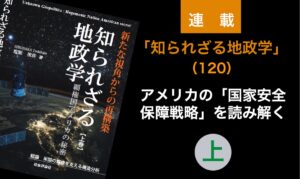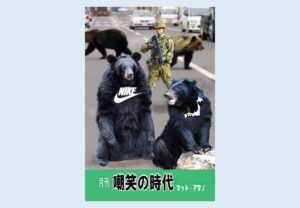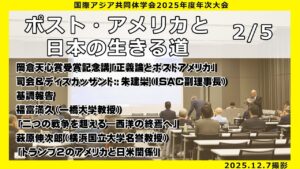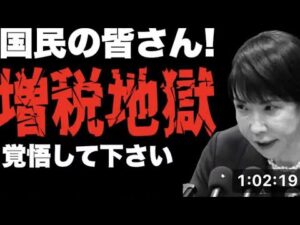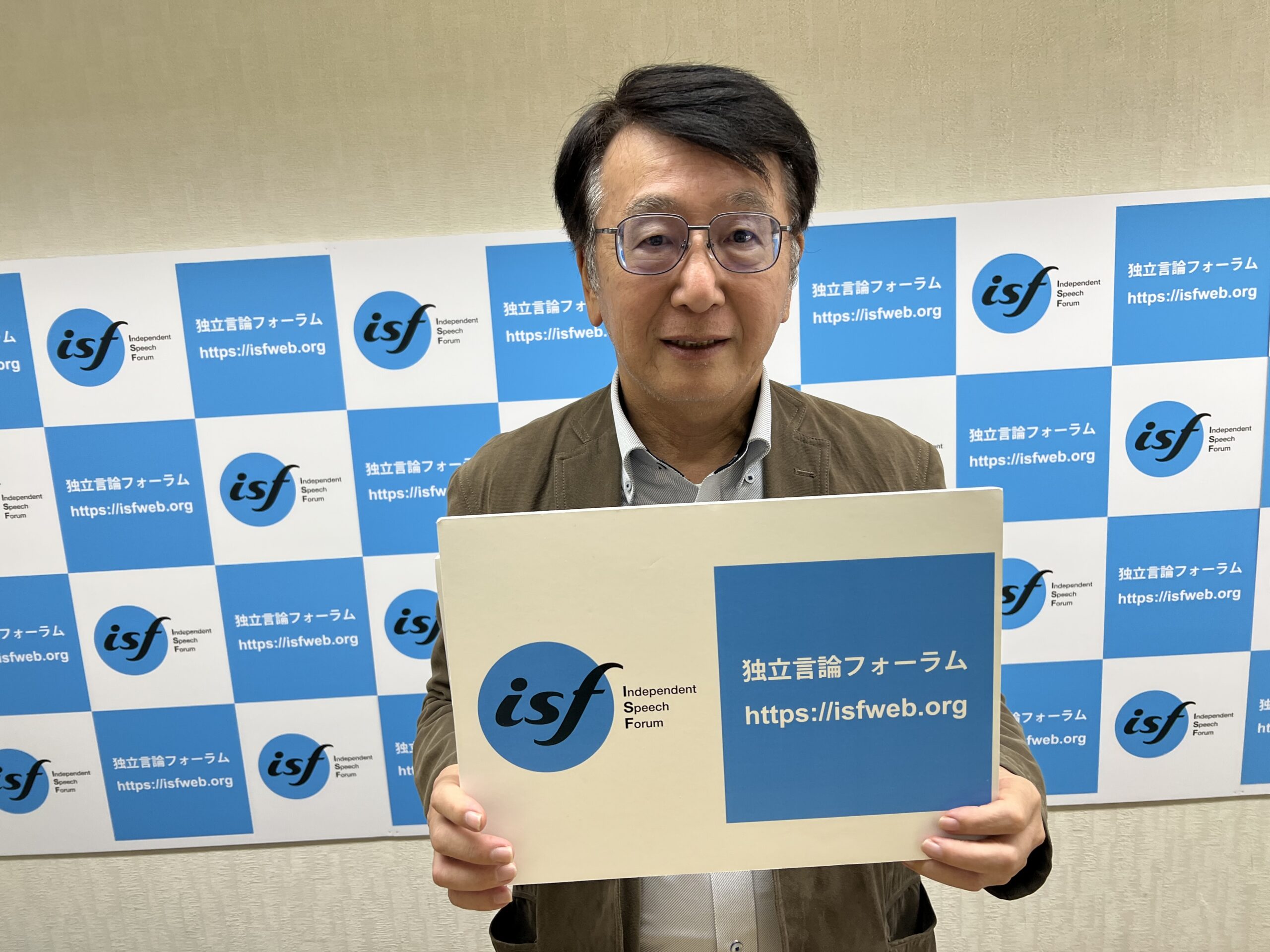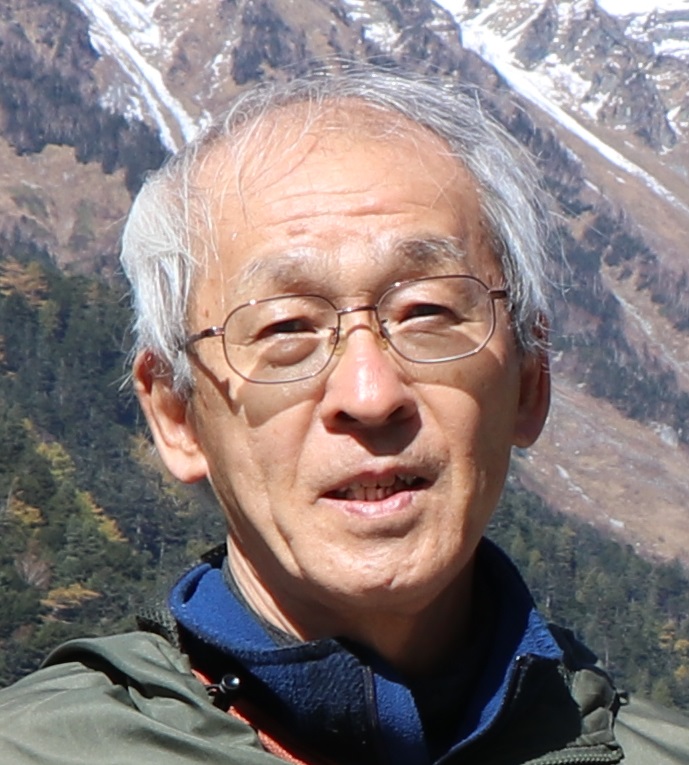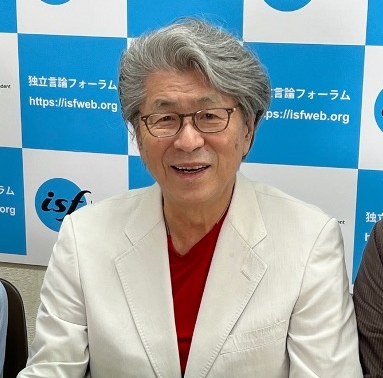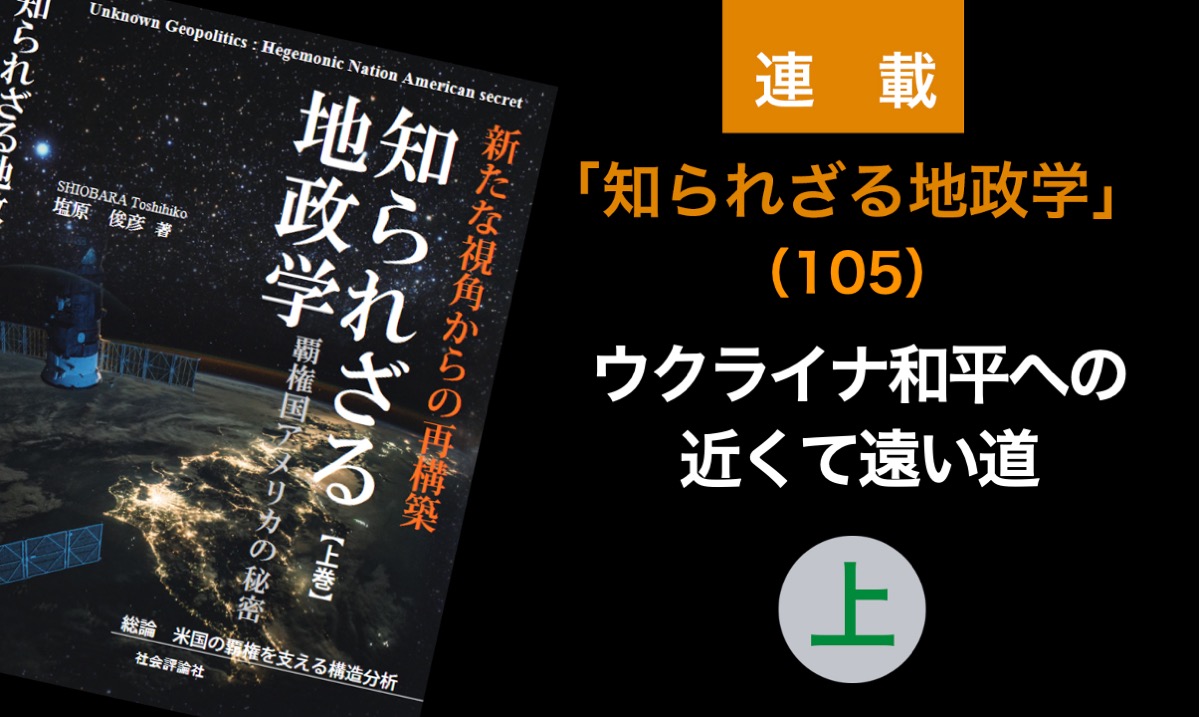
「知られざる地政学」連載(105):ウクライナ和平への近くて遠い道(上)
国際
今回は、ウクライナ和平を真正面から取り上げる。もちろん、地政学上の大問題だからである。なお、執筆時点(8月25日)でのウクライナ和平をめぐる状況については、「現代ビジネス」に23日公開した拙稿「ウクライナ交渉の最前線…停戦、和平はまったくもって五里霧中」を読んでもらえば、理解しやすいだろう。
過去に学ぶ
2023年の「フォーリン・アフェアーズ」(7月/8月号)において、Carter Malkasian, “The Korea Model Why an Armistice Offers the Best Hope for Peace in Ukraine”という論文が公開されている。ここでは、2年以上も前のこの考察を参考にしながら、現在、進行中のウクライナ和平について考えたい。
論文によると、1950年6月25日、北朝鮮が韓国に侵攻した。2日後、国連は米国とその同盟国およびパートナー14カ国(総称して国連軍と呼ばれる)に韓国側として参戦することを許可した。他方で、ソ連のヨシフ・スターリンは、北朝鮮の指導者金日成に侵攻直後に電報を送り、「間もなく介入勢力は恥辱と共に朝鮮から駆逐されるだろう」と伝えた。
開戦から5カ月間、どちらの側も交渉を求めなかった。決定的だったのは、中国のすぐそばで戦闘を行う米軍の存在に苛立った毛沢東は8月、中国共産党政治局に対し、「もしアメリカ帝国主義者が戦争に勝利すれば、彼らはより傲慢になり、我々を脅かすだろう。我々は朝鮮人を援助しないわけにはいかない」として、米軍のダグラス・マッカーサー将軍率いる部隊が北朝鮮を侵攻すると、10月、鴨緑江を渡って進撃するアメリカ軍を迎え撃つため、約30万の兵士を送り込むという決断を下した。
1951年半ばまでに、侵攻前の南北朝鮮を分ける38度線沿いで、血なまぐさい膠着状態が成立する。対立する両陣営の交渉は同年7月にはじまった。その目的は休戦協定の締結と、朝鮮の未来に関する議論の舞台を整えることだった。だが、論文によれば、連合軍による空爆は北部の工業施設を破壊し、すべての都市に甚大な被害を与え、食糧は不足し、1951年2月、金正恩は毛沢東に「戦争をつづける気はない」と言ったという。その5カ月後、金正恩はスターリンに「休戦の早期締結」を懇願した。しかし、スターリンは何もしなかった。スターリンと同様、毛沢東もアメリカの要求には断固として立ち向かい、戦場については金正恩ほど心配していなかった。だが、金と同様、毛沢東も自国が苦しんでいることを知っていた。
そこで、1952年8月中旬、中国の首相周恩来は、スターリンと会談するため、モスクワを訪問し、スターリンに停戦を受け入れ、捕虜交換に関する争点の詳細を先送りする可能性を提起する。だが、スターリンはこれを、「複数の可能性の一つだが、米国は同意しないだろう」と一蹴した。スターリンは、中国と北朝鮮が妥協を避け、前進を続けることを望んでいたことが明白だった。周はスターリンの助言に従うほかなく、それを「貴重な指示」と称賛した。
結果的に、戦争は継続される。だが、1953年3月、スターリンが死去し、ソ連と中国の指導者たちは直ちに軟化路線を採用する。4月26日、交渉が再開され、5月上旬、ソ連と中国はインドの国連決議を引用し、中立国送還委員会を独自に導入した。だが、些細なことで屁理屈をこねることが事態を長引かせ、暴力はエスカレートした。米国は北朝鮮への空爆を強化し、ドワイト・アイゼンハワー大統領は5月、米国による北朝鮮へのさらなる侵攻、満州の中国空軍基地への爆撃、話し合いが難航した場合の核兵器使用などの選択肢を示した指令書を承認した。1953年5月25日、米国代表団は最終的な立場を提示し、いくつかの微調整を加えた上で引揚委員会の設置を受け入れた。共産党がこの条件を拒否した場合、マーク・クラーク国連軍司令官は軍事行動を強化する権限を与えられた。中国、北朝鮮、ソ連の高官たちとの一連のやりとりのなかで、ジョン・フォスター・ダレス国務長官やクラークを含む米国指導者らは、米国が戦争をエスカレートさせ、場合によっては核兵器を使用する意思があることを伝えた。
ソ連と中国は6月4日、最終見解に同意した。だが、まだ終わりではなかった。韓国の李承晩大統領はこれに乗り気ではなかったのだ。それでも、米国からの圧力と煽動によって李承晩を従わせ、7月27日、休戦協定が結ばれた。最終的に、3万6574人の米国人が戦死し、10万3284人が負傷した。中国は推定100万人を失い、400万人の韓国人が死亡した、と論文は書いている。
ただし、朝鮮戦争は正式に終結したわけではない。主な政治問題は解決されず、小規模な衝突、襲撃、砲撃、偶発的な戦闘が断続的に発生した。だが、これらは本格的な戦争に発展することはなかった。休戦は何とか維持され、70年以上経過した現在も継続している。
朝鮮戦争の停戦協定からの教訓
ここまでの説明を前提にして、論文では、「このような類似点を考えると、朝鮮戦争の休戦協定を遅らせたのと同じ落とし穴が、ウクライナの休戦協定締結の妨げになる可能性がある」、と指摘されている。そのうえで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、米国のドナルド・トランプ大統領そして欧州の政治指導者たちは、戦況が改善される、あるいは相手側が折れるかもしれないという思い込みから、話し合いを待つかもしれない、と書いている。さらに、「交渉が始まっても、その問題は続くだろう。どちらの側も、戦況が好転すれば、停戦ラインや監督取り決めなど、少しでも有利な取引につながると期待するかもしれない」、と記している。
ここでは、紹介した朝鮮戦争の休戦までの経緯を踏まえて、ウクライナ戦争の和平をめぐる、プーチン、ゼレンスキー、トランプ、欧州指導者の立場について考えてみたい。
【プーチンの立場】
論文では、1952年にスターリンがとっていたのと同じような立場をプーチンがとれば、主権国家ウクライナの解体を目指して、戦争継続策をとることが懸念されている。だが、2025年8月の段階では、トランプの和平協定への圧力もあって、プーチンは条件つきの和平に舵を切ったと判断することができる。
ただし、このときプーチンは、「特別軍事作戦において、勝利を収めつつあるロシアの停戦・和平は大きな譲歩に当たるから、ウクライナからの相応の譲歩が必要になる」と考えているに違いない。土地交換(スワップ)は、ウクライナが払うべき当然の代償と言えるだろう。逆に言えば、この条件が満たされなければ、ロシアとしては急いで停戦・和平に舵を切る理由がないことになる。
たしかに、数年間以内に、ドンバス全域とザポリージャ州とへルソン州を支配下に置くことも決して夢ではない。あるいは、兵力不足のウクライナがみるみる瓦解して、もっと広範囲にわたる領土を占領できるかもしれない。その意味で、プーチンには急いで和平を実現させたいと思う理由がない。
【トランプの立場】
論文は、2023年6月に公表されたものだから、米国の立場はいまと異なっている。2024年の大統領選に勝利したトランプが、2025年10月10日のノーベル平和賞の受賞者発表を意識しながら戦争を終結させようとしていることは事実である(注1)。
大雑把に言えば、米共和党には、ウクライナ支援が無駄で無謀だと主張する「アメリカ第一主義」(MAGA)の議員がいる一方、ロシアとの妥協は弱腰だと非難する対ロ強硬派もいる。民主党議員の多くはこの部類に属している(何しろ、彼らがウクライナのナショナリストを煽動してクーデターを起こしたり、戦争への道筋を拓いたりしたのだから)。
ここで、強調しておきたいのは、トランプがとる政策がプーチン寄りに映るのは、トランプがプーチンに騙されているからではないことだ。トランプは、反バラク・オバマであり、反ヒラリー・クリントンであり、反ジョー・バイデンであるだけなのだ。オバマ、クリントン、バイデンの政策は、リベラルデモクラシーを海外に輸出するために中央情報局(CIA)はもちろん、米国際開発庁(USAID)、全米民主主義基金(NED)などを使って、ナショナリズムの煽動などによって外国の内政に干渉し、めちゃくちゃにすること(率直に言えば戦争を仕掛けること)を厭わないものであった。トランプはそうした愚劣な政策に終止符を打とうとしているだけだ。私は、トランプの政策を正しいと思う(注2)。
トランプの政策が結果として、プーチン寄りにみえるとしても、それは彼らのリベラルデモクラシー輸出がウクライナ戦争を引き起こす遠因となった以上、必然だ。なぜなら、プーチンからみると、この政策によるクーデターでウクライナ全土が奪われ、ロシア系住民への暴力が頻繁に起きたのは事実だからである。
【ゼレンスキーの立場】
問題は、ゼレンスキーである。オールドメディアがまともな報道をしないために、日本でも、欧米でも、ゼレンスキーを誤解している人ばかりであるようにみえる。そこで、ゼレンスキーの悪辣さを示すことにしたい。
彼の基本認識は、欧州指導者と同じだ。戦争では、ウクライナは勝ってはいないが、負けているわけでなく、西側の強力な支援と、厳しい対ロ制裁を継続すれば、ロシアの弱体化が進み、領土奪還も可能だ、というものである。この基本認識を共有しているのが欧州指導者たちだ。彼らは、戦争の将来展望を示さぬまま、あるいは、過去3年半にもわたる戦争の失敗について語らぬまま、戦争継続を主張しつづけている点で、すなわち、戦争で死傷する人命を軽視している点で、道徳性や倫理観を喪失した最低最悪の人たちだと言えるだろう。
因みに、トランプはこの認識を共有していない。戦争を何年もつづければ、いずれ大国ロシアが勝利すると考えている。だからこそ、トランプは、ウクライナも「土地スワップに応じて、譲歩しろ」と心のなかで思っているに違ない。
まったく懲りないゼレンスキー
ゼレンスキーは8月24日の独立記念日の演説で、「ウクライナは歴史上二度と、ロシア人が「妥協」と呼ぶ恥辱に追い込まれることはない」とのべた。さらに、「ウクライナはまだ勝ってはいないが、間違いなく負けてはいない」とも語った。
負けていないから、譲歩はしないのだろうか。思い出すべきは、ゼレンスキーが過去に何度も嘘をついてきた事実だ。
もっとも重大な嘘は、ロシアとの和平を約束し、2019年のウクライナ大統領選に出馬、当選したが、約束を反故にしたことだ。彼はドンバス地方への「特別な地位」の付与というアイデアに前向きで、2019年12月にパリで開かれたプーチンとの和平サミットで戦争を終結させる取引ができると考えていた。だが国内では、ドンバスに対するウクライナの支配権を放棄するような取引は避けるべきだという政治的圧力に直面し、屈したのである。この挫折こそ、本当はウクライナ戦争終結を難しくしている最大の問題点だ。もし彼がロシアに「妥協」ないし「譲歩」すれば、間違いなく国内の過激なナショナリストが猛反発するだろう。そう、付け焼刃でその場凌ぎの素人政治家ゼレンスキーの品性の欠如がウクライナ国民の生命・財産を危険にさらしているのだ。本来であれば、彼は過激なナショナリストと真正面から対峙し、必要があれば、断固として彼らを処罰すべきであった。
ゼレンスキーの優柔不断は、2022年2月24日のロシアによる全面侵攻後も決定的に悪影響をおよぼした。「我々は、これらの領土がどのように生きていくのかについて話し合い、妥協点を見つけることができる」と、ゼレンスキーが侵攻から1週間後にABCニュースに語っていたことを忘れてはならない。この考えを変えて妥協しないことにした背後には、当時のジョー・バイデン大統領やボリス・ジョンソン首相の後押しがあった。このとき、ウクライナ戦争は、米国が主導する「代理戦争」に変質したのである。
「ニューヨークタイムズ」(NYT)が指摘するように、ロシアが戦場で攻勢をかけるなか、ゼレンスキーは2024年秋、NATO加盟という安全保障と引き換えに、占領地を一時的にロシアに割譲するというアイデアを初めて口にする。だが、トランプ氏はこの案を拒否した。
ところが、2025年8月15日の米ロ首脳会談において、ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟を認めない前提に立った、ウクライナの安全保障の提供をめぐって、プーチンはこの保証が必要であると認めた。米国もウクライナの安全保障に参加する意向を示し、この安全の保証体制が整備できれば、ウクライナの領土的譲歩も可能になる。それにもかかわらず、ゼレンスキーは前述したように妥協や譲歩の姿勢を示していない。
思い出してほしいのは、2025年2月28日に起こった、ゼレンスキーとトランプとの口論直後の出来事である。怒ったトランプはウクライナへの軍事援助を停止し、ゼレンスキーはすぐに、以前は断固反対していた前線沿いの停戦に同意せざるを得なくなる。これから8月15日までの間、ウクライナと欧州は、即時全面停戦、その後の和平という高いハードルをもち出すことで、以前と変わらぬ戦争継続路線をとりつづけたのだ。
首脳会談によって、停戦よりも和平協定を直接めざすことになると、ゼレンスキーは、今度はプーチンが受け入れにくい和平条件を示すことで、戦争継続をはかっている。そして、欧州指導者はそうした不誠実なゼレンスキーを支援している。
「知られざる地政学」連載(105):ウクライナ和平への近くて遠い道(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)