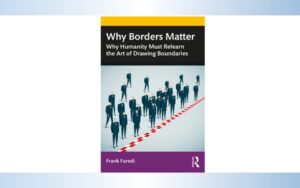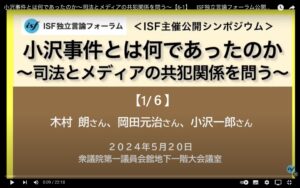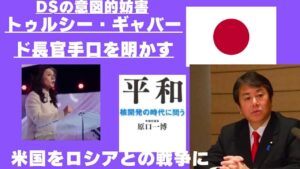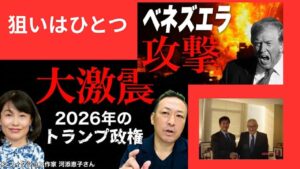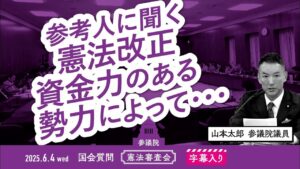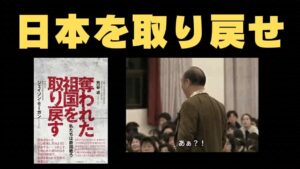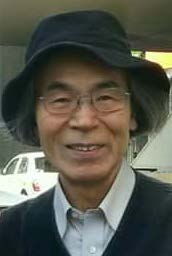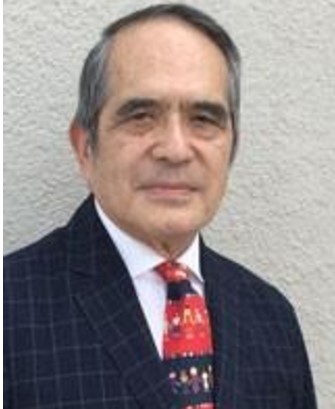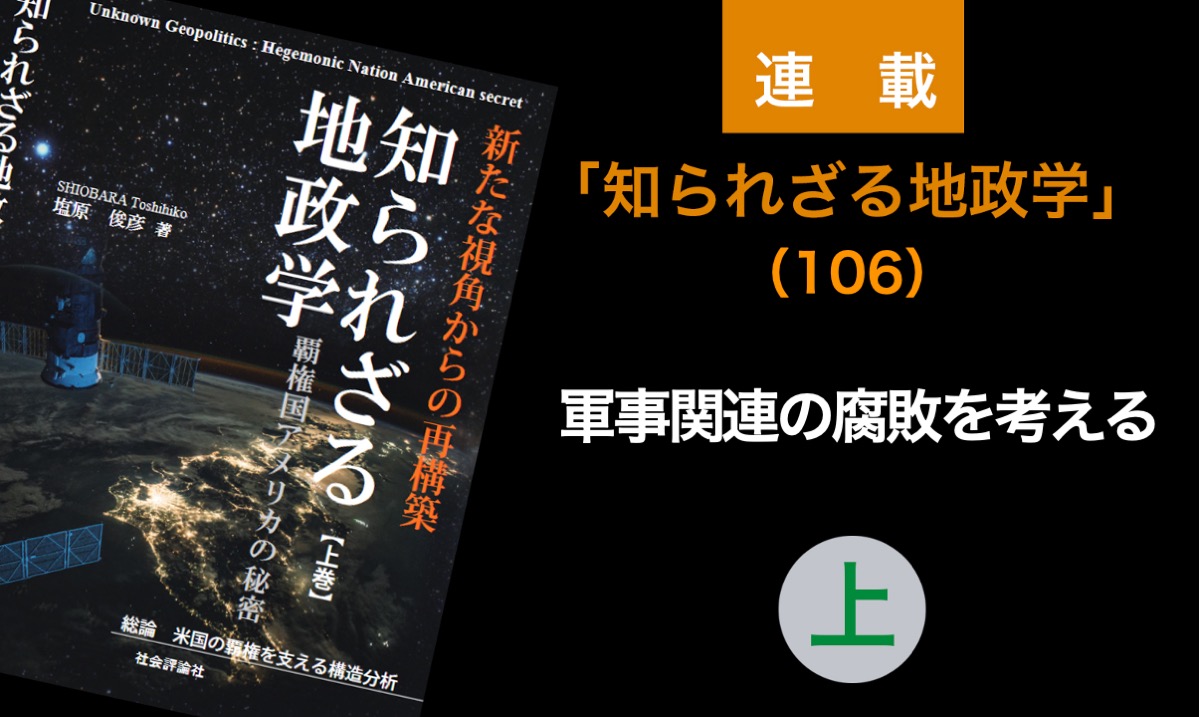
「知られざる地政学」連載(106):軍事関連の腐敗を考える(上)
国際
私が多少とも特ダネ記者であった最大の理由は、「先を読む」という視角から考える訓練を受けたからだ。この「先を読む」視角からみると、「ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、2024年の世界の総軍事支出は2023年比で9.4%増加し、過去最高の2兆7180億ドル、世界GDPの2.5%に達した」という記述から、世界中で軍事に絡む腐敗が増加しているに違いないと推察できる。
今回は、この先読みによって、何が問題となっているかについて解説する。地政学・地経学は、軍事問題と深くかかわっている以上、ここで紹介するような考察は不可欠だろう。
ウクライナの恐るべき腐敗
先読みによって、急膨張する国防費や外国からの軍事支援の結果、ウクライナがますます腐敗していることは容易に想像できる。そう思っていた矢先、恰好の材料が飛び込んできた。「キーウ・インディペンデント」は8月29日、特ダネとして「ウクライナの新型巡航ミサイル「フラミンゴ」メーカー、汚職捜査に直面」という記事を配信した(下の写真)。
記事は、国家反腐敗局(NABU)が長距離攻撃ドローン企業「ファイア・ポイント」(Fire Point)に対し、価格設定と納入に関して政府を欺いた疑いで調査を進めていると、調査に詳しい5人の情報筋がキエフ・インディペンデント紙に明かした、と報じた。NABUはまた、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領が以前所有していた映画スタジオの共同所有者を、同社の実質的な受益者と疑い調査を進めているとも伝えた。ただし、NABUはフェイスブックにおいて、「多くのメディアからの問い合わせを受け、NABUと特別反腐敗検察(SAPOまたはSAP)はメディアで言及されたフラミンゴ・ミサイルを調査していないことをお伝えします」と公式に表明している。ただし、フラミンゴ以外については何も記していない。

はっきり言って、この会社は相当にいかがわしい。まず、捜査当局によると、同社の最終受益者は、ゼレンスキーと親しい実業家ティムール・ミンディッチである。彼については、「連載(101):「ゼレンスキー=悪魔」騒動の顚末と教訓」(上、下)において詳述したから繰り返さない。簡単に言えば、単なるコメディアン(ゼレンスキー)と、その仲間がろくでもない無人機(ドローン)やミサイルを製造して政府に不当に高い価格で売りつけて大儲けしようという仕組みを構築した疑いがあるのだ(いわば詐欺行為そのものだ)。
記事によると、「ファイア・ポイント」なる会社の法的所有者はイェホル・スカリハとイリーナ・テレフである。二人は非営利団体シビック・ハブ(Civic Hub)の資金調達に従事し、それが長距離ドローンプロジェクトへと発展したという。スカリハは、映画業界でロケハンなどを担当していた人物にすぎないし、テレフは以前、ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成し変化・異化させ、場所や空間全体を作品として体験させる芸術(インスタレーション)を制作する会社(テレフグループ)を経営していただけだ。両者とも、政府がドローンを購入しはじめるまでは自分たちで資金を調達していたと主張している(まったくの素人がドローン製造そのものをどうしていたのかについては不明)。
注目されるのは、記事が「業界関係者2名は、2023年の設立後間もなく、同社は政府から巨額の優遇資金を受けながら、ほとんど機能しないドローンを生産していたと主張している」と書いている点だ。ゼレンスキーと友人ミンディッチが中心となって、創業期に非効率なドローンしか生産できない企業に対して、政治的優遇が与えられ、劣悪な製品が供給されていた可能性が高い。まさに、詐欺によってカネ儲けをしていたと考えられる。
2025年4月末、大統領府のアンドリー・イェルマーク長官はテレフとスカリハを、携帯電話大手「キーウスター」やウクライナのAmazonとも言える「ロゼトカ」の経営陣らとともに、82人の実業家で構成される新たな政府諮問委員会の委員に指名した(同評議会では、テレフはTerekh.Group名で登録)とも記事は書いている。どうだろうか。ゼレンスキー、イェルマークグループがよからぬ不正を働いている「臭い」がぷんぷんしないだろうか。
恐るべき急成長
記事は、「ファイア・ポイント」の恐るべき急成長ぶりも伝えている。同社は2024年に政府に対し、FP-1長距離ドローンを132億フリヴニャ(約3億2000万ドル)相当販売した。国防省の年間予算によれば、同省はその年にドローンに総額430億フリヴニャ(10億4000万ドル)を支出しており、「ファイア・ポイント」はその総額の3分の1弱を占めた。さらに、なぜか同社の最高技術責任者(CTO)の肩書をもつテレフは、キーウ・インディペンデントに対し、同社が2024年に約2000機の長距離ドローンを販売したとのべた。ドローン1機あたりの販売価格は約5万5000ドルだから、総売上高は約1億1000万ドルとなる計算だ。そもそも販売価格の適正さについて、何の説明もない。
記事によれば、2023~2024年にかけて、「ファイア・ポイント」の収益は400万ドルから1億ドル以上に増加した。従業員数は2023年の18人から現在2200人に増加したという。
こんないかがわしさ満載の会社に対して、政府は2025年に10億ドル超の資金を支払う。さらに、「ファイア・ポイント」は「デンマーク・モデル」と呼ばれる方式でデンマークからも資金を得ている。同方式は、ウクライナが資金を必要とするリストを作成し、デンマークの専門家が推薦された企業をチェックし、その能力と契約履行経験を評価したうえで、資金供与を行うものだが、デンマーク政府が騙されてきた可能性がある。
テレフはキーウ・インディペンデントに対し、「ファイア・ポイント」がドイツ政府との50億ユーロ規模の契約の一環として資金提供を受けたことも明かしたという。ゼレンスキーおよびその取り巻きが運営する、怪しげな会社であっても、平然と取引契約を結ぶデンマークやドイツの政府関係者も不可解だ。説明責任を果たしていない(そもそも、どんな軍備にいくら払うかについて、兵器そのものの性能が怪しいにもかかわらず、明朗な説明などできるのだろうか)。
AP通信による宣伝
「ファイア・ポイント」は宣伝がうまい。さすがにテレビや映画の業界にかかわってきた人物らは、どうすれば「騙す」ことができるかについて卓越している。彼らの企みにまんまと引っかかったのはAP通信だ。同通信は8月21日に長文の「提灯」記事「ウクライナの新興企業が長距離無人機とミサイルを開発、ロシアとの戦いを挑む」を公表した。
冒頭の写真にある巡行ミサイル「フラミンゴ」については、今年、初の巡航ミサイル「FP-5」の試験を完了したもので、FP-5は3000キロメートルを飛行し、標的から14メートル以内に着弾することが可能と書いている。積載量は1150キログラムが可能とされる。このミサイルの初期バージョンは工場のミスでピンク色になったため、彼らはこれをフラミンゴと呼んだのだそうだ。
しかし、これをまったく信じない人たちがいることをThe Economistは明確に書いている。8月27日付のThe Economistの記事のなかには、つぎのような記述があるのだ。
「開発スピードが非常に速く、ウクライナの防衛ニーズにほぼ正確に合致しているこのミサイルは、あまりにも出来が良すぎるように思える。一部の競合他社は、それが事実かどうかを疑っている。大統領府に近いという疑惑、非競争的な資金調達、ミサイルがウクライナのものなのかどうかといった噂が絶えない。」
そう考えると、「ファイア・ポイント」の数十の秘密工場の一つにおいて披露されたとAP通信が伝える、最大1600キロ移動可能なFP-1ドローンについても、はなはだ疑わしい。AP通信は、重さ60キロの爆薬を搭載し、石油精製所や武器庫への攻撃を含め、ロシア領内の奥深くへの攻撃の60%を担っているというテレフの説明をそのまま記事にしている。同社はFP-1ドローンを1日100機生産しているというのだが、この数字は年間約20億ドルに相当する。テレフは2025年は約9000機の生産を予定しているとのべたというのだが、こんな会社の主張を鵜呑みにしていいのだろうか。
「腐敗の追跡」
2025年8月、タフツ大学フレッチャー法外交大学院に所属する平和プロセス研究のための慈善財団、世界平和財団は、報告書「腐敗の追跡: 世界の武器取引における新たなパターン」を公表した。その出だしは、「世界的な武器貿易における腐敗は風土病のように蔓延しており、しばしば見え隠れし、調達プロセスに定着し、国家安全保障の適用除外によって不明瞭にされ、最小限の監視のもとで活動する民間と国家の不透明なネットワークによって支えられている」となっている。この報告書は、世界中の軍関連支出が不明瞭で、腐敗の温床となっている現状を的確に暴き出しており、関心のある者にとって必読の優れた内容になっていると書いておこう。
報告書は、45年間にわたる、63カ国、81社を対象とし、購入国と売却国の産業界と政府関係者が関与した、Corruption Tracker(CT)のデータベースで、CT調査チームによって文書化された59の個別事例から武器取引腐敗の新たな傾向を分析したものである。この分析の基本的視角は、「C=M+D-A」という公式によって表されている(Robert Klitgaard, “International Cooperation Against Corruption,” Finance & Development, International Monetary Fund 35, no. 1, March 1998)。腐敗(corruption)は、独占(monopoly)と裁量権(discretion)があると、より腐敗しやすくなり、説明責任(accountability)が果たされれば、抑制される傾向をもつ。
当然、急増するウクライナの軍事費に絡む腐敗も増えている。報告書は、「ウクライナ戦争に関連する武器取引や移転も例外ではなく、軍事調達に組み込まれた体系的な非効率性と腐敗を物語っている」としたうえで、「何十億ドルもの国際援助が国防に注ぎ込まれているが、その大部分は、管理不行き届き、技術的な不備、そして全くの不正行為によって効果を失っている」と指摘している。「ウクライナ国防省が10万発の迫撃砲を購入するために400万ドル以上を支払ったが、その金は仲介者のさまざまな口座に振り込まれたまま届かなかったという事件があるように、ウクライナ国防省は国防をめぐる官僚と企業の利益ネットワークを維持している」、とも書かれている。
軍事費に湯水のように資金が投入されるなかで、「ファイア・ポイント」のような政治家と癒着した組織に膨大なカネがつぎ込まれ、まったくいい加減な兵器が製造されている可能性があっても、そもそもそれを立証したり、監視したりすることが困難なのだ。だからこそ、この分野では確実に腐敗が蔓延するのである。
軍産複合体の腐敗の構造
報告書は、武器製造にかかわる軍産複合体をめぐる一般的な腐敗構造について、簡単に概括している。第一に、プライム・コントラクターと、ニッチな部品サプライヤーを含む下請け業者の網が、マージンを水増ししている。第二に、防衛省や軍事計画を管理する組織が、しばしば無駄な支出(「サンクコスト」)を公に認めることを避け、それでも「コスト・プラス」契約に繰り返し合意する結果、請負業者にコスト超過を許したり、あるいは引き起こしたりするインセンティブを与える。つまり、これは、プロジェクトが計画よりも多くの費用を費やす状況(オーバーラン)が抑止されるよりもむしろ報われるサイクルを永続させ、無駄遣いがより起こりやすくなる。
第三に、輸出信用機関や国営金融機関などの政府系金融機関は、武器がたとえ高値で輸出されたとしても、国際販売を保証したり、財政的に支援したりして、買い手が購入できるように保険や融資を提供し、輸出業者がより高い価格を請求することを奨励する。買い手(輸入国または外国企業)がローンを返済できなくなったり、支払いが滞ったりした場合、そのリスクと経済的負担は買い手ではなく、輸出国の納税者にのしかかる。したがって、輸出企業は買い手の支払能力に関係なく支払いが保証されるという恩恵を受ける。この一連の金融取引は恣意的であり、十分な説明責任を伴って行われるわけではない。
第四に、武器取引には、仲介業者がつきものであり、ロビイ活動をする会社や商業エージェントも取引にさまざまなかたちでかかわることがある。そして、それらは、最終契約価格に手数料を折り込む。ここでも、取引そのものが不透明で、恣意性が高く、説明責任が果たされることはない。産業界が資金を提供するシンクタンクやコンサルタント会社が脅威を煽り、新たな購入を正当化し、軍のエンドユーザー部門は予算シェアを守るために要件を膨らませ、国際調達機関は超過分を加盟国にばら撒く構造が存在するのだ。このなかには、いい加減な報道を繰り返すことで政治指導者に肩入れして、権力に迎合するだけのオールドメディアも含まれている。
第五に、武器取引においては、「オフセット・パッケージ」と呼ばれる独特の商慣習があり、それが腐敗の温床となっている。オフセット・パッケージとは、輸出企業または国が、軍備を売却する条件として、輸入国に経済的、産業的、または技術的利益を追加的に提供することを約束する協定を指す。つまり、軍事物資の供給以上の補償的取り決めで、現地生産、技術移転、雇用創出、買い手の産業への投資、訓練プログラムなどの要件が含まれることもある。なお、「ダイレクト・オフセット」と呼ばれるものは、購入した兵器の現地での組み立てやメンテナンスなど、軍事契約に直接関連する利益を、「間接的オフセット」は、買い手の国の民間企業、インフラ、教育イニシアティブの支援など、軍事契約そのものとは無関係の利益を指している。
オフセット・パッケージは、武器取引におけるサイド・アグリーメントであり、売り手が買い手の経済的または産業的利益をサポートすることを要求するもので、多くの場合、輸入国にとって取引をより魅力的なものにする。ただし、その分だけ取引が不透明になり、腐敗を隠しやすく、説明責任を不問にしやすい。
こうした状況をまとめて、報告書は、「結論として、武器貿易と軍事調達システムは、技術的陳腐化、政治腐敗、財政的不始末に深く悩まされている」、と的確に指摘している。ロビイ主導の非効率、賄賂、高騰した価格は、失敗の連鎖をさらに永続させ、市場の継続以外に戦略的価値を提供することなく資源を消耗する冗長なプロジェクトをもたらす。こうしたシステム上の問題は、国防を弱体化させるだけでなく、軍事作戦の有効性や安全性よりも金銭的利益を優先する利益主導の業界を支えている。ゆえに、「武器貿易は、無駄、汚職、加担する組織といった無用の長物によって支えられている利益主導の産業である」という記述までみられる。これが、世界中に広がっている現状だ。
「知られざる地政学」連載(106):軍事関連の腐敗を考える(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)