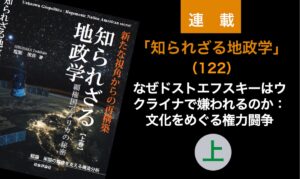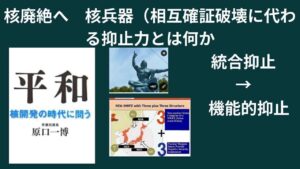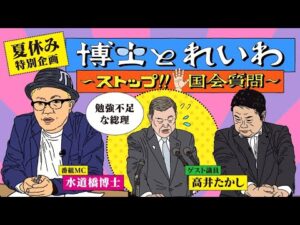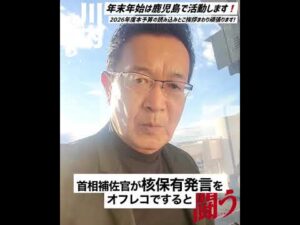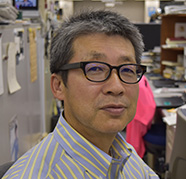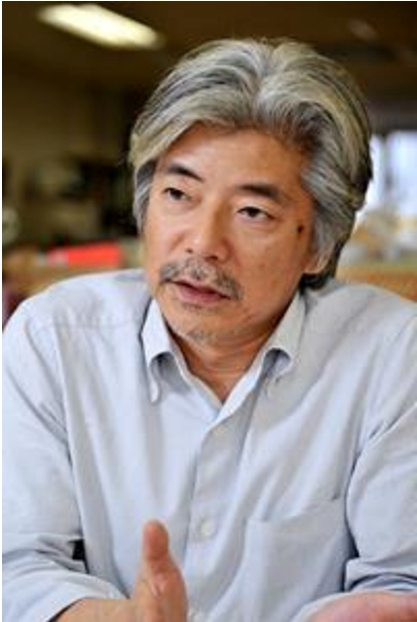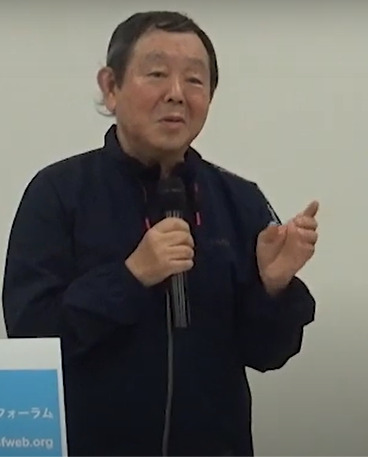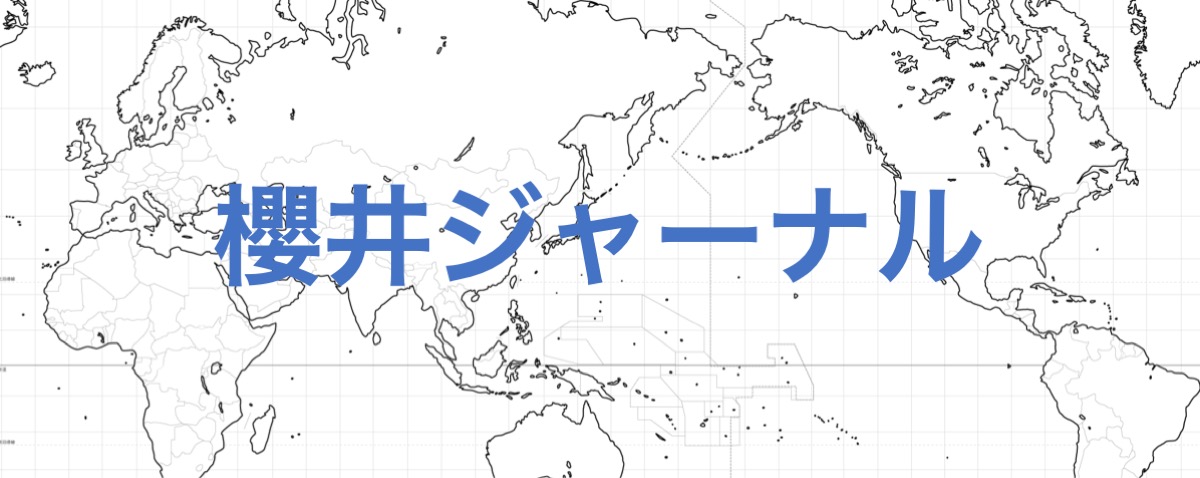
【櫻井ジャーナル】2025.09.07XML : 米大統領は実態に合わせようとしたのか、国防総省の副称号として戦争省を復活
国際政治ドナルド・トランプ米大統領は9月5日、国防総省の副称号として「戦争省」を復活させる大統領令に署名した。この命令は国防総省を戦争省へ恒久的に改称するために必要な措置をとるように勧告している。
第2次大戦後、アメリカは情報機関によるクーデターで他国の政権や体制を転覆させるだけでなく、侵略戦争を繰り返してきた。つまり「国防総省」という現在の省名は実体にそぐわないわけで、今回の命令は間違っていない。
侵略の下地を作るために情報を操作してきたが、それだけでなく、各国の要人を操るための秘密工作にも力を入れている。買収のほか、弱みを握って脅すという犯罪組織が使う手法を駆使してきた。
こうした侵略戦争は相手が弱小国なら有効なのだが、21世紀に入って機能しなくなった。1991年12月にソ連が消滅した直後の92年2月、アメリカの国防総省は新たな軍事戦略DPG(国防計画指針)の草案という形で世界制覇プロジェクトを作成した。その中心は国防次官を務めていたポール・ウォルフォウィッツだったことから、この文書は「ウォルフォウィッツ・ドクトリン」とも呼ばれている。
このドクトリンの前提は、ソ連の消滅によってアメリカが唯一の超大国になったということ。その中にはドイツと日本をアメリカ主導の集団安全保障体制に統合し、民主的な「平和地帯」を創設するとも書かれている。要するに、ドイツと日本をアメリカの戦争マシーンに組み込み、アメリカの支配地域拡大に利用するということだ。このドクトリンに基づき、最初に攻撃されたのはユーゴスラビアにほかならない。
アメリカ政府がユーゴスラビアを解体する準備を始めたのは1984年のこと。ロナルド・レーガン大統領がNSDD133に署名、ユーゴスラビアを含む東ヨーロッパ諸国のコミュニスト体制を「静かな革命」、いわゆるカラー革命で倒そうという計画だ。これにはローマ教皇ヨハネ・パウロ2世も関係していた。
ユーゴスラビアで人権が侵害されているとアメリカの有力メディアは宣伝、「制裁」という名目で経済戦争を仕掛けている。その「制裁」にIMFも協力していた。
IMFは国有企業の私有化を要求、その結果、ユーゴスラビアのGDPは1990年に7.5%、91年には15%というように低下、工業生産高は21%落ち込んで企業は倒産し、失業者が街にあふれた。社会は混乱、それを利用してアメリカは反乱を演出した。チトー(ヨーシプ・ブローズ)政権下に姿を消したファシストがユーゴスラビアを揺さぶりにかかったのだ。
本ブログで繰り返し書いてきたように、第2次世界大戦の終盤にナチスの幹部はアレン・ダレスたちと接触しはじめる。1942年冬に東部戦線でソ連軍にドイツ軍が敗北すると、SS(ナチ親衛隊)はアメリカとの単独講和への道を探りはじめ、実業家のマックス・エゴン・フォン・ホヘンローヘをスイスにいたアメリカの戦時情報機関OSS(戦略事務局)のアレン・ダレスの下へ派遣している。
大戦後、アメリカでは軍の内部で大戦の直後からソ連に対する先制核攻撃が計画され、国務省はコミュニズムに反対する亡命者、つまりナチスの元幹部や元協力者の逃走を助け、保護し、雇い入れる「ブラッドストーン作戦」を1948年から秘密裏に始めている。この年に作成されたNSC20では、「結果として戦争を起こし、ソ連政府を打倒する」という方針が示されていた。(クリストファー・シンプソン著、松尾弌訳『冷戦に憑かれた亡者たち』時事通信社、1994年)
また1945年から59年にかけてドイツから科学者や技術者をアメリカへ運び、雇い入れているが、その中にはSSやSA(突撃隊)を含むナチのメンバーもいた。この工作は「ペーパークリップ作戦」とも呼ばれている。そうした科学者や技術者の中には生物化学兵器の研究や開発に携わっていた人もいたが、この分野では日本人も保護、雇用されている。
大戦中、アメリカ軍も生物化学兵器の研究や開発を行っていた。そこで化学兵器部門の医学部長を務めていたコーネリアス・ローズはロックフェラー医学研究所の出身。化学兵器関連の新しい医学研究所が1943年末までにマサチューセッツ州のキャンプ・デトリック、ユタ州のダグウェイ実験場、アラバマ州のキャンプ・シベルトに設立された。
キャンプ・デトリックは1955年からフォート・デトリックに格上げされるが、ここは今でもアメリカ軍の生物化学兵器開発の中心的な存在である。日本軍による生物化学兵器の研究開発結果は大戦後、フォート・デトリックへ運ばれた。
日本の生物化学兵器の開発は軍医学校、東京帝国大学医学部、京都帝国大学医学部が中心になって進められた。その一環として生体実験をおこなうため、中国で加茂部隊」が編成されている。その責任者が京都帝国大学医学部出身の石井四郎中将であり、その後ろ盾は小泉親彦軍医総監だったとされている。
その後、加茂部隊は「東郷部隊」へと名前を替え、1941年には「第七三一部隊」と呼ばれるようになり、捕虜として拘束していた中国人、モンゴル人、ロシア人、朝鮮人を使って生体実験する。こうした人びとを日本軍は「マルタ」と呼んでいた。この部隊の隊長を1936年から42年、そして45年3月から敗戦まで務めた人物が石井四郎。途中、1942年から45年2月までを東京帝国大学医学部出身の北野政次少将が務めている。
ソ連の参戦が迫っていた1945年8月、関東軍司令官の山田乙三大将の命令で第七三一部隊に関連した建物は破壊され、貴重な資料や菌株は運び出された。監獄に残っていた捕虜を皆殺しになる。捕虜の多くは食事に混ぜた青酸カリで毒殺されたが、食事をとろうとしない者は射殺された。死体は本館の中庭で焼かれ、穴の中に埋められた。日本軍は監獄などを爆破した上で逃走している。(常石敬一著『消えた細菌戦部隊』海鳴社、1981年)
アメリカやイギリスの情報機関はナチスのメンバーや協力者をソ連と戦争する際の手先とも考えていた。例えば、大戦中、ウクライナでナチスやイギリスの対外情報機関MI-6と連携していたOUN-B(ステパン・バンデラの信奉者たち)は1943年春にUPA(ウクライナ反乱軍)として活動し始め、その年の11月には「反ボルシェビキ戦線」を設立。(Grzegorz Rossolinski-Liebe, “Stepan Bandera,” ibidem-Verlag, 2014)
第2次世界大戦後の1946年4月に反ボルシェビキ戦線はABN(反ボルシェビキ国家連合)へと発展し、66年にはAPACL(アジア人民反共連盟、後にアジア太平洋反共連盟に改名)と合流してWACL(世界反共連盟。91年にWLFD/世界自由民主主義連盟へ名称変更)の母体になる。(Scott Anderson & Jon Lee Anderson, “Inside the League”, Dodd, Mead & Company, 1986)
西側諸国はネオ・ナチを「民主勢力」だと主張、ユーロスラビアを侵略する際にはセルビア人を「新たなナチ」だと宣伝、解体作業に取り掛かった。そのための資金はジョージ・ソロス系の団体やCIAの資金を流す道具だったNEDなどから提供された。
1991年6月にスロベニアとクロアチアが独立を宣言、同じ年の9月にはマケドニアが、そして翌年の3月にはボスニア・ヘルツェゴビナが続く。4月になるとセルビア・モンテネグロがユーゴスラビア連邦共和国を結成、社会主義連邦人民共和国は解体された。そしてコソボのアルバニア系住民も連邦共和国から分離してアルバニアと合体しようと計画、それをNATOが支援している。
アメリカがロシアとの戦争に乗り出したのは2008年8月、北京で開幕した夏季オリンピックに合わせてジョージア軍が仕掛けた南オセチアに対する奇襲攻撃だろう。奇襲攻撃の約8時間前、ジョージアのミヘイル・サーカシビリ大統領はロシアとの関係強化を求める南オセチアの分離独立派に対話を訴え、油断させようとしていた。(The Times, August 8, 2008)
この攻撃の約1カ月前、7月10日にアメリカの国務長官だったコンドリーサ・ライスはジョージアを訪問、奇襲攻撃の直後、8月15日にもライスはジョージアを訪問、サーカシビリと会談している。
それだけでなく、アメリカの傭兵会社MPRIとアメリカン・システムズは元特殊部隊員を2008年1月から4月にかけてジョージアへ派遣して軍事訓練している。
またイスラエルの会社は2001年からロシアとの戦争に備えてジョージアへ武器を提供、それと同時に軍事訓練を行ってきた。ジョージアのエリート部隊を訓練していた会社とはイスラエル軍のガル・ヒルシュ准将(予備役)が経営する「防衛の盾」で、予備役の将校2名の指揮下、数百名の元兵士が教官としてジョージアへ入っていた。アメリカのタイム誌によると、訓練だけでなくイスラエルから無人飛行機、暗視装置、対航空機装置、砲弾、ロケット、電子システムなどの提供を受けている。
ロシア軍の副参謀長を務めていたアナトリー・ノゴビチン将軍もイスラエルがグルジアを武装させていると非難している。2007年からイスラエルの専門家がグルジアの特殊部隊を訓練し、重火器、電子兵器、戦車などを供給する計画を立てていたというのだ。(Jerusalem Post, August 19, 2008)ロシア軍の情報機関GRUのアレキサンダー・シュリャクトゥロフ長官は2009年11月、NATO、ウクライナ、そしてイスラエルがジョージアへ兵器を提供していると主張している。(Ynet, November 5, 2009)
当時、ジョージア政府には、イスラエルに住んでいたことのある閣僚がふたりいた。ひとりは奇襲攻撃の責任者とも言えるダビト・ケゼラシビリ国防相であり、もうひとりは南オセチア問題で交渉を担当していたテムル・ヤコバシビリだ。ふたりは流暢なヘブライ語を話すことができた。
南オセチアを奇襲攻撃したジョージア軍はロシア軍の反撃で撃退されたが、この攻撃はアメリカとイスラエルが入念に準備した作戦だった。衝突した部隊の規模はほぼ同じだったにも関わらず、その戦闘でロシア軍は圧勝した。勝利までに要した時間は96時間にすぎない。この先頭でロシア軍の強さを西側は認識しなければならなかった。(Andrei Martyanov, “Losing Military Supremacy,” Clarity Press, 2018)
しかし、アメリカ/NATOはスラブ人蔑視から南オセチアでの敗北を受け入れられなかったようで、2014年2月にはウクライナでネオ・ナチを使ったクーデターを実行、東部や南部のロシアから割譲された地域を征服しようしたが失敗、結局、ロシア軍に敗北した。シリアでもロシア軍は強さを示している。
パレスチナではイスラエルを利用して先住民であるパレスチナ人を欧米諸国は大量虐殺、トランプ政権は艦隊をベネズエラへ向かわせて恫喝し、東アジアで戦争を始める準備を進めている。
確かに「国防総省」より「戦争省」の方が適切な名称だ。
**********************************************
【Sakurai’s Substack】
※なお、本稿は「櫻井ジャーナル」https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
のテーマは「 米大統領は実態に合わせようとしたのか、国防総省の副称号として戦争省を復活 」(2025.09.07XML)
からの転載であることをお断りします。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202509070000/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202410130000/
ISF会員登録のご案内