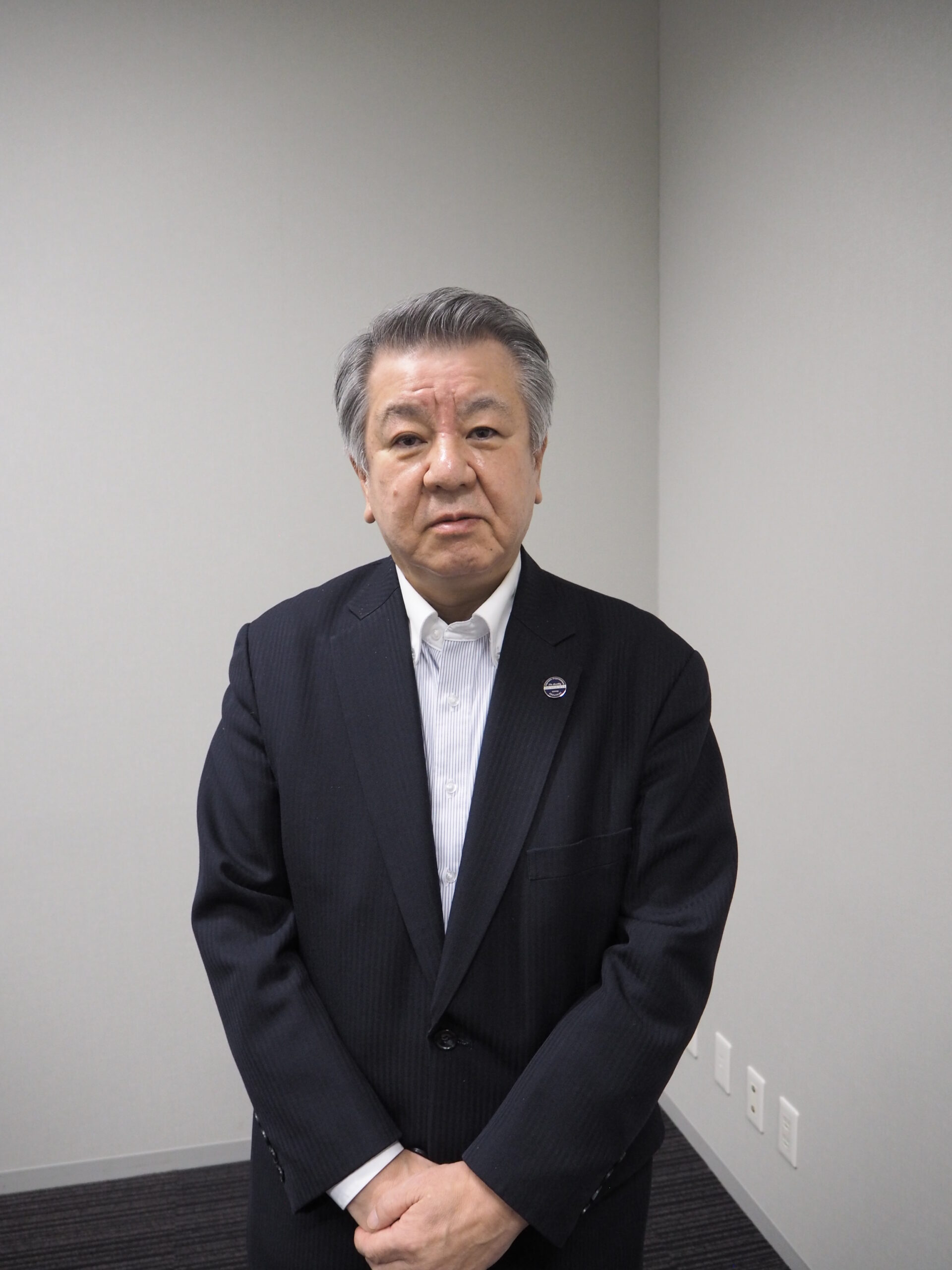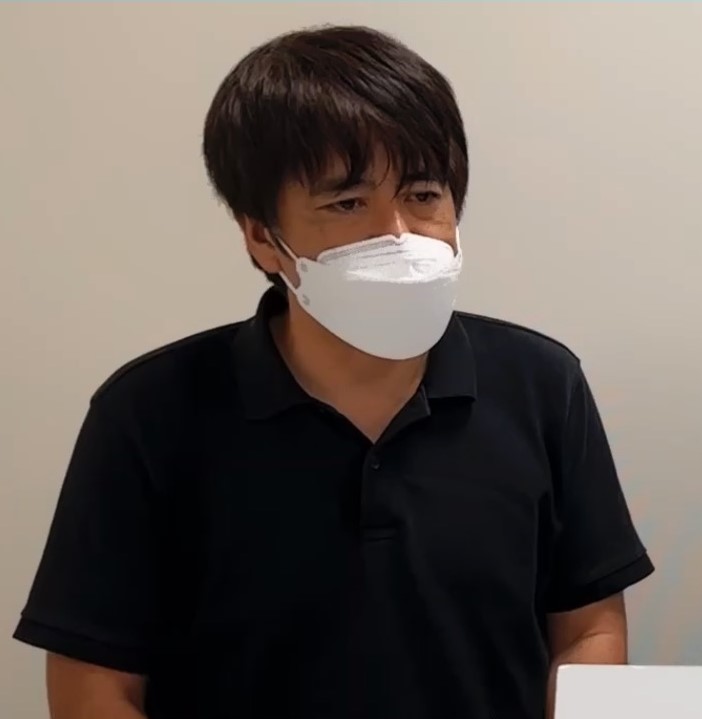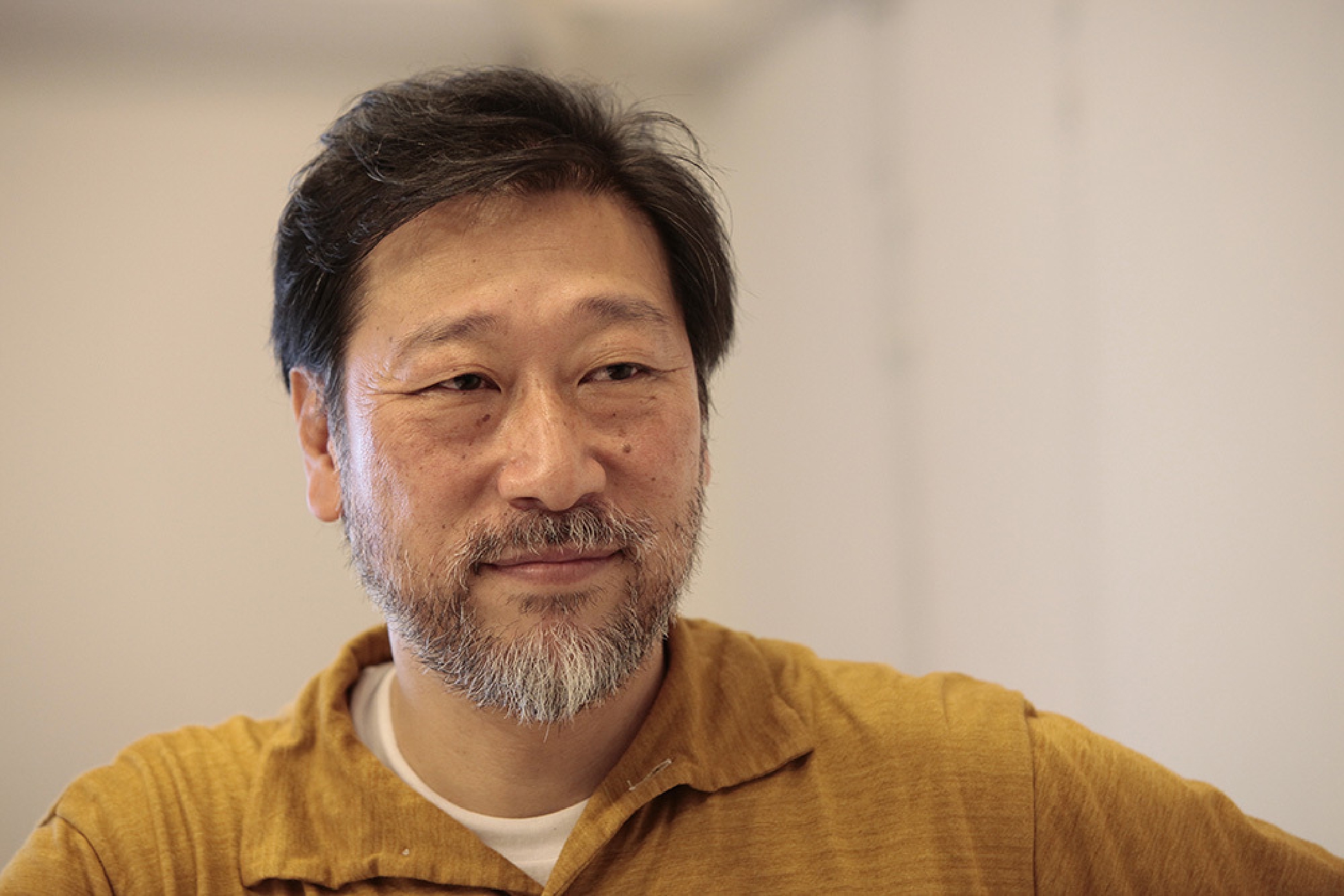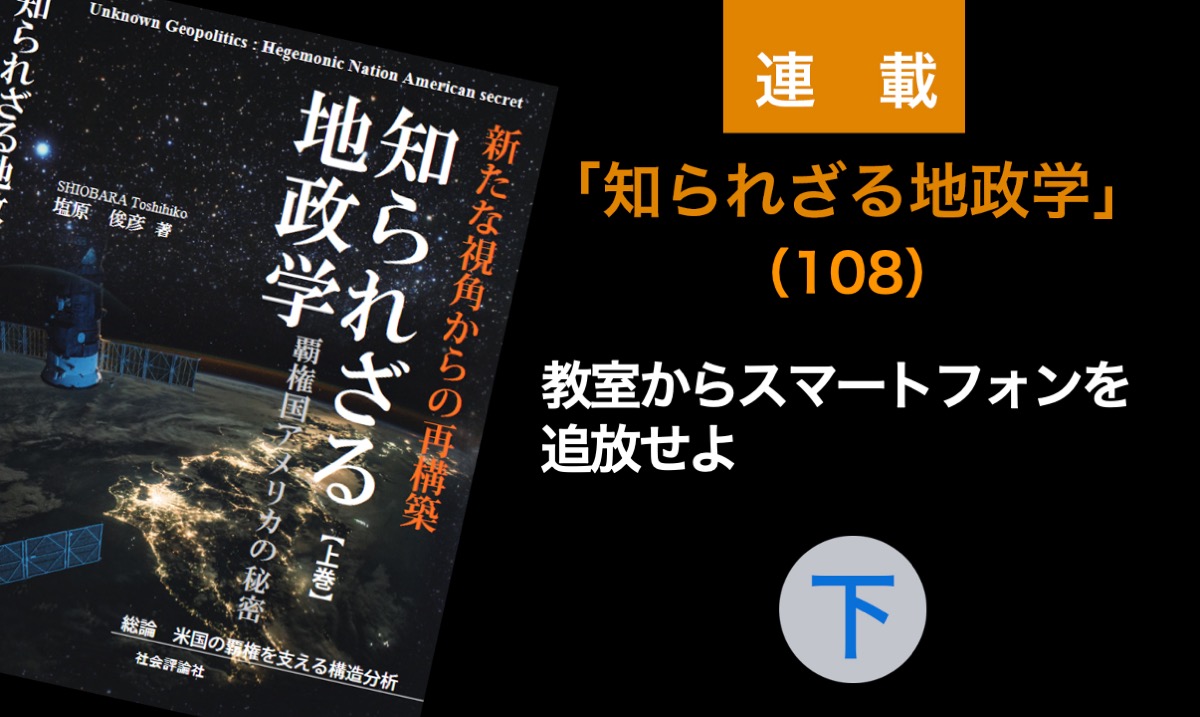
「知られざる地政学」連載(108):教室からスマートフォンを追放せよ(下)
国際「知られざる地政学」連載(108):教室からスマートフォンを追放せよ(上)はこちら
日本の対応
それでは、日本政府はどのように対応してきたのか。文部科学省は2008年7月に、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」、2009年1月に「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」を出し、後者において、「小・中学校の携帯電話持ち込みは原則禁止」としてきた(文科省によれば、「携帯電話」とは、①フィーチャーフォン[いわゆる「ガラケー」]、②スマートフォン、③子供向け携帯電話[基本的な通話・メール機能や GPS 機能のみを搭載しているもの])
だが、2018年6月の大阪府北部地震がきっかけに、大阪府教育庁が登下校時に限り、「持ち込み禁止」から「一部解除」することにしたことを受けて、文科省も、2019年5月に「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」を立ち上げ、緊急時の連絡手段として携帯電話を活用する検討に入った。その結果、2020年7月、「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」が出された。
小学校では、「学校への児童の携帯電話の持ち込みについては、原則禁止」が維持された。しかし、中学校では、「学校への生徒の携帯電話の持ち込みについては、原則禁止」としながらも、個別の状況に応じて、例外的に持ち込みを認めることも考えられることとし、学校又は教育委員会として持ち込みを認める場合には、「一定の条件のもとで持ち込みを認めるべきである」とされた。なお、高校については、校内での使用を制限するというこれまでの方針に変更はなかった。つまり、「児童生徒への携帯電話の普及率上昇といった環境の変化に加えて、自然災害や犯罪に遭遇するなど緊急時の連絡手段として保護者を中心にニーズが高まっていたこと、とくに登下校時は生徒が学校の管理下にないことなどが考慮され、中学校のみ条件付きでスマホの持ち込みを認めることになった」のである(「中学校の「スマホ持ち込み」原則禁止から容認へ災害時など緊急連絡手段としての活用を期待」を参照)。
大切なのは使用禁止
日本の場合、携帯電話を「持ち込み禁止」にするかどうかに着眼点が置かれている。だが、この議論は愚かしい。すでに書いたように、電源を切っていれば、使用できないのだから、学校に携帯電話を持ち込むこと自体は問題ではない。問題は、教育の場で携帯電話を使用することの是非である(持ち込む場合には、電源を切るという原則を徹底させるだけのことだ[地震速報には、教員の携帯電話で対応すればいい])。そのとき、教育の場をどう定義するかについては議論が必要だろう。あるいは、休み時間を含めるべきかどうかという論点もあるかもしれない。携帯電話の使用対象者は、おそらく小中高校生全体を対象者にすべきだろう。理由は簡単だ。「チャプチャプ脳」にならないようにするためである。
そのためには、携帯電話はもちろん、さまざまな情報通信技術(ICT)が「チャプチャプ脳」を生み出しかねない事実を国家がしっかりと認識すべきだろう。つまり、IT産業を儲けさせるために安易に導入されたICT教育そのものをもう一度抜本的に見直す必要がある。
ここまで幅広い影響をおよぼす大問題である以上、文科省が恣意的に学校にける携帯電話の取り扱いを決めるのではなく、国民的な議論をむしろ展開すべきではないか。ICT全般についての使用についての議論につなげることで、より多くの人に「チャプチャプ脳」の怖さに気づいてほしいのだ。
〝ネット・バカ〟の増殖を抑止せよ
2020年5月に、「論座」において、拙稿「内省力を鍛え〝ネット・バカ〟の増殖を抑止せよ」を公表した。そのなかで、「⼼配な『ネット・バカ』の増殖」という見出しのあとに、つぎのように書いておいた。やや長い引用をお許し願いたい。
「ところが、⼈間は残念ながら、この内省⼒を鍛える場を失いつつある。「ネット・バカ」の登場がこれを物語っている。ニコラス・カーは2010年にThe Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brainsを刊⾏した。単数形で「浅瀬」を、複数形で「浅はかな者」を意味する⾔葉がタイトルに使われている。その⽇本語訳が『ネット・バカ:インターネットがわたしたちの脳にしていること』ということになる。
いわゆるソーシャル・ネットワークの利⽤が広がると、深く考えたり内省したりすることなく、反射的に⾃分の想いを発信するような⼈たちが増える。よく⾔えば、フットワークのある柔軟な対応を可能にするが、それは浅薄で⽪相な受け答えだけを促すことになり、じっくりと考えて発⾔することを困難にする。ちょっとした⾔葉遣いや気になる表現だけに反応し、激情にかられて感情むき出しの発信をしたり、「ネット・バカ」たちの集団のなかで目立つために、ますますラディカルな発⾔が増えたりする現象が世界中に広がっている。まさに、「浅はかな者」が増殖している。」
2020年11月には、アンデシュ・ハンセン著『スマホ脳』が刊行された。「スティーブ・ジョブズを筆頭に、IT業界のトップはわが子にデジタル・デバイスを与えない」ことを喧伝しながら、スマホの便利さに溺れているうちに脳が確実に蝕まれていく現実を描いている。
こうした危機感は5年もの歳月の経過とともに、より深刻化している。「浅瀬」でチャプチャプするだけの脳をもつ「浅はかな者」がますます増殖しつづけているように思われる。まだ刊行していない拙著『無知』(仮題)のなかでは、塩田武士著『踊りつかれて』という連載小説を題材にして、つぎのように記述している。
「この小説のなかに、人間の思考が偏っていく行程として、「確証バイアス」、「アルゴリズム」、「フィルターバブル」、「エコーチェンバー」、「集団極性化」といった用語が紹介されている(『週刊文春』2023年9月21日号、72頁)。
「確証バイアス」は自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向のことである。「アルゴリズム」は機械学習のための計算方法で、それゆえに偏ったデータによるバイアスが生じる。「フィルターバブル」は、アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することである。個々のユーザーにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」のなかに孤立するという情報環境を指す。「エコーチェンバー」は、ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローする結果、意見をSNSで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたものだ。「集団極性化」は集団で意思決定を行う際、個人で意思決定を行う際よりも極端な意見になりやすいという心理現象を指している。
さらに、小説では、「コスパ」(コスト・パフォーマンス)や「タイパ」(タイム・パフォーマンス)、「アシスト機能」の重視が人々から思考時間を奪い、見栄えや承認欲求という「浅瀬」を延々移動し続ける漂流状態が「短小文化」と呼ばれていると紹介している。そのうえで、「浅瀬ですぐに善悪を決めてしまう人の増加は、ネット上の悪化と言うべき「偽情報と怒り」をウイルスのような速度で拡散させ、実体と乖離した虚像を「たった一つの事実」として信じ込ませる」と指摘している。
別言すると、本当はわずかな知でしかない個人知が安易な検索で得た集合知を活用しながら、外部に垂れ流され、それが小さな集合知をいくつも生じさせ、全体として知の劣化につながっているようにみえる。
こうした偏った見方が広がる現状に嫌気がさして、こうした情報を「ノイズ」として耳を塞ぎ、目を瞑ろうとする人もまた増えている。すでにのべた批評的無視が求められている所以である。」
ここに書いたような事態は、安易なスマホ使用によってますますひどくなっているのではないか。より多くの国民に事態の深刻さを知ってもらうためには、むしろ政治化させることが求められているように思えてくる。
とくに、テレビや新聞といったオールドメディアは、こうしたICTがもたらす変革について鈍感だ。その結果、本当はとても深刻な状況が起きているにもかかわらず、問題の所在さえ明確につかめていない。だからこそ、政治問題化させて、より多くの人々に「チャプチャプ脳」にならないように警鐘を鳴らさなければならないのだ。
恐ろしく変化するデジタル・デバイス
2025年9月8日付の「ニューヨークタイムズ」(NYT)は、「AIがスマホを過去のものにするかもしれない。次に来るものは?」という興味深い記事を公表した。もはや、スマホを教室から追い出すだけでは不十分な時代が到来するかもしれない。
記事がイメージしているのは、ソフトウェアのメニューをスマホの画面に指を軽く触れた状態で行いたい操作に応じて指を必要な方向に滑らせ(スワイプし)たり、キーボードをタイプしたりする必要がなくなる状況である。AIアシスタントが我々に代わってデバイスを使用し、友人との予定を立てたり、買い物リストを作成したり、会議でメモを取ったりといったタスクを自動的に実行するようになれば、アプリなどはあまり重要ではなくなるため、携帯電話で操作するのに慣れているオペレーティングシステムや起動するアプリなどはバックグラウンドで消えはじめるというわけだ。こうなると、近い将来、スマホのハードウェアは、新しい重要なパーソナル・コンピューティング・デバイスに取って代わられるかもしれない。たとえば、AIを搭載したメガネやブレスレットが我々の周囲を認識し、アシスタントは基本的に我々と共存して一日中助けを提供するようになるだろう。
たとえば、以前から有力なデバイスとして有望視されてきたスマートグラスは、さらなる進化を遂げている。メタは2024年、カメラ、スピーカー、マイクを備えたレイバンのスマートグラス「メタ」のソフトウェア・アップデートにより、AIアシスタントであるメタAIがメガネに搭載され、ユーザーは動物園の動物から歴史的建造物まで、見ているものについて質問できるようになった。さらに、メタは昨年、フレームにスクリーンを組み込んだメガネのプロトタイプ、オリオン(Orion)を発表した。グーグルは2025年、AIアシスタント「ジェミニ」を搭載した同様のメガネのプロトタイプを発表した。
ただし、薄くて小さいデバイスではバッテリーの寿命は短く、バッテリーが大きくなればなるほどメガネは大きく醜くなってしまう。その意味で、スマートグラスが本当に新しいパーソナル・コンピューティング・デバイスの主流となるかどうかは判然としない。
アンビエント・コンピューターが張り巡らされることで、スマホの一部の機能を代替できるようになるかもしれない。アンビエント(ambient)」には、「周囲の」あるいは「環境の」といった意味がある。スマホに依存するようになると、さまざまなアプリからの通知に常にさらされるため、気が散ることがある。こうした鬱陶しさを避けるために、「家のなかに溶け込む」ようにコンピューターを配置・利用するものだ。家の至るところに設置されたマイク付きのスピーカーやスクリーン、体に装着するガジェットなどがそれにあたる。
AIアシスタントの登場によってアンビエント・コンピューターの重要性が高まると予測されている。アマゾンが今年から展開し始めたAlexa+のような新しいアシスタントとの流動的な会話を可能にするため、人々は特定のタスクを電話で行うよりも簡単にこなすことができるようになる。
このように、スマホの時代もまた変化を遂げつつある。こうしたなかで、とくに子どもたちをどう守ればいいかについて、本当は真剣に考えてみる必要があるのではないか。
「政治化」の必要性
連載(107)「「国家資本主義」への傾斜がもたらす「政治化」の拡大」(上、下)において、つぎのように記した。
「本当の問題は、第二期トランプ政権の経済政策が公平・公正性を担保するための諸制度・規制を破壊し、競争的自由市場を歪め、国家のもつ合理的暴力装置を駆使した力による金権政治に陥っている点にある。国家資本主義に傾くことで、特定の金持ちの利益に沿った政策がさまざまな分野で脅迫や恫喝のもとに実施されるようになっている。いわば、トランプと親密な関係を築いた寡頭資本家(オリガルヒ)が国家権力を笠に着て権威主義的に市場でふるまうことが可能となり、それは長期的な成長戦略などを毀損してしまうのだ。
なぜなら、科学にしてもテクノロジーにしても、国家資本主義はさまざまな分野における「政治化」をもたらし、一部の富裕層(オリガルヒ)のために公的政策が恣意的に歪められてしまうからだ。人類全体にとって有益な長期戦略のもとに国家の資金を投入するといった発想自体が崩れてしまいかねないのである。」
至る所で「政治化」が起きている現実をみると、むしろ、この政治化に対して、人々をどう巻き込んでより良い解決へと導くのがいいかを検討するほうがいいように思えてくる。そのためには、近代化が生み出した各国家主権を中心に据えた権力構造ではない別の統治形態が必要な気がする。国家によって、スマホなどのデジタル・デバイドへの対処法が異なる以上、まったく別の「取扱説明書」があってもいいはずだ。そんなことをいま、考えている。
そのためにも、オールドメディアはここで紹介したような「スマホ利用の世界のいま」について詳細に報道しなければならない。不勉強でありながら、自分がアホであることにさえ気づいていないバカそのもののマスコミ関係者が多すぎる。こんなバカの報復を恐れて、マスコミを糾弾しない者も多い。それでは、この国はアホやバカによって埋没するだけだろう。そうなると、参政党に期待したくなるのは私だけか。立憲民主党や日本共産党はいったい何をやっているのだろうか。もっと大胆かつ的確な主張をしろよ!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)