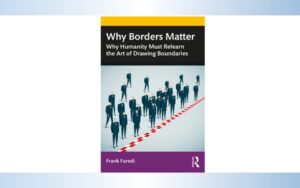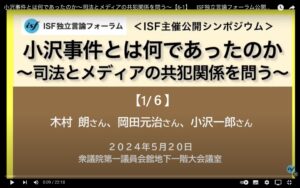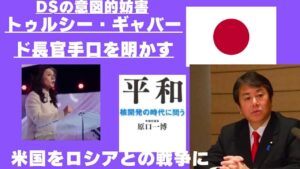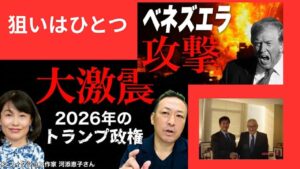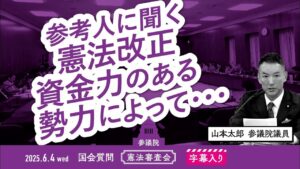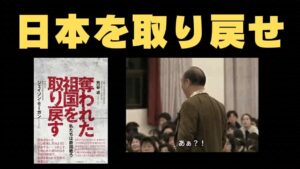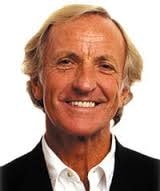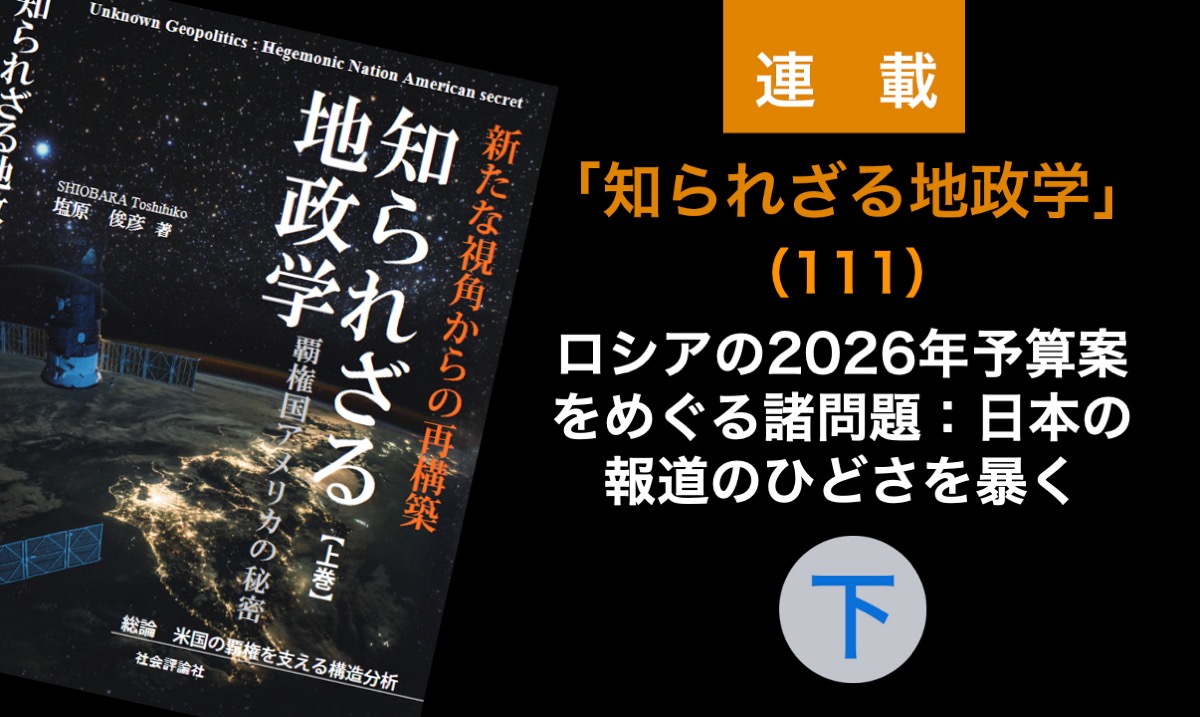
「知られざる地政学」連載(111):ロシアの2026年予算案をめぐる諸問題:日本の報道のひどさを暴く(下)
国際
「知られざる地政学」連載(111):ロシアの2026年予算案をめぐる諸問題:日本の報道のひどさを暴く(上)はこちら
ロシア経済をみる視点
すでに何度か書いたように、ロシアは軍事経済に移行している。そうしたなかで、重要なのは、もっとも優れたロシアの軍事経済分析家ジュリアン・クーパーが8月29日に公表した論文「対ウクライナ戦争開戦前後のロシアにおける軍事生産」および4月にストックホルム国際平和研究所(SIPRI)のサイトに公開された論文「4年目の戦争に備える: ロシアの2025年予算における軍事費」である。「この二つの論文を精読しなければ、ロシア経済を語ってはならない」と私は考えている(優れた先行業績をフォローするのは当然だ)。
まず、確認したいのは、前者において、「長年にわたるデータの調査によると、全体として、発表されたデータは信頼性が高く、誤った表現はあるものの、明らかな偽装はみられない」、とクーパーが書いている点だ。ソヴィエト連邦の崩壊後、ある程度は秘密主義が緩和されたが、今日に至るまで、ロシアの公式統計機関である連邦国家統計局(通称Rosstat)は、同国の防衛産業の軍事生産に関するデータを公表していないが、さまざまな情報を駆使すれば、ある程度まで秘密主義をかいくぐることができるというのである。
軍産複合体の集中化
前者の論文のなかで刮目すべき指摘は、2022年12月末、軍需産業に秩序をもたらすための断固とした措置がとられたというものだ。財務省管轄の企業数社を含む、この部門のもっとも著名な14社が、100%連邦所有の株式会社に転換するために、国家コーポレーションと呼ばれる国有のロシアテクノロジー(Rostec)に譲渡されるよう大統領令が出されたのである(注1)。次いで、その実施を命じる政府命令が出された。そのリストには、カザン、ペルミ、タンボフ(コトフスク)の火薬工場、およびカザン精密機械工場、サマラ・コムナル工場などが収載されている。その狙いは経営状態を改善し、できるだけ早く近代化することであり、Rostecの破綻企業再建に関する豊富な経験を活用することだった。
ロシアの戦時経済は、2022年10月にプーチンが、特別軍事作戦に必要なすべての物資が生産され、供給されることを保証するための新たな体制を構築する決定を下して以降、構築された(このあたりについては拙著『ウクライナ戦争をどうみるか』などですでに何度も論じた)。それは、軍需品の配送や修理、軍服、医療衛生用品、修理や復旧作業、後方支援など、戦争遂行中に発生するニーズに対応することを目的として設立された、「政府調整評議会」が主導して運営されている。この評議会は首相が議長を務め、国防省、内務省、非常事態省、ロシア連邦保安局、対外諜報庁、特別プログラム総局(いわゆる「特別オブジェクト」と呼ばれる安全な防空壕の建設と管理により、戦争時に政府の存続を確保する責任を負う)など、主要な「権力執行」省庁の代表者とその他の連邦省庁の代表者で構成されている。
ロシアでは2024年5月、ロシア政府の新閣僚が承認され、国防および軍需産業にかかわる人員の大幅な入れ替えが行われ、すでに長期消耗戦のための政府幹部の配置を終えている。セルゲイ・ショイグが安全保障会議書記に任命され、プーチンの軍事産業委員会(VPK)副委員長に就任した。国防相には、以前は第一副首相で、軍務経験のないキャリアエコノミストのアンドレイ・ベローソフが就任した。第一副首相には、以前は国防産業を監督する産業相であったデニス・マントゥーロフが就任した。この役職は現在、以前はカリーニングラード州知事であったアントン・アリハノフが務めている。プーチンは、国防産業の監督を担当する大統領府の補佐官として、国防産業の主要企業が集中するトゥーラ州の元知事アレクセイ・デゥーミンと、造船産業を担当する安全保障会議書記のニコライ・パトルシェフを任命した。デゥーミンは 調整評議会とVPKの両方に任命されている。これらの変更は、戦争遂行の決意、軍事予算の費用対効果の高い使用、必要な兵器と弾薬の効率的な生産と軍への供給を確保する決意を示している。
8月公表の論文でクーパーは、「しかし、観察者たちがしばしば表明する見解とは異なり、ロシアには「戦争経済」は存在しない」と結論づけている。「ロシアには「戦争に適応した」経済がある」というのである。それは、「国家管理下の防衛部門が機能する市場経済の枠組みのなかで運営されている」という経済だという。だからこそ、市場変動や対ロ制裁に機動的に対応できるのかもしれない。4月公表の論文では、クーパーは「2025年、ロシアはGDPの7.2%にあたる15.5兆ルーブルを軍事費に充てることを計画している。これはソ連時代以来最大の割合だが、1990年の12~13%の水準にはまだほど遠い」と指摘し、「経済実績が大幅に悪化しなければ、このレベルの支出は管理できるはずである」と結論づけている。
私も基本的にクーパー説に賛成だ。すでに何度か指摘したように、ロシアにはソ連時代からの国防発注制が整備されており、こうした管理制度があるからこそ、「戦争に適した」経済を運営できるのである(本当に戦争に備えるためには、日本もロシアの国防発注制を学ぶ必要がある。それは、岸信介が満州でソ連の5カ年計画を模倣したのと同じだ)。
アレクサーシェンコの見方
もう一人、ロシア経済を語るとき、耳を傾けるべき人物として、ロシア中央銀行元副総裁でロンドンNESTセンター上級研究員のセルゲイ・アレクサーシェンコがいる。9月10日に公表されたインタビューのなかで、彼はきわめて真っ当な議論を開示している。
まず、財政赤字について、彼は、「たしかに、現在、ロシアの予算支出の約5分の1は借入によって賄われており、財務省のデータによると、赤字はGDPの3.7%に達している」とのべている。そのうえで、「これはあまり良くないように思われるが、他方では、米国の財政赤字はGDPの6%を超え、予算支出の約3分の1が借入によって賄われている」、と指摘している。日本の財政赤字/GDPは200%を超えている。これらの事実を知っている者からみると、ロシアの財政赤字/GDPを議論すること自体が僭越ということになるだろう。
ついで、アレクサーシェンコは成長率について、「数字を真剣に追っている専門家の多くは、昨年末にはすでに経済が減速し始めていることに気づいていた」とのべる。ここで理解すべきは、ロシア経済は二つの交わらない部分で構成されているということだという。一つは軍事経済で、戦線のため、勝利のためのすべてがそこにある。もう一つは、戦争にかかわらない民間部門だ。民間部門が減速しはじめたことは、2024年の夏にはすでに明らかになっていた。そして2025年の初め頃、軍事セクターの成長の勢いは、民間セクターの落ち込みとほぼ同じくらいだったことがわかった。その意味で、有力財界人のゲルマン・グレフが「ロシアは技術的停滞状態にある」って言ったことは正しいという。
アレクサーシェンコは、「実際、専門家からみると、ロシア経済は悪い状況にある」という。なぜなら、経済成長は、社会や将来にとって何の役にも立たない分野に集中しており、成長していないからだ。これは、経済という体が健康ではないことを示している。それでも、「それはプーチン大統領が、軍事費は言うまでもなく、社会支出を賄う資金をもっていないことを意味するものではない」、とアレクサーシェンコは指摘する。そのため、経済の状況は社会にまったく影響を与えておらず、「現在、ロシア国民は成長の停滞を実感していない」というのだ。
おそらく、ここで紹介したクーパーやアレクサーシェンコの見方がロシア経済の実情に近いのではないだろうか。偏見にとらわれずに、真正面から現実に向き合えば、この程度のことしか言えない。なお、プロコペンコは論文の最後の一文として、「ロシアは、財政ステロイドのマラソンランナーから、徐々に低下する生活水準と民間部門の停滞を背景に、低成長、緩やかな高インフレ、長期化する高金利、増税による財政健全化、財政支出の中核維持という国へと変貌しつつある」と書いている。穏当な結論と言えるだろう。
足元の懸念
どうだろうか。日本の報道は相当にまずいと思わないだろうか。「嘘」を垂れ流しても、文句を言ったり批判したりする者も少ない。ゆえに、ディスインフォメーションを吹聴する者が減らない。
私がいま心配しているのは、ロシアの燃料危機を過度に喧伝する、愚かな報道である。またしても、ディスインフォメーション工作によって、もう少し戦争をつづければロシア経済が破綻するかのような幻想をもたせようとしている。
この動きに火をつけたのはドナルド・トランプ大統領だ。9月23日、彼はTruthSocialにおいて、つぎのように投稿した。
「実際、彼らを「紙の虎」(a paper tiger)のようにみせている。モスクワ、そしてロシア全土の大都市、町、地区に住む人々が、この戦争で何が起きているのか、長蛇の列ができてガソリンを手に入れることがほとんど不可能であること、そして、彼らのお金のほとんどが、偉大な精神を持ち、ますます良くなっているウクライナとの戦いに費やされている戦争経済で起きている他のすべてのことを知ったとき、ウクライナは本来の形で自分たちの国を取り戻すことができるだろう!プーチンとロシアは経済的に大きな問題を抱えている。今こそウクライナは行動を起こす時だ。」
「紙の虎」の物語
まず、「紙の虎」の物語について説明しておこう。日本人には、「張り子のトラ」がイメージされるが、一部の情報では、もともとは、毛沢東がインタビューのなかで米国とその原子爆弾を指して使った言葉だという。毛沢東はつぎのように話した。
「原爆は、米国の反動主義者が人々を怖がらせるために使う紙の虎だ。恐ろしいように見えるが、実際はそうではない。確かに原爆は大量破壊兵器だが、戦争の結果を決めるのは人間であって、一つや二つの新兵器ではない。反動主義者は皆、紙の虎である。表面的には反動派は威圧的だが、実際にはそれほど強くない。」
この言葉をトランプは、ロシアの経済問題に関連づけて使用したことになる。つまり、ロシア経済は戦争経済や制裁の打撃を受けずにしっかりしているようにみえるが、実際には、「経済的に大きな問題を抱えている」というのである。
なお、プーチン自身は10月3日、ソチで開催されたヴァルダイクラブの会議で、紙の虎を軍事問題に結びつけて論じた。プーチン大統領は、「もし我々がNATO圏全体と戦争状態にあり、非常に前進し、自信をもっているが、それが紙の虎のようなものだとしたら」と反問し、「では、NATOそのものとは何なのか?それでは何なのか?」とのべたのである。
ガソリン不足問題
むしろ、大問題なのはガソリン不足かもしれない。10月1日は、「9月28日現在、ロシアでは一次石油精製能力の38%(1日当たり約33万8000トン)が稼働停止中であると、RBCがSiala社のデータを引用して報じた。現在稼働している生産能力は、専門家が1日あたり55万5000トンと推定している」、といったニュースが流れた。
10月2日になると、「ノーヴァヤガゼータ・ヨーロッパ」という親米的なメディアが「燃料危機のなか、ロシアではガソリン価格が高騰している。ガソリンの販売規制を導入した地域もある」とする記事を公表した。それによると、9月23日から29日にかけてガソリン消費者物価の伸びは加速し、前週比0.80%に達した。年初と比較すると、9月29日には9.22%上昇し、一般的なインフレ率(年初から4.29%)を2倍以上上回ったという。
さらに、ディーゼル燃料市場でも問題が深刻化している。9月23日から29日にかけて、消費者物価は0.64%、軽油は年初から3.66%上昇した。9月29日現在、国内のディーゼル燃料の平均価格は1リットルあたり72.63ルーブルである。
この結果、下の地図に示した、少なくとも18の地域と併合されたクリミアの計19地域でガソリン問題が報告されているという。
燃料危機にはいくつかの原因がある。「ノーヴァヤガゼータ・ヨーロッパ」は、①ドローンによる製油所攻撃、②燃料需要の高騰、③製油所への予算補助金の削減――を挙げている。事態への対応策として、政府は2025年3月1日以降、非生産者(貿易業者や油槽所など)のガソリン輸出を禁止してきたが、政府間協定に基づく供給を除き、すべての企業に対して年末まで禁輸措置を延長することにした。アレクサンドル・ノヴァク副首相は、非生産者によるディーゼル輸出にも同様の禁止措置が課されるとのべたという。

2025年9月、19地域の住民がガソリン問題に言及
(出所)https://novayagazeta.eu/articles/2025/10/02/v-kanistry-zalivat-zapretili
このように紹介すると、大変な事態が起きていると思うかもしれない。しかし、本当はそう単純に解釈するのは間違いだ。「マイナス38%。ロシアの製油所の問題の大きさはどの程度か」という論文によると、「ロシアの製油所の総能力は年間約3億2700万トンだが、実際にはロシアは2億6000万トンから2億7000万トンしか精製せず、1億1000万トンから1億2000万トンの石油製品を消費している」。つまり、「つまり、遊休設備38%のうち22%は永遠に遊休状態であり、残りの78%はロシアの消費量をはるかに上回る製品を生産している」という。22%の設備がいつまでも休止している理由はさまざまだが、多くの場合、これらの設備は古いものであり、実際には、製油所に置かれたままほとんど廃止されたものであると説明されている。さらに、ロシアは、国内消費に必要な量のほぼ2倍のディーゼルを生産し、16%多いガソリンを生産している。また、ナフサ(ガソリンの半製品)の生産はガソリン消費量の60%に当たる。現在、そのほとんどすべてが輸出されており、必要であれば、最高品質ではないものの、非常に簡単にガソリンをつくることができる。
つまり、ガソリン不足が本当に深刻ならば、ナフサ生産を縮小すれば対応できる。たとえば、台湾は、他の対ロ制裁に参加し、自らをウクライナの同盟国とみなしているにもかかわらず、半導体産業に必要な化学物質を製造するために使用される石油派生品であるロシア産ナフサの世界最大の輸入国となっている、と「ザ・ガーディアン」は10月1日付で報じている。2025年上半期、台湾は13億ドル相当のロシア産ナフサを輸入し、月平均輸入量は2022年平均の約6倍の水準に達した。2024年上半期と比べ、台湾の今年のナフサ輸入量は44%増加したという。「2022年2月以降、台湾はロシア産ナフサ680万トン(49億ドル相当)を輸入しており、これはロシアの石油製品輸出総額の20%に相当する」という記述まである。ロシアに対する他の制裁措置に加わっているにもかかわらず、エネルギー需要を圧倒的に輸入に頼っている台湾は、ロシアの化石燃料の購入に制限を課していない。しかし、このナフサ輸入が問題化しても、ロシアは台湾に輸出できなくなったナフサでガソリン生産を増やせば、あまり大きな影響を受けないかもしれない。
他方で、先の論文は、「一次精製能力の低下(常圧蒸留塔の1基の故障)は、原則として、市場性燃料の生産量の比例的な低下を意味しない」と指摘している。一次精製能力(すなわち、生産するガソリンやディーゼル燃料の半製品の量)は、ほとんどの場合、規格に適合する自動車燃料を生産する後続のカスケードユニットの処理能力を上回るからだ。ゆえに、たとえば2基の同じ精製塔のうち1基が停止した場合、ガソリンの生産量は予想される50%減ではなく、25~30%減となる可能性がある。つまり、「ロシアでは一次精製能力の40%が休止している」と言っても、「ガソリンの生産量が40%減少したことにはならない」のである。
「騙されるな!」
このように、マスメディアや似非学者の一知半解の情報は、決して信用できない。その意味で、読者は騙されないように注意を払う必要がある。とくに、ウクライナ戦争をめぐっては、何かにつけて「ロシア=悪」、「プーチン=悪」という短絡的な偏見ばかりが際立っている。どうか、「転ばぬ先の杖」、「石橋を叩いて渡る」、「備えあれば憂いなし」、「濡れぬ先の傘」といった警句を思い浮かべてほしい。
もちろん、この論考への疑いの目も忘れてはならない。ただ、私はできるだけ情報源にアクセスできるようにURLを埋め込んでいる。疑惑を感じたら、そちらにアクセスして熟考してほしい。大切なのは誠実さであり、誠意こそ学問の基盤なのである。
【注】
(注1) ロシアテクノロジーについては、拙稿「「国家コーポレーション」と「ロシアテクノロジー」(『ロシアNIS調査月報』ロシアNIS貿易会2007年12月号, 11-24頁)や、「国家コーポレーションを探る:ロシアテクノロジーを中心に」(『ロシアNIS調査月報』ロシアNIS貿易会2010年9-10月号, 80-93頁)を参照してほしい。あるいは、Kindle版の『ロシアの最新国防分析』(2016年版)も参考になるだろう。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)