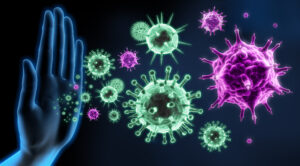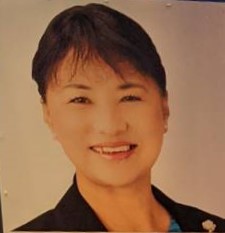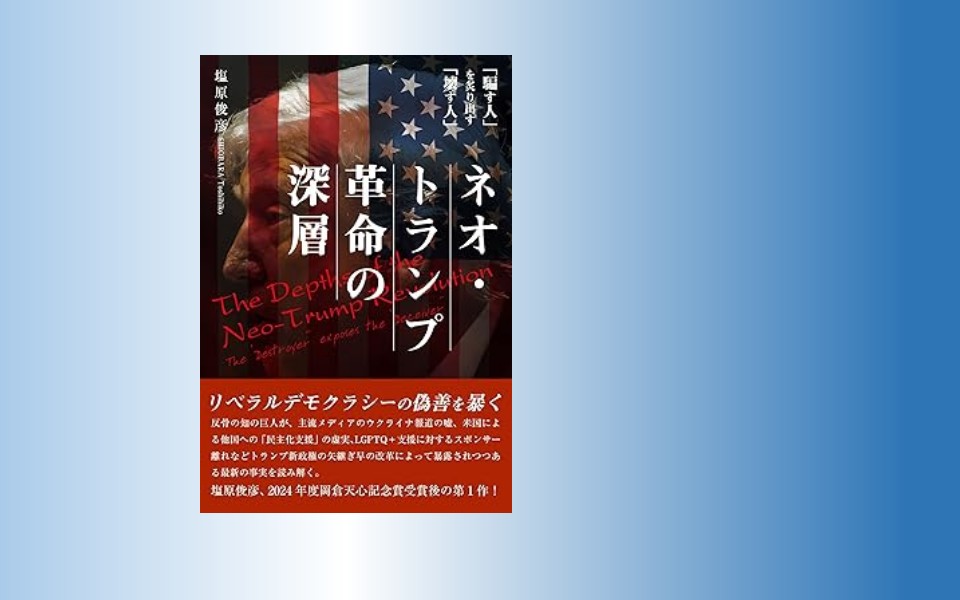
【書評】塩原俊彦著『ネオ・トランプ革命の深層 「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社)
映画・書籍の紹介・批評塩原俊彦氏は、ISF独立言論フォーラムに連載中の「知られざる地政学」(https://isfweb.org/series/【連載】知られざる地政学(塩原俊彦)/)や、主催する「21世紀龍馬会」(https://www.21cryomakai.com/21cryomakai/)での活動等で知られる気鋭の論客である。
ただし、大手マスコミへの露出度はさほど高くはない。同氏がこれらマスコミを「オールドメディア」と呼び、その欺瞞性や不勉強ぶりを問いかけてやまないためだろうと、私は思っている。植草一秀氏らとともに、彼らの真の急所を痛撃する正論の数々は、当然ながら大手マスコミには出てこない性質のものだ。今回の新刊「ネオ・トランプ革命の深層」も、大変有益な情報や洞察を多く含む優れた著作であるが、大手マスコミにはその書評が載る確率は低い。そこで僭越ながら、私がその書評を書かせていただくことにした。
ドナルド・トランプという人は、様々な面で極端というか目茶苦茶なことをやっている面があり、世界中に混乱を招いているのは事実だ。日本では米国民主党びいきな主要マスコミの論調もあってトランプ否定論が多い。しかし本書の著者塩原氏は、大多数のトランプ叩きとも、右派系論者のトランプ礼賛一辺倒とも一線を画し、是々非々の評価に徹している点が優れている。
トランプは、ヘゲモニー(覇権)国家アメリカの構築してきた秩序や価値観の体系のようなものを壊そうとしている。つまり彼は「壊す人」である。その結果、そうした秩序や価値観への信頼もまた揺らいでいる。「多様性、公正性、包摂性」を意味する”diversity, equity and inclusion (DEI)”という言葉の「言葉狩り」をも生み出し、少しずつ言語にも大きな変化を引き起こそうとしているように見える(詳しくは第3章)と塩原氏は述べる。
かつ、トランプは大統領権限を最大限に活用することによって、事実上「法の上に立つ」ことさえ辞さない姿勢を見せる。「自国を救う者はいかなる法にも違反しない」と述べているのだから。これは近代市民社会における大原則である「法の支配」を斥け、封建社会時代の王侯貴族による「人の支配」に戻ってしまうのではないかとの疑念をもたらす。だからこそ、今の米国では大統領令に対する各種の「差し止め訴訟」が多数提起されている事態がある。しかし一方、この事態は、当たり前に見える「法の支配」が、実は脆くて危険性を潜在的に持つシステムである事実を、誰の目にも露わにして見せたとも言える。
この破天荒なトランプ革命を、本書の著者塩原氏は積極的に評価しようとする。それは、日ごろの秩序や価値観に浸りきってきた人々が気づかない「嘘」や「インチキ」に気づきを与え、自分たちを取り巻く周辺について別の角度からながめてみる機会をもたらしてくれるように思えるからだと。つまり「壊す人」のおかげで、日ごろ、私たちを騙してきた人「騙す人」のインチキを炙り出し、その不正を暴いてくれる、と評価するのである。実際、現在の主要メディアは必ずしも信じるに値しない。それらは「騙す人」だからだ。「騙す人」を信じてしまうと、騙されるだけでなく、自分が騙す側になってしまう可能性が大いにある。大切なのは、騙されないようにする情報リテラシーを養うことだ。その意味で、ネオ・トランプ革命が炙り出す気づきは実に意義深いと評価するのである。ただしそれは、ネオ・トランプ革命のすべてを肯定するという意味ではない。
なお、ネオ・トランプ革命は現在も進行中で、彼自身の言動も様々な状況によって千変万化する。実際、今年7月以降、彼の中には大きな方針転換があったのではないかと推測される根拠が幾つか存在するがここでは詳述しない。本書は、当然ながら今年5月の執筆時点までの事実のみを論じているので、その後の変化には触れられていない。
第1章でネオ・トランプ革命の全体像が説明される。それには、トランプの政策を国内と国外、短期と中長期に分けて考えるのが便利である。まずは国内の短期的には、2026年11月の中間選挙で勝利し、議会における共和党勢力を安定過半数に保つことが課題になる。そのために減税策の継続が最優先課題で、その財源捻出のために政府効率化省(DOGE)を使って様々な補助金を削減した。またトランプ関税を課して、歳入増加を図ろうとした。外交に関連する予算削減としては、ウクライナ戦争を停戦・和平にもちこむことで戦費の削減を図ろうとした。なおトランプ関税は、目先の歳入増加だけでなく、中長期的な観点からの変革も狙っている。高等教育のあり方、技術革新、経済成長に至る広範な諸制度の中長期にわたる全面的な改革を目指しているからだ。教育に関してトランプは、ハーバード大その他のエリート大学に手厳しい政策(補助金削減その他)を課したり、歴史認識にも踏み込んで「米国史に真実と正気を取り戻す」ことを目論んでいる。しかしこれは一方で、特定の歴史的価値観のみを重んじる点で、文化への監視と言う面を持つ。また、個人の行動・思想信条等の監視にも直結する。
移民制限も優先度の高い国内政策で、歳出削減策も兼ねている。さらに特徴的な動きとして、過去に受けた屈辱や被害に対する復讐・報復を具体的に行うことが挙げられる。これは第9章で詳述される。
トランプ外交には二つの面がある。一つは、北はグリーンランドから南はパナマに至る北米大陸の支配を重視する「北米中心主義」と、中国・ロシアなどの大国とは競争ないし覇権争いではなくむしろ「共謀」と呼ぶべき協調関係を追求する姿勢である。いずれも、従来の米国が採用してきた全地球的覇権主義とは一線を画している。トランプが国際機関を軽視し、パリ協定やWHOから脱退したことも、これらの動きと繋がっている。
トランプは25年1月に大統領に就任するとすぐに、多数の大統領令を発出している。その数は就任1ヶ月で72件にのぼり、歴代大統領に中でも際立って多い。基本的に、バイデン前政権の行政措置を全否定するものに近い。それらを全部列挙する暇はないが、それら大統領令に対する数多くの訴訟例が、裏側から見たトランプ政治の中身を見せているだろう。それらは、1)市民権:これまで米国の伝統でもあった出生地主義による市民権を認めないことに対する異議申し立て。2)亡命禁止:南部国境で非常事態を宣言し、米国の利益を損なうとみなす外国人に対する入国を一時停止できるとする行政権限を発動したが、これは連邦法や国際条約に違反するとして提訴されている。3)強制送還の拡大:米国に2年以上居住していることを証明できない移民の迅速な強制送還を拡大した。人権擁護団体が反対している。4)連邦補助金と貸付金の凍結:合計数兆ドルのこれら資金を保留した。これを受けるはずだった州や非営利団体が抗議し、一時的差し止め命令も出ている。5)公務員の雇用保護の廃止:数万人もの政府職員の雇用保護を撤廃し、いつでも人員削減が行えるようにした。むろん、労働組合や公務員団体は猛反発中。6)USAIDの解体:政府の国際援助機関である米国国際開発庁(USAID)の解体計画を発表、などなど。
中でも最も注目される大統領令として著者が挙げるのが、「学校教育における過激な教化に終止符を打つ」というものだ。つまりトランプは、これまでの学校教育が特定のイデオロギーによる「洗脳」「教化戦略」と捉え、これを終わらせるように迫っている。しかし同時に「愛国教育を推進する」との規定があり、この方面への「洗脳」には熱心なようだ。この事態は、何も問題がなさそうに見える義務教育においても、偏った見方や見落としているものがあるかも知れないとの「気づき」を与えてくれると、著者は述べている。
ここまで、第1章の紹介と要約を試みた。しかし正直に言うと、この第1章を私は4度読んだのだが、「トランプ政策の全体像」は明確な像を結ばなかった。政策が多岐にわたることは分かるし、個々の狙いも理解できないのではない。しかし、全体としてトランプは何を狙っているのか、どんな社会を目指してこれだけの活動を進めているのかに関して、明確な理解は出来なかった。それは本書全体を通読した後も同じだった。簡単に言えば、トランプはMake America Great Again(MAGA)を標榜するのであるが、アメリカが偉大であった時期とは何時の時代で、どのように偉大だったのかが不明確であるのと、ほぼ同じ意味である。米国の250年の歴史において「偉大だった時代」って、何時の話なんだろう?というのが私の素朴な疑問なのだ。
第2〜4章までは芸術、言語、科学の「政治化」について論じている。それぞれ、興味深い内容だ。例えば第2章では、ケネディ舞台芸術センターにおける出し物の選択にもトランプ色が強まる話が出てくるし、建築において「ブルータリズム」と呼ばれる様式が批判された例も出てくる。ブルータリズムは、1960年〜70年代に米国で流行した建築様式で、コンクリート打ちっぱなし、ブロック構造、機能性を重視したシンプル重視のデザインに特徴がある。その典型例としてFBIフーバービルがトランプの攻撃材料になり、「正直言って、この街で最も醜い建物のひとつだと思う」と酷評したそうだ。本書67頁にそのFBIフーバービルの写真が載っているが、私から見て、確かに機能性のみで多少殺風景な感じはするが、いかにも現代建築との印象しかなく、特に醜いとは感じなかった。一方でトランプは「連邦の公共建築物には、古典的建築様式が好まれる」と明示した。これは、政治家の芸術に対する一種の「好みの強制」に過ぎないと私は思う。いずれにしても、ネオ・トランプ革命は芸術にも権力が深くかかわっていることを教えてくれている、と著者は述べている。
しかし、政治権力が芸術に介入した例は歴史に数多い。かつて、ナチスはドイツで現代的芸術を推進したバウハウスを強制閉鎖し、現代絵画・音楽の多くを頽廃芸術だとして排斥した。またスターリン時代の旧ソ連でも、当時の前衛芸術「ロシア・アヴァンギャルド」が弾圧された。現代のトランプの芸術に対する政治介入も、これらに似たニオイがする(故に私はそれが嫌だ)。かつて旧ソ連体制下の東欧でロック音楽が禁止されたが、地下で人々は密かに歌い続けた。その後、ロックは自由を求める運動のシンボルとなって、世界を変革する原動力の一つになった。ピカソのゲルニカが反戦の力になったように。芸術にはそんな力があるし、だからこそ芸術を政治的に利用する動きが出てくるのも必然であると感じられる。
第3章は「言語の政治化」で、例えばメキシコ湾をアメリカ湾と呼ばせるように、言葉の使い方をも政治的に支配しようとする動きが紹介される。むろんこれはメキシコ政府からも通信社からも反発された。この種の「言葉狩り」が、通信社を始めとする各種メディアにおける言論の自由の使命を弱体化させる危険性を孕んでいることは言うまでもない。この点は、ネオ・トランプ革命の「負の部分」として肝に銘じておくべきだと、著者も述べている。
もう一つの言葉狩りとして「多様性、公共性、包摂性」を意味する、”diversity, equity, and inclusion(DEI)”を重視する考え方への攻撃がある。トランプはかねがねDEIを破壊的で分裂的なものと評価し「違法な差別の元」であるとして連邦政府からDEIを消滅させると宣言した。これは人種、性別、出自などによる各種の優遇措置を廃止し、政府機関などにおけるすべての人員選抜を実力主義に改めるとの面を持つ。トランプ政権による「DEI排除」は政府機関内や教育機関内だけでなく、企業活動にも大きな影響を与えている(個別企業のDEIからの撤退・縮小)。
また米国の公用語としての英語指定も行われたが、これは多くの移民の話す英語以外の言語を排除し、敵対化することを明確化したことになる。著者は、その政策を首肯するわけにはいかないと明言する。そして「ネオ・トランプ革命は油断すると国家がとんでもない政策を国民に強いるようになることも教えてくれている。」と述べている。全く同感である。
第4章は「科学の政治化」である。現代は科学技術が高度に進歩しつつあるため、科学を政治的に利用しようとするのは当然の動きであり、世界中どこでも進行中の話である。トランプ政権で特徴的な話題としては、二期目の最初の数時間でトランプがパリ協定とWHO(世界保健機関)から米国を脱退させたことが挙げられる。これは、人為的地球温暖化説とコロナワクチンに対する彼の反撃である。実際、トランプは国連で人為的温暖化説は史上最大のデマだと演説したし、NIH(国立衛生研究所)に対する大幅な人員・予算の削減を行った。確かに、気候変動が人為によるものかどうか、遺伝子組換えやワクチンの安全性が科学的に本当に担保され得るのか、疑わしい面はある。しかし、だからと言って政治権力がこうした科学的諸問題を強引に判断して良いものかどうかには、当然ながら疑問符がつく。
また本章の最後はAI規制に関する話題を取り上げている。AIに関してトランプ政権が示す4つのポイントは以下の通り。1)米国のAI技術が世界標準であり続けることを保証する、2)AI分野に対する過度な規制は避けたい、3)AIがイデオロギー的な偏見から自由であり続けなければならず、米国のAIが権威的な検閲の道具として利用されることはない、4)AIが米国における雇用創出のための強力なツールとなるよう、労働者寄りの成長路線を維持する、となっている。ただしこれらがどんな具体策として現れるかは現時点では分からない。私の個人的な感想だが、3)は事実上、実行困難ではないかと思う。そもそも「AIがイデオロギー的な偏見から自由であり続ける」ことなど、あり得るのだろうか?AIは膨大な学習情報を複雑な演算処理した結果で答えを出すのであるが、それらの学習情報自体が、イデオロギー的偏見から自由であるはずがないのに。本書の著者は、この章の最後にこう述べている。「現状では、行政サービスへの安易なAI利用は多くの問題を引き起こしかねない。それでもトランプ政権はAI重視の政策を闇雲に実現しようとしているように見える。まさに、指導する政治家によってAI政策や規制が大きくブレてしまうのである。」と。これまた、同感である。
第5章は「トランプ関税」を取り上げる。相互関税の計算式の問題に続いて、各国別適用について具体的に述べられており、説明は多岐にわたるので個々には紹介しない。なぜトランプが関税問題に執着するかと言えば、彼の主張によれば国内製造業と輸出の復活を進め、貿易赤字を解消したいがためだった。しかしこれまで米国は、世界におけるドル支配を確実なものにするために、通貨ドルによる貿易・サービス決済を広げ、旺盛に輸入してきた。そして各国の利益をドル建て国債に換えて各国中央銀行に保有させてきた。通貨ドルの「強さ」は、このようにして維持されてきたのだが、トランプの政策はこれらを全部逆方向に変えるものだ。混乱が起きるのは当然の成り行きだろう。それを承知で、トランプはこれを進めている。そこで本章の末尾で、著者が指摘するのは、民主主義の弱点である。今回のトランプ関税では、たった一人の米国大統領の決断によって、米国の通商政策を180度転換できるという現実が存在することを教えていると。しかもそれは、トランプが1期目に署名したものも含め、米国の過去の貿易協定を無視している、とも。「そう考えると、民主主義国家であるはずの米国において、貿易政策も外交政策も国民の意向をまったく無視し、たった一人の判断で進められることがいかに異常な事態であるかが分かるだろう、とも述べている。貴重な警鐘である。
第6章はウクライナ戦争に関わる問題を、ネオ・トランプ革命に関連づけながら論じる。ウクライナ戦争が起きるまでの経緯を客観的・歴史的に眺めるならば、単純に「プーチン=悪、ゼレンスキー=善」などとは言えないことは明白な事実なので、これらの説明はここでは省く。本章での重要な指摘としては、欧州の軍備強化の動きについてで、ロシアが欧州を侵略したがっているなどと言うのは「被害妄想」そのものであるにもかかわらず、ロシアを脅威に仕立て上げ、猛烈な軍国主義化に舵を切った欧州の指導者たちの暗愚さを述べている点が注目される。日本のマスコミにはまず出てこない意見である。これらに関して本書では「恥ずべき学者」として実名を挙げられている人物が複数名いるのであるが、ここでは紹介しない。
第7章は鉱物資源の争奪戦について論じる。まず本章冒頭で、米国がロシアの天然資源を窃盗した事案が取り上げられ、この例に限らず、米国が天然資源に関して種々の搾取、窃盗を行ってきたことが紹介される。この内容自体、多くの日本人には衝撃的だろう。「アメリカが泥棒だなんて・・。」しかしトランプ政権が進めるウクライナでの資源開発問題やグリーンランドの買収問題は、その延長線にある。本章の内容も多岐に渡るので個別の紹介をする暇は無いが、ここでも章末に興味深い指摘がある。それは資源や土地などの「所有」の仕組みに関する原理的な問題点の指摘である。それは「所有」は「他者」による承認を受けなければならず、土地や地下資源な
どの天然資源は生態系の一部だから、特に「誰から」承認されるかが複雑な問題になるからだ。
第8章は「リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ」という、極めて刺激的な内容である。日本では外交的な挨拶文などで「自由と人権に関する価値観を共有する」と言った文言がしばしば登場するが、これがリベラルデモクラシーの一種と言える。つまり「人権」や「自由」「民主主義」が疑いのない「価値」であると見なしているわけだ(わが国でも長年の政権政党名が「自由民主」党であることを思い出そう)。しかし特に米国では、他国への「民主化」支援を口実に軍事介入や政権転覆を行ってきた歴史がある(ウクライナの「マイダン革命」もその一つ)。つまり「人権」その他のリベラルデモクラシーが、実態としては帝国主義的・介入主義的な政策を正当化するための理念的レトリックに過ぎなくなってしまった実態があるのだ。本書の著者はかねがね、このリベラルデモクラシーの欺瞞的な側面を批判してきた。米国は実際、イラク、シリア、ウクライナなどへの軍事介入を、リベラルデモクラシーを広げることを口実に進めてきた。トランプは、それを止めようとしている。著者は、トランプの「力による平和」を支持しないが、リベラルデモクラシーを批判する点は正しいと評価する。そしてリベラル派の矛盾や実例としてのUSAID(米国際開発庁)やNED(全米民主主義協会)の実態などを紹介している。これらの実態を知れば、あきれるほかないような活動内容である。その結果現れるものは、現存する民主主義なるものが、きわめていい加減なものに過ぎないという事実である。なぜなら、現代においては大金持ちや権力者が、その豊富な資金力や暴力を用いて自分の意見だけを通すことが実際に可能になっているからである。本章では、その実態が詳しく述べられている。そうした米国の現実について、著者は「そこにはリベラルデモクラシー自体が存在しないように思える。そんな国が海外にリベラルデモクラシーを輸出できるわけもない。皮肉なことだが、こうした現実をネオ・トランプ革命は教えてくれているのだ。」と述べている。
第9章では「復讐・報復」について論じる。トランプはバイデン政権に対して、かなり根深い恨みを抱いているようだ。選挙不正その他、彼が被ってきた被害の詳細は、多くの日本人には知られていない。私自身はトランプの個人的な恨みや「ルサンチマン(憎悪、ねたみ、怨恨)」には大きな関心を抱かないが、本章には重要な指摘が書かれている。それは次の文章だ。「トランプのルサンチマンの扇動は決して彼の発明ではない。民主主義によって「妬み」が苛烈さを増し、それが邪悪さを撒き散らすようになる。そのとき、弱者という大多数者がもつ妬みをうまく利用して、扇動し、権力闘争に展開させることを考えた者がいた。」という指摘だ。つまり、単なる個人的な恨みや、何が何でも報復したいとの心理を隠して、弱者や被害者に寄り添い、ルサンチマンを煽って、被害者救援を装っているだけかも知れないということである。
第10章は「新しい地政学の地平」として、ネオ・トランプ革命がおよぼす世界全体のヘゲモニー争奪について考える。特に、核兵器の拡散について俎上にあげている。2026年2月に迫っている新戦略核兵器削減条約(New START)の失効後、どういう展開になるかが注目点である。
あとがきにも、興味深い記述がある。「私にとっての先達は柄谷行人であり、丸山真男であり、井筒俊彦であった。」私はこの文章を読んで、大いなる共感を覚えたのだった。私にとってもこの3人は大いなる先達であったから。本書の記述の中には柄谷を思わせる用語は出てくるが、丸山、あるいは井筒を連想させる文言は私には見出せない。それでも丸山と井筒の名を挙げるからには、よほど強い影響を受けたに違いないし、それには理由があると私は考える。特に多くの日本人は井筒俊彦と言う大学者を知らないと思うが、彼の著作を読めば必ずその偉さが分かる。
以上、少しまとまりを欠く書評になってしまったが、ネオ・トランプ革命という多面的な変革には、それほど語るべきことが多い事実の裏返しでもある。本書を読みながら私の脳裏に去来したイメージは、歴史家ヴァルター・ベンヤミンの描いた「歴史の天使」だった。「歴史の天使」は後ろ向きに未来に進んで行く、だから未来は見えないが目の前(=過去)には様々な歴史的事象が積み重なってゆくのが実相だ、という捉え方・イメージはとても魅力的で説得力がある。本書の著者塩原氏の目の前にも、書くべき事実が次々と積み上げられて行き、情報は書いた端からどんどん古くなって行くので、いくら書いても足りることはなかっただろうし、今後もないはず。だから今回の新作も同氏にとっては一つの「経過報告」に過ぎないだろうと、読んでいて感じさせられた。ついでながら、このベンヤミンの「歴史の天使」に挿画として使われたのがパウル・クレーの天使の絵で、この風変わりな絵は、私を大いに惹きつけたのだった。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 松田 智(市民記者)
松田 智(市民記者)
まつだ・さとし 1954年生まれ。元静岡大学工学部教員。京都大学工学部卒、東京工業大学(現:東京科学大学)大学院博士課程(化学環境工学専攻)修了。ISF独立言論フォーラム会員。最近の著書に「SDGsエコバブルの終焉(分担執筆)」(宝島社。2024年6月)。記事内容は全て私個人の見解。主な論文等は、以下を参照。https://researchmap.jp/read0101407。なお、言論サイト「アゴラ」に載せた論考は以下を参照。https://agora-web.jp/archives/author/matsuda-satoshi