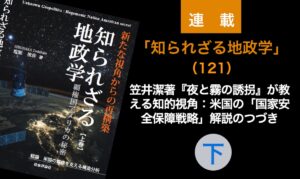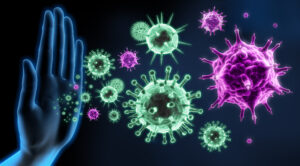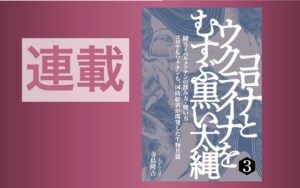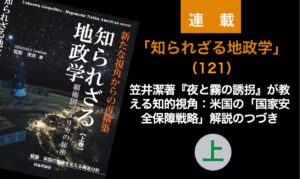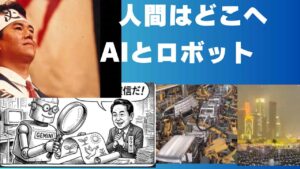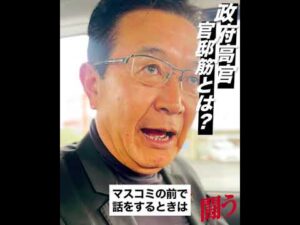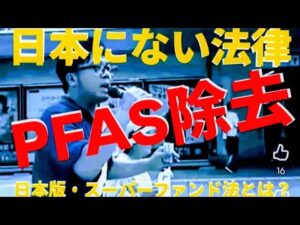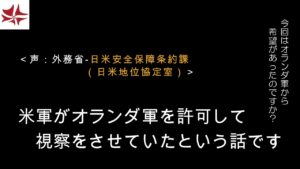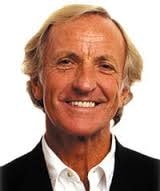登校拒否新聞24号:健康診断
社会・経済ヨミドクターに載った記事「不登校の子、健診受けず病気見逃す恐れ…総務省が初の全国調査で実態把握へ」は2025年9月12日付。
不登校の子供が学校の健康診断を受けられず、病気などが見逃されてしまう恐れがあるとして、総務省は年内にも、不登校の児童生徒の健康診断受診状況について、初の全国調査に乗り出す方針を固めた。結果を基に文部科学省などに受診促進を求める考えだ。・・・学校の健康診断は学校保健安全法に基づき、学校医が主に学校で行う。このため登校できない児童生徒は受診が難しく、早期治療が必要な病気などの発見が遅れる懸念がある。文科省は昨年9月、対応を求めて都道府県などに事務連絡を出したが、実際は現場の判断に任されているという。
https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20250911-OYT1T50190/
いつものようにヤフーニュースにて再配信された際に多数のコメントが寄せられた。上のURLは有効だが、こちらの再配信のほうはすでに無効となっている。それと共にコメントも消えてしまう。それがもったいないから、折を見て、ぜんぶ走査しながら目ぼしいものをピックアップしている。匿名による意見。それでもコメントを寄せるほど言いたいことがある人たちの意見は貴重だ。「不登校の専門家」の意見よりも、私はこのような匹夫匹婦の意見を大事にしたい。
まず、この記事の内容が実態を把握していないようだ。
不登校生の実態調査については必要かと思います。ただ実際は現場では対策は行っています。不登校に限らず、さまざまな健康診断に欠席した生徒は、再検査があり、それでも欠席したら養護教諭が校医まで引率します。それでも欠席したら、保護者に案内文を出して、検診を促します。校医であれば無料ですが、校医以外なら有料で検診を受けて、学校に結果報告します。これ以上の方法があれば教えて欲しいです。(qhn********)
私はこの件について、以前から工夫を凝らしてなるべく受けられるように案内してきました。せめて尿検査や心臓検査などは、予備日や別施設での検査・提出を促してましたが、実際に関心を寄せて受けてくれる家庭は不登校生徒の1割もいません。ただ、この取り組みの労力は、学校に来ている子たちに費やす労力以上のものになります。実際ここまでしている学校は少ないと思います。とても大変なので。(*********)
この二つの意見は養護教諭の意見なのか定かではないが、現場の声である。次のように、はっきりと養護教諭が名乗りを上げている意見もある。
養護教諭をしていました。不登校の状況になっている子どもには、学校医と連携して保護者が引率して希望する日に学校医のクリニックで健診を受けられるようにしていましたし、検尿などもできる限り保護者の協力で運んでいただいていました。あくまでも子どもの状態に応じてですが、健康についてはできるだけ不利にならないよう取り組んできました。養護教諭の職務はこのように全校児童生徒の一人ひとりの状況を考え、子ども達の心身の健やかな発育発達を促すものです。一人職で多忙を極める養護教諭の複数配置を進め、学校に来れない子にも養護が行き渡るようにしてほしいです。((a_a))
スクールカウンセラーの配置よりも養護教諭の複数配置のほうが有用なのかもしれない。養護教諭は短大で資格を取ることが多いようだ。心理職のほうが高学歴になっている現状はいかがなものか?
こうした問題にメスを入れること自体は望ましいことだと思います。ただ、なぜ総務省が調査を担うのでしょうか。むしろ、このような事案こそ、こども家庭庁の役割ではないでしょうか。同庁は「子どもの健やかな育ちを支える」「子どもの安全・安心を守る」「多様な子どもへの支援」といった任務を掲げています。今回の問題も、本来はこども家庭庁の管轄に含まれるのではないでしょうか。(*********)
いったい総務省の管轄なのか、こども家庭庁の管轄なのか、それともやはり文部科学省なのか。所轄官庁の問題がありそうだ。この意見は厳しい。たしかに、こども家庭庁は何をしているのだろう?
そもそも健康診断ではわからない「病気」もある。
起立性調節障害も発覚することが多いですが、精神的なことが一番ではないでしょうか?政府が共働きを推し進めるようになった現代、うまくイジメを隠す、うまくイジメられていることを隠すのが上手くなっているのかなあと。ずっと!沢山の子供達をみていて思います。近所のお子さんが朝からやってくる我が家でしたが、吐き出す場所がみんな子供ながらにないんだなあと、オープンに、時には忍耐強く見てきましたが、参政党さんのいう、『お母さんが家にいる大事さ』をしみじみ痛感します。(dhy********)
不登校には有名どころで言えば起立性調節障害などの身体の不調が原因になることもある。だから不登校の生徒がちゃんと医師の診察を受ける事が有用になることもあるだろう。(baluto)
不登校児には通常の健康診断だけでなく、もっと緻密な検査をしてもいいと思います。もちろん、保護者と本人の同意の上です。不登校児の多くは自己肯定感が無く、鬱や起立性障害のような意欲が出ない症状を持ち、学校に行けない子です。全部原因不明、謎です。怠け者、ポンコツと言われます。何人も見てきました。優秀な子もいました。外部要因によるいじめや人間関係の葛藤は実は少数で、そういうケースは精神的に健康だから学校の対応や転校、フリースクールなど対処の方法があるのです。問題は「お手上げ状態」の子供たちなのです。心理士や神経系の専門医の研究に協力してくれる意思と究明のための公的資金援助があるようなら、将来同じ苦しみを持つ子供が減る可能性があるのではないかと思います。遠い未来、究明されると思っています。(tak********)
不登校のすべてではないが、不登校の子の半数は、夜がねむれず、朝方ねむる。朝は起きられず、だんだんいろいろな学校でいやなことや雨とか天気を理由に休み出す。勉強が分からなくなる、友達が疎遠になる。そして学校にいきづらくなり、不登校が日常化する。この夜がねむれないのは昼夜逆転しているのだが、その引き金は不眠症。睡眠導入がうまくいかない。それは自律神経の交感がうまくいかない。つまり、うつの状態が起きやすい。脳神経がやすまらない。学校と精神科医、カウンセラーなど共同して治療する必要がある。親や教師だけ、カウンセラーだけではなく医学的な治療も必要な子供がいる。子供は自分のちからではどうにもならないのだ、足がうごかない。体がうごかない。学校にいくにはこの二つが必要だ。精神的なものだが、説得だけではなおらないことを理解すべきです。単なるわがままではない。病気なのだ。(みちこ)
起立性調節障害は健康診断ではわからない。この問題についてはまた次号で詳しく書こう。発達障害、あるいは起立性調節障害という診断は健康診断では下せない。ところが、長期欠席の内訳として増えているのはそういった診断が下される例だ。長期欠席者の多くが病院でそうした診断を受ける。体重を図るとか血液検査くらいは頼めばしてもらえる。学校の健康診断はどこまで必要なのだろう?
不登校も病気だろうに。学校に行けない症候群。先ずは、そちらの対策の方が大切だろうに。対策できないことを棚に置いて、検診を実施とは。あきれる。(tom********)
かつては「登校拒否症」という診断もあった。「症候群」がブームになってからは「青い鳥症候群」とか「思春期挫折症候群」とか言ったものだ。「学校に行けない症候群」は初耳だが一口に言えばそういうことなのだろう。
閑話休題。健康診断が重要なのは体の発育のチェックではないのか?
学校健診で異常が見つかるような子は、自覚症状があったり、病気が悪化してたりしててもう既に医者に通ってるはずだよと、ある内科医の先生が仰ってました。まだ若いので滅多なことはないだろうという意味でもあると思います。健診を受ける機会がないぶん、普段から体調に注意して、何かあったら直ぐに病院に行くようにした方がよいですよね。(fbc********)
私も不登校とか、体が弱かった加減でしょっちゅう発熱や入院してて、一部の予防接種(追加接種分)とかもしなかったけど、病院で聞いたら小さい頃に1回でもしてたら良いし、アフリカとか特殊な地域に行くわけじゃないから気にしなくて良いと言われてそのままです。健診受けるのは大事だけど、よっぽど精密検査でもしない限り、大きな病気って見つかりにくい。学校健診程度で病気って見つかりにくい。私自身、心臓が悪いのもたまたま精密検査でわかったので、学校健診ではスルーされてきた身なので別に不登校で健診受けれなかったからと言って心配いらない。虫歯や視力低下とかならわかるけど、それ以外は無理。(da5********)
学校の健康診断にそこまで気にするほどの効果実績があるのだろうか。保護者が子どもの不調に気付いて対処することのほうが圧倒的多数なのでは。学校のは栄養失調や発育不良の統計的把握が目的としか思えない。登校不登校によらず、ひとり親ひとりっ子のほうが危なかろう。検診漏れという意味では自営や退職離職した人のほうが深刻だ。(the********)
結局、健診の目的が統計にあるという指摘は正鵠を射ている。軍需品の規格を定めるために健康診断をしたという学校史の事実がある。そもそも装備品の重さや軍服のサイズなどを決めるために必要な調査である。現代の子どもが抱えているようなメンタルヘルスを調べるものではない。それに――、
そうですよね。イギリスでは、とっくの昔にコロナによる後遺症で不登校増えまくったってデータ出してきてるもんな。日本は調べもしなかったよね。(mpog*****)
コロナの後遺症なのか、はてまたワクチンの副作用(副反応?)なのか、コロナ禍による欠席率の上昇は登校拒否新聞としても何度か指摘してきた事実だ。いつも言っているように「年間30日以上の欠席」と定義されるのは長期欠席である。その総数が増えると「不登校」が増えた、と報道が騒ぐ。しかし「不登校」は長期欠席の理由別分類の一つである。「病気」もまた理由別分類の一つ。発達障害や起立性調節障害という診断を受けているのなら「病気」と、またコロナの後遺症なのであれば「病気」と分類される例が増えているということだ。それを「不登校」が増えたと騒ぎ、フリースクールを行政が支援するなどと言うからおかしい。病気といえば抵抗もあろうが医療を必要とする例と考えれば、そういう例こそが増えていることは明らかである。登校拒否と言っていた頃から実際にはそういう例が多かった。脅迫行動に駆られる子どもが精神科を受診したという例は枚挙にいとまがない。「乱塾時代」という言葉も流行った時代のことである。偏差値重視の教育が原因とされただけのことで、医療の手を借りなければ解決に至らない例が登校拒否のプロトタイプなのである。原因論が横行したことで、そうした子は個性的な子どもとして祭り上げられた。それが今も「学校になじめない子ども」として尾を引いている。
権利には義務もつきもの。学校に行かないから検診を受けられないだけで、そこを配慮する必要があるのか。心配なら親が病院に定期的に連れて行けばいいだろう。学校に通う子供は客じゃないし、親もお客様ではない。親は子供の権利を守るなら、学校に通わせることも大切な義務である。学校に行かなくていいと言うなら、権利を放棄したと見做されても仕方ないのでは?(chi********)
「無理に行かなくてもいいんだよ」という雰囲気が最近出回っているが、学校に行かないことによって受ける不利益は大きい。普通に学校に行ける人たちは普段意識していないが、学校に行くことで守られている利益がどれだけ多いか…だからこそ、誰もが気持ちよく学校に行けるよう、周囲も本人も努力していかなければならないと思う。(orange)
私はこの二つの意見に賛成だ。義務でなく権利という主張に私は与しない。義務教育は義務教育としてある。戦後、受教育権を憲法が認めたにせよ、学校に就学させる義務が養育者に課せられている点に変わりない。そして、市町村には学校設置の義務が課せられている。学校に行かないことは権利でも何でもない。むしろ受教育権を自ら放棄していることになる。デメリットは現実にある。私自身、中学校に一日も通わなかったばかりか、敷地に入ったこともない。つまり、健康診断を受けたことはない。整列することもなくなったから自分の背丈が高いのか低いのかもわからなくなった。そうか。背が低い高いという自己認識だって学校があるからなんだ、と当時の私は考えたものだ。学校哲学の誕生だ。
後者の意見には返信が29件もついた。「無理に行かなくてもいいんだよ」というよく聞くフレーズを批判しただけで反対意見が寄せられる。私はこのorangeさんの意見に賛成だ。というよりも、この意見は現実を突いている。先のchi***さんの意見も同じ。「無理に行かなくてもいいんだよ」と言うのなら権利保障をすべきである。健康診断はどうするのか、という問いは案外に盲点であった。
それで藤井君は健康なんですか?
元気ですよ。毎日、2合のお酒を欠かさず呑んでいますから。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。