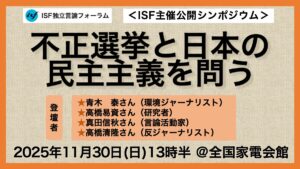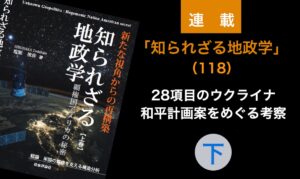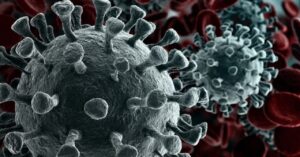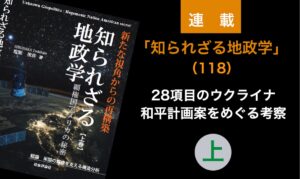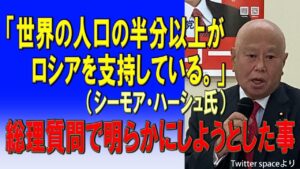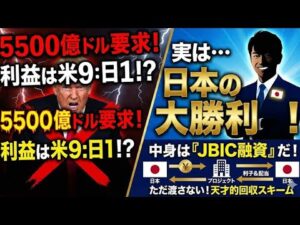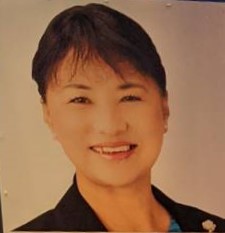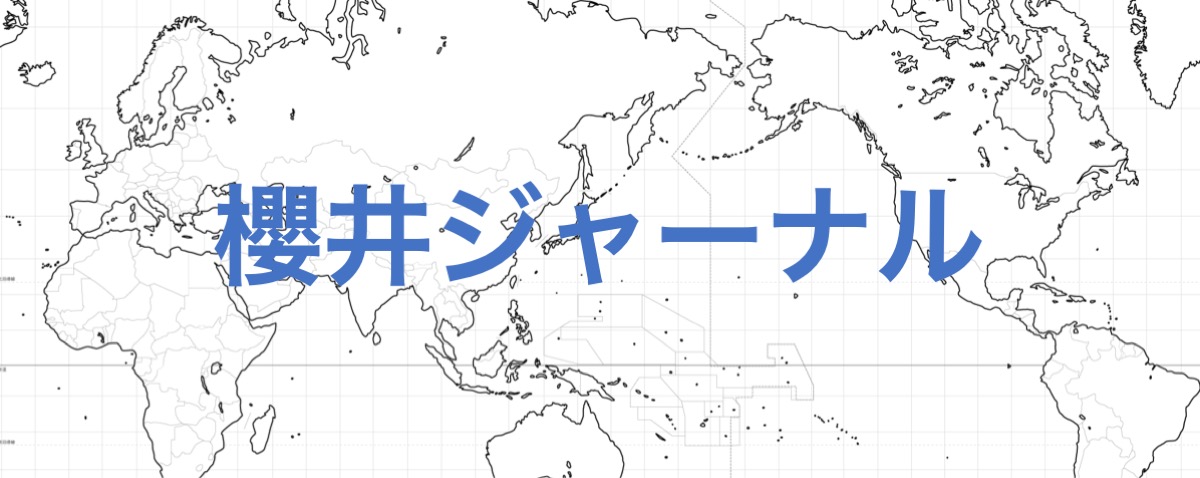
【櫻井ジャーナル】2025.10.20XML : ロシアとの戦争から抜け出せないNATO諸国のシオニスト
国際政治ドナルド・トランプ米大統領はウクライナへ巡航ミサイルのトマホークを供与するとしていたが、ウラジミル・プーチン露大統領と電話会談した後、供与に関して姿勢を変え、消極的になった。ソ連消滅後にロシア征服プロジェクトを始め、ウクライナにおけるロシアとの戦争を推進している西側の勢力は巻き返しを図っているようだ。
トマホークは射程距離が1500から2500キロメートルで、核弾頭を搭載できる。つまりモスクワを核攻撃することも可能だ。このミサイルをウクライナ軍が使うということは、アメリカの軍や情報機関が目標に関する情報を提供し、衛星を利用してミサイルを目標へ誘導しなけらばならない。ロシアが問題にしているこのミサイルを自衛隊とアメリカ軍は与那国島、奄美大島、宮古島、石垣島に並べる計画だ。

トランプ大統領に反ロシア政策を吹き込んでいるグループの中心には筋金入りのネオコンとして知られているウクライナ担当特使のキース・ケロッグがいる。もしトマホークがウクライナに送られ、ロシア国内の標的への使用が承認されたなら、ロシアとウクライナの紛争の「力学を変える」ことになり、「不確実性」が増すだろうとケロッグは主張しているのだが、S-500やEW(電子戦)システムを含むロシアの防空能力を考えると、この巡航ミサイルが戦況を変えるとは思えない。それでもアメリカがロシアとの戦争で前面に出てくる意味は小さくない。
つまり、トマホークをウクライナへ供与するということは、アメリカの軍や情報機関がロシアを攻撃することを意味する。だからこそロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官はトマホークの供与に関し、状況の重大な変化をもたらすと語ったのだ。アンカレッジにおける米露首脳会談で生まれたウクライナ情勢解決への勢いが失速したとも彼は口にしている。
西側諸国はソ連消滅後、NATOを東へ拡大、2014年2月のクーデターでウクライナに到達した。これは新たなバルバロッサ作戦の始まりを意味するが、それをロシアが容認するわけはなかった。脅せば主導権を握れるとアメリカ側は考えたのかもしれないが、ロシアは中国と同様、脅しに屈しない。実際、ロシア政府はアメリカ政府に対し、圧力や脅迫で目的を達成することはないと伝えたようだ。
歴代のアメリカ政府は外交や軍事の分野をシオニストに任せてきた。ジョン・F・ケネディのように、その政策に逆らった大統領もいたが、政策を変えることはできていない。ケネディの場合、暗殺された。トランプ大統領の周辺もシオニストに囲まれ、その影響下にある。その行動を見る限り、彼はイスラエルに従属しているとしか考えられない。つまりシオニストに操られている。
トランプは2018年8月にINF(中距離核戦力)条約から正式に脱退、ロシアは今年8月に条約を遵守しないと発表した。ウクライナでNATOがロシアに敗北する中、アメリカが始めた行動に対し、ロシアはアメリカに対し、容赦しないことを伝えたと言えるだろう。トマホーク供与に対しても容赦しないということだ。
2020年5月、トランプは既存のミサイルと比べ17倍もの速さで飛行する「スーパーデューパー」ミサイルを開発していると宣伝した。AGM-183 ARRW(空中発射即応兵器)ミサイル、あるいはLRHW(長距離極超音速兵器)を指しているのではないかと言われているが、2023年3月にAGM-183 ARRWプログラムは中止、今のところ、この兵器は空想の産物に過ぎず、LRHWも存在しないようだ。トランプは空想の兵器でロシアと戦おうとしているのだろうか。
【Sakurai’s Substack】
※なお、本稿は「櫻井ジャーナル」https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
のテーマは「ロシアとの戦争から抜け出せないNATO諸国のシオニスト 」(2025.10.20XML)
からの転載であることをお断りします。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202510200000/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/202410130000/
ISF会員登録のご案内