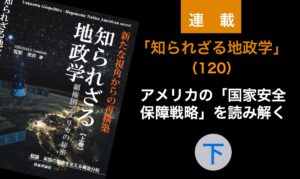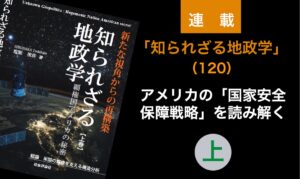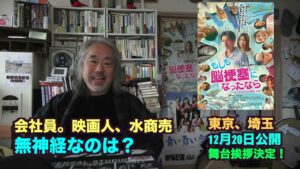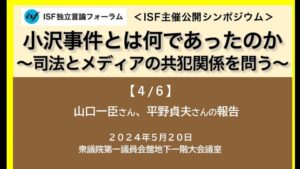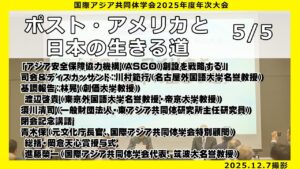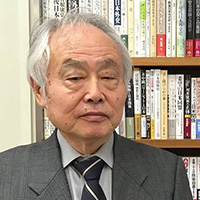登校拒否新聞25号:起立性調節障害
社会・経済読売新聞の記事「「起立性調節障害」中学生の有病率10%、朝がつらく学校に行けない子もいるが…「怠けている」誤解も」は2025年10月3日付。「九州発」ということで、西部本社編集局としてあるが全国配信された。記者は今村知寛。
日本小児心身医学会によると、ODの有病率は中学生の約10%とされ、不登校の3~4割に潜んでいると言われる。早期に適切な治療を受けることで症状の軽減が見込まれるが、周囲の理解不足から悪化するケースもある。こうした中、当事者を支えようという取り組みが各地で進む。・・・久留米大医療センターは昨年11月に「登校支援外来」を開設した。小児科の窓口で対応している病院は少なく、大分や熊本から通院する子どももいる。20歳頃までには症状が改善していくとされているが、個人差もあるという。担当の山下大輔医師は「症状とうまく付き合う視点を持ち、体がきつくなる原因がどこにあるのか、一緒に探っていきたい」と話した。山口県和木町のパート従業員、生駒真美さん(54)は2016年10月、ODの子を持つ親が悩みを分かち合う座談会「親の会」を始めた。同県岩国市で9月にあった座談会では中高生の子を持つ親たちが、進路先について情報交換していた。中学3年の娘がODという40歳代の女性は「夫婦間でも温度差があり、悩みを共有できない。ここでは共感することが多く、気持ちが楽になる」と明かした。生駒さんの長女(23)も小学5年の時にODの診断を受けた。中学校では学校側の理解も乏しく、不登校になった。生駒さんは神戸市で活動する親の会を知り、中国地方に拠点を作ろうと活動を始め、専門講師による学習会などを開いてきた。現在、大分や鹿児島など全国12の「親の会」の代表が、情報共有など連携を強めている。生駒さんは「各地の団体と協力し、病気の認知度を上げていきたい」と語る。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20251003-OYTNT50104/
起立性調節障害=ODについては、登校拒否新聞としても何度か書いたことがある。登校拒否と言っていた頃にはなかった概念で、「心因性登校拒否」「神経症的登校拒否」が社会病理化されて「不登校」になってから、内科の診断として出てきたものだ。前者は精神科医の診立てにより概念化されたものだが、後者は内科の小児科医の診立てである。出自が異なるので、異なる意味を担った別な概念と言えよう。
記事に「日本小児心身医学会によると、ODの有病率は中学生の約10%とされ、不登校の3~4割に潜んでいると言われる。早期に適切な治療を受けることで症状の軽減が見込まれるが、周囲の理解不足から悪化するケースもある」とあるように明確に治療の必要がある「病気」とされている。ただ、ここで「不登校」と言われているのは不正確だ。これは長期欠席と言わなければならない。
では、ヤフーニュースのコメント欄を見てみる。URLはすでに無効となっているから省略する。実のところ、あまりコメントがつかなかった。「多様な学び」ではなく「病気」という線で記事が書かれているからだろう。そういう関心の偏りが「不登校」という概念を形成している。同じ「親の会」にしても「不登校の子ども」の親の会ではなくODの親の会ということである。概念的に違うのである。
一通り読んでみると、夜遅くまでスマホをいじっていて寝不足という意見が多い。それが実態なのではないかと思われるが、やはり診断がある以上、そうとも言えないのだろう。しかし、素人目にはサボってるとしか思えない。それが無理解という話である。
ちゃんと血液検査などをして、数字としてきっちりと客観的に判断できる材料での診断が下るのであればそれは、罹患者にとっても、周りにとってもいいことだと思いますが、実際この病気についてはどうなんでしょう?何かしらの数字として現れるものなのでしょうか?(je_*****)
こういう質問が出てくるのも当然である。
この意見について返信がついた。
現れますよ。不登校だと思いながら娘をとりあえず小児科に連れて行ったら色々と検査をされ起立性調節障害とわかりました。本人も病気だとわかりとても安心して、担任の先生、クラスのお友達の協力があって何とか無事に小学校を卒業し、中学生になり自分でも病気との向き合い方を覚えたり工夫したり、30歳近くなった今では病気だったわね〜と言えるほどになりました。何より学校の協力がとてもありがたかったです。担任次第で扱いが変わる病気なので娘は本当に幸せでした。今、戦っている親御さんは大変だと思いますが、それでもいつかは何とかなります。長い目で子供さんを見てあげて下さい。応援してます。(hpj********)
コメントの総数が少ないわりに登校拒否新聞として上の記事を取り上げようと思った理由は、この方のコメントを紹介したかったからである。
「病気」という認識である。つまり「不登校だと思いながら小児科に連れて行ったら起立性調節障害とわかりました。病気だとわかりとても安心」という構造がある。「不登校」と明確に区別された「病気」という点に意味がある。「不登校」が増えている。だから学校に合わない子が増えている。だから「多様な学び」という論理は起立性調節障害のような診断を受ける例が増えているという実態を無視して成り立っている。「不登校」という概念は「心因性登校拒否」「神経症的登校拒否」を否定する過程において成り立った。つまり「病気」ではないという主張がこしらえた概念である。「学校病理」などという社会病理論がその主張を支えた。病的な子がいるとしても「病んでいるのは学校だ」と斬り返す論理が登校拒否から「不登校」へ、という言葉の展開を生んだ。この点、起立性調節障害は「不登校」ではなくて「病気」という、その正反対の論理により成り立っている。それも気の病ではなく思春期の頃に特有の心身の不調である。
その理由はどこにあるのか?
あくまでも「病気」とするのであれば、ホルモンバランスが崩れやすいという一般論ではなく、上の意見にあるように検査をした上で診断を受けるような明確な定義があるのだろう。しかし――、
コロナ禍から、起立性調節障害の記事をよく見かけるようになりました。怠けじゃないんだけど、、、少しづつ体調が良くなっても、休みが続いてしまうと、学校に行くのが億劫になってしまうんじゃないかと思います。中学生は思春期で難しいけど、行けそうだと思ったら、多少は無理してでも頑張って登校した方がいいですよ。ほとんどの子はそのうち治ってますから。(******)
自分も異常に朝弱くて起きれず遅刻ばかりだったけど、起立性と言われれば当てはまる気もするし、怠けと言われればそうだった気もする。怠けが1%も無いと言い切れる人はいない気がする。(Ttt*****)
一般論としてはこういう話になりそうだ。私も「起立性調節障害だった」と言うことはできるのかもしれない。少なくとも「不登校だった」「不登校を経験した」と言うよりはしっくりくる表現である。このあたり、意味の争いがあるように思う。先の意見に「不登校だと思いながら小児科に連れて行ったら起立性調節障害とわかりました。病気だとわかりとても安心」とあったような構造がある。これは単純に「不登校」は病気ではなくて、起立性調節障害は「病気」という話ではない。そうであれば「不登校」は病気としてしまえば済む話である。なかなか概念論としておもしろいわけだが、私自身、あまり起立性調節障害という診断については理解がない。専門医ではないから識見を欠くのは当然として、発達障害と同じで、診断に問題はないかと疑問が残る。
「不登校」という概念は「病気」でもなければ「怠け」でもないという除外診断的な定義のもとに掲載された。その過程について書いたのが拙著『不登校とは何であったか?心因性登校拒否、その社会病理化の論理』である。つまり器質性でもなければ内因性でもない「心因性登校拒否」という神経症の除外診断を社会病理化したものというのが私の主張である。であるから「不登校」は「病気」と「怠け」をアプリオリに排除している。学校が嫌いなわけではない。本当は学校に行きたい。けれども学校がおかしい。そういう含みを持った概念である。「多様な学び」という解法もそこから出てくる。ところが、その「不登校」が幅を利かす一方で、起立性調節障害という内科の診断と発達障害という神経科の診断を受ける例が増えたわけである。
話を単純にするために「不登校」と「病気」と二つに限って考えよう。
長期欠席の理由として「不登校」と「病気」の二つがある。では、記事にあったように「ODの有病率は中学生の約10%とされ、不登校の3~4割に潜んでいる」のか?
違う、と私は考える。
長期欠席の理由として「病気」が増えているのが実態である。診断を受ける例が増えているのだから、そう考えるのが妥当だろう。それを「不登校」が増えていると言うのでは、言葉の上ですり替えていることになる。コメントにあったように「コロナ禍から、起立性調節障害の記事をよく見かける」という事態をどう考えるか?
次号においては「ロング・コロナ」の問題を扱う予定である。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。