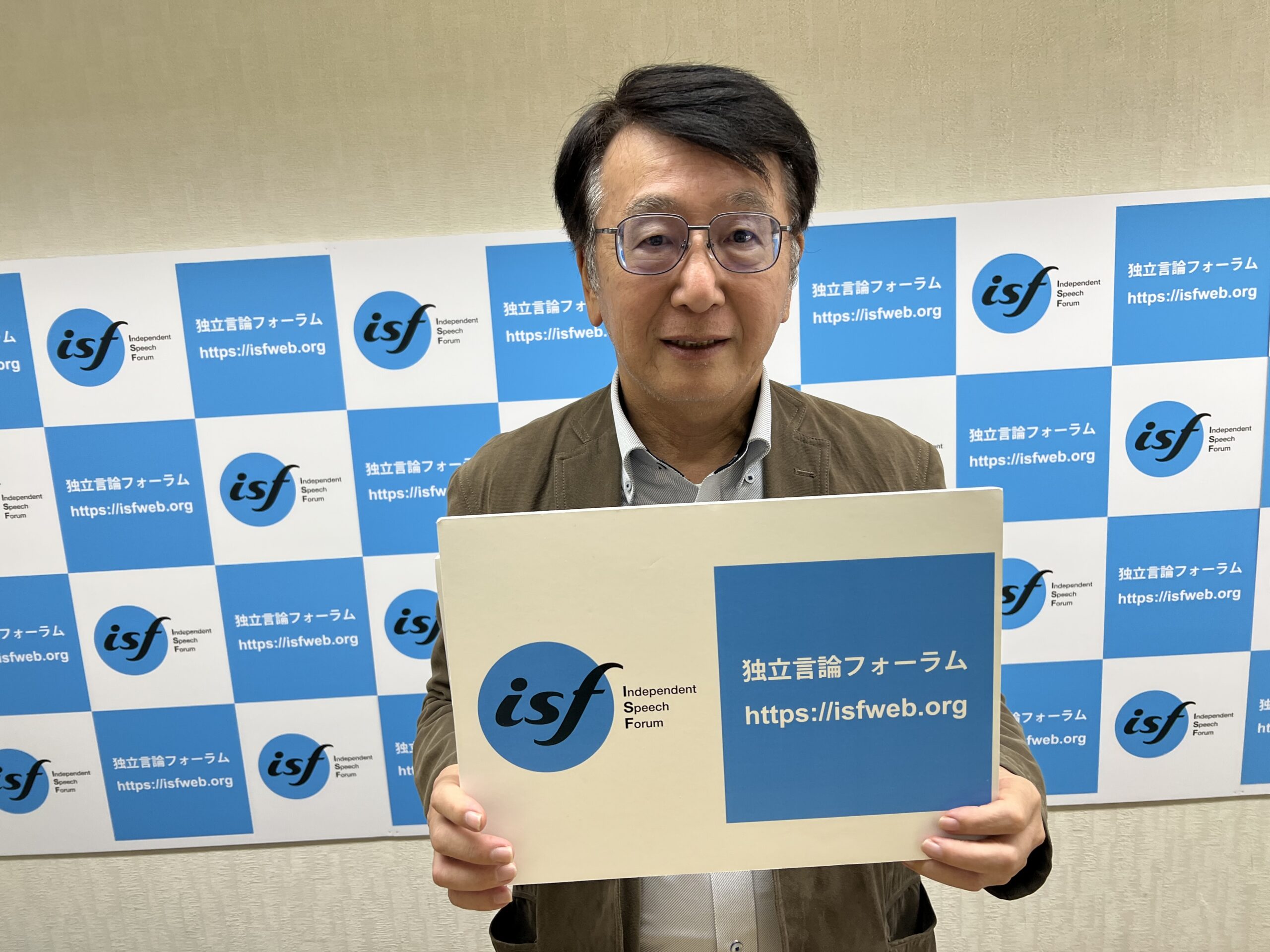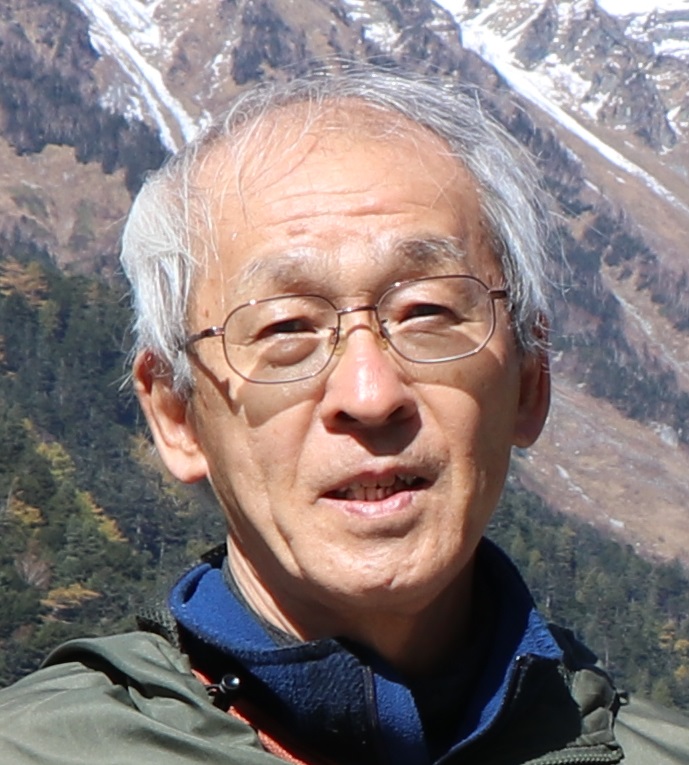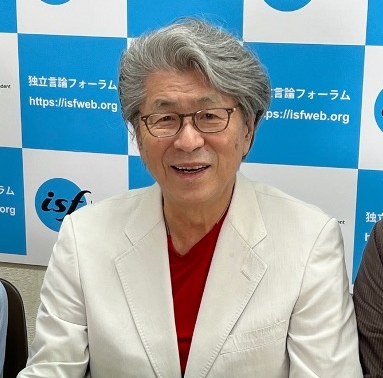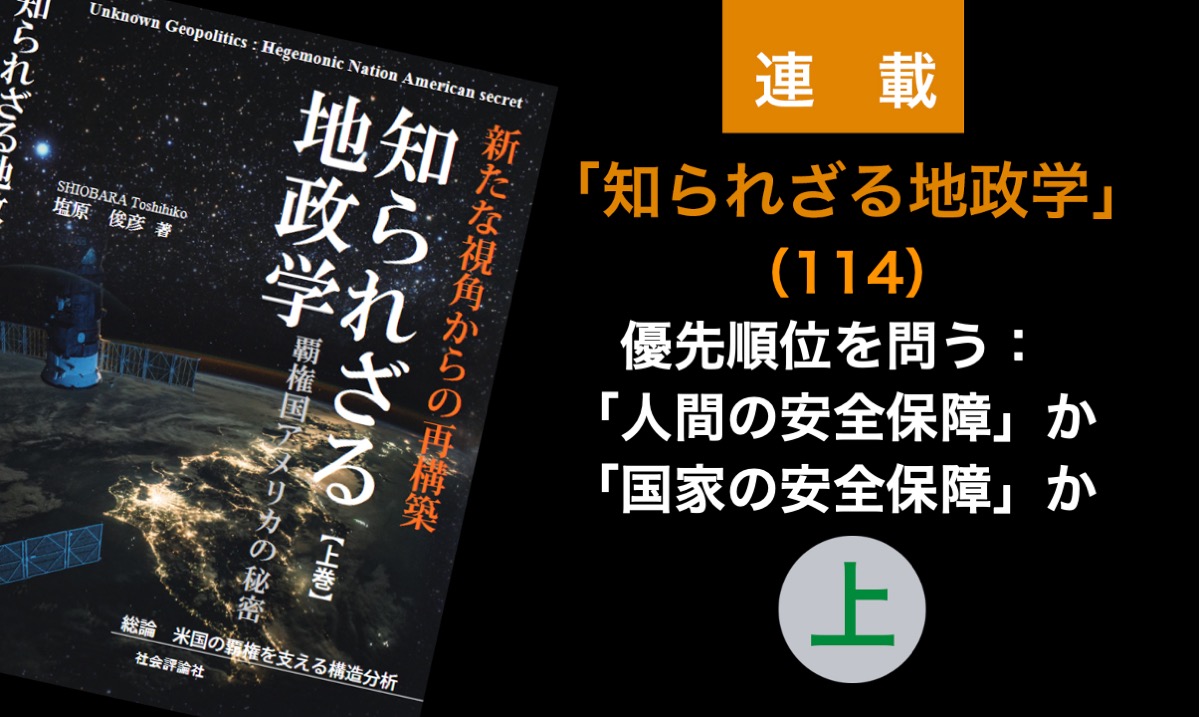
「知られざる地政学」連載(114):優先順位を問う:「人間の安全保障」か「国家の安全保障」か(上)
国際まず、2025年10月25日付で「現代ビジネス」に公表された拙稿「拝啓高市新総理、トランプとのパイプ作りの「秘訣」指南します!」の話をしたい。この原稿は、高市が首相になった21日に書いたものである。その後、24日、高市は同日開催された、英国のキア・スターマー首相の肝いりで結成された「有志連合」の会議にテレビ会議形式で参加した。これは、ロシアの石油とガスのボイコット、ロシアの国家資産を利用したウクライナへの融資の可能性、武器の輸送の加速を推進するためにつくられたもので、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領もデンマーク、オランダ、北大西洋条約機構(NATO)の指導者たちとともにロンドンを訪れた。
アイルランドに学べ!
高市の同会議への出席は、私の高市への書簡の趣旨からすると、最悪である。なぜなら、この「有志連合」参加国はいずれも「戦争継続派」であり、少しでも長くウクライナによる代理戦争を継続させるためにロシアの凍結資産を事実上、没収するという国際法違反も厭わない国々だからだ。なぜこんなものに日本が参加するのだろうか。
折しも、アイルランドのキャサリン・コノリー(68歳、下の写真)は、10月24日、63%以上の得票率で大統領選に勝利した。「国内での経済的公正の要求と国外でのガザの窮状への怒りを選挙キャンペーンに掲げた無所属議員の地滑り的勝利である」と、「ワシントンポスト」は伝えている。ただし、投票率は46.3%と非常に低く、13%以上の投票用紙(165万票のうち約21万4000票)が無効となったことも知っておくべきだろう。
アイルランドの大統領は儀礼的な役割を担っているにすぎないことも付け加えておきたい。首相が大統領よりも大きな権限をもっているのである。それでも、NATOを「戦争主義」と非難してきた人物が大統領に選出された意義は大きい。冷静に議論すれば、ウクライナ戦争のきっかけにもなり、戦争が勃発するとその戦争を軍備拡張に活用してきたNATOの戦争継続姿勢はたしかに批判すべきだ。選挙運動期間中、彼女はガザ地区の状況にとくに注目し、ウクライナへの欧州の軍事支援の拡大に反対の立場を表明した。他方で、ウクライナ紛争におけるロシアの行動を支持していないことを繰り返し強調した。
こうしたしっかりした議論がいまこそ、日本でも欧州でも必要だと強調したい。
9月27日、ダブリンで開催されたシン・フェインの「団結のためのビルディング」全国会議でのアイルランド大統領候補キャサリン・コノリー (Niall Carson/PA Media/AP)
(出所)https://www.washingtonpost.com/world/2025/10/25/ireland-president-catherine-connolly-elected/
外務省の戦争継続派を一掃せよ!
ここで、言いたいことがある。それは、ほとんど何も知らない新首相に対して、前述の会議に出席させた外務省幹部を全員更迭しろということだ。彼らは、いわばウクライナ戦争を「バイデンの戦争」に仕立ててきた連中であり、基本的に戦争継続派だ。いわば、戦争派であるNATOの路線を踏襲者たちである。
彼らには、2022年4月、和平寸前までこぎつけたウクライナに対して代理戦争をはじめるよう要請したジョー・バイデンや、収賄の疑いのあるボリス・ジョンソン(拙稿「The Guardianの報道 「100万ポンドの男:なぜボリス・ジョンソンはドナーをウクライナに連れて行ったのか?」は必読だ!」を参照)によるウクライナ戦争に加担したという「大いなる前科」があるとも言える。こんな人たちは全員、更迭しなければならない。そのうえで、「バイデンの戦争」を終結させることに尽力すべきなのだ。高市が本当に「安倍2.0」をもくろむのであれば、官邸に少なくとも代理戦争継続派ではない人物(たとえば東郷和彦)を据えて、日本外交を根本的に立て直さなければならない。その必要性をコノリー当選は教えてくれている。
安全保障の本質
ここまでは、最近の出来事への怒りを書き留めた部分である。今回は、安全保障について論じたい。安全保障を探究した成果から、問題の本質を理解してほしいのだ。2016年に刊行した『官僚の世界史』では、つぎのように記述したことがある(282~283頁)。やや長いが引用してみよう。
「最後の最後に、安全保障について考えてみたい。安全保障を意味する“security”は、ラテン語の“securus”(形容詞)ないし“securitas”(名詞)を語源とし、これらは欠如を意味する“se”(~がない)という接頭辞と、気遣いを意味する“cura”の合成からなっている。気遣いのない状態こそ安全を意味している。だが、気遣いのない状態は、気遣いなしには到達できないことに気づかなければならない。これは自由が不自由を意識できるところでしか意識化できないのとよく似ている。気遣いのない状態は気遣いという概念なしには語れないのである。気遣いと安全の関係に着目すると、「気遣いがあるから危険が立ち現れるのであり、また、危険が見出されるから、それへの気遣いが求められるのである」ということになる。これが安全保障問題を考察する際、もっとも重要な視角である。安全保障のための諸装置は、安全を脅かすある危険に対して、それを除去・否定する気遣いに傾斜することで、別の危険に対する気遣いへの配慮を忘れ、結局、その諸装置の安全が脅かされかねない。これを避けるには、気遣いを再帰的に繰り返し継続することが必要になる。
否定的な結果に対する気遣いこそ、人類の歴史そのものであると言えるかもしれない。ここで、「超自然的罰」(supernatural punishment)という結果への強迫観念が宗教を機能させてきた「歯車」であり、人間社会の統治という協力関係を可能にしてきたとするドミニク・ジョンソンの主張を紹介したい(Johnson, 2016, p. 238)。否定的結果は人類の生存に直結するからその影響力は絶大であった。人の可死性を克服するための不死の政治体として教会が生み出され、アウグスティヌスの「神の国」の発明によって、そこで人々は死後もなお共同体のなかに生き続けることが可能となった。
実は「自己への配慮」を意味する“epimeleia heautou”(ギリシア語)や“cura sui”(ラテン語)は、多くの哲学教義のなかに繰り返し見出される命令である(Foucault, 1984=1987, p. 62)。「自己への配慮」、「自己陶冶」といった課題こそ、人間が共同体で生きるための生活術の核心をなしていたのである。その裏返しとしての「他者への配慮」こそ、安全保障に直結した問題であったと言えるだろう。序章の註(5)で紹介した「ハラスメント賄賂」のような強要された贈賄が目立つ共同体では、同調しなければ、自己が属する共同体から白い目でみられたり、排除されたりする脅威が強く働いている。共同体の統治は暴力だけでなく宗教上の信仰心や国王や国家への忠誠心によって保持されているので、そうした統治に合わせることで自分の身の安全をはかろうとするところに賄賂が出現するのだ。その共同体の内部にあっては、賄賂が生きるための「配慮」、「気遣い」なのだが、外部からみると強要による腐敗と映るのだ。」
なぜ、この部分を引用したかというと、安全保障が腐敗の問題にも強くかかわっていることを最初に意識してもらいたいと思ったからだ。
高市に問う:「人間の安全保障」か「国家の安全保障」か
私の書簡では、ウクライナ問題を取り上げた。今回は、高市に、「人間の安全保障」と「国家の安全保障」のどちらの優先度が高いかを問いたい。それは、国民優先か国家優先かという選択を迫るものでもある。私の答えは「人間の安全保障」である。ところが、中途半端な議論によって、結局、国家を優先する権力者によって人間あるいは国民が蔑ろにされているのが現状ではないか。
「人間の安全保障」について比較的よくまとまった論文、栗栖薫子著「序論:安全保障研究と「人間の安全保障」」『国際安全保障』(2002年12月)を読むと、つぎのような気になる記述がある(7頁)。
「「人間の安全保障」を採用する諸国や国際機関は、程度の差はあれ、いずれも安全保障概念の中身をより人々を重視したものへとシフトさせることを意図している。しかし、これは、国家安全保障か「人間の安全保障」かという二者択一的な問題ではない。」
彼女があげる理由は、人々の安全を確保する上では、社会、国家、地域、国際それぞれのレベルからの重層的な安全保障の施策が必要となるからであるという。しかし、その場合でも、まず人間重視ではないか。どうにも、まどろっこしい、判然とした記述は「逃げている」という印象を与えるだけだ。「二者択一な問題でない」としても、どちらを最優先にするべきかという議論は必要なのではないか。
私は、高市早苗首相および小野田紀美内閣府特命担当大臣に同じ問いかけをしたい。なぜかというと、日本は明らかに「人間の安全保障」を「国家の安全保障」よりも軽視しているからだ。「人間の安全保障」を守る姿勢なくして「国家の安全保障」など無意味なのではないかと問いたいのである。
10月24日の高市の所信表明演説では、経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、健康医療安全保障という言葉はあっても、これを包摂する「人間の安全保障」という言葉もなければ、概念自体もなかった。要するに、「国家の安全保障」のなかですべてが低位に押し込められていたという印象をもつ。これでは、優先順位の順番がまったく違う。
重いメディアの責任
ここで私が注目するのは、「戦後80年に寄せて」という石破茂首相(当時)が10月10日に発表した所感である。そのなかで、先の大戦について、「国内の政治システムは、なぜ歯止めたりえなかったのか」を問うている。その答えの一つに、軽視してはならない問題としてメディアが取り上げられている。そのうえで、メディアについて石破はつぎのように記している。
「使命感を持ったジャーナリズムを含む健全な言論空間が必要です。先の大戦でも、メディアが世論を煽り、国民を無謀な戦争に誘導する結果となりました。過度な商業主義に陥ってはならず、偏狭なナショナリズム、差別や排外主義を許してはなりません。」
ところが、メディア側の反応といえば、読売新聞の社説は「戦後80年の所感 メッセージの発出に見識疑う」と取りつく島もない。東京新聞の社説「石破氏の所感 戦後80年には不十分だ」では、メディアに向けられた批判を完全にスルーしている。朝日新聞の社説「首相80年所感 言いっ放しで済ますな」は、「閣議決定した政府の正式見解ではなく、退任間際の表明であっても、首相として発したメッセージは重い」と書いてはいるが、自分たちへの批判については、無視している。
私は、日本が現在、「人間の安全保障」さえ守ろうとしていないのは、メディアにその責任の多くがあると考えている。このままでは「人間の安全保障」が守られないまま、「国家の安全保障」を守るという名目で国民の税金が無駄遣いされてしまうのではないか。
アルコール飲料の警告表示とテレビCM禁止
石破がメディアについて、「過度な商業主義に陥ってはならず、偏狭なナショナリズム、差別や排外主義を許してはなりません」というのは至極全うである。実は、いま、メディアは過度な商業主義(別言すると、厳しい経営難)に陥っており、偏狭なナショナリズムを喧伝し、差別や排外主義に対して鈍感になっている。
とくに、「過度な商業主義」が「人間の安全保障」の軽視につながっている点を強調したい。すでに、拙稿「知られざる地政学」連載(72):アルコール飲料とがんリスク:テレビCMは停止、ラベル表示は義務づけよ!」(上、下)に書いたように、アルコール飲料が高いがんリスクをもつにもかかわらず、日本のメディアは、このリスクをめぐる議論や海外での警告表示についてほとんど報道しない。理由は簡単だ。広告主たるアルコール飲料メーカーの広告料が失われるのを恐れているからだ。テレビでアルコール飲料のCMを流すこと自体、メディアが「人間の安全保障」をまったく無視している。それどころか、「がんになれ!」と推進していると言ってもいい。
政治家はメディアで騒がれないことをいいことに、アルコール飲料が人間の命を奪う可能性について問題視しようとしない。その一方で、「国家の安全保障」を過度に騒ぎ立てている。もちろん、メディアもそのお先棒を担いでいる。これは、性加害者ジャニー喜多川の罪を無視して、ジャニーズ事務所のタレントを公然と使いつづけることで、事実上、性加害を助長してきた日本のメディアのひどさに通底している。
人権を守ることも「人間の安全保障」の根幹である。それにもかかわらず、日本のメディアはこれを軽視してきた。これは、「人間の安全保障」への無理解の裏返しなのである。
アルコール飲料、少量でも認知症に
アルコールを少量でも飲むと認知症になるリスクがあるとしたら、みなさんはどう思うだろうか。この問題もまた「人間の安全保障」に直結する大問題ではないのか。そう思う私は、2025年10月15日に「ワシントンポスト」に掲載された「アルコールはいくら飲んでも安全ではない、少なくとも認知症リスクでは、との研究結果 1日1、2杯の飲酒でもリスクがないわけではないことが新しい研究で示唆された。」という記事を読んで驚愕した。
記事には、BMJ Evidence-Based Medicine誌に発表された新しい研究によると、軽い飲酒でも認知症リスクを高める可能性があることが示唆された、と紹介されている。この論文は、「多様な集団におけるアルコール使用と認知症リスク」というもので、56~72歳の成人55万9559人以上のデータと、参加者240万人の遺伝解析情報から得られたものである。
その結果、「我々の非線形解析は、低アルコール摂取が認知症に保護効果をもたらすという従来の仮説を支持せず、代わりにアルコール摂取量に比例してリスクが単調増加することを示した」という。さらに、「この知見は、適度なアルコール摂取が脳を保護する可能性という長年の通説に異議を唱えるものであり、公衆衛生上極めて重要な意味をもつ」としている。結論として、つぎのように記述されている。
「要約すると、今回の研究結果は、すべての種類のアルコール摂取が認知症リスクに有害な影響を及ぼすことを支持するものであり、以前から示唆されている適度な飲酒の保護効果を支持する証拠はない。」
WPの解説によると、これまでの研究では、一般に自己申告によるアルコール摂取量に依存しており、非飲酒者の認知症リスクはわずかに増加し、軽度から中等度の飲酒者のリスクはもっとも低く、大量飲酒者のリスクははるかに高く、増加することが繰り返し報告されていたという。ただ、自己申告データだけに頼ることには多くの問題があるため、論文の研究者たちは次善の策を採用した。240万人から抽出したゲノムデータを使って、生涯にどれだけの量を飲む可能性があるかを予測し、因果関係を推測したのだ。
その結果、アルコール摂取量が増加すると、必ず認知症リスクが上昇することがわかった。飲酒量が3倍増えるごとに、生涯認知症リスクは15%増加した。飲酒量が週1杯から3杯に、あるいは週3杯から9杯に増加すると、認知症リスクは15%増加したのだ。そして、記事は、この研究論文の執筆者の一人のつぎの言葉を紹介している。
「習慣的に飲酒している場合、1日に1杯程度なら、脳の健康にひどく害を及ぼすことはないが、多少は害がある。」
「知られざる地政学」連載(114):優先順位を問う:「人間の安全保障」か「国家の安全保障」か(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)