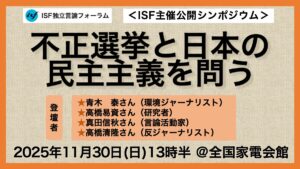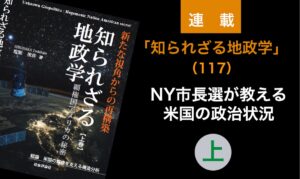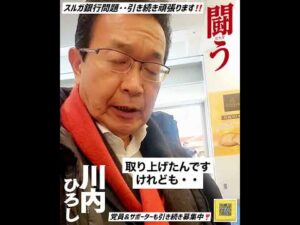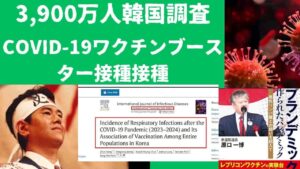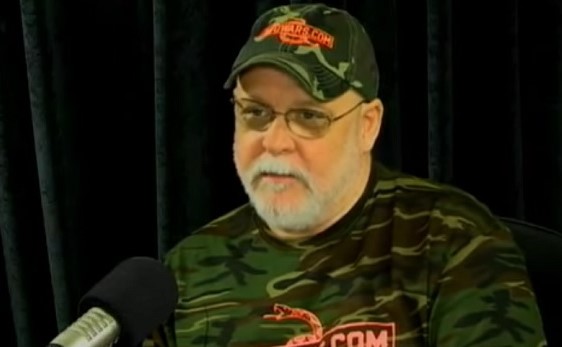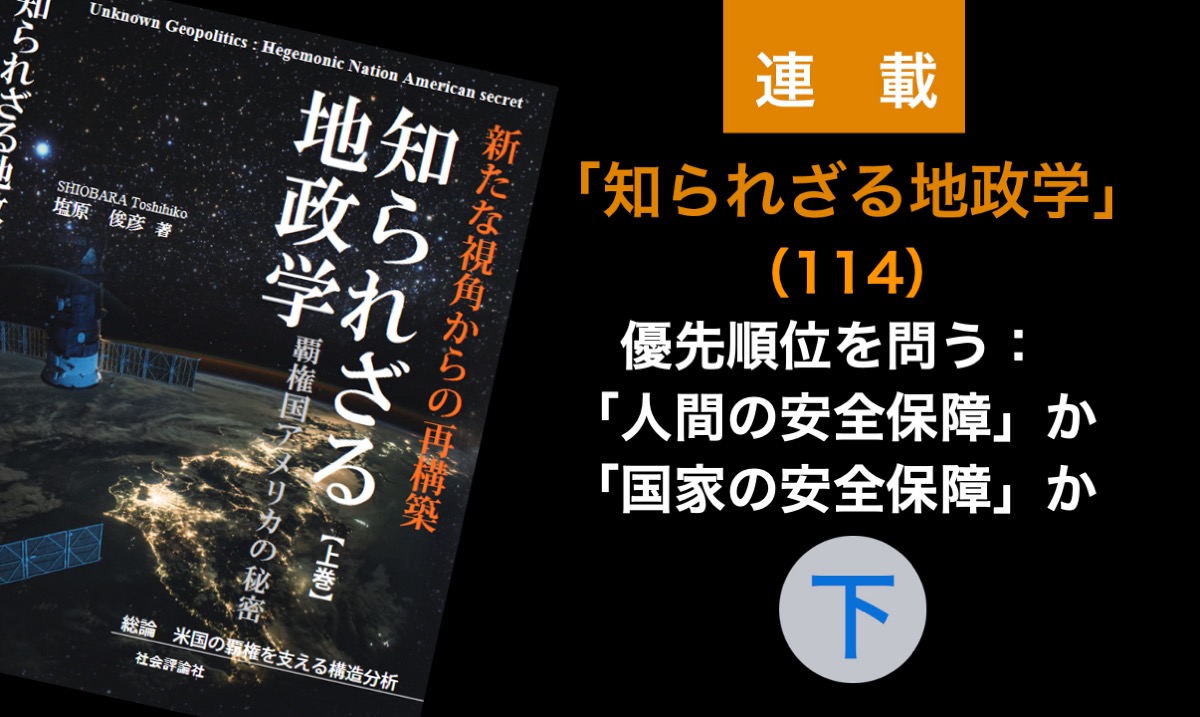
「知られざる地政学」連載(114):優先順位を問う:「人間の安全保障」か「国家の安全保障」か(下)
国際
「知られざる地政学」連載(114):優先順位を問う:「人間の安全保障」か「国家の安全保障」か(上)はこちら
少しだけまともな日経新聞
アルコール飲料のがんリスクや認知症リスクについて、日本国民はどの程度知っているのだろうか。私のみるところ、日本経済新聞(といっても、本紙ではなく別媒体)だけは多少とも、「人間の安全保障」の観点から、アルコール飲料への注意を払っていた。
たとえば、2022年6月6日付のNIKKEI STYLE(健康・医療)は、「1日ビール1缶でも脳が萎縮? 認知機能への影響は…」という興味深い記事を公表している。そこには、「最近になって、それほど量は多くなくとも、つまり「ほどほど」の飲酒でも、習慣的に続けると脳は萎縮する可能性があるという研究結果[注1]が発表された」と書かれている。
この注1に示されているのは、「UK Biobankにおけるアルコール摂取と灰白質および白質容積との関連性」という論文だ。

少量でも習慣的に飲酒を続けると、脳が萎縮してしまうことが、英国の中高年約3万7000人を対象とした研究で明らかになった(写真はイメージ=PIXTA)
(出所)https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXZQOLM31AIE0R30C22A5000000/?msockid=30fb7330d4bb604638466145d5c86182
この拙稿を執筆している最中に、2025年10月20日付のThe Economistの記事のなかに、「昨年、世界保健機関(WHO)は、欧州における非伝染性疾患の主な原因として、タバコ、化石燃料、超加工食品とともにアルコールを挙げた」と書かれているのを発見した。そこで調べてみると、WHO欧州地域事務局が発表した先駆的な報告書のなかで、特定の強力な産業が、心血管系疾患、がん、糖尿病などの非感染性疾患(NCDs)や、タバコ、アルコール、不健康な食生活、肥満などの危険因子の予防・管理努力に干渉し、影響を及ぼすなどして、欧州と中央アジア全域でいかに不健康と早期死亡を促進しているかを明確に示していることを知った。
その紹介記事によると、「タバコ、超加工食品、化石燃料、アルコールの四つの企業製品は、全世界で年間1900万人、全死亡者の34%を死亡させている」と断じている
「欧州地域だけでも、これらの産業が年間270万人の死亡の原因となっている」とも記している。「業界の手口には、ターゲットを絞ったマーケティング戦略による社会的弱者の搾取、消費者を欺くこと、自社製品の利点や環境面での信頼性について虚偽の主張をすることなどが含まれる」という指摘もある。一連の戦術には、健康、政治、経済、メディアなど、社会システム全体に影響を及ぼすことで、健康や社会に大きな害をもたらすことを目的としたものがあるという。その結果、「今日に至るまで、個々の政府や政府間組織による行動は、このような有害な商法を防止・制限するには不十分であった」と結論づけている。
欧州においてさえ、「人間の安全保障」が明らかに蔑ろにされてきた。もちろん、日本も同じである。
自閉症への無関心
日本のメディアの「人間の安全保障」への軽視はアルコール飲料のリスクの無視だけではない。ドナルド・トランプ大統領の誕生後、ロバート・F・ケネディ・ジュニアが保健長官になって任命されて、米国では、自閉症(autism)への関心が高まっていることをご存じだろうか。この問題でも、日本のメディアはこれをほとんど報道していない。つまり、日本のメディアは「人間の安全保障」に無関心を装い、その結果として、政治家も国民も世界の医療現場の変化を知らされていないのだ。
トランプ大統領とケネディ・ジュニア保健長官は2025年9月22日、自閉症の原因についての報告書を発表した。まず、この日の日付で公表されたNYTの記事「鎮痛剤、ワクチン、遺伝子、自閉症について知っておくべきこと」を紹介してみよう。
自閉症(autism)は、正式には「自閉症スペクトラム」と呼ばれ、社会性やコミュニケーションの問題、反復行動、思考パターンなどが広範囲に混在している。自閉症と診断された子どもは、単に社会的な合図に苦労するだけかもしれないし、重症の子どもは、助けを借りなければ話すこともトイレを使うこともできないかもしれない。血液検査や脳スキャンで誰が自閉症であるかを判断することはできない。
神経発達障害のひとつである自閉症には、これまで何百もの遺伝子が関係しているとされてきた。しかし、科学者たちによれば、自閉症は遺伝的要因と環境的要因の複雑な組み合わせから生じているようだという、とNYTは書いている。
鎮痛剤「タイレノール」の有効成分であるアセトアミノフェンを妊娠中に服用した可能性
科学者は、タイレノールやその他の鎮痛剤の有効成分であるアセトアミノフェンについて10年以上研究してきた。妊婦のアセトアミノフェン使用を調査したいくつかの研究では、子供が後に神経発達障害を発症するリスクが高いことが判明している。そのような障害の根底にある可能性のある他の要因(遺伝を含む)をコントロールしようとした他の研究では、関連性は認められなかった。
8月、ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院とマウントサイナイ大学アイカーン医学部の研究者は、妊娠中のアセトアミノフェンに関する46の先行研究のレビューを発表した。
研究者らは既存の研究のみを評価し、アセトアミノフェンの影響に関する新たなデータは提供していない。研究者らは、妊娠中にアセトアミノフェンを使用した女性と注意欠如・多動症(ADHD)および自閉症との間に関連性があると結論づけたが、これは薬が自閉症を引き起こしたことを意味するものではないと述べた。タイレノールを使用した女性とそうでない女性では、妊娠中に生じた健康問題や基礎にある遺伝的要因など、重要な点で異なる可能性がある。2024年にスウェーデンで行われた250万人の子供を対象としたある大規模な研究では、同じ母親から生まれた兄弟姉妹を比較したところ、アセトアミノフェンの使用と神経発達障害との関連は消えていた。
ワクチンとの関係性
1990年代後半、アンドリュー・ウェイクフィールドというイギリスの研究者が、はしか、おたふくかぜ、風疹のワクチンと自閉症との関連性を明らかにするため、12人の子どもを対象とした研究を発表する。同論文は、デンマークの全児童を対象とした研究を含む多くの大規模な研究によって、その後数年間で完全に否定された。ワクチンの種類、含有成分、小児期ワクチンの接種時期にかかわらず、研究者たちは自閉症との関連性を認めていない。ウェイクフィールド博士の1990年の論文は2010年に撤回され、彼は医師免許を失った。
現状
2000年には150人に1人であった自閉症の診断が、現在では31人に1人と推定されている。この増加には、過去数十年にわたる自閉症の定義と診断方法の拡大が拍車をかけている。自閉症が初めて登場したのは、1980年のアメリカ精神医学会の『精神障害の診断と統計マニュアル』第3版である。1987年の改訂版では、30ヵ月以降に症状が現れた子供も含まれるように、障害の定義が調整された。自閉症の診断基準も6項目から16項目に増やされ、従来の6項目すべてではなく、16項目のうち半分を示すことが必要とされた。
1994年に発表された「精神疾患の診断と統計のためのマニュアル」(DSM)第4版では、単一の興味やその他の特徴にとらわれる社会的障害であるアスペルガー症候群が自閉症スペクトラムに含まれることになった。これは、障害がより軽度で、知的能力が平均的か、あるいは平均以上であっても診断を受けられることを意味するため、重要な変化であった。
2013年に発表された診断マニュアルの第5版では、自閉症、アスペルガー症候群、そしてPDD-NOSと呼ばれる状態(「他に特定されない広汎性発達障害」の略)が、自閉症スペクトラム障害という単一の診断に統合された。また、臨床医が自閉症スペクトラム障害と注意欠陥多動性障害の複合診断を下すことも可能になった。
米国疾病予防管理センターが発表した自閉症診断に関するデータによると、知的障害と重度の言語障害を有すると定義される深在性自閉症の有病率は、2000年から2016年にかけてわずかに上昇したが、他の自閉症診断はより急激に上昇した。
9月22日の発表
9月22日の発表で、トランプ大統領とロバート・ケネディ Jr. 保健長官は、「矛盾した証拠や自閉症の原因となるという証拠がないにもかかわらず、妊婦にタイレノールの使用を控えるよう呼びかけるなど、自閉症に関する主流の理解に対して大規模な攻撃を開始した」、とNYTは指摘する。
トランプは、「服用するな」とホワイトハウスで行われたブリーフィングで発言した。「アセトアミノフェンを服用しないよう、必死に戦え」というのである。
政権は自閉症の原因研究に5000万ドルを投資することを約束し、トランプとケネディの両者は、小児用ワクチンとの関連の可能性を指摘した。だが、これについて、NYTは、「数十年にわたる研究にもかかわらず関連性は確認されておらず、主流の科学者は自閉症が単一の原因に帰せられない遺伝的・環境的要因の複雑な組み合わせによる結果であると圧倒的に合意している」、と指摘している。同様に、医療団体は9月22日、タイレノールに関する大統領の警告を即座に反論し、アセトアミノフェンは妊娠中の女性の発熱に対する安全な治療法であると擁護した(ただし長期使用は推奨されない)。
過去の切り抜き
ついでに、過去に興味深いと思って切り抜いた記事について簡単に紹介しておこう。2022年10月、The Economistの「人間の脳組織をラットに移植するとどうなるか」という記事のなかには、「ティモシー症候群は、自閉症の一種を引き起こす稀で危険な病気である。また、発作や手足の指の融合などの解剖学的異常、生命を脅かす不整脈も引き起こす。これは、カルシウムイオンチャネル遺伝子の突然変異によるものである」という記述がある。
2021年2月のThe Economistの記事「口腔と腸内の微生物生態系は、多くの病気に関連している」には、カリフォルニア工科大学のサルキス・マズマニアン博士が自閉症の人々の腸内フローラを研究し、いくつかの関連する細菌のレベルが上昇していることを確認したときに、自閉症とリンクしているようにもみえる、という。
会議でマズマニアン博士は、これらの物質の一つである4-エチルフェノール(4ep)に関する研究について話した。この物質は体内で4-エチルフェニルサルフェート(4eps)に変換される。マウスを用いた研究では、4epsは感情行動に関連する脳の領域を活性化し、ニューロン間の接続性を重要な形で低下させる可能性があることが示されている。また、彼と彼のチームは、4epsを産生する細菌を腸内に持つマウスは、人間の自閉症の症状を反映した社会的行動を示すと主張している。
この研究には賛否両論があるという。ある者はマズマニアン博士の以前の論文の統計的な頑健性を疑問視し、また別の者は、マウスの行動が複雑な人間の状態について何か役に立つことがあるのではないかという考えそのものを疑問視している。この第二の異議を克服することは、人を使った実験をすることを意味する。
2021年5月公表のロシア語資料では、「自閉症や統合失調症は、まさにチンパンジーよりも人間の方が顕著な機能を壊している」といった指摘がみられる。チンパンジーの赤ちゃんがおもちゃで遊んでいる様子を、自閉症の子どもとそうでない子どもが遊んでいる映像と比較してみると、チンパンジーは自閉症の子どもと多くの点で似ていることがわかる。サイコロを振ったり、バケツを拾って壁にぶつけたりするが、部族や世話をしてくれる人、慣れ親しんだ人たちとは一切交流しない。しかし、人間の赤ちゃんはバケツでノックして、大人に「僕がどうやってできるか見てて」と見せてくれる。だが、チンパンジーはそれをしない。重要なのは、チンパンジーに自閉症や統合失調症がないということではなく、これらの病気の際に壊れてしまう機能が人間に最も顕著にみられるということだ、という。
私が自閉症について関心をもつようになったのは、竹内願人著『アンナチュラル』(上、下)という小説を読んだからである。かつて、私の研究室に送りつけられてきたものだが、いろいろと考えさせられた。「人間の安全保障」だけでも、勉強すべきことは多い。
多岐にわたる「人間の安全保障」
実は、「人間の安全保障」は生命にかかわるだけではない。2017年の国連の「人間の安全保障ハンドブック」によれば、「人間の安全保障は、平和と開発におけるもっとも困難な欠陥に対する、より強力で持続的なアプローチである」とある。このアプローチは、気候変動や自然災害への耐性を強化し、平和的で包摂的な社会を促進し、根強い貧困の根本原因に取り組み、人類の危機から長期的な持続可能な開発への移行を強化する上で、加盟国に対する国際連合の支援を強化することができる、と書かれている。
こうした認識は、緒方貞子とアマルティア・センが主導した、人間の安全保障委員会が1994年に発表した『人間開発報告書』と2003年に発表した『安全保障の今日的課題』、さらに、国連開発計画の2022年の特別報告書『人新世の脅威と人間の安全保障』にまで脈々と受け継がれてきたものだ。ゆえに、2005年に発効した「国連腐敗防止条約」(UNCAC)の序文にもつぎのように記されている。
「腐敗は民主主義や法の支配を傷つけ、人権違反をもたらし、市場を歪め、生活の質を侵害し、そして、組織犯罪、テロリズム、およびその他の繁栄に必要な人間の安全保障へのその他の脅威を許してしまう。」
私が「人間の安全保障」に関心をもったのは、この記述を知ったからであった。だからこそ、最優先課題である「人間の安全保障」にかかわる問題として、腐敗の研究に取り組んだのであった。その成果が『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)といった一連の著作である。前半部分で、『官僚の世界史』の長い引用を紹介したのも、安全保障と「人間の安全保障」の深いつながりを理解してほしいと思ったからだ。
こう考えると、「人間の安全保障」を最優先にし、生命や医療にかかわるだけでなく気候変動、生態学などはもちろん、腐敗問題まで、包括的にとらえた、さまざまな施策に取り組まなければならないことに気づく。こうした問題に真正面から取り上げつつ、そのうえで、「国家の安全保障」についても考えるべきなのである。
「人間の安全保障」軽視の報い
どうだろうか。日本の場合、すでにメディアの「過剰な商業主義」がすでに目に余る。その結果、「人間の安全保障」を最優先に位置づけているメディア自体が存在しない。政治家もまた「人間の安全保障」をまったく軽視している。まるで、「国家の安全保障」がすべてであるかのような空恐ろしい状況になっている。
図式的にわかりやすく解説してみよう。近年、経営悪化が著しいメディアは、広告料欲しさに、アルコール飲料のがんリスクや認知症リスクに蓋をして、「人間の安全保障」を無視してきた。それを無視することで、「国家の安全保障」を全面化させて、結局、日本に住む人間や国民、あるいは生態系全体を戦争に巻き込もうとしている。
それは、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領と同じく「悪」であることを隠蔽して、敗色濃厚ななかでウクライナ国民を「犬死」へと追いやっている「人間の安全保障」の決定的な軽視を無視してきた。その結果、「国家の安全保障」だけが重視されて、権力維持をねらうゼレンスキーを正当化し、腐敗にまみれたゼレンスキー政権を支援することで、何とか投下したカネを回収しようと躍起になっている欧州の政治指導者の邪さを覆い隠すことにつながっている。戦争派のNATOを先のコノリーが非難したのは当然なのだ。
既存政党はオールドメディアとの「共犯関係」
さらに、「人間の安全保障」軽視のメディアは、政治家の「人間の安全保障」軽視をもたらしているようにみえる。日本の既存の政党を見渡してみると、アルコール飲料への警告表示義務化とかCM禁止といった「人間の安全保障」重視の公約を見たことがない。残念ながら、既存政党の多くは、メディアを批判することすらできないまま、結果として、「人間の安全保障」を長年にわたって軽視しつづけてきた。つまり、オールドメディアと既存の大多数の政党は持ちつ持たれつの「共犯関係」にあるように映る。
私は、自民党でも、日本維新の会でも、公明党でも、あるいは立憲民主党でも日本共産党でもかまわないから、「人間の安全保障」を最優先とする政党を支持したいと考えている。ところが、既存政党の多くはオールドメディアに取り込まれてしまっている。既存政党に属していても、本当に誠実な政治家であれば、「人間の安全保障」を最優先に位置づけ、まず、「人間の安全保障」を守れという声をあげられるはずだ。しかし、そんな政治家もほとんどいない。「「人間の安全保障」を守らずして、「国家の安全保障」を語る勿れ」、と心の底から言いたい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)