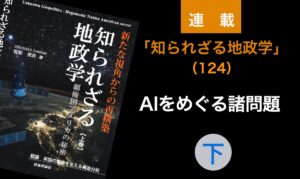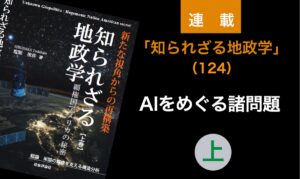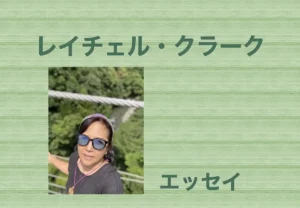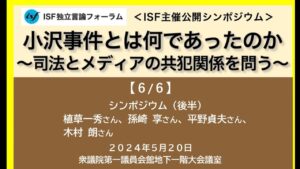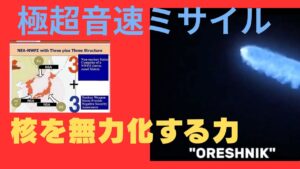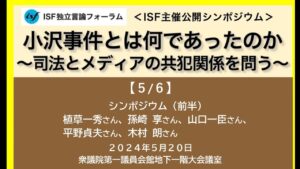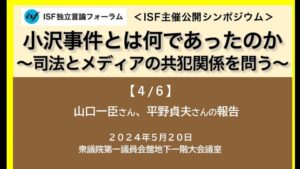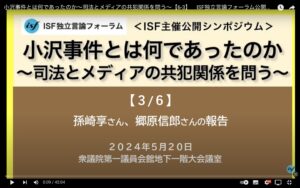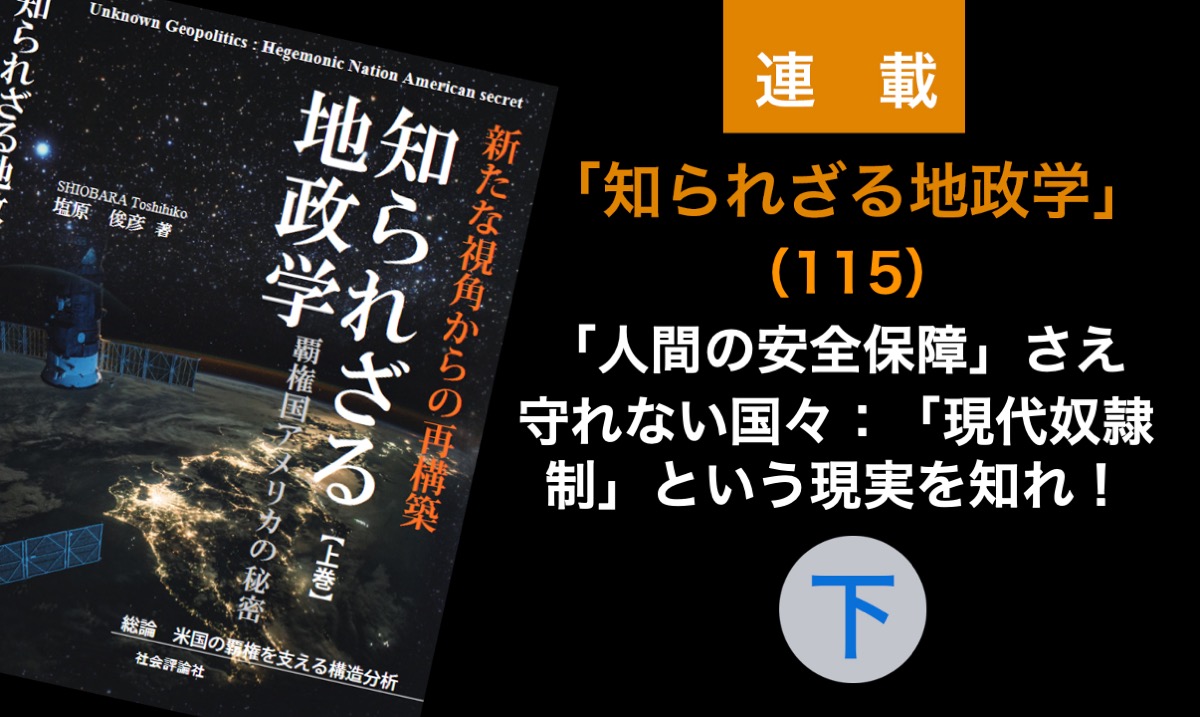
「知られざる地政学」連載(115):「人間の安全保障」さえ守れない国々:「現代奴隷制」という現実を知れ!(下)
国際
「知られざる地政学」連載(115):「人間の安全保障」さえ守れない国々:「現代奴隷制」という現実を知れ!(上)はこちら
米国の強制労働=「現代奴隷制」の実態
つぎに、ほとんどの日本人が気にもかけていない米国での奴隷労働について解説しよう。なぜなら、エイブラハム・リンカーン大統領が、南北戦争中の1862年9月に連邦軍の戦っていた南部連合が支配する地域の奴隷たちの解放を命じた宣言(奴隷解放宣言)を出し、終戦後、南部連合支配地域が連邦軍の支配下になり、アメリカ合衆国憲法修正第13条が承認されたため、奴隷たちの解放は公式に確立されたと理解しているからだろう。
しかし、憲法修正第13条は、「当事者が正当に有罪判決を受けた犯罪に対する刑罰としての場合を除き」、非自発的な隷属を禁じていたにすぎなかった。2024年6月19日付の「ニューヨークタイムズ」(NYT)は、つぎのように記述している。
「北部では、このいわゆる例外条項は、既に進行中だった強制的な囚人労働の民間請負を認めるものと解釈された。一方、旧南部連合地域では、解放された男女が虚偽の罪状で日常的に逮捕され、その後プランテーション所有者や実業家に貸し出され、刑期を労働で償わせるという、はるかに残酷な制度を生み出した。一部の歴史家は、この囚人貸与制度(convict leasing system)を「奴隷制よりも酷い」と評している。なぜなら、彼らを死に追いやるほど働かせることを避ける動機が全くなかったからだ。」
この囚人貸与制度こそ、今日まで米国でつづけられている「現代奴隷制」の根幹をなしている(後述)。
米国の奴隷制の歴史
ここでは、米国の奴隷制の歴史を詳述するだけの紙幅はない。興味のある読者は、ぜひ2021年1月27日付のWPの記事「廃止後も抜け穴が奴隷制を150年以上存続させた」を読んでほしい。
修正第13条が追加された直後、南部の各州は、突然自由になった黒人人口と、根底から覆された労働制度に反発した。ミシシッピ州は、公共の場での行動や白人との交流を規制する黒人の掟(Black Codes)を最初に制定し、自由な黒人に雇用証明書を携帯させなければ再奴隷化される危険を課す浮浪者法を制定した。少なくとも南部の六つの州は、ミシシッピ州をモデルにしてBlack Codesを制定した。
修正第13条の犯罪例外の抜け穴は、奴隷制度に組み込まれた経済的利益と社会秩序を維持するための条件を作り出した。奴隷制推進派の議員たちは、イリノイ州がBlack Codesで行ったように、違反しても例外の対象となる法律をつくる。南北戦争後のBlack Codesは、自由黒人人口の事実上の再奴隷化をもたらしたのである。Black Codesは1868年までにほとんど廃止されたが、19世紀後半から20世紀半ばにかけてのジム・クロウ法(人種隔離を強制する法律群)の基礎を築いた。
紹介したWPの記事では、「1970年代以降、麻薬戦争による刑事罰の強化が大量収容に拍車をかけ、収容された人々は、今日も続く 刑務所産業複合体の隠れた労働力を形成している」と指摘している。事態の深刻さから、各州が例外規定を再検討するようになったのは、刑事司法改革が推進されるようになってからだ。2018年、コロラド州は州憲法から奴隷制に関する文言を削除した。その際、「進歩的」で「先導的」と称賛された。2020年11月の選挙では、ユタ州とネブラスカ州の有権者もこれに追随する。
2022年11月の段階では、アラバマ、オレゴン、テネシー、バーモントの4州は例外なく奴隷制を廃止することになったが、ルイジアナ州の提案は否決された(The Economistを参照)。驚くのは、2024年11月において、カリフォルニア州憲法を改正して受刑者が刑罰として強制労働させられるのを防ぐ議案第6号が否決されたことである(NYTを参照)。
これほどまでに、米国では囚人労働が「現代奴隷制」として切り離しがたく位置づけられてしまっているのだ。そこには、「人間の安全保障」といった概念そのものが通用しない世界が広がっている。
2025年1月に公表された論文「「自由の国」における強制的な囚人労働」によると、全国で200万人近くが、州や連邦の刑務所、郡の拘置所、少年院、移民収容所、その他収容施設に収容されており、州と連邦の刑務所に収監されている120万人のうち、80万人近くが刑務所の労働者で、そのほとんどが強制労働であるという。これらの労働者の大部分(約80%)は、清掃業務、食事の準備、敷地内の整備、洗濯など、収容施設の運営を維持するための施設の維持・運営業務に従事している。残りの約20%のうち、約17%は政府が運営する企業で働いており、陸運局のコールセンターのスタッフや公立病院の洗濯係、あるいは公共事業で、危険物の流出清掃や国有林の消火活動に従事している。残りの3%は民間の雇用主で働いており、米国経済全体の産業のために商品やサービスを生産し、わずかな賃金を得ているにすぎない。他方で、貸与する側の自治体の収益源となっている。なぜなら、たとえば、カリフォルニア州の場合、民間企業で働くのは1%未満だが、民間企業は現行賃金を支払わなければならない一方、その最大80%は刑務所側が徴収できるからである(2022年11月11日付のThe Economistを参照)。
先に紹介したNYTは、「今日、州や連邦の刑務所に収監されている120万人の米国人の大半は、独房の掃除から熟練した製造業まで、あらゆる分野の仕事を、時給数セントの低賃金で、あるいはいくつかの州ではまったく無賃金で、強要されて働いている」と書いている。「議会の議員たちは、中国の新疆ウイグル自治区などで囚人労働によってつくられた輸入品を非難しているが、ワシントンをはじめとする多くの政府機関のオフィスには、この国の囚人によって作られた家具や備品が置かれている」のだ。「実際、連邦政府機関は連邦刑務所から物品を購入することが義務づけられており、公立学校や大学などの州政府機関も、しばしば州刑務所からの調達を検討しなければならない。多くの州では、刑務所で製造された物品は一般市場で自由に入手でき、海外にも出荷されている」、とも指摘している。
「人間の安全保障」を無視した米国のひどさ
先の論文はまず、法外な投獄率に注目している。強制労働させるには、とにかく囚人の数を増やす必要がある。そこで、下図に示したように、米国では人口10万人あたり614人が投獄されている。これは、英国(146人)の4倍以上であり、カナダ(88人)の7倍近くであることを示している。
南部16州(およびワシントンDC)のうち13州は、全米平均(614人)よりもはるかに収容率が高い。ルイジアナ州(1067人)とミシシッピ州(1020人)が人口10万人あたり1000人を超える収容率でトップとなり、僅差でアーカンソー州(912人)とオクラホマ州(905人)がつづく。
それだけではない。人種差別とおぼしき事態が存在する。論文によれば、全米の約12%が黒人であるのに対し、州および連邦刑務所に収監されている人の32%が黒人なのだ。さらに、男性、ヒスパニック系、アメリカ・インディアンおよびアラスカ先住民(AIAN)も、全人口に占める割合に比べ、収監者の割合が高い。つまり、「人間の安全保障」をまったく無視した現実が広がっているのである。

世界でもっとも高い割合で投獄されている各州を国に見立てた場合の人口10万人当たりの世界投獄率
(出所)リンクはこちら
何も支払われないという現代奴隷制
論文は、「アメリカ全土で、収監中の労働者の時給は、もっとも一般的な職種で平均13~52セントである」と書いている。さらに、南部の7州(アラバマ州、アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、ミシシッピ州、サウスカロライナ州、テキサス州)では、囚人による労働はほとんど無給のままである。ルイジアナ州の収監労働者のほとんどは、時給2~4セントと、ほとんど無給である(下図を参照)。
なお、日本の場合、刑務作業を実施した受刑者等には、出所後の生活資金の扶助として、作業報奨金が支給されているが、その作業報奨金の1人1月当たりの平均支給計算額は、約4537円にすぎない(2022年度)。また。2025年6月からの法改正により、「懲役」と「禁錮」は廃止され、新たに「拘禁刑」が導入された。これにより、拘禁刑では、刑務作業はようやく義務ではなくなった(といっても、実態は不明である)。
米国では、収監中の労働者が得るわずかな賃金は、税金で差し引かれ、裁判所が科す罰金、弁護士費用、返還金の支払いのために差し押さえられ、彼ら自身の収監費用に充てられる(いわゆる「ペイ・ツー・ステイ」料金が、こうした差し引きの大部分を占めることが多い)。多くの州では、収監者はマットレス代や食費のほか、医療費の自己負担分、電子メールや電話代、配給品などのサービス料を日割りで請求される。

南部全域の収監労働者の時給は平均20セント以下 州および地域別、ならびに全米における収監労働者への平均最高時給
(出所)リンクはこちら
ほかにも、南部の州は、囚人から労働力を引き出すためにさまざまな偽装を行っているという話もある。収監労働者の約2%は、「作業解放プログラム」や「返還センター」を通じて雇用されているのだが、このプログラムでは、施設外で公共部門や民間部門の雇用主から低賃金の仕事を請け負う代わりに、より警備の甘い収監施設に送られる。このような労働は全国の刑務所の労働に占める割合はわずかだが、アラバマ州ではこの慣行に大きく依存している。過去5年間だけでも、大手ファーストフードフランチャイズ、ホテルチェーン、自動車サプライヤーなど500以上の企業が収監労働者を雇用し、彼らの給与から差し引かれた賃金は、2000年以降、州に2億5000万ドル以上をもたらしたという。つまり、「現代奴隷制」の受益者に州がなっている。
さらに、論文のつぎの記述は、「ほんとうの米国」を語っている。少しでも多くの日本人に読んでほしい内容になっている。
「全国の刑務所労働に占める農業雇用の割合はわずか2.2%だが、南部の州では、刑務所労働を農業に活用する割合が高く、アーカンソー州では17%が農業に従事している。アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、テキサス州では、1万人以上の収監労働者(そのほとんどが黒人)が、罰則付きのプランテーションや刑務所農場で、150年前に奴隷にされた人々が働いたのと同じ土地で、同じ作物の一部を栽培し、農業労働に従事している。このうち五つの州では、収容労働者はこの労働に対して全く賃金を支払われておらず、毎年数百万ドルの収入を州にもたらしている。」
もちろん、「人間の安全保障」を無視した囚人労働という現代奴隷制を廃止しようという動きもある。先に紹介した2024年6月19日付のNYTによると、2016年以降、コロラド州、ユタ州、ネブラスカ州、バーモント州、オレゴン州、テネシー州、アラバマ州の7州で、強制的な刑務所労働すら例外としない奴隷制の全面禁止を定めた修正条項の可決に成功した。現在(2024年6月)、最大20州と連邦レベルで修正条項の提案が進められており、連邦議会では2020年に共同法案が提出され、それ以降毎回の会期で審議されている。これらの措置は強制労働を違法化するのみであり、刑務所労働に現行賃金の支払いを義務づけるものではない。そのためコロラド州やアラバマ州などでは、収監者が賃上げを求めて訴訟を起こす事態が生じている。ニューヨーク州では、最低賃金と団結権を保障する追加法案の制定を求める活動が行われている。
「ほんとうの米国」と神
忘れてほしくないのは、米国のキリスト教神学の罪深さである。2018年2月にTimeが公開した「不道徳にもかかわらず福音派がトランプ大統領を支持する理由」という興味深い記事がある。記事は、「白人福音派の80%がトランプ大統領に投票し、そして大多数がトランプ大統領を支持し続けている」と書いたうえで、トランプ信奉者は、「神が不完全な人間の代理人を通してアメリカを再び偉大な国にしていると信じている」と指摘している。
こうした人々が実は、奴隷所有者の宗教信者である点が重要だ。つぎの記述は肝要である。
「19世紀、アメリカで黒人と白人が奴隷制廃止の道徳的運動を起こしたとき、プランテーション所有者たちは牧師たちに報酬を払い、白人至上主義を神学的に擁護する文章を書かせた。奴隷所有者の宗教にとって、人間の束縛は単に許容されるものではなかった。それは神の設計を反映したものであり――いかなる犠牲を払っても守られるべき社会の正義の秩序であった。」
つまり、白人と黒人という人種差別を当然視し、それが「神の設計」(God’s design)つまり「神の摂理」(God’s providence)と信じて疑わないのである。だからこそ、いまでも、少なくとも南部では、いわば厳然と現代奴隷制が存在している。それが、米国の現実であることを読者は知るべきだろう。「人間の安全保障」にまったく目を向けない、恐るべき人種差別国家アメリカという側面に気づいてほしい。その背後には、恐るべきキリスト教神学がいまでも息づいている。
キリスト教神学の咎
奴隷制は消えた。しかし、現代奴隷制として囚人への強制労働は残存したように、この特異な米国の信仰は消えていない。
もちろん、他方には、奴隷制廃止の闘いにおいて人々がすべてを賭けて戦った信仰もある。そうしたキリスト教信仰も米国の歴史のなかで世代から世代へと受け継がれてきた。この信仰は、国外追放に直面している移民の隣人に聖域を提供する教会や、ウィリアム・J・バーバー二世牧師が率いる道徳運動のなかにある。
このような見方を示したうえで、Timeの記事は、「奴隷所有者の宗教が21世紀の今もなお存在するならば、この別の伝統の道徳的力もまた我々と共にある」と指摘する。そのうえで、「両者を区別することは、信仰をもつ者たちが選択を迫られている」ことだとする。そして、最後に、「我々の歴史は、信仰をもつ者たちがより良い道を主張するために身を挺する覚悟がなければ、奴隷所有者の宗教が支配的になることを明らかにしている」、と記事は締めくくっている。
わかってほしいのは、キリスト教神学の咎である。キリスト教という信仰自体について、とやかくいう意図も資格もないが、キリスト教神学という、教会のつくり出した統治のための言説に惑わされてはならないのだ。だからこそ、私は拙著『復讐としてのウクライナ戦争』において、この問題について徹底的に考察したのであった。
残念ながら、こんなキリスト教神学に騙されている人々がいまの世界を支配している。その結果として、「人間の安全保障」が軽視され、「国家の安全保障」が優先されているとも言える。この大いなる宗教問題にも関心をもたなければ、世界全体の統治をめぐる地政学・地経学をより現実的な学問に引き上げることはできないだろう。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)