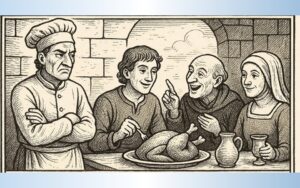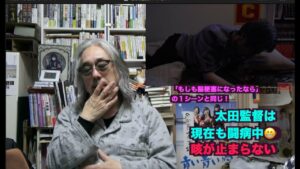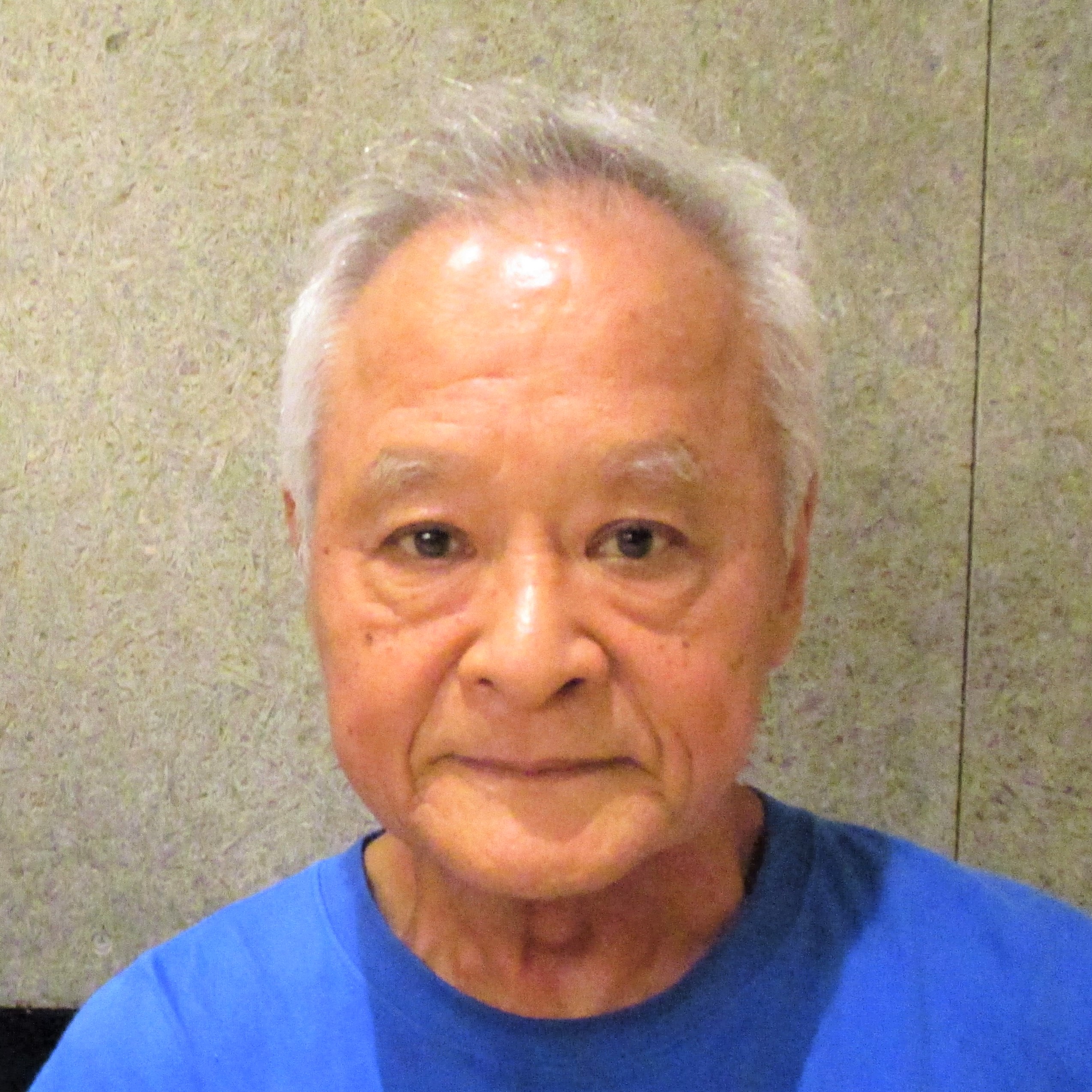登校拒否新聞26号:ロング・コロナ
社会・経済「見えない病に取り残される10代たち ロング・コロナが変えた「ポスト・パンデミック世代」」という記事が『Rolling Stone』誌に載った。記者はイーライ・ケイハン。10月18日付。日本語版の翻訳記事である。
CDCによれば、ロング・コロナは「感染後3カ月以上続く慢性的な症状」と定義される。疲労、集中力の欠如、睡眠障害など、症状は多岐にわたる。推計では、アメリカの成人2,200万人が一度はこの症状を経験し、そのうち900万人が今も苦しんでいる。子どもも例外ではなく、小児科学会の研究では最大600万人が影響を受けたとされる。だが、診断までの道のりは険しい。感染当時に検査を受けていなかった子が多く、医師に「気のせい」「思春期の不調」と片付けられるケースも後を絶たない。・・・病そのもの以上に、彼らを苦しめているのが教育制度だ。体調不良で欠席が続けば、たちまち「怠け」「不登校」とみなされる。支援を受けるための制度――504プランやIEP(特別支援教育計画)――はあるが、学校側がロング・コロナを正式な障害と認めないことが多い。・・・一方で、学校には出席率を維持しないと予算が減るという事情がある。そのため、欠席を繰り返す生徒への対応が“懲罰的”になる傾向が強い。ミズーリ州では、出席率が低い親が刑事罰を受ける可能性がある。インディアナ州では、欠席を「無断」と判断すれば家族が調査対象となる。診断書の提出を毎回求める学校もあり、慢性的な体調不良を抱える子どもほど不利になる。・・・教育省のデータでは、特別支援を必要とする生徒の数はパンデミック後に急増しているが、実際に適切なサポートを受けている子どもはごく一部だ。特別支援を監督する連邦機関も縮小され、監査や救済の仕組みは機能していない。こうした現場の混乱を支えるべき連邦政策も、いま大きく後退している。第2次トランプ政権のもとで、NIHによるロング・コロナ研究「RECOVER」の約20億ドルの予算は打ち切られ、HHS(保健福祉省)のロング・コロナ研究室も閉鎖。ワクチン研究センターも縮小され、教育省の民権局は人員削減により未処理案件を抱えたままだ。「数百万人のロング・コロナ患者がいるのに、連邦政府は背を向けている」と上院議員ティム・ケインは批判する。医療も教育も、支援の網がほどけていくなかで、病気を抱える家庭はますます孤立している。・・・この記事が描くのは、単なる医療の問題ではない。それは、社会が「もう終わったこと」として切り捨てた病と、そこに取り残された子どもたちの物語だ。ロング・コロナという言葉は、もはや一時的な診断名ではない。教育、医療、政策――すべてのレベルで支援を失い、孤立した若者たちをどう支えるか。
https://rollingstonejapan.com/articles/detail/43771/1/1/1
記事には「ポスト・パンデミック世代」の実例として、女の子と男の子の例が出ているが省いた。というのも感染症が長引いているのか、ワクチンの薬害、あるいはマスクや自宅待機などによる体調不良なのか、そのあたりの事情が不明なので。
体調不良で欠席が続けば、たちまち「怠け」「不登校」とみなされる――という一文は日本の状況と同じだ。文中に「気のせい」「思春期の不調」とある。前者は気の病として、後者は起立性調節障害と日本では診断されるかもしれない。このあたりの事情はアメリカと日本とでは異なる。「怠け」「不登校」の定義も異なるので注意したい。
英語の元記事は有料なので一部しか見ることができなかった。しかし、かなりの抄訳であることはわかった。音楽雑誌とはいえ記事の質は高い。「怠け」「不登校」の原語はそれぞれtruancyとabsenceのようだ。「不登校」の原語はschool non-attendanceだと思っている識者は多い。それも間違いではない。訳語として「不登校」という用語が考案されたことは事実である。ただ、用語を概念として見た場合、その意味は訳語という観点からは説明がつかない。
日本の長期欠席の理由別分類に「怠け」「怠学」はないが、アメリカには昔からtruancyという概念がある。日本ではこの「怠け」「怠学」と区別したところに「神経症的登校拒否」「心因性登校拒否」を概念化したところに特徴がある。というのも、truancyという概念が日本ではしっくりこないのである。これは本人の怠けというよりも親の就学拒否のようなニュアンスが強い。つまり、親の養育放棄のような意味合いであるから、昔の文部省が認めていた「学校ぎらい」という欠席理由とは異なっている。ということで、truancyではない。しかし「病気」でもないというところに形成されたのが日本の「不登校」という特殊な概念である。この辺の事情は拙著『不登校とは何であったか?―心因性登校拒否、その社会病理化の論理―』(2017年)を参照してほしい。
その「病気」ではない「不登校」という特殊な概念が現実にそぐわないという点は登校拒否新聞としても何度か指摘してきた。文部科学省の学校基本調査では年間30日以上の長期欠席の理由別分類として「病気」「不登校」「経済的理由」「その他」と認めている。今、問題を「病気」と「不登校」に絞れば、長期欠席者の総数が増えたという統計からして「不登校」が増えたとメディアや専門家が騒ぐのが日常である。私はそれに異を唱えている。この記事にあるように「病気」が増えているのである。それを「不登校」が増えたとすり替えて、学校になじめない子が増えている。畢竟して、多様な学びが求められていると政治的な主張をする人たちが多い。教育論としては理解できるけれども実態として、学校が合わなくなっている子どもが増えているのか、それとも健康を害している子どもが増えているのか、という点は慎重に見定めたいところである。仮に後者だとしよう。この場合はロング・コロナということで何が問題かと言うと診断である。ロング・コロナという診断が認められるか、ということだ。
診断書がなければ病欠として認められないというのは仕事の上では通例だ。教員が休職する際にも鬱病という診断書をもらっている。言うならば、子どもにも鬱病があるのだから「心理的理由」による欠席があると認めたのが「神経症的登校拒否」「心因性登校拒否」の本来の意味である。それを「病気」にあらずと、むしろ学校の問題とひっくり返したところに成立したのが「不登校」である。であるから「不登校」という概念には「病気」ではないという含意がある。その含みが、現状とミスマッチしているのではないか、と私は考えている。もちろん学校に行かないこと自体は病気ではない。けれども、記事のタイトルにあるように「見えない病」があるとしたらどうだろう?
10月以来、小学校、中学校、高校を合わせて、1,015校で学級閉鎖、学年閉鎖、そして学校閉鎖――休校の措置が取られたという。表向きにはインフルエンザと報じられている。なぜ、そんなにもインフルエンザに罹患するのか?
インフルエンザのウイルスが猛威を振るっているからか?
それとも子どもたちの免疫力が落ちたからか?
旧ツイッターでは「学級閉鎖」が話題となった。その中に栄養教諭のツイートを見つけた。――あしたの抜け殻@kyushoku9449 35人中19人休み。学級閉鎖決定…と誰もが思うのに、教育委員会の担当者「何℃?症状は?」としつこく聞き、決定してくれない。挙げ句に「こんなに休んでたら閉鎖しても意味ないんじゃない?」と。変更締切の時間過ぎてしまい、業者に平謝りして、明日のごはんをキャンセル。#学級閉鎖 #栄養教諭
https://x.com/kyushoku9449/status/1985636789277913492
こうなってくると「不登校」どころではない。半分が流行感冒で休んでいる。「学校外の学びの場」ことフリースクールだって閉鎖になるだろう。
「つくられたパンデミック」の影響は直接には超過死亡として顕在化しているが、潜在的にはロング・コロナ――「見えない病」として尾を引いている。インフルエンザという診断は見える。学級閉鎖の指令を出すのは教育委員会であるから「何℃?症状は?」と聞いて来る。けれども「見えない病」が子どもたちをむしばんでいるとしたら?
こんな状況が長く続けば義務教育制が維持できない。喜ぶ人もいるだろう。しかし、塾に通う子と通わない子との学力差――「通塾格差」(尾木直樹)は広がる。学校が休みになったからといって学校化された社会が休みになるわけではない。
きっとワクチン接種、マスク着用、手洗い、「黙食」が徹底されていないから感染症が増えているのだ。そんな学校なら登校拒否でもしたくなる。ところが教育委員会が先手を打って休校にする。岸政権の頃、教職員組合のストに合わせて教育委員会が一斉休校でもって応じたことを思い出した。一斉に有給休暇を取るという戦略に対して、当日は休校にしてしまうという逆手である。
国民学校期の少国民たちは朝早く起きて井戸水で乾布摩擦をした。教職員組合の左派の頭領だった平垣美代司の本『日教組とわが戦い』(暁書房、1982年)の扉にそんな写真が掲載されている。今、そんなことを言えば極右だと思われるかもしれないが案外にそれが正解なのではないかと私は思い始めている。というのも水シャワーを始めてから風邪をひかなくなった。ちなみに、私は毎日、お寺に通う習慣があり、雑巾で下駄箱の掃除をしたりトイレ掃除をしている。そのお寺に入ってくる人が手を消毒すると、その臭いが鼻につく。こっちは素手で靴箱の掃除をしているのに入ってくるほうは手を消毒して靴を脱ぐ。
鉄筋コンクリートの建物は体が冷える。木造校舎のほうが良かったのだ。禅寺のように床を雑巾がけしていれば良かったのだ。それがワクチン接種、マスク着用、手洗い、「黙食」――病的なまでに免疫力を落とす教育がなされている。こうなるともう文明の病である。それが「見えない病」というものか。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。