
東アジア情勢と日本の対応(前)
国際東アジアで、次の時代を予想させる変化が始まっている。
ここでは、第二次世界大戦後、米国が圧倒的な影響力を行使してきたが、近年は中国が急速な経済発展を背景に国際政治における発言力を強めている。

Double exposure of China flag on coins stacking and stock market graph chart .It is symbol of china high growth economy and technology.
中国は、軍事的にも米国に対抗する勢力になり、台湾海峡などの紛争が懸念されている。中国の動向と、その米国との関係は、地域の情勢に大きな影響を与えずにはおかない。
これに対して日本は、米国との軍事同盟を強化し、世界最大の米軍海外基地をおいている。米軍はここから地球的規模で海外の紛争に出撃している。
国連憲章に示される国際規範を破った大国の戦争は、これまでも米国のベトナム戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争、ロシアのアフガン侵略など数々あるが、いま世界中の人々の眼前で行われているウクライナ戦争は、21世紀の大国によるあからさまな侵略戦争という点で、戦争の歴史に新たなページを開くものとなっている。
そうした中で東南アジアでは、ASEAN(東南アジア諸国連合)に示されるように、世界の平和と安定に影響する新しい動きが成長している。
日本が東アジアで周辺の諸国と平和的な関係を築き上げることは、日本と世界の平和・安全にとって欠くことができないが、大きく変容する東アジア情勢の中で、日本はどうするのか。
Ⅰ 東アジア情勢を左右する米中の外交的火花
〇バイデン・習近平会談が示したもの

Stencil graffiti representing the agreement of two countries (USA – CHINA). Photographer’s own design.
まず、東アジアの情勢に大きな影響をあたえる米中の関係を見よう。中国の習近平国家主席と米国のバイデン大統領は2022年7月28日、電話会談を行った。バイデン大統領が昨年1月に大統領に就任して以来5回目の会談である。
翌日の中国各紙はこの会談を大きくとりあげた。有力紙「文匯報」は、バイデン大統領が「米中協力が両国民とともに、世界の諸国民の利益になる」と述べたと報じた。人民日報社発行の英文紙「グローバル・タイムズ」は、「電話会談は米中両国が悲劇しかもたらさない競争者(competitor)とする見方を否定した」として、米中双方が互いに協力しあえることを強調した。
一方、米国の有力紙「ワシントン・ポスト」は同日、米中関係をインド太平洋地域で最も重要な2国間関係としたカービー国防総省報道官の発言を引用して、バイデン大統領があらゆる問題について習近平国家主席と連絡をとりあうことを希望すると述べたことを報じた。
首脳会談では、緊迫する台湾海峡問題が中心的に議論されたが、それについては次の項で詳述する。両国首脳が互いに譲れない問題を抱えながらも、両国関係が双方の利益になると確認したところに、今の米中関係の特徴がある。
バイデン政権は22年2月11日、「インド太平洋戦略」を公表し、その中で中国について「経済、外交、軍事、技術の力を合わせ、インド太平洋地域での勢力圏拡大、世界で最も影響力のある国家になることをめざしている」と述べた。中国に対するこのような警戒感はクアッド外相会議の共同声明でも表明された。
クアッド(Quad)は、日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国が参加する準軍事同盟的組織である。米国がインド洋からアジア太平洋にまたがる国々を組織するクアッドを、米大統領府の文書で記述するほど重視するのはなぜか。
〇軍事的手段で中国に対抗
その理由は、続いて米国防総省が3月28日に米議会に提出した「国家防衛戦略」(NDS)を見るとわかりやすい。そこには、国防の最優先事項として、「多くの領域で増大する中国の脅威に対応し、国土を防衛すること」と書かれている。
米国の安全のためには、太平洋から東アジアを経てインド洋にいたる広大な地域で中国に対抗する必要がある、というのである。バイデン政権は、発足後最初に出した同報告で早くも、最重視する相手は中国であることを明確にしていたわけである。
報告はその理由を「中国は国際システムとその中での我々の利益に挑戦する軍事・経済・技術的な潜在力をもっている」と言う。
米国など西側軍事同盟諸国が中国の発展を脅威と見ていることは間違いないが、それと対抗するために、科学技術の発展など平和的手段によるよりも、軍事同盟や軍事力など戦争態勢の強化をはかるのである。
今年3月に行われた前回のバイデン大統領と習近平国家主席のテレビ会談では、前月末から始まったロシアのウクライナ侵攻が議論の中心になった。バイデン大統領は「もし中国がロシアを経済的軍事的に支援するなら、重大な結果をもたらす」と警告した。
この点では習近平国家主席は巧妙、狡猾である。中国は当初は「中立」と言って、ロシアの侵略を支持も支援もしていない。
けれども国連人権理事会では、ウクライナにおけるロシア軍の非人道的行為を議題にすることに反対し、当局の管理下にある国内メディアはロシアの侵略と言わない。ウクライナ戦争における残虐行為を報じても、それをロシア軍がやったと書かない。習近平政権がプーチン政権の侵略を是認し、事実上支持しているからである。
〇一連の外交トップレベル会談では
それでは、いったい中国は米国に敵対しているのか。
米中間では、外交当局による対話がかなり頻繁に行われている。最近も、インドネシアのバリ島で開催されたG20(20カ国・地域)外相会議で、王毅中国外相とブリンケン米国務長官が会談した。米中外交当局者の会談は、21年のアンカレッジ、ローマで、22年6月のルクセンブルクで、楊潔箎国務委員とブリンケン国務長官による会談があった。
「グローバル・タイムズ」3月14日付は、ローマでの楊潔箎・ブリンケン会談について「ウクライナ危機の中で前向きのサイン」として、米中双方が「競争を前向きに処理すること」を議論したと報じた。また中国日報社発行「チャイナ・デイリー」7月11日付によれば、バリ島での王毅外相とスリバン国務委員の会談では、中国側が「実用主義的、先見性、最大の率直さ」を表明したという。
一連の会談からは、中国側が米国に対して、米中関係の改善にむけて積極的に行動したことが読み取れる、日本では、米中関係がきわめて険悪でいまにも戦争するかのように報じられているが、かなり様子が違うようである。
〇利潤追求経済と「同船共済」「継承共進」
実は、今世紀にはいってからも、米中両国は極めて緊密な関係を続けていたのであり、台湾海峡の紛争は長期にわたり情勢の後景に退いていた。
現在の米中関係の緊張には、中国の経済的軍事的発展に対する米国の対応が大きく作用していることは間違いない。かつて中国が発展しつつあった時には米中関係が順調に進んでいたのであり、そのことは今の米中関係を考えるうえでも重要である。
中国は、1960年代から70年代にかけての毛沢東の専横により経済が破綻した後、78年に市場経済を導入し、90年代には新自由主義経済学のメッカといわれていたシカゴに多くの経済学者を派遣して、国家が管理する国有企業最優先の経済から、企業による利潤追求を生産の推進力とする経済に大きく舵を切り替えた。これがその後の中国経済の転換と発展につながったのである。
今世紀に入ってオバマ政権、胡錦濤政権の時代には、米中関係は大きく進展した。2009年2月にはクリントン国務長官が訪中して、米中関係を「同船共催」(同じ船に乗って助け合う)と言い、温家宝首相は「携手共進」(手を携え共に進む)と応えたものである。

Philadelphia, PA, USA – October 22, 2016: Democratic presidential candidate Hillary Clinton and running mate Sen. Tim Kaine campaign together at a rally in Philadelphia, PA
米中の軍事交流も発展した。11~12年には米国の国防長官と中国の国防相が、双方の核兵器部隊を相互に訪問するほどになった。
米中関係が暗転したのは、米国で17年1月にトランプ政権が発足して1年ほどたってからである。トランプ政権は中国に対する敵愾心(てきがいしん)をあおることにより、共和党政権の支持基盤の強化をはかったのである。
現在、中国で習近平政権による独裁が強まり、米国民の対中国感情が悪化するなか、バイデン政権もアジア太平洋における対中国シフトを強めており、それが今日の東アジア情勢に反映している。
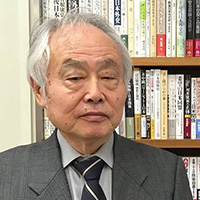 末浪靖司
末浪靖司
1939年 京都市生まれ。大阪外国語大学(現・大阪大学)卒業。著書:「対米従属の正体」「機密解禁文書にみる日米同盟」(以上、高文研)、「日米指揮権密約の研究」(創元社)など。共著:「検証・法治国家崩壊」(創元社)。米国立公文書館、ルーズベルト図書館、国家安全保障公文書館で日米関係を研究。現在、日本平和学会会員、日本平和委員会常任理事、非核の政府を求める会専門委員。日本中国友好協会参与。


























































































































































































