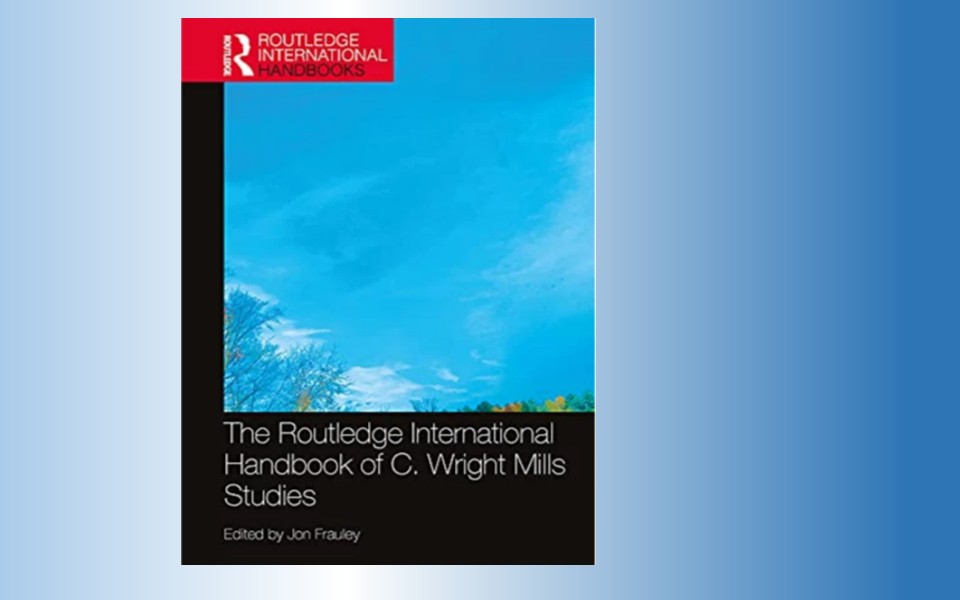
パンデミックで露呈した大衆操作の歴史:伝説の社会学者C・ライト・ミルズが暴いた「パワー・エリート」と「大衆社会」の共犯関係
国際政治「反連邦主義者たちが恐れたのは、新共和国において政治的自由が失われることだった。なぜなら『少数者は決して眠らず、多数者は真に目覚めることが稀だからだ』」
「権力は裸で表示されない限り、権力ではないと信じ込まされている」
はじめに
あなたは政治に無力感を抱いたことがあるだろうか?投票しても何も変わらない。デモをしても政策は動かない。SNSで声を上げても、結局は大きな流れに飲み込まれていく。そんな感覚を抱いたことがある人は少なくないはずだ。
「自分の声など届かない」──この感覚は、あなた個人の無能力さから生まれたものではない。それは構造的に作り出されたものだ。
過去にも、民主主義の機能不全を多角的に分析してきた。クリストフ・ビュファン・ド・ショザルの『民主主義の終焉』は、選挙システムそのものが「組織化された少数者による多数者支配」の装置でしかないことを暴露した。投票しても権力構造は変わらない。なぜなら、有権者が「選択」できるのは、エリート層によって事前選別された候補者の中からに過ぎないからだ。
https://note.com/alzhacker/n/n18e7899cd774
さらにニーマ・パルヴィニの『ポピュリストの妄想』は、モスカ、パレート、ミヒェルスらのエリート理論を駆使し、「組織化された少数者が組織化されていない多数者を支配する」構造的必然性を明らかにした。歴史上、民衆が真の権力を握った事例は一度も存在しない。2016年以降の「ポピュリズム」も、実際には既存エリート内部の権力闘争に過ぎなかった。
https://note.com/alzhacker/n/n8d92f9b2873e
こうした選挙制度の欺瞞、そして権力の寡頭制的本質を踏まえたとき、1956年に社会学者C・ライト・ミルズが『パワー・エリート』で描いた洞察は、さらに別の角度から民主主義の空洞化を浮き彫りにする。ミルズが着目したのは、権力構造の頂点ではなく「底辺」だった。彼は、アメリカ社会が「能動的な公衆の社会」から「受動的な大衆社会」へと変容していく過程を描き、こう予言した──この変容こそが、エリート支配を可能にする土壌となる、と。
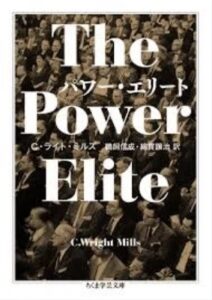
つまり、選挙制度が最初から欺瞞であり、真の主権者など構造的に存在し得ないという現実に加えて、市民自身が批判的思考を失い、政治的主体性を放棄していく過程が並行して進んでいる。両者は相互に強化し合う。選挙が機能しないことへの諦めが市民の無力感を生み、無力感が批判的思考を奪い、思考を失った市民はさらに操作されやすくなる。
パンデミックを経験した私たちは、これらすべての予言が驚くほど現実のものとなっていることを目の当たりにした。政府の発表を疑問なく受け入れる人々、専門家の権威に盲従する社会、異論を「陰謀論」として排除するメディア。ワクチン接種を巡る議論は、まさにミルズが描いた「大衆社会」の縮図であり、同時にショザルが指摘した「選挙以外の選択肢が封じられた社会」の姿であり、パルヴィニが分析した「ボトムアップ変革の不可能性」の証明でもあった。
批判的思考を失った市民は、自らの状況を理解できない。理解できなければ、変革の意志も生まれない。そして行動がなければ、構造は温存される。
この論文を読むことで、私たちが直面している政治的無力感の正体が多層的に見えてくる。それは半世紀以上にわたって洗練されてきた「支配の技法の帰結」なのだ。選挙という儀式、エリートによる寡頭支配、そして市民の大衆化──これらは独立した現象ではなく、一つの統合されたシステムとして機能している。
書籍・著者紹介
本記事が分析するのは、ジェームズ・E・フリーマン(James E. Freeman)による論文「Another Side of C. Wright Mills: The Theory of Mass Society」である。この論文は、C・ライト・ミルズの1956年の古典的著作『パワー・エリート』を再検討し、従来見過ごされてきた「大衆社会論」に焦点を当てる。
ミルズ自身は1916年生まれのアメリカの社会学者で、コロンビア大学で教鞭を執った。『ホワイトカラー』(1951年)、『パワー・エリート』(1956年)、『社会学的想像力』(1959年)という三部作で知られ、アメリカ社会の権力構造を鋭く批判した。彼の著作は、マルクス主義とウェーバー主義を統合し、フランクフルト学派の批判理論とも共鳴する独自の社会分析を展開している。

フリーマンの論文は、2009年のミルズ没後50周年記念の機運の中で書かれたものだが、その分析は現代においてこそ重要性を増している。トランプ現象、企業の不正行為の横行、軍産複合体の拡大、陰謀論の蔓延──これらはすべて、ミルズが半世紀前に予見した「大衆社会」の症状なのだ。
見過ごされてきた「もう一つのミルズ」
「変化の本質は、公衆が大衆へと変容することにある。そしてこの変容こそが、パワー・エリートの意味を理解する重要な手がかりを提供する」
従来、『パワー・エリート』は「支配階級論」として読まれてきた。軍・企業・政治の三位一体が権力を独占しているという主張だ。しかしフリーマンは、この解釈がミルズの核心を見誤っていると指摘する。
ミルズの真の洞察は、権力構造の頂点ではなく「底辺」にあった。パワー・エリートの存在は、原因ではなく結果なのだ。社会が「能動的な公衆の社会」から「受動的な大衆社会」へと移行したことで生まれた真空状態を、エリートたちが埋めているに過ぎない。
ミルズは書いている──「パワー・エリートの台頭は、アメリカにおける公衆の大衆社会への変容の上に成り立ち、その一部でもある」。つまり、市民が政治的主体性を失ったからこそ、エリートによる支配が可能になったのだ。
この視点は、民主主義理論に根本的な問いを投げかける。もし市民が真の公衆として機能していたら、パワー・エリートは存在し得たのか?
そして、あえて、私はこう問い直したい。もし市民が真の公衆として機能していたら、コロナパンデミックは起こらなかったのか?遺伝子ワクチンによる空前の薬害は防げたのか?
多くの政治学者や社会学者は、この問いから目を背けてきた。なぜなら、それは「多元主義」という民主主義理論の根幹を揺るがすからだ。アメリカ社会は多様な利益集団が競合し、バランスを保っている──この「神話」を維持することが、学術界にとって都合が良かった。
しかしミルズは容赦なく指摘する。多元主義は「ロマンティック多元主義」に過ぎない。18世紀の民主主義理念を、現代社会にそのまま投影したイデオロギー的幻想なのだ。
「公衆の死」──四つの構造的変化
「個人は自分の狭い領域に閉じ込められ、切り離され、社会の構造とプロセスを理解することから疎外されている」
ミルズは、公衆が大衆へと変容する過程を、四つの構造的変化として分析している。
多元主義の空洞化
民主主義理論は、多様な利益集団が議会で競合し、公共の利益が形成されると想定する。しかし現実には、多元主義はエリート内部でのみ機能している。
議会で繰り広げられる「政治」は、移民問題、中絶、銃規制といった「中間レベルの権力」を巡る争いに過ぎない。これらの問題は、市民の関心を引きつけるが、本質的な権力構造には触れない。
なぜ軍事予算が国内総生産の相当部分を占めるのか?なぜ企業の利益が政策決定の中心にあるのか?なぜ金融資本の論理が社会全体を規定するのか?──こうした「大きな問い」は、議論の対象にすらならない。
メディアは、この茶番劇を「民主主義の健全な対立」として報道する。市民は、些末な争点を巡る政治家の罵り合いを見せられ、「政治は混乱している」と感じる。そして冷笑主義と無関心が広がる。
実際には、重要な決定はすべて「エリート内部の合意」によって行われている。議会は、その決定を正当化するための舞台装置に過ぎない。
メディアによる情報の一極集中
18世紀の民主主義理論は、小規模な独立した意見生産者が多数存在し、それらが「アイデアの市場」を形成することを前提としていた。しかし現代の大衆社会では、情報は中央集権的に管理されている。
少数の巨大メディア企業が、何が「ニュース」であるかを決定する。彼らが取り上げない問題は、存在しないも同然だ。これを政治学者ピーター・バクラック(Peter Bachrach)とモートン・バラッツ(Morton Baratz)は「アジェンダ設定(agenda setting)」と呼んだ。
しかしミルズの分析はさらに深い。メディアは単に議題を設定するだけでなく、「人々の思考様式」そのものを規定している。
コミュニケーション理論家ニール・ポストマン(Neil Postman)は『娯楽として死ぬ』の中で指摘している──私たちの政治的リテラシーの多くはメディアから得られるため、テレビで見る世界を、実際に歩く世界よりも真実だと信じてしまう。
パンデミック期間中、私たちはこの現象を目の当たりにした。「専門家」として登場する人物の発言は疑われず、異なる見解は「誤情報」として削除された。ソーシャルメディアは、表面的には多様な意見を許容しているように見えるが、実際にはアルゴリズムと検閲によって情報空間が管理されている。
ミルズが警告したのは、まさにこの事態だった──メディアが人々を合理的洞察から切り離し、政治的・社会的現実を理解する機会を奪う。
合理的討議の消失
大衆社会では、意見形成は「一方向的」になる。少数の情報発信者が、大多数の受動的な受信者に向けて発信する。フィードバックはなく、対話も存在しない。
ミルズが理想とする「公衆の社会」では、コミュニケーションは「双方向的」である。人々は顔を合わせて議論し、異なる視点をぶつけ合い、合意を形成する。しかし現代では、こうした討議の場が失われている。
政治的コミュニティは、もはや人々によって定義されない。メディアがパッケージ化した「コミュニティの利益」が、あたかも人々の総意であるかのように提示される。
SNSは一見、双方向的なコミュニケーションを可能にしているように見える。しかし実際には、アルゴリズムによって同質的な意見が増幅され、異なる視点は排除される。「いいね」の数が真実性の指標となり、人気が正しさと同一視される。
ミルズは、このような状況を「大衆の群衆化」と呼んだ。人々は孤立した個人としてではなく、「扇動によって動員される群衆」として機能する。
政治的無力感の構造化
大衆社会の最も深刻な特徴は、市民が政治的無力感を内面化していることだ。
ミルズは、この状況をデュルケームの「アノミー」やハーバーマスの「正統性の危機」に類似したものとして分析する。人々は自分たちが生きる社会の真実から隔離され、公的な主体としての自信を失い、無意味感に苛まれる。
政治参加には見返りがない。投票しても何も変わらない。デモをしても無視される。だから、人々は政治から撤退する。
この無力感は、時として攻撃性に転化する。キャンセルカルチャーはその一例だ。SNS内での罵倒、罵り合いもそうかもしれない。本質的な権力構造に挑戦できない人々が、手の届く範囲で「敵」を探し、攻撃する。しかしこの攻撃は、決して、意思決定エリートには向かわない。
ミルズは指摘する──「個人は自分の狭い領域に閉じ込められ、切り離され、社会の構造とプロセスを理解することから疎外されている」。
この無力感こそが、パワー・エリートの存在を可能にしている。市民が政治的主体性を失ったからこそ、エリートは自由に行動できるのだ。
「ロマンティック多元主義」という神話
「バランスの理論は、18世紀の古典的民主主義の織機に過ぎない」
民主主義理論の根幹には、「バランスの理論」がある。多様な利益集団が競合し、相互に牽制し合うことで、権力の集中が防がれる──これがアメリカ政治学の基本的な前提だ。
しかしミルズは、この理論を「ロマンティック多元主義」として批判する。それは18世紀の理想を現代に投影した「幻想」に過ぎない。
実際の権力構造は、理論が想定するようなバランスではない。軍・企業・政治のエリートは、互いに緊密に結びついている。彼らは同じ大学を卒業し、同じクラブに所属し、同じ価値観を共有している。彼らの間には対立があるかもしれないが、それは「戦術的な相違」であって、根本的な利害の対立ではない。

政治学者の多くは、この現実を直視しない。なぜなら、それは自分たちの学問的前提を揺るがすからだ。代わりに彼らは、選挙行動や利益団体の研究に没頭する。
ミルズは、この学問的実践を痛烈に批判する。実証主義的手法への偏重は、権力の本質的な構造分析を放棄することを意味する。政治学者は「観察可能な政治行動」を研究することで、表面的な現象を記述するだけに終わっている。
「バランスの理論」は、単なる記述的な誤りではない。それは「イデオロギー的な機能」を果たしている。この理論を信じることで、人々は現状を正当化し、変革の必要性を感じなくなる。
ミルズが主張するのは、社会科学が批判的な役割を取り戻すべきだということだ。社会科学は、権力構造を正当化するのではなく、それを暴露し、変革の可能性を示すべきなのだ。
エリートと大衆の非対称性
「パワー・エリートは、民主的公衆社会の基本条件をすでに独占的に満たしている」
フリーマンの論文が提示する最も皮肉な洞察は、パワー・エリート自身が「公衆社会」の条件を満たしているという事実だ。
ミルズは、「公衆社会が機能するための四つの条件」を挙げている。
-
合理的討議と意思決定の構造
-
実現可能な政治的責務感
-
実現可能な政治的意志
-
高度な市民参加
皮肉なことに、これらの条件はエリート内部では実現されている。
エリートたちは高度な教育を受け、複雑な問題を分析する能力を持っている。彼らは自分たちの利益を明確に認識し、それを実現するための戦略を立てる。彼らは効果的に組織化され、政策決定に影響を与える手段を持っている。そして彼らの政治参加は、実際に結果をもたらす。
一方、社会の底辺では、これらの条件がすべて欠けている。
一般市民は、合理的討議の訓練を受けていない。教育制度は批判的思考を教えず、メディアは固定観念と常識を強化する。人々は政治的義務を感じるが、それは「実現不可能」に見える。政治的意志は構造的に阻まれ、市民参加には見返りがない。
だから「冷笑主義」と「無関心」が広がる。この現象は、今日のSNS上で顕著に現れているが、それはアルゴリズムによるエコーチェンバー効果の単なる副産物だけではなく、ミルズが半世紀前に予見したような、社会の底辺から生じる構造的な疎外感──公衆が大衆へと変容する歴史的プロセス──の延長線上にあると言えるだろう。
https://note.com/alzhacker/n/nee880d43efb2
この「非対称性」こそが、現代社会の権力構造を維持している。エリートは「公衆」として機能し、大衆は「群衆」として操作される。
ミルズは、この状況を「高度な不道徳(higher immorality)」と呼んだ。それは、明確な悪意や抑圧ではない。むしろ、「思考そのものの不在」である。
エリートたちは、自分たちが不正を働いているとは思っていない。彼らは単に、自分たちの利益を追求しているだけだ。そして大衆は、自分たちが搾取されているとは気づかない。彼らは単に、「政治とはこういうものだ」と思っている。
この「組織化された無責任の体制」では、誰も責任を取らない。政治家は「専門家の助言に従った」と言い、専門家は「データに基づいて判断した」と言い、メディアは「事実を報道した」と言う。
パンデミック期間中、私たちはこの構造を目の当たりにした。ワクチンの安全性に関する疑問は「誤情報」とされ、政策の有効性に関する批判は「科学否定」とされた。そして今、超過死亡が問題になっても、誰も責任を取らない。ここには「戦略的無知」が明らかに用意されていたが、それは彼らの体質であって、パンデミックで突如として始まったわけではない。
https://note.com/alzhacker/n/na7ca4f9258b0
専門家・社会科学の共犯性
「社会科学の主要な任務は、私的な困難を公的な問題に翻訳することである」
ミルズは、「現代の社会科学」が権力構造の正当化に加担していると告発する。
多くの政治学者や社会学者は、実証主義的手法に固執し、「観察可能な行動」の研究に没頭している。彼らは選挙行動、利益団体の活動、世論調査のデータを収集し、それを「民主主義の実証研究」として発表する。
しかしミルズは問う──この種の研究は、何を明らかにしているのか?
選挙行動の研究は、人々がどのように投票するかを教えてくれる。しかしそれは、誰が本当の決定を下しているのかについては何も教えてくれない。利益団体の研究は、中間レベルの権力構造を描写する。しかしそれは、なぜ特定の問題だけが議題になり、他の特定の(かつ重要な)問題は、けして議題にならないのか(アジェンダ設定)については説明しない。
ミルズにとって、社会科学の役割は単なる事実の列挙ではない。それは構造の解明であり、批判的分析である。社会科学は、人々が自分たちの置かれた状況を理解し、変革の可能性を見出すための道具であるべきなのだ。
ミルズは『社会学的想像力』の中で、社会科学が「私的な困難を公的な問題に翻訳する」責務を持つと述べた。個人が経験する失業、不安、孤立といった問題は、個人的な失敗ではなく、社会構造の産物である。社会科学は、この関連性を明らかにすべきなのだ。
しかし現代の社会科学は、この責務を放棄している。代わりに彼らは、現状を記述し、正当化することに満足している。
パンデミック期間中、私たちはこの共犯性を目撃した。多くの社会科学者は、政府の政策を「科学的根拠に基づいている」として擁護した。ロックダウンの社会的・経済的コストを指摘する研究は「非科学的」とされ、ワクチンの安全性に関する疑問は「陰謀論」として片付けられた。
社会科学は、権力を批判するのではなく、権力を擁護する装置となっている。
大衆社会からの脱出は可能か?
「公衆と指導者が応答的で責任を持つ時にのみ、人間の営みは民主的秩序にある」
ウルフ(Robert Paul Wolff)は、ミルズの分析が「出口のない絶望」を提示していると批判する。しかしフリーマンは、この批判がミルズの処方箋を見落としていると指摘する。
ミルズは確かに、大衆社会の構造を厳しく批判した。しかし彼は、変革の可能性を完全に否定したわけではない。むしろ彼は、何が変わらなければならないかを明確に示している。
公衆社会への回帰には、前述した四つの条件が必要だ。「公衆社会が機能するための四つの条件」をより詳しく見ていこう。
-
合理的討議と意思決定の構造
みんながテーブルを囲んで、熱く本音をぶつけ合う場だ。SNSの浅いやり取りではなく、相手の視点をじっくり聞き、論理的に考え抜いて「これでいこう」と合意する議論の場である。まるで家族会議のように、誰もが尊重され、賢い結論が生まれる──そんな本気の「話し合い」が、社会の心臓部になるのだ。 -
実現可能な政治的責務感
「政治に参加しなきゃ」と思う気持ちが、ただの義務ではなく、「これをやったら本当に変わる!」というワクワクする実感に変わるものだ。デモや署名が無駄に終わらないよう、参加した人が「自分の一歩が社会を動かした」と胸を張れる自信を養う。あなたが小さな声でも、大きな波を起こせる──そんな希望が、みんなの原動力になるのだ。 -
実現可能な政治的意志
あなたの「こう変えたい」という強い想いが、壁にぶつからず、ストレートに政策に届く仕組みだ。選挙の「選ぶだけ」では満足せず、アイデアが実際に法やルールに反映される道筋を整える。まるで会社のプロジェクトのように、意志が形になる──これで、政治は「上からの決定」から「みんなの共同作業」へシフトするのだ。 -
高度な市民参加
ただ投票ボタンを押すだけではなく、政策が生まれる「裏側」に飛び込んで、アイデアを混ぜ、形作る深い関わりである。町の未来を決める会議に、あなたの声が欠かせない存在になるのだ。結果、誰もが「自分ごと」として社会を愛し、守りたくなる──これが、真の「参加」の醍醐味だ。

これらの条件は、決して不可能なものではない。実際、エリート内部では既に実現されている。問題は、これを社会全体に拡大することだ。
ミルズが提案するのは、社会科学がこの過程を支援することだ。社会科学は、人々が自分たちの置かれた構造的状況を理解し、変革の可能性を見出すための知識を提供すべきなのだ。
しかし現実には、この道のりは険しい。なぜなら、既存の権力構造がこの変革を阻んでいるからだ。
おわりに: 循環する自己強化システム──脱出不可能性
大衆社会の最も厄介な特徴は、その自己強化的な性質だ。
批判的思考を失った人々は、自分たちが操作されていることに気づかない。気づかなければ、変革の必要性を感じない。必要性を感じなければ、行動しない。行動しなければ、構造は温存される。そして構造が温存されれば、人々はさらに批判的思考を失っていく。
この循環を断ち切るには、どこかで介入しなければならない。しかし、どこから始めればいいのか?
教育改革か?しかし教育制度自体が、批判的思考を抑圧している。メディア改革か?しかしメディア自体が、権力構造の一部だ。政治改革か?しかし政治システム自体が、エリートの利益に奉仕している。
ミルズの分析は、この矛盾を解消しない。彼は処方箋を示したが、その処方箋を実行するための前提条件が、まさに達成すべき目標そのものなのだ。公衆社会を取り戻すには公衆が必要だが、公衆はすでに大衆へと変容している。
この矛盾は、革命理論が常に直面してきたジレンマでもある。抑圧された人々が解放されるには意識の覚醒が必要だが、抑圧構造そのものが意識の覚醒を妨げている。マルクスは「階級意識」の形成を説いたが、資本主義はイデオロギー装置を通じて階級意識を抑圧する。
パンデミックは、この矛盾を鮮明に浮き彫りにした。政府とメディアの言説に疑問を持った人々は「陰謀論者」として排除され、ワクチンの危険性を指摘する声は「誤情報」として削除された。批判的思考を持つ人々は、まさにその批判的思考ゆえに、周縁化された。
では、この循環から抜け出す道はないのか?それとも、大衆社会は不可避的な帰結なのか?ミルズはこの問いに明確な答えを与えていない。そして、私たちもまだ答えを見つけていない。
論文が暗に示唆するのは、構造的変革には構造の外部からの介入が必要だということだ。
しかし大衆社会においては、その「外部」がどこにも存在しない。全員が構造の内部に取り込まれ、その論理を内面化している。
ミルズが『パワー・エリート』を書いたのは1956年だった。それから約70年が経過した。ミルズが描いた大衆社会への移行は、完了したのか、それとも進行中なのか?
素直に見れば、「自己強化のサイクル」は続いているというよりも、むしろ「加速化」している—メディアの集中化は進み、監視技術は高度化し、アルゴリズムによる情報操作は洗練された。パンデミックは、国家権力が「緊急事態」を口実にどれほど容易に市民の自由を制限できるかを示した。中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、金融取引の完全な監視を可能にする。デジタルIDは、個人の行動を追跡する手段となる。AIは、プロパガンダを個人ごとに最適化する。
一体、私たちは今、どこにいるのか!?
ミルズの分析から私が得た洞察は、陰謀と構造の二元論が過度に単純化された概念だということだ。ミルズが指摘するように、権力の空白や大衆の受動性は構造的な産物であり、そこに陰謀(例: カーネギーやロックフェラーのような)が忍び込み、支配を強化する。これが構造の自己強化を促し、再び新たな陰謀の温床を生む──「陰謀—支配構造の歴史的サイクル」が繰り返される。この連鎖が何度起こった帰結なのかは不明だが、コロナパンデミックの陰謀も、このサイクルの中で生じた一環に過ぎない。ミルズの問いかけは、こうした循環を断ち切る人間の生き方を、私たちに投げかけ続ける。
この鶏と卵のような連鎖を、どこでどのようにして断ち切るべきなのか、残念ながら、私は良い答えを持っていない。しかし、結局のところ、ミルズが問うているのは民主主義の技術的問題ではなく、「人間の生き方そのもの」だ。批判的思考を持ち、自律的に判断し、連帯して行動する──これらは政治制度の問題である以前に、「日常的実践の問題」である。
大衆社会からの脱出は、壮大な社会変革としてではなく、一人ひとりの気づき、そして小さな抵抗の積み重ねとしてしか実現しないのかもしれない。そしてその抵抗は、決して勝利を約束されていない。しかし、抵抗しないことは、認知的主権の放棄、つまり精神的奴隷を意味する。
ミルズが私たちに残した問いは、今も有効だ:私たちは公衆として生きるのか、大衆として生きるのか。
 Alzhacker図書館
Alzhacker図書館
学術文献・外国書籍・海外記事を中心に、報道されない深層情報を淡々と伝えていく一般市民の図書館。 有料会員の支援によって、公開記事(著者×LLM)は提供されています。余裕のある方は、サポートをお願いします。 免責事項:記事は医療アドバイスでなく、教育目的で提供されています。 https://note.com/alzhacker


























































































































































































