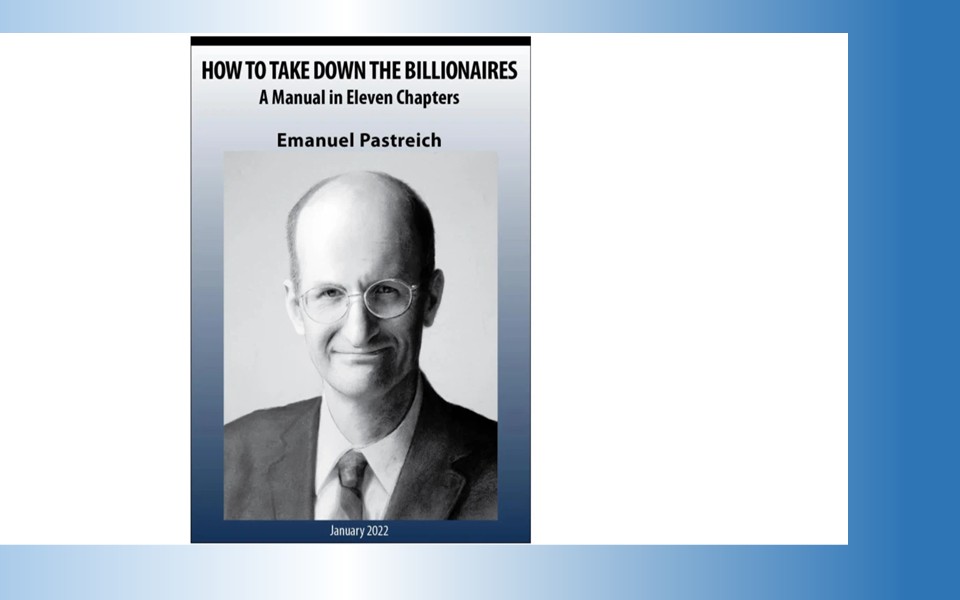
書籍紹介『超富裕層を倒す方法 11のマニュアル』エマニュエル・パストリッチ
国際政治
『How to Take Down the Billionaires』を読む — 現代文明の欺瞞を超えて
いまの世界では、ほとんどの人が「システムに従う」以外の選択肢を持たない。巨大企業と金融勢力があらゆる制度を乗っ取り、政治もメディアも学問も、すべてが資本の論理に従属している。誰もが心のどこかでその異常を感じながら、具体的な打開策を見出せずにいる。そんな時代において、エマニュエル・パストリッチ博士の『How to Take Down the Billionaires』は、単なる批判書でも陰謀論でもない──現実を正面から見据え、出口を描き出そうとする、稀有な書である。
パストリッチ博士は、アメリカと東アジアの架け橋として長年知的活動を続けてきた人物である。彼の強みは、思想の深さと現実認識の鋭さ、そして何よりも「誠実さ」である。彼は派手な言葉や敵意の扇動とは無縁で、冷静な分析と事実に基づきながら、現代の支配構造を一歩ずつ解体していく。その筆致は学者というよりも、文明の医者として腐敗した社会の病巣を診断するようであり、誰も口にしようとしない根本的な問題を、遠慮なく突く。
現代の政治的・学術的迫害の犠牲者が声を上げる エマニュエル・パストリッチ
本書でパストリッチ博士が示すのは、単なる抗議のレトリックではなく、「市民による主権の奪還」という具体的な行動のビジョンである。彼は、AI・通信衛星・電気自動車・脳神経インターフェースなどの先端技術が、いかにして少数の超富裕層の支配装置として統合されつつあるかを描き出す。スターリンクによる通信インフラ、オープンAIによる情報操作、ボーイング・カンパニーによる都市構造の独占、そしてニューラリンクによる人間の意識の侵入──これらはもはやサイエンス・フィクションではなく、現実に進行する「企業国家の誕生」である。
だが、彼は絶望を語らない。むしろ本書は「抵抗のための希望の戦略書」だ。地域経済の再生、テクノロジーの市民所有化、そして国際的な連帯による情報の独立──それらを段階的に実践するための手順を、彼は十一章にわたり具体的に提示する。「億万長者を倒す」という一見、挑発的なタイトルの背後には、実際には「人間の尊厳と自由を守り抜く」ための倫理的闘争がある。暴力ではなく透明性、破壊ではなく再構築、個人崇拝ではなく共同の知恵。そこに彼の真の革命精神が息づいている。
今日、SNSとメディアの喧騒の中で、“正しい言葉”を語る知識人は多い。しかし、理念と実践、告発と建設を同時に行う者はほとんどいない。その意味でパストリッチ博士は、単なる批評家ではなく「行動する知性」である。彼の主張には、時に過激に聞こえる部分もある。しかし、彼が放つ問いの本質を見誤ってはならない。「誰が世界を所有するのか」「私たちは、自らの思考を自分のものとしているのか」。この二つの問いこそ、現代の哲学が失った根源的テーマであり、パストリッチ博士はそこから人類の再生を構想している。
『How to Take Down the Billionaires』は、読者に深い不安と同時に、強烈な覚醒をもたらす書だ。私たちは、無力ではない。知ること、つながること、そして勇気をもって行動することから、すべては始まる。混乱する世界の中で、この書を読むことは「思考の再起動」であり、文明そのものを「再設計する招待」である。真に自由な時代を望むすべての人に、静かな決意とともに手に取ってほしい。
日本語訳:
https://alzhacker.com/how-to-take-down-the-billionaires/
書評:超富裕層を倒す方法:「孫子的抵抗」と「弱者の抵抗」
by Alzhacker × Claude 4.5
「倒す」という言葉が示す根本的な問い
この文書を読んで最初に浮かぶのは、なぜエマニュエル・パストリッチ(Emanuel Pastreich)がこれほど直截的な表現を選んだのかという疑問だ。「超富裕層を倒す方法」——この挑発的なタイトルは、単なる修辞ではなく、彼が現状を本質的な「戦争」として認識していることを示している。
多くのオルタナティブメディアが「批判」や「懸念の表明」に留まる中で、パストリッチは具体的な「行動計画」を提示している。これは重要な違いだ。なぜなら、彼が指摘するように、現代の抵抗運動の多くは「不満の表明」という安全地帯に閉じこもり、実質的な権力構造への挑戦を回避しているからだ。
しかし、ここで立ち止まって考えてみる必要がある。「倒す」という言葉の暴力性は、彼が批判する超富裕層の手法と何が違うのか?この問いは安易に答えられるものではない。パストリッチ自身も、この文書の中で「献身的な市民グループ」「道徳的原則への献身」を強調しており、単純な暴力革命を提唱しているわけではないことがわかる。
むしろ、彼が提案しているのは「制度的暴力への制度的対抗」とでも呼ぶべきものだ。COVID-19政策、ワクチン義務化、ロックダウン、経済的締め付け——これらを「緩慢な暴力」として認識し、それに対する防衛的行動としての「倒す」という表現なのだろう。
孫子から学ぶ現代の権力闘争
パストリッチが『孫子』を引用しているのは興味深い。「自分自身を知り、相手を知る」——この古典的な戦略原則を、彼は現代の権力分析に適用している。
彼の分析で最も鋭いのは、反ファシズム運動側の「自己認識の欠如」を指摘している点だ。多くの抵抗運動が「私たちは正しい」という前提から出発し、自分たちの組織的弱点、資金的依存、テクノロジー的脆弱性を直視していない。Facebook、Google、Twitterといった企業プラットフォームに依存しながら、それらの企業と戦おうとする矛盾。これは、私自身、そしてこの記事にも言えることだが、確かに致命的な盲点だ。
しかし、ここでパストリッチの分析に疑問も浮かぶ。彼は超富裕層の弱点として「傲慢さ」「孤立」「一般市民からの反感」を挙げているが、これらは本当に決定的な弱点なのだろうか?歴史を振り返れば、権力者が民衆から嫌われながらも長期にわたって支配を維持した例は無数にある。ローマ皇帝たちの多くは民衆から憎まれていたが、それでも帝国は何世紀も続いた。
より深刻な問いは、「市民の目覚め」が本当に権力構造を変えるのかということだ。パストリッチは「正確な分析と組織化」によって流れを変えられると主張するが、これは楽観的すぎないか?権力構造は、単に「知識の欠如」によって維持されているのではなく、経済的依存、心理的適応、社会的規範、制度的慣性など、複雑に絡み合った要因によって支えられている。
スターリングラードの比喩が見落とすもの
パストリッチは現在の状況を1942年のスターリングラード攻防戦に例えている。ナチス・ドイツが手を広げすぎ、その弱点が露呈し始めた転換点だという。この比喩は魅力的だが、重要な違いを見落としている。
スターリングラードでは、対立する両陣営が明確に区別され、地理的に分離されていた。しかし現代の権力闘争では、「敵」と「味方」はあるとしても、例えばワクチンを盲信する善良な末端医師など、その中間的なグループの存在が極めて大きく、彼らの境界線は曖昧だ。
この曖昧さは意思や思想だけに基づかない。私たちは皆、批判している企業のサービスを使い、それらの企業が作り出す経済システムの中で生活している。Amazon、Google、Microsoftを批判しながら、それらなしでは日常生活が困難になっている。
これは単なる皮肉ではなく、根本的な問題だ。パストリッチが提案する「完全な経済的独立」「自給自足コミュニティ」は、理論的には私も願うところだが、実践的には極めて困難だ。現代社会の相互依存性は、19世紀や20世紀初頭とは比較にならないほど深く、複雑になっている。
秘密主義という本質的な権力装置
パストリッチの分析で最も説得力があるのは、「秘密主義による統治」の章だ。彼が指摘する機密分類システム、秘密法、非開示契約の拡大は、確かに民主主義の基盤を侵食している。
ケネディ大統領の1961年の演説からの引用は示唆的だ。「『秘密』という言葉そのものが、自由で開放的な社会においては不愉快なものである」——しかし、そのケネディ自身が1963年に暗殺され、その真相は今なお機密の壁に隠されている。これは単なる皮肉ではなく、秘密主義がいかに深く権力構造に組み込まれているかを示している。
9.11以降の機密分類の爆発的増加、COVID-19対応における情報統制、ワクチン契約の秘密条項——これらはパストリッチが指摘する通り、民主的統制を不可能にしている。市民は、自分たちの生活に影響を与える決定の基礎となる情報にアクセスできないのだから、どうやって「情報に基づいた判断」ができるのか?
そこで、パストリッチは「すべての機密資料は公開されなければならない」と主張するが、これは本当に実現可能なのか?また、望ましいのか?国家安全保障、外交交渉、進行中の捜査など、一定の秘密保持が正当化される領域は存在しないのか?
問題は「秘密」そのものではなく、「何を秘密にするかを決める権力が、民主的統制を受けていない」ことではないか。つまり、必要なのは秘密の全面的廃止ではなく、秘密指定のプロセスの民主化かもしれない。
自己崇拝のカルトと構造的洗脳
パストリッチが「自己崇拝のカルト」として批判しているものは、新自由主義的個人主義の文化的表現だ。消費主義、自己最適化、個人的達成への執着——これらが集団的行動と連帯を妨げているという彼の分析は鋭い。
ここで興味深いのは、この「自己愛」の促進が単なる副作用ではなく、意図的な戦略だったという彼の主張だ。1920年代のエドワード・バーネイズ(Edward Bernays)以来の広告・広報キャンペーンが、市民を受動的な消費者に変えることを目的としていた——これは十分に文書化された歴史的事実である。
実際、バーネイズ自身が著書『プロパガンダ』(1928年)で、「大衆の心理を意図的に操作することは、民主主義社会における重要な要素である」と公然と述べている。これは陰謀ではなく、公然と語られ、実践されてきた技術だ。
ここでパストリッチの分析は、一般的な「陰謀論」批判を超えている。彼は、単に「悪い人々が秘密の会合で陰謀を企てている」という単純な物語を語っているのではなく、広告産業、心理学、メディア研究の発展が、どのように権力者に「合意の製造」の技術を与えたかを指摘している。
この、自己愛や消費主義は、完全に外部から押し付けられたものなのか?それとも、人間の本性の一部——例えば、地位への欲求、新奇性への好奇心、快楽の追求——を利用し、増幅したものなのか?この区別は重要だ。なぜなら、それによって「解決策」の性質が変わるからだ。
経済的独立という幻想と現実
パストリッチが提案する「独立した自給自足コミュニティ」の構想は、私自身も強く支持するところであり、関連記事を過去に投稿してきた。地域通貨、物々交換、食糧自給、手工業の復活——これらは理想的には、グローバル資本主義からの解放を約束する。
以下は、自己批判的な意味合いが強いが、いくつかの共通する問題を指摘しておきたい。
第一に、規模の問題。現代の高度に専門化した経済において、どこまで自給自足が可能なのか?医療機器、コンピューター、複雑な化学物質——これらを地域レベルで生産することは不可能ではないにしても、極めて困難だ。パストリッチをはじめ、私自身、この文書をコンピューターで書き、インターネットで配布している。
第二に、知識と技術の問題。現代人の多くは、基本的な食糧生産や手工業の技能を失っている。これは単に「学び直せばいい」という問題ではなく、何世代にもわたる知識の断絶を意味する。
第三に、最も厄介なのは、孤立したコミュニティが外部からの圧力に対していかに脆弱かという問題だ。歴史を見れば、自給自足を試みたコミュニティが、税制、規制、あるいは直接的な暴力によって破壊された例は無数にある。
それでも、パストリッチの提案には重要な価値がある。それは、完全な自給自足が不可能だとしても、「部分的な経済的独立」が戦略的に重要だという点だ。これはまさに私が考えてきたことであり、食糧、エネルギー、基本的なサービスにおける自立性の向上は、交渉力を高め、選択肢を増やし、生存の確率を高める。
これは二者択一——グローバル経済への完全な依存か、完全な自給自足か——ではなく、程度の問題として捉えるべきだろう。
教育とジャーナリズムの再生という核心的課題
パストリッチが最も説得力を持って論じているのは、教育とジャーナリズムの腐敗と、その再生の必要性についてだ。彼が「知識人の反逆」と呼ぶもの——専門家たちが市民の信頼を裏切り、権力者に奉仕するようになった過程——は、確かに現代の危機の核心にある。
COVID-19パンデミックは、この問題を劇的に浮き彫りにした。科学者、医師、ジャーナリストの多くが、疑問を提起するのではなく、公式見解を繰り返すだけになった。反対意見は「偽情報」として検閲され、異論を唱える専門家は職を失った。
パストリッチの分析は倫理的には正しいとしても、実践的にはいくつかの問題があると考えることもできる。彼は知識人を「賄賂を受け取った裏切り者」として描く傾向がある。多くの庶民が知識人の言説を信じ、それによって多大な犠牲を払ったことを考えれば、彼の意見は至極当然であり、むしろ数少ない知識人の最後の良心とも言えるだろう。
一方で、多くの知識人は、意識的に裏切ったというよりも、制度的圧力、同調圧力、認知的バイアスの組み合わせによって、批判的思考を停止させてしまったように見える。私には大多数の知識人は「凡庸な悪」に見える。
これは重要な区別だ。なぜなら、「悪意ある裏切り者」と「制度的圧力に屈した人々」では、対処法が異なるからだ。前者には対抗するしかないが、後者には対話と説得の余地がある。しかし、この解釈は、私が過度な性善説で判断してしまっている可能性もある。
パストリッチが提案する「市民による独立した教育システム」の構想は魅力的だが、いくつかの難問に直面する。第一に、誰が教えるのか?第二に、どのような基準で「真実」を判断するのか?第三に、どうやって、単なる別のイデオロギー的洗脳にならないようにするのか?
「ホームスクーリング」はひとつの答えかもしれないが、これらの問いに簡単な答えはない。しかし、パストリッチが正しく指摘しているのは、現状——企業や政府に資金提供され、統制される教育システム——が持続不可能だということだ。
革命の実践可能性という最大の問い
この文書全体を通して、最も根本的な問いは、パストリッチが提案する革命が実際にどこまで実現可能なのかということだ。
彼は11の章にわたって詳細な計画を提示している。地域組織化、経済的独立、教育の再建、秘密主義の終焉、そして最終的に超富裕層の逮捕と資産没収。しかし、これらのステップは、それぞれが極めて困難な課題だ。
最大の問題は、彼が想定する「臨界質量」——十分な数の献身的な市民——が果たして形成されるのかということだ。パストリッチは、人々が「真実を知ることで興奮やインスピレーション、自由を感じる」と述べているが、これは楽観的すぎるかもしれない。
歴史を見れば、人々は多くの場合、不正義を知りながらも、個人的な安全と快適さを優先する。これは道徳的弱さではなく、生存戦略だ。家族を養い、生活を維持しなければならない人々にとって、革命的行動のリスクは極めて高い。
パストリッチ自身、この問題を認識しており、「退職資金や子供の大学進学を心配する人々」では運動は崩壊すると警告している。それは大多数の人々を排除することを意味するかもしれない。
もう一つの問題は、権力構造の適応能力だ。パストリッチは超富裕層の「傲慢さ」を弱点として挙げているが、実際には、支配階級は歴史的に極めて柔軟で適応的だ。市民運動が脅威になれば、彼らは戦術を変更し、譲歩し、取り込もうとするだろう。
日本への示唆と限界
パストリッチの分析は主にアメリカの文脈で書かれているが、日本にも多くの示唆がある。
COVID-19対応における日本政府の政策——ワクチン推進、緊急事態宣言、行動制限——は、パストリッチが批判するグローバルな権力構造の一部だった。日本の製薬会社、メディア、医療機関も、同様の利益相反と情報統制の構造に組み込まれている。
しかし、日本特有の要因もある。「忖度」文化、同調圧力の強さ、権威への服従——これらは、パストリッチが提案する「市民による直接行動」を特に困難にする。日本では、公然と権威に挑戦することの社会的コストが、欧米以上に高い。
また、日本の市民社会は、欧米に比べて組織化の伝統が弱い。労働組合の影響力低下、町内会の形骸化、NPOの資金的脆弱性——これらは、パストリッチが提案する「強力な地域組織」の形成を困難にする。
個人的には、ジェームズ・C・スコットの提唱する「弱者の武器」——すなわち、公然たる反乱ではなく、日々の生活の中で行われる「見えざる抵抗」(日常的な不服従、怠業、言葉の操作など)は、同調圧力が強く、公然と体制に刃向かうコストの高い日本社会において、適した抵抗の作法かもしれないと考えている。
日本の伝統的な「やんわりとした拒否」や、建前と本音を使い分ける文化的作法は、この「弱者の武器」の実践と親和性が高い。パストリッチが描く大規模な革命的行動にすぐに結びつかなくとも、そうした小さな日常的抵抗の蓄積が、やがて支配的な物語の正当性を浸食し、別の生き方の土壌を育てうる。
意図性と構造の弁証法
パストリッチの分析で最も論争的なのは、現在の権力構造がどの程度「意図的」なのかという問いだ。彼は、超富裕層が「組織的に」「計画的に」市民を支配しようとしていると主張する。これは陰謀論なのか、それとも合理的な分析なのか?
実際には、この二者択一は誤った対立だ。権力構造は、意図的な計画と、構造的な力学の両方によって形成される。
例えば、製薬会社がワクチン開発に莫大な資金を投じたのは、「人口削減」という邪悪な計画のためだったのか?それとも、単に利益を最大化しようとした結果なのか?おそらく、その両方の要素がある。個々の企業は利益を追求し、その過程で、より大きなシステム——トランスナショナル資本家階級(TCC)、医療産業複合体、規制当局との癒着、メディアとの共謀——が形成される。
これは、誰か一人の首謀者がすべてを計画したわけではないが、同時に、単なる「偶然」や「市場の自然な働き」でもない。利益追求という動機は燃料であり、制度的構造がそのエンジンである。支配階級のグループが運転者としてそれらを利用しているという構図が、もっとも整合的な説明だろう。
パストリッチの強みは、この複雑性を認識しつつも、「構造」という言葉を免罪符にしないことだ。確かに、構造的な力学が働いているが、その構造は誰かが作り、維持しているのだ。
革命か改革か——あるいは第三の道
パストリッチは明確に「革命」を提唱している。既存の政治システム、経済システム、教育システムは根本的に腐敗しており、改革不可能だという。
ただし、歴史を見れば、完全な革命が成功した例は稀だ。フランス革命はテロルと独裁を生み、ロシア革命はスターリニズムに帰着し、中国革命は文化大革命を招いた。一方、漸進的な改革——奴隷制の廃止、女性参政権の獲得、労働者の権利の確立——は、長い時間がかかったが、より持続的な変化をもたらした。
パストリッチに対する最大の批判は、彼が提案する「革命」が、実際には新たな専制を生むかもしれないということだ。「献身的な市民グループ」による「臨時政府」——これは、歴史上何度も悲劇的な結果に終わった構想だ。
しかし、パストリッチの反論は明確だろう。現在進行中の変化——デジタル監視、経済的締め付け、情報統制——があまりにも急速で根本的なため、漸進的改革では間に合わない。COVID-19対応で見られたように、一夜にして基本的権利が停止され、何百万人もの生活が破壊された。このスピードと規模の変化に対して、「漸進的改革」で対抗できるのか?
おそらく、必要なのは体制をひっくり返す「革命」でも「改革」でもなく、「複数の戦略の並行実施」だろう。地域レベルでの自立的コミュニティ構築、制度レベルでの改革圧力、知的・文化的レベルでの意識変革——これらすべてが同時に必要だ。
最終的な問い——努力は合理的か
この文書を読み終えて、最も根本的な問いは、抵抗の努力をすることが合理的なのかということだ。
パストリッチは、超富裕層の弱点を指摘し、市民が組織化し行動すれば勝利できると主張する。しかし、彼が描く権力構造——軍事力、情報統制、経済支配、技術的優位性——は圧倒的だ。
それでも、歴史は予測不可能性に満ちている。ソ連の崩壊、南アフリカのアパルトヘイト終焉、東欧の民主化——これらはすべて、数年前には不可能と思われていた。大規模なシステムは、見た目より脆弱であることが多い。
パストリッチの文書の真の価値は、具体的な計画の詳細というよりも、「思考の枠組み」を提供していることにある。彼は、現状を「自然」や「不可避」と受け入れることを拒否し、代替案を想像し議論することの重要性を示している。
最終的に、「努力は合理的か」という問いには答えられない。しかし、より重要な問いは、「完全に道が閉ざされるのか、可能性を残すのか」だろう。パストリッチの文書は、たとえ成功の確率が低くても、抵抗し、組織化し、代替案を構築しようとすることの価値を主張している。
それは、突き詰めて言えば、プロセスそのものに意味があるという主張だ。超富裕層を実際に「倒す」ことができるかどうかは不確かだが、そのための努力の中で、より自律的で、より連帯した、より批判的な市民性が生まれる。チャンスを次の世代に引き渡すことが、最大の責任であり希望なのかもしれない。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 オルタナ図書館—Alzhacker
オルタナ図書館—Alzhacker
学術文献・外国書籍・海外記事を中心に、報道されない深層情報を淡々と伝えていく一般市民の図書館。 有料会員の支援によって、公開記事(著者×LLM)は提供されています。余裕のある方は、サポートをお願いします。 免責事項:記事は医療アドバイスでなく、教育目的で提供されています。 https://note.com/alzhacker



























































































































































































