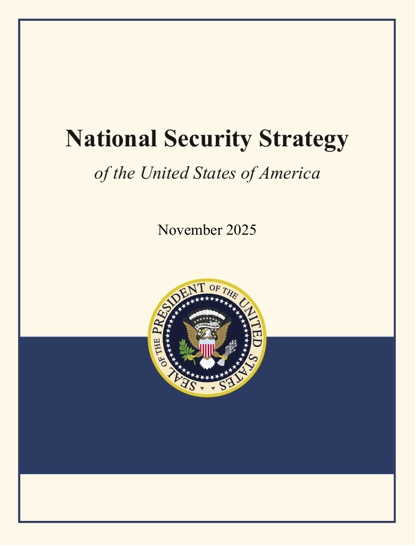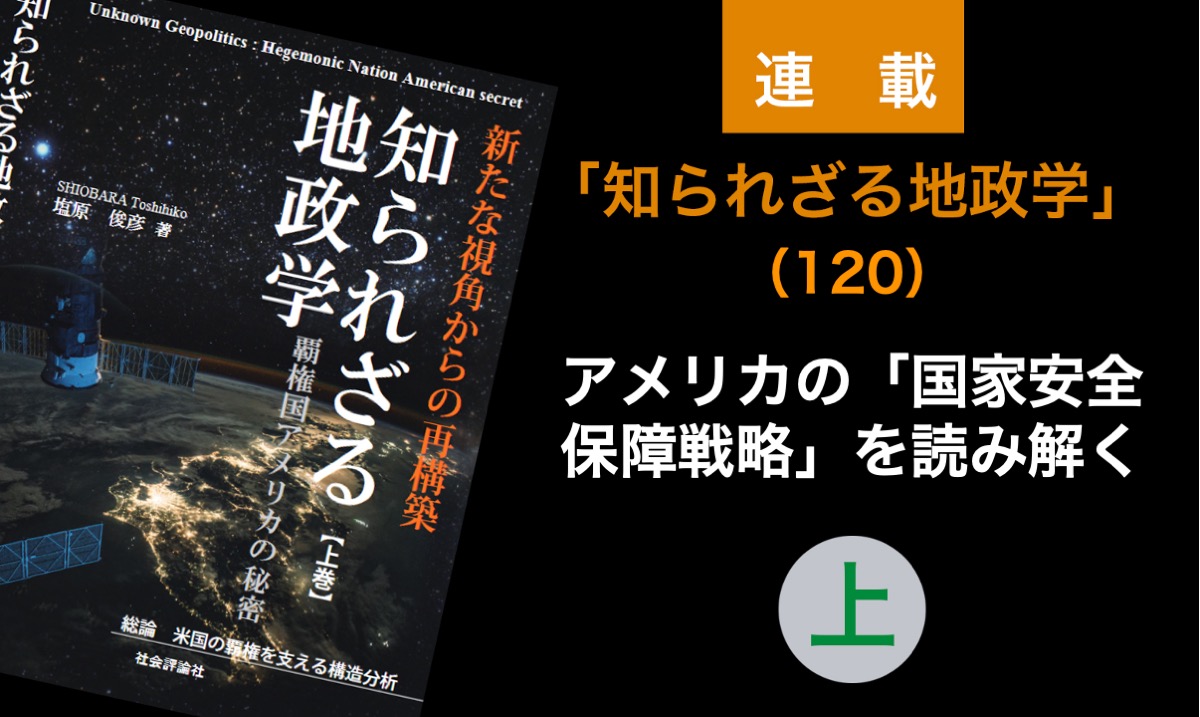
「知られざる地政学」連載(120):アメリカの「国家安全保障戦略」を読み解く(上)
国際2025年12月4日夜、ホワイトハウスは、大統領が通常任期ごとに発表する「国家安全保障戦略」(以下、「戦略」)を公表した。外交政策における「アメリカ第一主義」(Make America Great Again, MAGA)の適用に関する包括的な声明とみなすことができる(なお、表紙[下の写真]には、「2025年11月」と印刷されているが、これは予定よりも遅れて公表されたことを物語っている)。いずれにしても、この「戦略」表明は、米政府の各部門が予算配分や政策優先順位を設定する際に指針となり得るもので、中間選挙結果にもよるが、もう3年つづく第二期ドナルド・トランプ政権の外交の指針となる。つまり、世界統治をめぐる地政学・地経学上のメルクマールになりうる。このため、今回は、この「戦略」を考察対象としたい。
アメリカ合衆国の国家安全保障戦略
(出所)https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
外交政策エリートへの批判
「戦略」はその序論において、過去の外交政策エリートを批判している。「冷戦終結後、米国の外交政策エリートたちは、全世界に対する恒久的なアメリカの支配こそがわが国の最善の利益であると自らを納得させた」が、「わが国のエリート層は、米国民が国益との関連性を認めない国際的負担を、米国が喜んで永遠に背負いつづける意志があるという点について、ひどく誤算していた」というのである。
彼らは、巨大な福祉・規制・行政国家と、巨大な軍事・外交・諜報・対外援助複合体を同時に資金面で支えるアメリカの能力を過大評価した。「グローバリズム」と、いわゆる「自由貿易」に大きく誤った破壊的な賭けを行い、米国の経済的・軍事的優位性の基盤である中産階級と産業基盤そのものを空洞化させたのである、と指摘している。「要するに、我々のエリート層は根本的に望ましくなく達成不可能な目標を追求しただけでなく、その過程で目標達成に不可欠な手段そのものを損なったのである、すなわち、国家の力と富と品位を築き上げてきた国家の基盤そのものを」と書く「戦略」は、半世紀以上つづいた米国の外交戦略からの決別を明確に宣言しているのだ。
これまで、ジョージ・W・ブッシュ、バラク・オバマ、ジョー・バイデンの過去の国家安全保障戦略を思い出してみると、彼らの戦略には「敵」(enemy)や「敵対者」(adversary)が列挙されていた。トランプの「戦略」では、こうした表現を明確に避けようとしている。その結果、バイデンの「戦略」では、ロシアが70回以上言及され、そのたびに非常に否定的で敵対的な口調で語られていたが、今回の「戦略」は10回しか言及されておらず、否定的な表現は一度もない。
つづく「宣教師的」姿勢
別言すると、これは、拙著『帝国主義アメリカの野望』で指摘した「リベラルデモクラシー」に基づく外交戦略からの離脱を意味している。「アメリカの外交戦略」を論じた6章において、「この章では、アメリカの外交戦略について論じたい。その外交戦略は長い間、基本的に変わっていない」と書いておいた(252頁)。そのうえで、米国外交の特徴として、キッシンジャーが「アメリカ人は交渉を心理的というより宣教師的な観点でとらえる傾向があり、相手の思考に入り込むというより、相手を改宗させたり非難したりしようとする」と語っていた話を紹介した(256~257頁)。さらに、「この「宣教師的」(missionary)という言葉こそキーワードである」と指摘しておいた。そして、つぎの記述をつづけた。
「先住民たちの「魂の救済」を心から願い、異国での殉教も厭わないばかりか、それを望みさえしながら、布教活動を推し進めた宣教師像こそ、いまでもヘゲモニー国家アメリカの介入主義を突き動かしている原動力なのだ。非民主主義的な場所に住む人々に、アメリカ流の民主主義への「信仰」のようなものを定着させることで、自国の安寧につなげようとしている。
こうした宣教師的な熱意をもつアメリカ人の代表格が、ミアシャイマーが「リベラルな覇権主義者(ヘゲモニスト)」と呼ぶ人々なのだ。」
彼らは、「リベラルデモクラシー」を海外に輸出することで、米国の安寧が保たれると信じて疑わなかった。しかし、本当はこの政策は大失敗であった。トランプは、「戦略」において、これを率直に認めている。その意味で、この指摘はまったく正しい。ただし、トランプもまた「宣教師的」点を忘れてはならない。そう、別の宗派の宣教師が現れたにすぎないのである。
「トランプ流モンロー主義」の実践を宣言
「米国は何を望むべきか」という章では、米国の外交政策上の核心的利益が語られている。最初に登場する目標(としての利益)は、①西半球(Western Hemisphere)が米国への大規模な移民を防止・抑制できる程度の安定性と適切な統治を維持することを確保したい、②麻薬テロリスト、カルテル、その他の国際犯罪組織に対して各国政府が我々と協力する半球を望む、③敵対的な外国の侵入や重要資産の支配から自由であり、重要なサプライチェーンを支える半球を望む、④戦略的に重要な拠点への継続的なアクセスを確保したい――という4点である。そのうえで、「言い換えれば、我々はモンロー主義に対する「トランプ補則」(Trump Corollary)を主張し、実行に移す」と記されている。
どうやら、「戦略」は「トランプ流モンロー主義」の実践を宣言しているようにみえる。ここで、少しだけ補助線を引いてみよう。「西半球」という概念については、先に紹介した拙著において、つぎのように記述しておいた(210頁)。
「だが、その絶頂期にあるなかで、イギリスの植民地から独立したアメリカは、ヨーロッパ中心主義から離脱する過程において、イギリスに代わるヘゲモニー国家に向けた胎動をはじめる。いわゆる「西半球」(Western Hemisphere)という概念の登場によって、アメリカが特別の地位を勝ち得るのだ。1823年12月2日、米大統領ジェームズ・モンローは議会への教書のなかで、アメリカとヨーロッパの相互不干渉の原則を表明し、ラテンアメリカ諸国へのいかなる干渉もアメリカに対する非友好的態度とみなすことを宣言する。いわゆる「モンロー・ドクトリン」の宣言だ。これ以降、グリニッジ標準時の西経20度の大西洋を通る線で区切られた「西半球」という空間概念が、ヨーロッパ中心主義の世界観に対抗して、もはやヨーロッパ中心主義ではない新しい世界観を打ち出すのである。この動きは20世紀の新しい国際法へとつながっている。」
この説明を踏まえて、さらに、つぎのように書いておいた。
「足早に説明すると、モンロー・ドクトリン以降、西半球において地歩を固めたアメリカは第一次世界大戦に際しても、参戦したのは1917年4月であり、事実上中立を保った。その後、アメリカは孤立主義から介入主義へと移行する。その典型が前述した1928年の不戦条約(ブリアン・ケロッグ協定)であろう。だが、その前段として、アメリカは西半球において、新しい国際法の基準が生まれる。「トバール主義」だ。
これは、1907年にエクアドルの外相カルロス・トバールが提唱した、合法政府擁護の主張である。新政府の承認に際して、憲法違反および武力を用いて成立した政府の承認を拒否すべきというもので、同年12月、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドルの平和友好条約で採用される。アメリカはこの「トバール・ドクトリン」を支持し、民主的な合法性と正統性が国際法の基準であることが重要視されるようになる。ウィルソン大統領は、西半球におけるこの民主的正統性の基準を、国際法上の原則のレベルまで引き上げる。それ以後は、民主的な憲法を持つという意味で合法的な政府だけが認められるようになるのだ。民主的、合法的といった言葉の実際の意味を定義・解釈・承認するのはアメリカということになる。こうして西半球では、「中南米のあらゆる国の憲法や政府の変更を、アメリカがコントロールできるようになった」と、シュミットは指摘している。この経験がアメリカの世界的な介入主義の淵源となるのである。」
もう少し詳しく説明すると、この「トバール・ドクトリン」の直前に、「ルーズベルト補則」(Roosevelt Corollary)と呼ばれるものがあったことも知っておくべきかもしれない。20世紀に入って自信を深めた米国は地域の警察官としての役割を担うことを厭わなくなる。その結果、セオドア・ルーズベルト大統領はベネズエラとその債権者間の危機が欧州列強による同国侵攻の引き金となることを懸念し、1904年12月のルーズベルト補則を提唱したのである。西半球諸国が国際債権者に対する債務を履行し、米国の権利を侵害せず、「米州諸国全体に損害を与える外国の侵略」を招かないよう、米国が最終手段として介入すると宣言したのだ。この「ルーズベルト流モンロー主義」が実際に運用されるにつれ、米国は地域諸国の内政安定回復のために軍事力を行使する機会を増やした。キューバ、ニカラグア、ハイチ、ドミニカへの米国の介入を正当化する根拠として、この「ルーズベルト補則」が一定の機能を果たしたと考えられている。
ここまでの知識があれば、「トランプ流モンロー主義」といっても、米国の「世界的な介入主義」の継続という点に変化はないことがわかるだろう。「宣教師的」な外交がつづくように、「トランプ流モンロー主義」となっても介入主義そのものは変わらない。
戦略上の優先順位
第4章では、「戦略」が語られている。そこには、「優先順位」が具体的に書き込まれている。第一に、「大量移民の時代は終わった」として、国境警備の重視の姿勢が示されている。第二に、「基本的人権と自由の保護」が掲げられている。興味深いのは、この項目の最後に、「我々は、欧州、アングロ圏(主にイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど)、そして民主主義世界のその他の地域、とくに同盟国において、エリート主導の反民主的な基本的人権の制限に反対する」と書かれている点だ。この背景には、言論の自由への制限に反対するトランプ政権の強い意向がある。
第三に、「負担分担と負担転換」が示されている。「米国がアトラス(ギリシャ神話で両腕と頭で天の蒼穹を支えるとされる巨人)のように世界秩序全体を支えてきた時代は終わった」という認識から、ここでは、同盟国との協力関係を前提に、それらが「自地域に対する主たる責任を担い、集団防衛への貢献を大幅に増やさねばならない」と主張している。そのうえで、「モデルとなるのは、経済的手段を用いてインセンティブを調整し、志を同じくする同盟国と負担を分かち合い、長期的な安定を基盤とする改革を要求する対象を絞ったパートナーシップである」と指摘されている。
最優先地域は「西半球」
地域ごとの優先順位も示されている。注意を引くのは、例によって、「あらゆる指標において、米国は史上最も寛大な国家である」としながらも、「しかし、世界のあらゆる地域や問題に等しく注意を払う余裕は我々にはない」と率直に認めている点だ。そのうえで、もっとも優先順位の高い地域として、「西半球」が挙げられている。すでに言及した「トランプ流モンロー主義」が「米国の安全保障上の利益と合致する、米国パワーと優先事項の常識的かつ強力な回復策」であると説明されている。西半球における目標として、「結束と拡大」が掲げられ、「西半球の既存の友好国と連携し、移民管理、麻薬流通阻止、陸海における安定と安全の強化を図る」とされている。
その方法として、シーレーン(海上交通路)を管理し、不法移民やその他の望ましくない移民を阻止し、人身売買や薬物売買を減らし、危機時に重要な通過経路を管理するため、沿岸警備隊と海軍をより適切に配置するという。
もちろん、西半球として意識されているのは、ラテンアメリカ諸国である。米国政府は、同地域における米国企業向けの戦略的買収・投資機会を特定し、これらを国務省、国防総省、エネルギー省、中小企業庁、国際開発金融公社、輸出入銀行、ミレニアム・チャレンジ・コーポレーションを含む(ただしこれらに限定されない)すべての米国政府融資プログラムによる評価に付す、と記されている。
アジア重視と対中戦略
つぎに重視するのは「アジア」である。ここでの最大の課題は中国への対応だろう。「戦略」はまず、「市場を中国に開放し、米国企業の中国投資を奨励し、製造業を中国にアウトソーシングすることで、中国がいわゆる「ルールに基づく国際秩序」に組み込まれると考えた」、これまでの政策を覆すと宣言している。つまり、同盟国やパートナー国との協力を重視するというのである。具体的には、「オーストラリア・日本・米国との四者協力(クアッド)を通じて、ニューデリーがインド太平洋地域の安全保障に貢献するよう促す必要がある」としている。こうした協力は軍事に限らず、最先端の軍事技術および軍民両用技術にも広げる。米国の優位性が顕著な分野は、すなわち水中・宇宙・核分野に加え、軍事力の未来を決定づける人工知能(AI)、量子コンピューティング、自律システム、そしてこれらを支えるエネルギー分野である。
他方で、経済分野では、米国はインド太平洋における戦争を防ぐために、抑止力に強固かつ継続的に焦点を当てる。そのために終止符を打つ対象として、①略奪的で国家主導の補助金や産業戦略、②不公正な取引慣行、③雇用破壊と非工業化、④大規模な知的財産の窃盗と産業スパイ、⑤鉱物やレアアースを含む重要資源への米国のアクセスを危険にさらすサプライチェーンに対する脅威、⑥米国のオピオイド蔓延に拍車をかけるフェンタニル前駆体の輸出、⑦プロパガンダ、影響力工作、その他の文化破壊活動――が挙げられている。
なお、これらはいずれも中国を強く意識したものだが、「戦略」では、対中交渉への影響を考慮して、より穏便な記述にとどめている。
ただし、「軍事的脅威の抑止」の項目を立てて、ここで台湾問題に触れている。「台湾への注目が高まっているのは当然であり、その背景には台湾の半導体生産における支配的地位もあるが、主に台湾が第二列島線への直接アクセスを提供し、北東アジアと南東アジアを二つの明確な戦域に分断する点にある」と説明したうえで、「世界の海上輸送の3分の1が毎年南シナ海を通過していることを考慮すれば、これは米国経済に重大な影響を及ぼす」という。したがって、「軍事的優位性を維持することで台湾をめぐる紛争を抑止することが最優先課題である」と書かれている。さらに、「我々は台湾に関する従来の宣言的政策を維持する」と明言されている。つまり、「米国は台湾海峡における現状の一方的変更を支持しない」ということだ。
「知られざる地政学」連載(120):アメリカの「国家安全保障戦略」を読み解く(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)