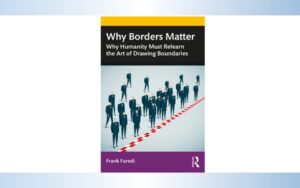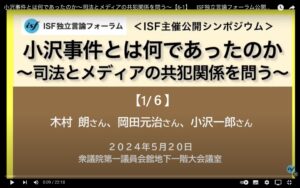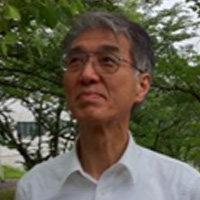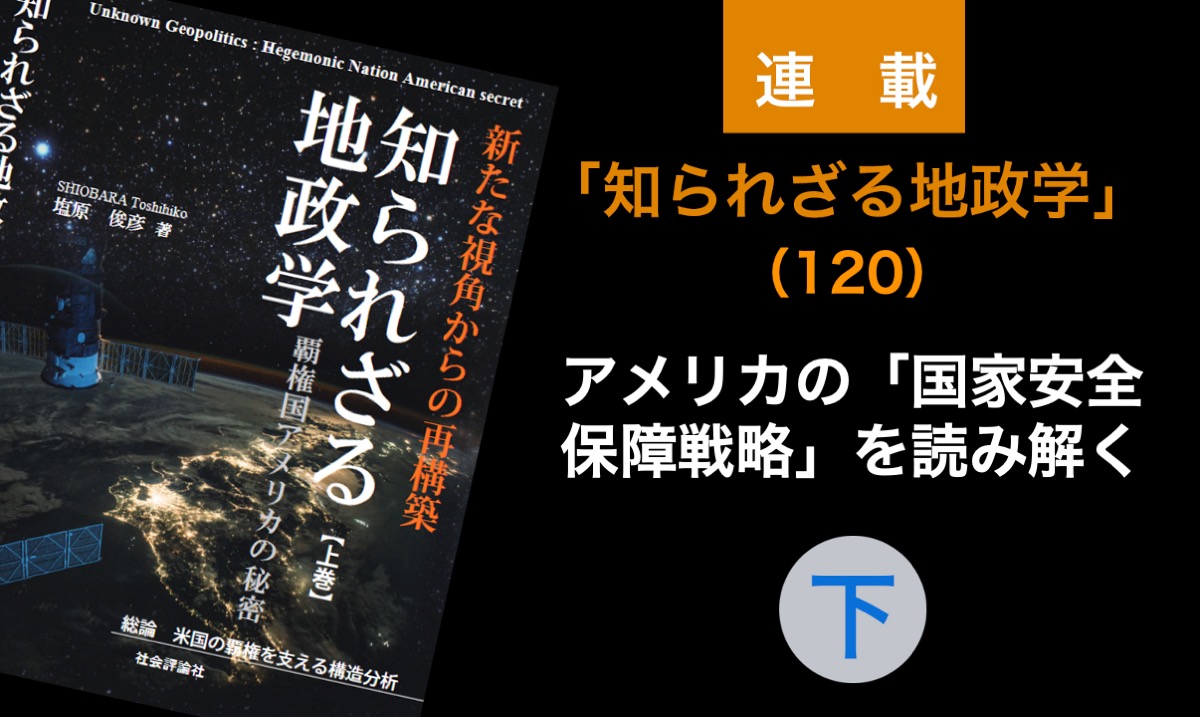
「知られざる地政学」連載(120):アメリカの「国家安全保障戦略」を読み解く(下)
国際
「知られざる地政学」連載(120):アメリカの「国家安全保障戦略」を読み解く(上)はこちら
「欧州の偉大さの促進」
つぎに登場するのが「欧州」である。「欧州の偉大さの推進」という項目で登場するのだが、その内容は物議を醸すものとなっている。12月7日付の「ワシントンポスト」は、「戦略」が「ブリュッセルに手榴弾のように着弾した」と書いているほどだ。
そこで、本稿では、いわば批判の対象となっている欧州をめぐる記述について詳しく考察することにしたい。
冒頭において、「米国当局者は、欧州の問題を軍事費不足と経済停滞という観点で捉えることに慣れきっている」と記されている。トランプ政権の欧州への率直な見方がある意味で正直に書かれていると言えるだろう。
「戦略」は欧州を容赦しない。「この指摘には一理あるが、欧州の真の問題はさらに根深い」とつづけているのだ。大陸欧州は世界GDPに占める割合を低下させ続けており――1990年の25%から現在では14%にまで減少した――、その一因は、「創造性と勤勉さを損なう国内および域内の規制にある」、とまで手厳しく指摘している。さらに、「この経済的衰退は、文明の消滅(civilizational erasure)という現実的でより厳しい見通しによって覆い隠されている」と書かれており、きわめて辛辣な表現が用いられている。
こうした欧州への厳しい見方が本気であることは、「我々は、ヨーロッパがヨーロッパでありつづけ、文明としての自信を取り戻し、失敗に終わった規制による窒息状態への集中を放棄することを望む」という文章によって理解できる。トランプ政権は、「戦略」という公式文書のなかで、欧州を決定的にバカにし、蔑んだと言えるだろう。
ウクライナ戦争と欧州
欧州を蔑視する「戦略」では、ウクライナ戦争と欧州についても、辛辣な見方が示されている。それは、「この自信の欠如は、欧州とロシアの関係においてもっとも顕著である」という指摘によく現れている。ほぼあらゆる指標において、欧州の同盟国はロシアに対して圧倒的なハードパワー(通常兵器)の優位性を有しているにもかかわらず、核兵器についてはロシアにまったく劣っているために、自信を喪失し、「多くの欧州人がロシアを存亡に関わる脅威とみなしている」のだ、と「戦略」は分析している。
その結果、欧州とロシアの関係を管理するには、ユーラシア大陸全体における戦略的安定の条件を再構築するとともに、ロシアと欧州諸国間の紛争リスクを軽減するため、「米国による重要な外交的関与が必要となる」、と我田引水的な記述がみられる。つまり、ウクライナ戦争の終結においても、米国が一定の役割を果たさなければならないというわけだ。それは、「欧州経済を安定させ、戦争の意図せざる拡大やエスカレーションを防止し、ロシアとの戦略的安定を回復するとともに、ウクライナが存続可能な国家として再生できるよう、敵対行為終結後の同国の復興を可能とするため」であると説明されている。だからこそ、「米国にとって、ウクライナにおける敵対行為の迅速な停止を交渉することは核心的利益(a core interest)である」ということになる。
民主主義の基本原則を踏みにじる欧州
この結果、「戦略」は、「トランプ政権は、不安定な少数与党政権に支えられた(ウクライナでの)戦争に対して非現実的な期待を抱く欧州当局者と対立している」との見方を示している。この「非現実的な期待」というのは、敗色濃厚なウクライナ戦争であるにもかかわらず、消耗戦を継続すれば、やがてロシアが衰退し、ドンバスやクリミアを奪還できるというものだ。逆に、トランプ政権は、ウクライナの戦況悪化を率直に認めるだけでなく、発電施設や暖房供給網への打撃から、今冬、ウクライナ国民の苦渋が深刻化するだけでなく、経済的な行き詰まりも懸念している。
私が興味深く思ったのは、先の文につづけて、「こうした政権の多くは、反対派を弾圧するために民主主義の基本原則を踏みにじっている」と指摘されている点だ。これは、J・D・ヴァンス副大統領がルーマニアの大統領選をめぐって、2025年2月14日にミュンヘン安全保障会議で行った演説のなかで批判したことに通じている。その発言は、以下のようなものだ。
「最近、元欧州委員がテレビ番組に出演し、ルーマニア政府が選挙をすべて無効にしたことを喜んでいるように聞こえたことに私は驚いた。彼は、計画通りにいかなければ、ドイツでもまったく同じことが起こり得るだろうと警告した。このような軽率な発言は、米国人にとっては衝撃的である。長年、我々が資金援助し、支援しているものはすべて、共有する民主的価値の名のもとに行われていると聞かされてきた。ウクライナ政策からデジタル検閲に至るまで、すべてが民主主義の防衛として正当化されてきた。しかし、欧州の裁判所が選挙を無効にし、高官が他者をキャンセルすると脅すのを目にするとき、我々は自分たちが適切な高い基準を維持しているのかどうかを問うべきである。」
拙著『ネオ・トランプ革命の深層』では、つぎのように記述しておいた(294頁)。
「ここでヴァンスがやり玉に挙げたルーマニアの大統領選について説明したい。2024年11月24日に行われた選挙の第一回投票において、23%の得票率でトップとなったカリン・ジョルジェスクについて、憲法裁判所は第二回投票の行われる12月8日の2日前に選挙を無効とし、やり直しを指示したのである。憲法裁は当初、第一回投票の再集計を命じたが、大きな問題は見つからなかったため、12月5日には第二回の投票実施を承認した。だが、翌日には前言を撤回した。同裁判所は、有権者が「誤った情報」に惑わされたこと、また候補者が「ソーシャルメディア・プラットフォームのアルゴリズムの悪用」により不正に利益を得たことを理由に選挙を無効としたと断じた。
冷静に考えれば、投票結果は厳粛に受け止めるべきであり、憲法裁の判断は民主主義そのものを冒涜しているようにみえる。だからこそ、ヴァンスはこうした「似非民主主義」を厳しく断罪したのである。曰く、「この12月、ルーマニアは諜報機関の薄弱な疑いと大陸の近隣諸国からの多大な圧力に基づいて、大統領選挙の結果を真っ向からキャンセルした」。ルーマニアの民主主義は、大統領選の結果さえ近隣諸国からの圧力によって覆せるほど脆弱だということになる。」
ヴァンスが懸念するように、いまの欧州の政治指導者の大多数は民主主義を踏みにじっている。そんな暴挙を可能にしているのがいわゆる「オールドメディア」による既存政権との癒着や結託だ。オールドメディアは、政権側の不正を批判しないだけでなく、そもそも隠蔽に加担している。先のルーマニアの憲法判断に対しても、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は支持した。そんな彼女を厳しく非難したマスメディア報道を私は知らない。
欧州におけるオールドメディアの報道は、日本と同じく、ウクライナ支援の継続で凝り固まっている。そのため、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領を「善」とみなし、ゼレンスキーを批判することもない。あるいは、ゼレンスキーに不利益になるような報道はほとんど報道しない。まさに、既存の権力当局にとって都合のいいように情報が統制されているとも言える。
たとえば、欧州連合(EU)は、2027年からブロック全体でロシア産ガスの輸入を禁止することに合意する準備を始めたばかりだが、欧州諸国が石油製品の供給をインドに求め、ロシア産原油を精製するインドの製油所から石油製品を輸入しているという不都合な事実を覆い隠してきた。1年前に、シンクタンクの民主主義研究センターは、「制裁の回避術 洗浄されたロシア産石油がインドから欧州へ逆流」というタイトルの報告書を公表済みだ。そこには、ロシア産原油で稼働しているインドの三つの主要製油所からEUへの石油製品輸入量が、2024年第1~3四半期に、ロシアのウクライナ侵攻前の平均輸出量と比較して58%増加し、EUの精製の抜け穴が拡大した、と書かれている。
こうした事実を知る欧州の住民がどれだけいるのだろうか。もちろん、日本人のほぼ100%がまったく知らないはずだ。オールドメディアが隠蔽してきた結果なのだ。つまり、露骨な情報操作(マニピュレーション)が横行し、各国の国民が欺かれ騙されていると言えるだろう。こんなところに民主主義は存在しない。あるのは、国民を飼いならすための「洗脳」であり、それはバカな国民の大量創出に基づく「似非民主主義」にすぎない。
ゆえに、「こうした政権の多くは、反対派を弾圧するために民主主義の基本原則を踏みにじっている」という「戦略」の指摘は正鵠を射ている。「こうした政権」のなかには、ドイツのフリードリヒ・メルツ政権やフランスのエマニュエル・マクロン政権も含まれていると言えるだろう。もちろん、高市早苗政権も同じである。
トランプ政権の対欧州批判の背後には、現在の懸案も影響している。EUは12月5日、イーロン・マスクが所有するソーシャルメディア・プラットフォーム「X」が、認証済みアカウントの青いチェックマークを「欺瞞的なデザイン」と呼ぶなど、EUの透明性規則に違反したとして、1億4000万ドルの罰金を科すと発表した。罰金に関する噂が4日に流れると、ヴァンス副大統領はEUを批判し、EUは「ゴミのことで米企業を攻撃するのではなく、言論の自由を支援すべきだ」とXに書き込んだ。もちろん、マスクは怒り狂い、「EUは廃止され、主権は各国に返還されるべきである。そうすることで、各国政府は自国民をより良く代表できるようになる」と投稿した。
米国は極右政党を支持
さらに、「戦略」は、「欧州の大多数は平和を望んでいるが、その願望は政策に反映されていない。その主な理由は、それらの政府が民主的プロセスを妨害していることにある」と指摘している。これをわかりやすく別言すると、政府がマスメディアによるウクライナ戦争の報道を歪めているために、ゼレンスキー政権の腐敗のひどさ、戦況の悪化、兵員不足、強制動員による暴力、電力不足、暖房供給の停止、インフレ悪化、経済不振といった現実が報道されず、その結果、あくまでウクライナ支援を継続し、代理戦争をつづけさせようとしている非道な政策が是正されないままになっている。ゆえに、いつまでも平和が訪れないのである。
そのため、「戦略」は、「我々の目標は、欧州が現在の軌道を修正する手助けをすることである」と書いている。政治だけでなく文化も含めた軌道修正を欧州に臆面もなく求めているのだ。半面、「戦略」は、「米国の外交は、真の民主主義、表現の自由、そして欧州諸国の個性的特徴と歴史を臆することなく称賛する姿勢を今後も堅持すべきである」としている。そのために、「米国は欧州の政治的同盟国に対し、この精神の復興を推進するよう促しており、愛国的な欧州政党の影響力拡大はたしかに大きな楽観材料となっている」という
「ニューヨークタイムズ」によれば、「愛国的な欧州政党」は「欧州の極右運動」を意味している。つまり、トランプ政権は極右政党を支持し、その影響力の拡大こそ、米国の楽観的な見方につながるというのである。
その証拠に、「戦略」は「我々の欧州に対する包括的政策」において優先すべき複数の事項の一つとして、「欧州諸国における欧州の現状の進路への抵抗の醸成」という項目がはっきりと挙げられている。
さらに、「北大西洋条約機構(NATO)が恒久的に拡大する同盟であるという認識を終わらせ、その現実を防ぐこと」という項目もある。これは、ロシアが懸念してきたNATOの東方拡大という、これまで長くつづいてきた米国の外交戦略を明確に否定するものだ。そして、ウクライナの希望するNATO加盟が少なくともトランプ政権下ではありえないことを明示している。
加えて、「長期的には、遅くとも数十年以内に、特定のNATO加盟国が、非欧州系住民が過半数を占めるようになる可能性は十分にある」という記述もある。移民の急増がトランプの前提とする白人キリスト教徒による国家支配をなし崩しにすれば、「そうした国々が自らの国際的立場や米国との同盟関係を、NATO憲章に署名した国々と同じように捉えるかどうかは未解決の問題である」とまで書いている点にも留意しなければならない。
コケにされた欧州
これだけコケにされた以上、欧州の政治指導者の反応が気にかかるところだ。12月6日付のブルームバーグは、「欧州、米国との分裂回避に向けもっとも困難な局面を迎える」というタイトルの記事を公表した。あるいは、Foreign Policyは、「欧州がロシア・ウクライナ戦争と大陸の安全保障に関して、最良の場合でも孤立していることを認識すべき時機はとっくに過ぎている。最悪の場合、欧州は今や二つの敵対勢力に直面している。東にはロシア、西にはトランプのアメリカが存在するのだ」と書き、欧州の政治指導者の能天気さを嘲笑している。
それにもかかわらず、欧州の政治指導者たちは、トランプの怒りを恐れて、いまのところ目立った反発は示していない。それどころか、相変わらず迎合的な姿勢を示している。EUの外交政策責任者であるカヤ・カラスは、トランプ政権による欧州への厳しい評価を軽視し、その批判の一部は事実であるとさえ示唆している、とPoliticoは報じている。「たとえば、欧州はロシアに対して自分たちの力を過小評価している」と、外交官などの国際的なリーダーが集まるドーハ・フォーラムのパネルに出席したカラスは語り、「我々はもっと自信を持つべきだ」と、「戦略」に同調するような姿勢をみせたのだ。
本稿執筆時点の12月8日午後1時時点で言えば、マクロンがXにおいて、「月曜日(12月8日)にロンドンへ赴き、ウクライナ大統領、英国首相、ドイツ首相と会談し、米国仲介の枠組みにおける現状と進行中の交渉について検討する」と書いた程度である。
一つだけ、「似非学者」の反応を紹介しておきたい。全体主義とロシア研究の著名な学者で、イェール大学歴史学部教授のティモシー・D・スナイダーは、「戦略」が「露骨なロシアのプロパガンダ」と類似しているとのべた、とNYTが報じている。スナイダーは、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』(26~27頁)に書いたように、まったく出鱈目な学者にすぎない。重要なのは、トランプ政権がこれまでのリベラルデモクラシーを基軸とする米国の外交戦略を真っ向から否定したことであり、それがいまでもリベラルデモクラシー外交を信じている欧州の政治家をコケにする理由となっている点なのだ。そこには、ロシアは関係ない。
私は、拙著『帝国主義アメリカの野望』において、その副題「リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ」が示すように、リベラルデモクラシーおよびそれに基づく米国の外交戦略を厳しく批判した。そのうえで、リベラルデモクラシーを批判するトランプ政権を積極的に評価する拙著『ネオ・トランプ革命の深層』を上梓した。関心のある読者はこの2冊を読んでほしい。
ここでは、トランプ政権による「戦略」の内容が、これまでリベラルデモクラシーを信奉し、その裏面に気づかないままリベラルデモクラシーをいまでも盲従している人々に鉄槌を下すものであると指摘しておきたい
もちろん、トランプらしい唯我独尊的な記述に満ちているし、宣教師的で鼻につく表現も多い。だが、リベラルデモクラシーが間違っていることに気づく必要があると思う。
今回の考察の最後に、拙著『ネオ・トランプ革命の深層』の第八章の出だしの部分を引用しておこう(266~267頁)。関心のある読者には必読の作品だ。
「ネオ・トランプ革命は、リベラルデモクラシーという「仮面」を剥ぐことにも貢献している。岡倉天心記念賞を受賞した拙著『帝国主義アメリカの野望』の副題は「リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ」であり、ネオ・トランプ革命は私の持論を強く支持してくれているように思われる。私の最初の問題意識は2014年に刊行した拙著『ウクライナ・ゲート』の「注」に書いておいた。もう10年以上前から、こんなことを考えている私だが、このリベラルデモクラシーを批判するのは、そう簡単ではない。
かつて、ベルリンの壁崩壊の数カ月前の1989年、元米国国務省政策企画局次長のフランシス・フクヤマは、その時流を先取りして「歴史の終わり?」という論文を発表し、1992年になって、The End of History and the Last Man(邦訳題「歴史の終わり」渡部昇一訳、三笠書房)を刊行したことを覚えているだろうか。その原著の45頁に、「つまり、勝利を収めているのはリベラルな実践というよりもリベラルな思想である。言い換えれば、世界の大部分において、リベラルデモクラシーに挑戦できるような普遍性を主張するイデオロギーは存在せず、人民主権以外の普遍的な正統性の原則もない」と書いている。
拙著では、252~267頁において、このリベラルデモクラシーを徹底的に批判している。ここでは、その内容を説明するだけの紙幅は残されていないが、トランプはこのリベラルデモクラシーを広げようとしてきた米国の外交戦略がイラク、シリア、ウクライナなどの大混乱を招いたことを知っている。だからこそ、その息の根を止めようとしているのだ。
私は、「力による平和」を唱えるトランプの立場を支持しない。だが、リベラルデモクラシーを批判するトランプの主張は正しいと思う。ところが、いまなお、リベラルデモクラシーの「大嘘」に気づかない人が多すぎる。そこで、まず、リベラルデモクラシーの支持者(リベラル派)の矛盾を暴くことからはじめなければならない。」
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)