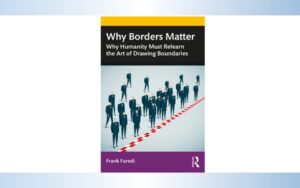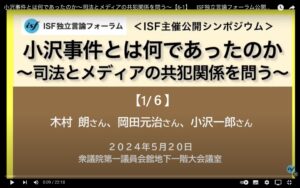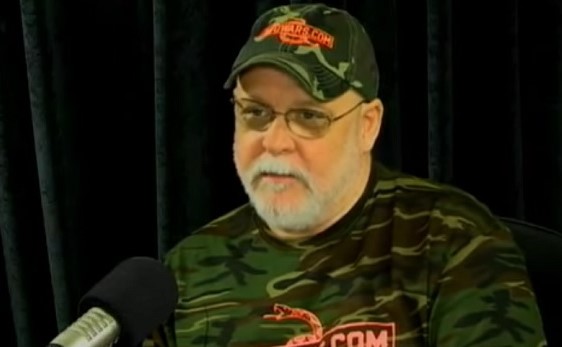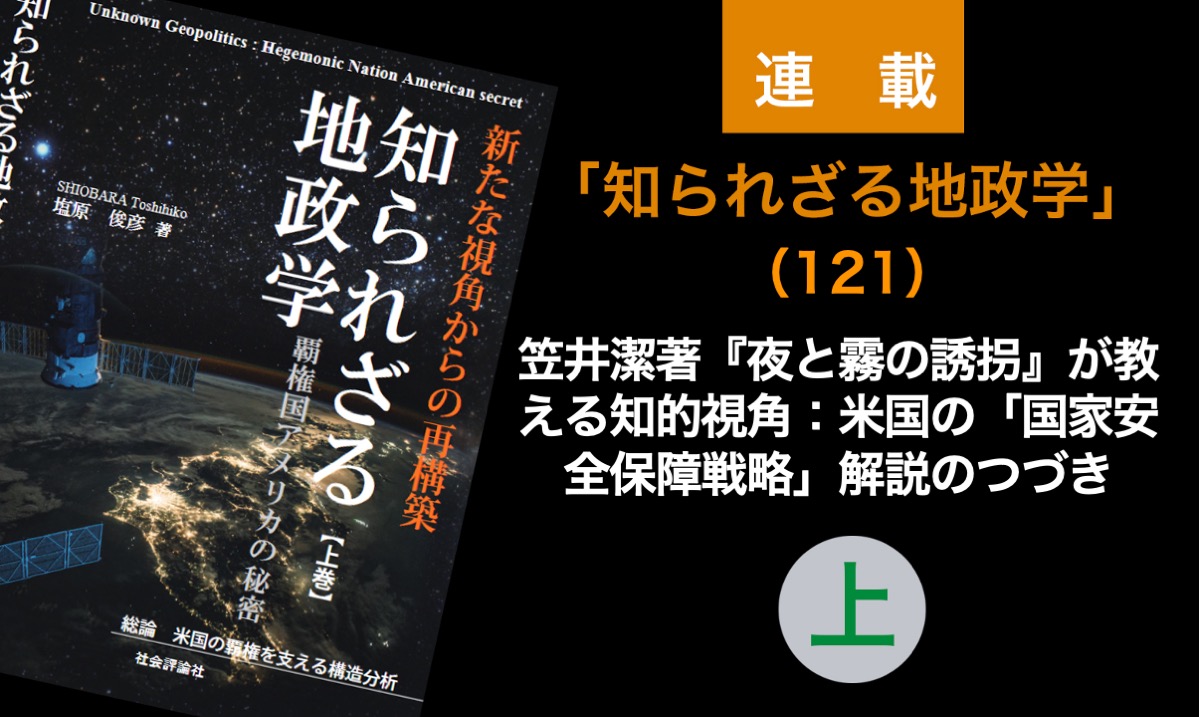
「知られざる地政学」連載(121):笠井潔著『夜と霧の誘拐』が教える知的視角:米国の「国家安全保障戦略」解説のつづき(上)
国際
今回は、連載(120)「アメリカの「国家安全保障戦略」を読み解く」のつづきとして、考えることの楽しさを披歴したい。「知」の醍醐味を味わってほしいのだ。それは、笠井潔著『夜と霧の誘拐』(2025年4月刊行、講談社)に触発されたものである。私は、笠井の書く「矢吹駆シリーズ」のファンであり、そのシリーズを、ラインマーカーを引きながらずっと読んできた。拙著『復讐としてのウクライナ戦争』では、第1章「ネオコンの復讐」の注(10)として、つぎのように記述しておいた(33頁)。

(出所)Amazon.co.jp: 夜と霧の誘拐 : 笠井 潔: 本
「笠井潔著『煉獄の時』では、ファシズムとボリシェヴィズムの類似点や相違点が分析されている。たとえば、「ボリシェヴィズムとナチズムはいずれも政治化されたニヒリズムの産物にすぎない」とある(326 頁)。スペイン戦争で強いられたボリシェヴィズムかナチズムかという選択肢をめぐるフィクションが小気味よく描かれている。「二つの悪のどちらかを選ばなければならない場合には、より小さい悪を選ぶしかない」という記述は私の心をいまでも離さない。この探偵小説は一読の価値がある。」
この記述は、拙稿「決定版! 28項目ウクライナ和平計画に込められたヴァンス副大統領の「怒り」」において、The Timeのジャーナリスト、ニール・ファーガソンの「最善は善の敵である」という警句の紹介につながっている。こうした「出会い」があるから、勉強は愉しい。そして、自分の思考の「深まり」を実感できる。
そんな私にとって、『夜と霧の誘拐』もまた、たくさんの知的刺激をもたらした。それは、地政学や地経学をより真っ当な学問へと引き上げるうえで、大いに役立ちそうなので、今回はこの本を参考に、歴史の流れに沿った地政学的視角とその醍醐味を示したい。
「唯一の被爆国」という歪んだ発想
矢吹駆(カケル)の発言から紹介したい(645頁)。
「小学生のときから、日本では『唯一の被爆国』という言葉を飽きるほど聞かされます。『唯一の被爆国として世界に平和を訴えなければならない』といった具合に。しかし僕は納得できませんでした。日本はアメリカと戦争をはじめて、あげくの果てに原爆を落とされた。この事実を持ち出すことで、反戦や平和をめぐる日本人の発言には特別な重さが与えられるというのは、どこかしら歪んだ発想ではないか」
この発言は、この小説の書き手ナディア・モガール(パリ警視庁警視の娘)とハンナ・カウフマン(アメリカ在住の哲学者、モデルはハンナ・アーレント)の前でなされた。書き手であるナディアはつぎのように記す。
「被爆して生き延びた広島市民や長崎市民が『唯一の被爆市民』というのなら、まだわからないでもない。しかし、原爆被災者でもない、その他大勢の日本人が自身の蒙った被害でもあるかのように「唯一の被爆国」の国民と称するのは僭越といわざるをえない。そんなふうに思ったというのだから、この日本人は理屈っぽくて変わった小学生だったようだ。」
その後、ハンナの発言を受けて、カケルはつぎのようにのべる。
「ナショナリズムの欺瞞に反撥したというよりも、『唯一の被爆国』という言葉に被害者のルサンチマンを感じたからです。被爆市民への加害者は明確ですね。ハーグ陸戦条約など戦時国際法を蹂躙する戦略爆撃の先例は、ドイツ軍のゲルニカ爆撃や日本軍の重慶爆撃ですが、原爆投下によって極大化したのはアメリカだった
占領下の日本では戦勝国の加害性や犯罪性を批判し告発することが禁じられていたため、アメリカによる外的な禁止は内面化され、その後も長く日本人自身を精神的に拘束し続けました。無意識化された拘束はきわめて強力で、今日にいたるまで戦後日本人は日本の占領が継続している事実、日本がアメリカの属国にすぎない事実を否認し続けることになる」
ここまで読んだとき、私の脳裏には、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』の第4章「復讐精神(ルサンチマン)をめぐって」に書いたさまざまな論点が浮かんだ(85~112頁)。さらに、柄谷行人著『憲法の無意識』も思い出された。おそらくこの2冊を読まなければ、このカケルの話を理解することはできないだろう。さらに、「無意識化された拘束はきわめて強力で、今日にいたるまで戦後日本人は日本の占領が継続している事実、日本がアメリカの属国にすぎない事実を否認し続けることになる」という指摘は、いまでも「現実」を語ろうとしないオールドメディアによる「洗脳」のために的確にあてはまる状況にある。
日本の平和主義的観念は倒錯的で病的な観念
話をつづけると、書き手のナディアはつぎのようにのべる。
「蒙った被害を加害者への同害で均衡化できないときに、ルサンチマンが生じるとカケルはいう。地上では主人に跪き続けるしかない奴隷の怨恨こそが、天上での救済の観念と禁欲主義的理想をもたらした。同じことで敵国に無条件降伏した国民の解消されえない集団的怨恨が、平和主義的理想を声高に語らせることになる。」
原爆被災を含めて被害の事実からは二つの態度が生じてくる。際限ない被害感情への耽溺が第一だ。失われた均衡を同害報復や、その置き換えとしての賠償によって回復しえない無力感から、被害の客観的なルサンチマンの鬱積に帰結する。」
この記述につづけて、カケルはつぎのように語る。
「キリスト教の禁欲主義的理想も戦後日本の平和主義的理想も、崩れた均衡を回復できないことから生じた倒錯的で病的な観念です。補足しておきたいのは、無力性が無力のままでは終わらないこと、倒錯的観念を経由することで暴力化しうることです。
被害者を掴んだ観念的暴力は、加害者への限定された暴力という同害報復の倫理的拘束など無視して、無制約的で無方向的な大爆発を惹き起こしかねません。奴隷の宗教だったキリスト教も帝国の宗教として権力を獲得するや、オリュンポスの神々を信仰する異教徒を迫害しはじめ、アレクサンドリアの図書館や文化遺産は容赦なく破壊されました。古代の異教徒迫害から中世末期の魔女狩りや異端派の弾圧にいたるまで、キリスト教が発揮してきた残忍な暴力の源泉は奴隷のルサンチマンにある」
このカケルの考えを日本の原爆被害に当てはめるとつぎのような記述になる。
「当事者にとって原爆の被害は言語に絶するし、かろうじて生き延びた被爆者も深刻な後遺症に悩まされてきた。それが悲惨であればあるほど、その他大勢の日本国民は被害者性を外に向けて発信できる。日本の侵略戦争はアジアと太平洋で二千万人ともいわれる膨大な犠牲者を出しています。日本人は1937年から1945年までに二千万のアジアと太平洋の人々を殺害した」
ここまでの説明は、「原爆被災を含めて被害の事実からは二つの態度が生じてくる」というなかの「際限ない被害感情への耽溺」という第一の態度だ。つぎに、第二の態度をみてみよう。カケルの発言を引用する。
「第二の態度は、被害体験をめぐる当事者の二重性とも関係します。原爆被災を生き延びた広島や長崎の被爆者が被害感情に耽溺しても、その他大勢の日本人が同じようにすることとは意味が違う。たとえば日本政府が『唯一の被爆国』の立場から語ろうとするとき、そこにあるのは原爆犠牲者や被爆者の存在を政治的な資産として有効利用し、戦争の加害責任を薄めようとする作為です。この作為は、その他大勢の日本人が加害責任の面積と自己慰撫のために、広島と長崎の死者を欺瞞的に活用する心理的詐術を超えて、被害の事実の狡猾な政治利用に他なりません」
この認識の上で、つぎのナディアの指摘は重要だ。
「もし日本政府が外交の場で、「唯一の被爆国」を政治的資産として利用するなら第二の態度の事例となるだろう。ただし対米従属的な保守勢力が政権を独占してきた日本は、「唯一の被爆国」を積極的に政治利用することがない。そうすればアメリカの加害責任を問題化する結果になるからだ。ただしアジア諸国による日本の侵略責任の追及と補償要求にたいしては、「唯一の被爆国」などの被害者意識に染められた国内世論を政治的な楯として活用できた。」
さらに、日本とドイツの違いを説明した、つぎのナディアの解説も興味深い。
「同じ第二次大戦の敗戦国でも、この点で日本とドイツは大きく異なっている。東プロイセンなど旧東方領土から追放されたドイツ系住民は、移動の過程で二百万もの病死者、餓死者、報復暴力による犠牲者を出した。しかし戦後ドイツ国家は東西とも、こうした自国民の被害を積極的に語ることはない、対外的にはむろんのことドイツ国内でも、アウシュヴィッツという絶対悪を前にしては、どれほど悲惨なドイツ民間人の戦争被害も、語るに値しない些末な問題にすぎないとされたからだ。」
アメリカの加害責任を問題化せず、被害者意識だけを声高に叫ぶ、オールドメディアによる「洗脳」はたしかに倒錯的観念を蓄積し、いずれ同害報復というかたちでアメリカへの核兵器使用として暴発しかねない。もちろん、その前段として、日本の核兵器保有という大問題もある(エマニュエル・トッドがいうように、核武装は比較的安価ですむし、絶大な抑止力を手にすることにつながる。韓国の核保有議論と並行して、日本でももっと深く議論すべき問題と言える)。
私が強調したいのは、これまでオールドメディアが隠蔽してきた事実に真正面から向き合わなければ、必ずしっぺ返しを受けるということだ。「唯一の被爆国」などの被害者意識に染められた国内世論は事実として存在するが、それでいいというわけではない。この一面的な見方を厳しく批判する言説を隠蔽するのではなく、白日の下にさらすことで、議論の俎上に載せなければ、いつかマグマが噴出する。それは、日航機墜落事件の隠蔽工作が不穏な結末をもたらすことになるのと同じだ。
あるいは、多数の圧力団体によって、発がん物質であり、認知機能低下にもかかわっているアルコール飲料へのCM規制や警告表示義務の見送りが日本国民の健康被害を拡大しつづけることで、その被害総額は膨大になるのと似ている。あるいは、いわゆる「押し紙」の独禁法違反状態の解消に加えて、再販禁止の見直し、新聞への軽減税率適用の廃止などの政策が採られないことで、オールドメディアはますます政権当局に迎合してしまう。それが、軍靴を近づけることにつながっている。
イスラエル国家の建設
つぎに、イスラエル国家の建設について紹介しよう。649頁において、「シオニズム運動で修正派の主張が勝利し、パレスチナ人の排除によるイスラエル国家の建設という方向が決まられたのは、どの時点だったといえますか」という、カケルのハンナへの質問が記されている。ハンナ・アーレントとおぼしき老婦人はつぎのように答える。
「1944年にアメリカのシオニストが、アトランティックシティで開催された年次総会で、ユダヤ人国家創設を決議したのが転換点でしょうね。世界シオニスト機構の最大支部は修正派の主張を受け入れ、その4年五にはイスラエルが建国された」
つまり、ヨーロッパのユダヤ人がアウシュヴィッツで大量虐殺されている、まさにそのときに、ナチの暴力から守られていたアメリカのユダヤ人がイスラエル建国を決定したのだ。こう考えると、本来であれば、イスラエル建国の正当性などまったくないようにみえる。
この点について、書き手ナディアはつぎのように記す。
「パレスチナの村々を破壊し抵抗する人々を虐殺し、多数のパレスチナ人を国外追放して建設されたイスラエル国家は、誕生のために行使した暴力をナチによるユダヤ人の大量虐殺の被害によって国際的に正当化した。しかし、これが事実に反していることは明らかだろう。アウシュヴィッツの実情が暴露される以前に、シオニストはユダヤ人国家の建設を決定していたのだから。」
これに対して、ハンナは反論するのだが、カケルはつぎのように厳しく話す。
「アウシュヴィッツの産物として被害感情の絶対化があるなら、本来それはナチとナチを支持したドイツ国民に向けられるべきですね。解消されることのない被害感情の鬱積は、癒されることのない憎悪をもたらします。やむをえないところがあるとしても、これもまた倒錯ですね。
この憎悪や攻撃性の標的をドイツ人から、アウシュヴィッツとは無関係であるパレスチナ人に詐欺的な仕方で振り向けようとした勢力が存在する。いうまでもありません、シオニストとイスラエル国家の指導者たちです。そうしたのはシオニストの利益のためですが、それによってユダヤ人による報復を回避しえたドイツは、イスラエルのいかなる要求も拒みえない立場に立たされた。どれほどの一方的な暴力と加害をイスラエルがパレスチナ人に加えようと、それを批判するなど問題外で、残虐な暴力行為をひたすら容認し支持し続けるしかない」
言論の自由を禁止しようとするドイツ
このようにみてくると、現在のガザ戦争に対する見方も、あるいは、ドイツにおける右傾化も、オールドメディアが語る視角とは異なる視角からみなければならないことに気づくのではないか。
ドイツは、ナチズムの二の舞を避けるという決意に導かれ、戦後憲法に憲法秩序を破壊することを目的とする政党の禁止を認める条項を盛り込んだ。ドイツの基本法と呼ばれる1949年の憲法は、政党が 「自由民主主義の基本秩序を損ない、廃止し、ドイツ連邦共和国の存立を危うくしようとする 」場合は違憲であると定めている。それ以来、1952年にナチスの後継政党が、東ドイツと西ドイツがまだ別々の国だった1956年に共産党が、それぞれ禁止されている。最近では、極右政党である国民民主党(NPD)を禁止しようとしたが失敗した。2003年には、党員名簿に国家の機密情報提供者が多数含まれていたため、そして2017年には、憲法裁判所が同党は政権奪取の真の脅威にはならないと判断するほど少数政党であったためである。
2025年12月6日付の「ワシントンポスト」の報道によると、いまになって、ドイツのフランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領は先月、水晶の夜(1938年のナチスによるユダヤ人虐殺)を記念する演説のなかで、「ドイツのための選択肢」(AfD)を名指しすることなく、「われわれの憲法は明確である。憲法に対して攻撃的な敵意の道を歩む政党は、常に禁止される可能性を考慮しなければならない」とのべた。しかし、これでは、ドイツという国家が言論の自由を蹂躙する、恐るべき言論統制国家である証になってしまう。まあ、事実として、自国が民主的で自由な国であると「洗脳」してきただけの話だ。そして、その洗脳は米国でも日本でも同じように行われてきた。しかし、その結果として、ルサンチマンの鬱積は重ねられつづけている。もう暴発は必然かもしれない。
「知られざる地政学」連載(121):笠井潔著『夜と霧の誘拐』が教える知的視角:米国の「国家安全保障戦略」解説のつづき(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)