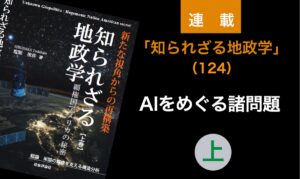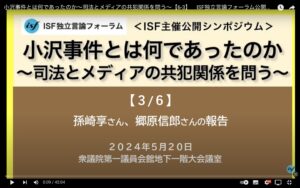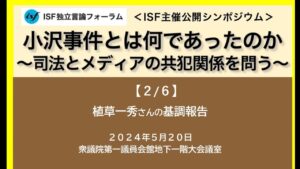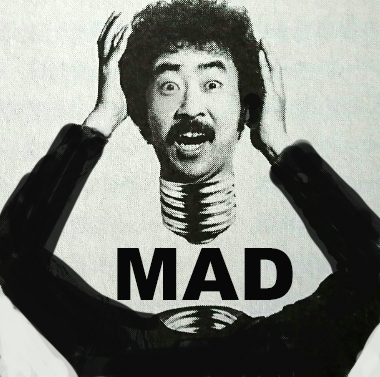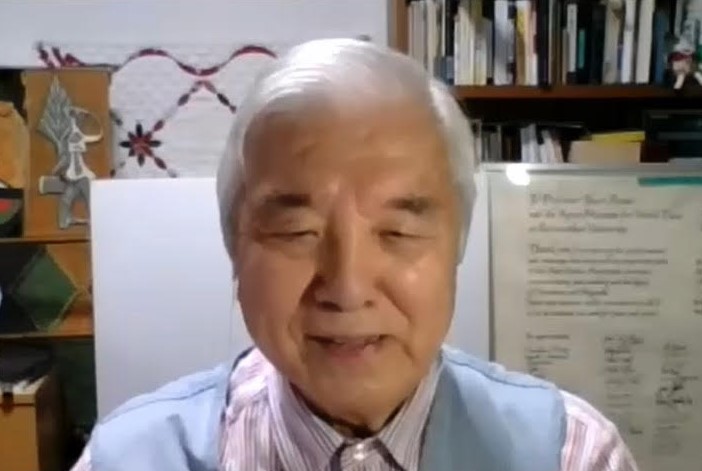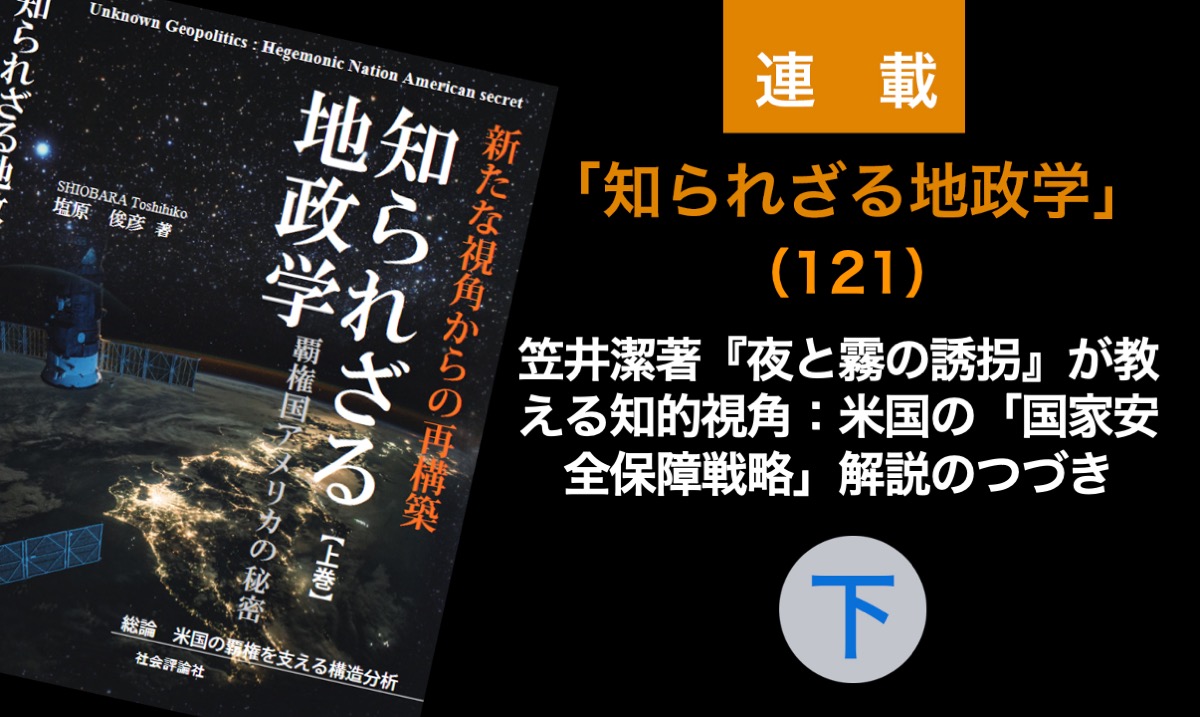
「知られざる地政学」連載(121):笠井潔著『夜と霧の誘拐』が教える知的視角:米国の「国家安全保障戦略」解説のつづき(下)
国際
「知られざる地政学」連載(121):笠井潔著『夜と霧の誘拐』が教える知的視角:米国の「国家安全保障戦略」解説のつづき(上)はこちら
カウフマン(アーレント)批判
つぎに、カケルによるカウフマン(アーレント)批判を紹介しよう。まず、書き手ナディアの地の文からはじめよう(652頁)。
「女や奴隷などの他者を暴力的に支配し、私的領域に閉じこめ、労働と清算を強制することで家長は生命維持という動物的必然性の重荷から解放される。そのようにして家長たちは、生殖の血と苦役の闇が淀んだ家(オイコス)の閉所から光に満ちた自由の政治空間であるポリスに、市民として参入するための条件を確保しえた。このような古代民主制を肯定し評価するカウフマンの議論の背景には、ユダヤ人が蒙ってきた差別と抑圧と虐殺の歴史があるのではないか。
第二次大戦後の良識的知識人は人権の観点から、奴隷の暴力的抑圧を前提とした古代民主制を手放しでは礼賛できない。後ろめたさから、それは時代的限界だとか改善されるべき欠陥だとか、さまざまに弁解しながら相対的に評価するのが限度だろう。」
この説明につづけて、カケルはつぎのように語る。
「こうした点での人権派のおよび腰は、自身が奴隷か奴隷に類する被抑圧者ではないことの結果です。けれどもカウフマンさんは違う。たとえ女や奴隷たちの犠牲の上にであろうと、言論によって卓越性が競われる場、自由な政治空間が存在したことを全面肯定し、あらゆる留保なしに礼賛します。どちらかといえば抑圧者の側にいる疚しさの意識から、良識的な知識人は女や奴隷への抑圧を見ないような発言はなしえない。どうしてカウフマンさんにはそれが可能だったのか」
さらにつづける。
「カウフマンさんの言葉には、欧米男性知識人の良識派や人権派を黙らせる力がある。しかし批判者が黒人奴隷やアメリカ先住民だったらどうでしょう。古代アテネの民主側と同じように、アメリカ革命による自由の創設を最大限に評価するカウフマンさんですが、前者が家(オイコス)の女と奴隷たちを排除していたように、後者は黒人奴隷と先住民を排除していた。つねに被害者だったと称するユダヤ人が横からなんといおうと、黒人奴隷や先住民は自分たちを排除することなしには存立しえない政治制度など、小指の先ほども肯定しないのでは」
どうして黒人奴隷や先住民排除が持ち出されたかというと、歴史的な連続性にある。絶対主義国家スペインが国内ではユダヤ人を追放し虐殺し、大西洋では先住民を奴隷化し虐殺した。その画期は1492年だ。宗教がそれを正当化した。大西洋の東と西での蛮行には、ユダヤ人もアメリカ先住民もキリスト教徒ではない、異教徒だという共通点がある。
ナディアの説明を紹介しよう(659頁)。
「虐待によって先住民の奴隷労働力が枯渇し、17世紀以降は西アフリカからアメリカに黒人奴隷が大量移送されるようになる。大西洋三角貿易による過剰利潤と膨大な資本蓄積から産業革命が開始され、19世紀にはイギリスの産業資本主義が世界を制覇するにいたった。これが近代世界の基本的な構造だとすれば、その二本の脚が反ユダヤ主義と植民地主義だった。」
ゆえに、「アメリカの個人問題とは植民地主義の遺産に他なりません」とカケルはいう。「とすればユダヤ人の解放は黒人の解放と切り離せない」、とカケルは指摘する。
パクス・アメリカーナの構造
こうした理解のもとで、つぎのナディアの記述はわかりやすくなるだろう(661頁)。
「反ユダヤ主義と植民地主義への二つの解放闘争を分断することが、ヨーロッパによる16世紀以来の世界支配の最新版であるパクス・アメリカーナには不可欠だった。だからアラブ世界という旧植民地の中心部に、存続するにはアメリカに全面的に依存するしかない人工国家を埋めこむことにした。
世界最大の油田地帯を支配下に置くためにも、アメリカに保護された人工国家イスラエルには多大の利用価値がある。パレスチナやアラブ諸国がイスラエルと敵対し、双方が憎悪を募らせ続ける限りアメリカによる世界支配は安泰だ。」
ここで、2025年12月13日、ミュンヘンで開催されたキリスト教社会同盟の党大会で、フリードリッヒ・メルツ首相が「パクス・アメリカーナの数十年間は、欧州の我々にとっても、ドイツの我々にとっても、ほぼ終わりを告げた」と演説したことを紹介しておこう。ただし、メルツがここで紹介したパクス・アメリカーナを支えてきた反ユダヤ主義と植民地主義への二つの闘争の分断という話を理解しているとは思えない。彼は単に「何十年にもわたって欧州を支えてきた米国主導の安全保障体制がもはや当然とは考えられないという、米国の同盟国間の懸念の高まり」を意識しただけだ。
実際には、反ユダヤ主義が高まっているだけでなく、植民地主義への反発も盛り上がっている。ガザ戦争でハマス殲滅を名目とするパレスチナ人への攻撃は反ユダヤ主義を欧米諸国で勃興させているのはたしかだろう。鉱物資源の豊富なグリーンランドに対するドナルド・トランプ政権の主張や、石油埋蔵量に富むベネズエラへの攻撃は植民主義的であり、こうした動きへの反発も顕著になっている。つまり、メルツの想定する米国主導の安全保障体制だけが問題化しているわけでは決してない。
欧州の「三バカトリオ」
私が今回、『夜と霧の誘拐』を使って、この連載を書くことにした理由は、欧州の政治指導者を批判するためだ。地政学的な視点から、現在の世界情勢を分析するためには、矢吹駆が教えてくれた視角が不可欠と考える私は、ここまで、あえてこの探偵小説を紹介してきた。ここからは、英国のキア・スターマー首相、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、ドイツのフリードリッヒ・メルツ首相という「三バカトリオ」を中心に批判を展開したい(12月11日に「現代ビジネス」で公表した拙著「ついに暴かれた「腐敗で真っ黒」ゼレンスキー政権、それでも支持し続ける欧州3首脳の私利私欲」を読んでもらえれば、そこでも「三バカトリオ」を批判しておいた)。
この三人に、ウルズラ・ゲルトルート・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長を加えた四人が欧州と欧州連合(EU)を主導している。彼らはいずれも欺瞞に満ちている。実に興味深いのは、The Economistが12月11日付で「欧州のポピュリスト右派を誰が止められるのか? 主流派政治家による終末論的な警告は失敗に終わる運命にある」という記事を公表したことだ。この記事の「三バカトリオ」批判は基本的に正しい。
まず記事は、ポピュリスト右派へのナチズム再来やヒトラー回帰といった批判が自分たちの失敗から注意を逸らそうとしているように思えると批判している。英国では、保守党政権下で14年間停滞した後、キーア卿率いる労働党政権は福祉への支出を増やし、急速な成長が見込めないにもかかわらず、記録的な税金を課そうとしている。フランスでは、マクロン大統領が3年間で5人目の首相を任命したが、国民年金の受給年齢を引き上げる法律が頓挫した。ドイツではメルツ首相が打ち出した「改革の秋」の計画は、ほとんど空振りに終わった。こうした自ら招いた失政にもかかわらず、ポピュリスト右派だけを批判してみても、誠実さがまったく感じられない。
第二に、彼らの脅しが信用できないからだ。危険なポピュリスト右派政権もあれば、そうでない政権もある。ジョルジャ・メローニは従来の政治家と同じようにイタリアを運営してきた。英国の「リフォームUK」議員は今のところいたって普通だ。確かに、ヴィクトール・オルバン党はハンガリーの諸制度を掌握し、搾取してきたが、すぐに追い出されるかもしれない。
こうして、The Economistは、「膨大な数の欧州有権者は、伝えられていることを単純に信じていないのだ」と書く。一方、権力の盛衰に敏感なエリート層は、かつて敬遠していたポピュリストたちに近づきはじめている。国民連合のジョルダン・バルデラは、フランスのビジネスリーダーたちと密かに会談を重ねている。英国では、保守党の政治家たちが「リフォームUK」に離党し、ナイジェル・ファラージに切実に必要とされていた立法および閣僚としての経験をもたらしている。ドイツにおいてだけ、主流派によって「ドイツの選択肢」(AfD)との協力が排除されている。議会で第2位の勢力であるAfDの議員たちは、連邦議会の副議長職すら禁じられている。
こうした事情が、ポピュリスト右派を悪魔化しようという戦略が自滅的である理由を説明している。主流派政治家は寛容と労働者階級を守ると言いながら、有権者の大半を偏狭な人間だと決めつけることで、自ら不寛容で独善的に映ってしまう。そして、「ポピュリズムが自らの理想とする欧州像を破壊すると警告すれば、現状を打破したいと切望する有権者をかえって奮起させるのだ」、とThe Economistは指摘する。
The Economistの推奨する対策は、「ポピュリストが欧州を安逸から揺り動かす可能性を精査することだ」。ポピュリストが政策変更に前向きなら対話で悪政を改善できるし、拒否すれば彼らの愚かさを露呈させるという。
不誠実な欧州の政治指導者たち
だが、「三バカトリオ」や「四バカカルテット」はまったく信頼できない。彼らは不誠実だからだ。たとえば、2025年9月、トランプはイスラエルとハマス間のガザ戦争を終結させることを目的とした和平案を突然発表した。欧州の外交官たちは、あまりにイスラエル寄りであり、論理的に実行不可能であると内々に評していた。それにもかかわらず、欧州の外交官たちは、この案を破棄するどころか、受け入れた(NYTを参照)。それどころか、スターマーはすぐに声明を発表し、米国の提案は「大歓迎であり、トランプ大統領のリーダーシップに感謝する」とのべたのである。
彼らはユダヤ人問題にも、あるいは移民という「奴隷」問題にも、真正面から向き合うことができないまま、反ユダヤ主義と植民地主義への二つの解放闘争を分断するという、これまでのパクス・アメリカーナを支えたアプローチに逆らえないでいる。といっても、彼らはこの問題にどこまで自覚的であるか、よくわからない。何しろ、彼らの低能さや不誠実さのために、彼らの真意が見えないのだ。
彼らの不誠実は対ロ制裁についてもよく現れている。EUはロシア産天然ガスの輸入を大幅に削減し、12月3日には2027年9月までに輸入を完全に停止することを決めた。しかしEUは依然として天然ガスから製造されるロシア産肥料を購入しており、一部の品種ではロシアのウクライナ全面侵攻以前よりも多くの量を輸入している。The Economistは、「肥料はクレムリンにとってエネルギーほど収益性の高い輸出品ではないが、欧州の食料安全保障を敵国に依存させる結果となっている」と指摘している。だが、この事実を知っているEU加盟国の国民は何人いるだろうか。要するに、「三バカトリオ」はかたちばかり対ロ制裁をしているだけで、ロシアからの肥料輸入禁止に猛反対する欧州農民の反発に耐えるだけの毅然たる姿勢がないのだ。その結果、表面上だけ対ロ制裁を装い、不勉強でマヌケなオールドメディアに報道させているのである。
すでに何度か指摘したように、対ロ制裁としてロシア産原油の輸入を禁止してきたEUだが、その原油をガソリンなどの石油製品に精製したものをインドから大量に輸入しているのがいまの欧州諸国の状況だ。こんな「現実」を知ると、彼らはいったい何のために対ロ制裁なるものを科しているのか、私には理解できない。不誠実な彼らの行動は、普通の人々の倒錯的観念を強めるだけではないか。
Spiegelのひどさ
ディスインフォメーション(騙す意図をもった不正確な情報)を広めるオールドメディアの代表格はドイツの「シュピーゲル」(Spiegel)だろう。たとえば、下に示したように、同誌は、12月12日発売の新刊の表紙にロシアとアメリカの大統領ウラジーミル・プーチンとドナルド・トランプを起用した。イラストでは、プーチンはヨーロッパにナイフを突きつけており、トランプはロシア大統領の隣に立って彼の肩に手を置いている。こんな報道しかできないオールドメディアによって、ドイツの人々は騙されている。あるいはすでに、こんな報道しかしないSpiegelなどは最初から相手にされていないのかもしれないが。
そもそも、ウクライナ問題をこんな構図でとらえてはならない。問題なのは、米国の数十年にわたる外交戦略がリベラルデモクラシーに基づく、ナショナリズムを利用した民主主義の輸出を優先してきたことにある。それを改めようとするトランプはむしろ評価すべき政策をとろうとしている。だからこそ、連載(120)で解説したトランプ政権による「国家安全保障戦略」はきわめて真っ当なものなのだ。もちろん、「宣教師的」であるにしても。

2025年12月12日付のSpiegelの表紙
(出所)https://www.rbc.ru/politics/12/12/2025/693b2c909a7947114e70af41?from=from_main_6
性懲りもなく「洗脳」をつづける「悪い奴ら」
ここで紹介したような「世界観」からみると、オールドメディアは相変わらずリベラルデモクラシーを前提とする第二次大戦後、数十年にわたって支配的だった視角にとらわれていることがわかる。こうした視角が倒錯的でいびつなものであることに気づいていないのだ。その結果、古い価値観をバックに、いまでも性懲りもなく「洗脳」をつづける「悪い奴ら」が目立つことに気づくだろう。
シオニズムの匂いのするピューリッツァー賞を3度受賞した、トマス・フリードマンという、「ニューヨークタイムズ」の外交問題担当オピニオンコラムニストは12月6日、「プーチンが笛のように操るアメリカの「役に立つ愚か者たち」」という意見を公表した。
そのなかで、このユダヤ系米国人は、つぎのように記す。
「まず第一に、ウラジーミル・プーチンがウクライナで不動産事業を行っていると言えるかもしれない。しかしそれはトランプやウィトコフ、クシュナーが事業を行ってきた方法とは異なる。プーチンがウクライナで不動産事業を行っているのは、ヒトラーがポーランドで不動産事業を行っていたのと同じ方法だ。ヒトラーが領土を欲したのは、ホテルや住宅を建設して利益を得て地元住民に恩恵をもたらすためではない。彼はむしろ、国家主義的な幻想を実現するために不動産を欲したのだ。プーチンも同様である。彼はウクライナ国民の福祉には全く関心を示していない。」
そもそも、こうした記述はプーチンとヒトラーを類比的に捉えようとする悪意に満ちている。この悪意は、「戦争をはじめたのはロシアではなくウクライナであり、非合法な独裁者はロシアではなくウクライナの指導者だと露骨に嘘をついた」というトランプ批判につながっている。
本当は、ウクライナ戦争がいつからはじまったと考えるかで、戦争をはじめた国は異なってくる。2014年2月のバラク・オバマ政権下でのクーデターから紛争がはじまったとみなせば、このクーデターを主導したウクライナの過激なナショナリストおよびその支援国米国が紛争開始の首謀者となる。2022年2月24日にはじまったロシアによるウクライナへの全面侵攻が戦争のはじまりと考えれば、それはプーチン主導で勃発したと言えるだろう。
注目に値するトランプ大統領インタビュー
ここで、12月8日に行われた、トランプのPoliticoとのインタビューを紹介しなければならない。そこで、ウクライナにおける紛争のはじまりについて、トランプは、「この対立が本当にはじまったのはいつだと思う?何年もくすぶっていたが、オバマがクリミアを諦めたときが大きな分岐点だったんだ」と語っている。つまり、2014年の紛争こそ、いまの戦争のはじまりと、トランプは考えていることになる。そうなると、その責任はロシアよりも、クーデターを支援し、クリミアを諦めさせたオバマにあるとみなしていることになる。もちろん、当時、ウクライナを担当していたジョー・バイデン副大統領の責任はきわめて重い。
それにもかかわらず、「クリミアを返せ」というウォロディミル・ゼレンスキー大統領に対して、トランプは怒っている。同じインタビューのなかで、つぎのように話した。
「あのね、ゼレンスキーが初めてプーチンと会ったとき、彼はこう言ったんだ。「二つの要求がある。クリミアを返せ。そして我々はNATOに加盟する」と。しかも彼はそれを非常に丁寧な言い方で言ったわけでもない。」
この発言のあとに、ゼレンスキーについて、トランプは、「彼は…彼は天才的なセールスマンだ。私は彼をP.T.バーナムと呼んでいる。P.T.バーナムが誰か知っているだろう?」とのべた。バーナムとは、巡回サーカスの主催者テイラー・バーナムのことで、米国ではショービジネスではなく詐欺師として知られる人物である。だからこそ、トランプは、つぎのようにつづけた。
「地球上で最も偉大な人物の一人だ。彼はどんな商品でもいつでも売れた。それが彼の口癖だった、「俺はどんな商品でもいつでも売れる」と。それは真実だった。彼は言った、「それが機能するかどうかなんて関係ない」と。でも彼はP.T.バーナムですよ。あの…あの…不正なジョー・バイデンに3500億ドルも引き出させたんだ。その結果が…見ろよ。自国の約25%が消え失せた。」
トランプは、ゼレンスキーを詐欺師呼ばわりしていることになる。私の場合、ゼレンスキーを「非合法な独裁者」とみなしている。これについては、拙著「ついに暴かれた「腐敗で真っ黒」ゼレンスキー政権、それでも支持し続ける欧州3首脳の私利私欲」を読んでもらえればわかるだろう。ゼレンスキーによる恐怖政治は「非合法な独裁者」を髣髴とさせるのだ。
優れた探偵小説を読むことで、さまざまな視角からの考察が可能となる。多少なりとも、「知」の醍醐味を味わってもらえただろうか。まだ書き残した論点もあるので、そのうち、『夜と霧の誘拐』を題材にした別の論考を書きたいと考えている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)