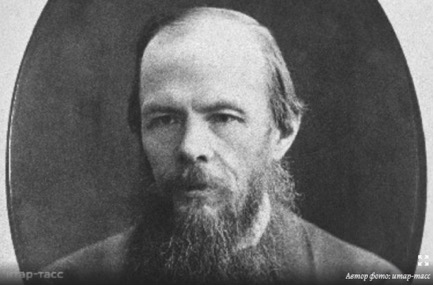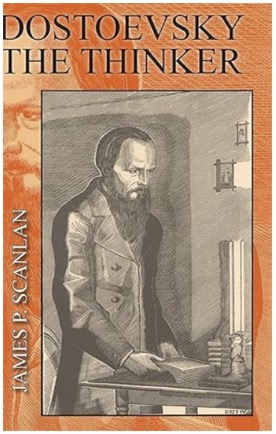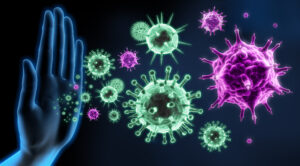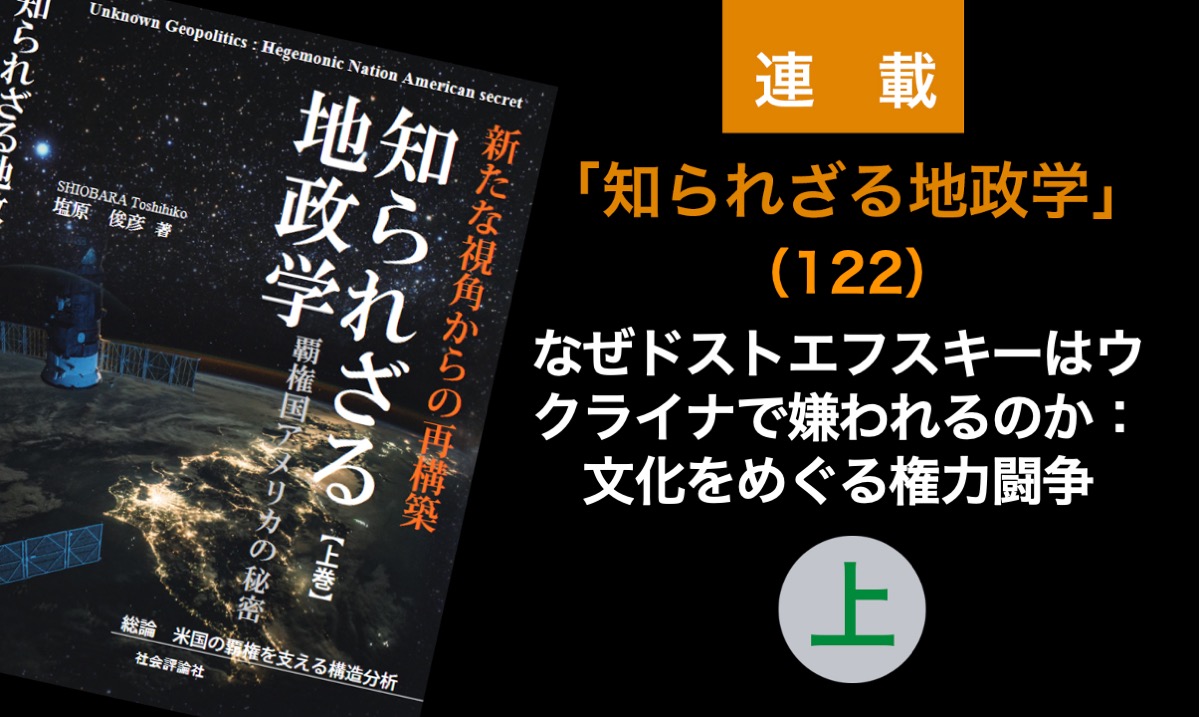
「知られざる地政学」連載(122):なぜドストエフスキーはウクライナで嫌われるのか:文化をめぐる権力闘争(上)
国際今回は、年末年始の読み物として、ドストエフスキーを取り上げたい。この考察に要した時間はほぼ3カ月であり、文豪ドストエフスキーへのオマージュを前提にしている。
フランス人作家兼映画監督エマニュエル・カレール(下の写真)という人物がいる。母は歴史学者エレーヌ・カレール・ダンコースだ(改題増補新版『崩壊したソ連帝国 ― 諸民族の反乱』くらいしか読んだことはないが)。その彼について書かれた記事「著名なフランス人作家はロシアを愛した。戦争が清算を迫った」が2025年11月3日付で「ニューヨークタイムズ」に公表された。それによると、彼はウクライナを訪問し、2023年末にウクライナの哲学者ヴォロディミル・エルモレンコと共に前線都市ヘルソンとハリキウを訪れ、道中、彼らはロシア文化を排除しモスクワの影響から脱却しようとするウクライナの取り組みについて長時間にわたり議論を交わした、と書かれている。そのうえで、記事はつぎのように書いている。
「この経験はカレール氏を不安にさせた。しかし彼は、この経験がウクライナ人の「目を通して物事を見る」助けとなり、反西洋的で民族主義的な傾向をもつドストエフスキー(下の写真)が現地で嫌われる理由を理解する一助となったと語った。それでも彼は、戦争が終わった時、その清算がより冷静なものになることを望んでいる。」
残念ながら、この記事には「反西洋的で民族主義的な傾向をもつドストエフスキーが現地で嫌われる理由」について何も書かれてはいない。そこで今回は、この「反西洋的で民族主義的な傾向をもつドストエフスキーが現地で嫌われる理由」について論じることにしたい。地政学は、いわば「ソフトパワー」にも深くかかわっているから、ドストエフスキーへの理解を通して、ロシアとウクライナとの間の文化的相克について考えれば、ソフトパワーにおける権力関係の考察が可能となると考えたからである。
なお、私がカレールの見識にこだわるのは、彼が「悪の問題」を提示しつづけてきたからである。「悪」を見つめつづけたドストエフスキーと似ていると言えるかもしれない。だからこそ、二人の姿勢は「腐敗」について20年以上考えてきた私の琴線に触れるのだ。
Emmanuel Carrère Credit…Gueorgui Pinkhassov/Magnum, for The New York Times
(出所)https://www.nytimes.com/2017/03/02/magazine/how-emmanuel-carrere-reinvented-nonfiction.html
https://www.youtube.com/watch?v=ncPW2pyOzJU
フョードル・ドストエフスキー
(出所)https://www.dp.ru/a/2013/11/21/Kak_Putin_s_Dostoevskim_r
政治利用されるドストエフスキー
ドストエフスキーがウクライナで嫌われる理由について考えると、すぐに思いつくのは、ウラジーミル・プーチン大統領によるドストエフスキーの政治利用の話だろう。その結果として、ウクライナ国民はプーチンに利用されてきたドストエフスキーそのものに嫌悪感をいだくようになったと考えられる。
たとえば、プーチンは2024年2月に行われた、タッカー・カールソンとの2時間以上におよぶインタビュー(下の写真)で、「西欧で非常に著名なドストエフスキー、ロシア文化の天才、ロシア文学はこれについて、ロシアの魂について多くを語っている」とのべ、ドストエフスキーの周辺にプーチン自身、あるいはロシア政府の主張を位置づけた。なお、「これ」とは、文脈から「心の問題としての宗教」を指しているように思われる。
ただ、この程度の話では、プーチンがドストエフスキーの主張を露骨に政治利用しているようには思えない。たとえば、2019年7月、ローマ教皇フランシスコに会ったプーチンは、教皇に引用許可を得たうえで、「私は(ローマ教皇は) 『ドストエフスキーの著作を読まず、その哲学の深みを理解しなければ、真の司祭にはなれない』と司祭たちに語っている」とのべたという話がある(RBCを参照)。これも、ドストエフスキーの精神性の高さが評価されている事実を示すだけで、ドストエフスキーの政治利用とまでは言えまい。
タッカー・カールソンによるウラジーミル・プーチン大統領へのインタビュー
(出所)https://www.rev.com/transcripts/tucker-carlson-interviews-vladimir-putin-transcript
ただ、2022年10月、世界中の学者やジャーナリストが所属するヴァルダイクラブの総会での演説で、ナチスは本を燃やしたが、西側諸国は現在、ドストエフスキーやチャイコフスキーの作品を禁止するまでに堕落している、とプーチンはのべた。この際、彼はドストエフスキーの『悪霊』を引用した(「VESTI」を参照)。その登場人物であるニヒリスト、シガレフの「無限の自由から抜け出すと、私は無限の専制政治に陥ってしまう」という言葉を紹介して、西側諸国はまさにこの状態に陥っていると語ったのだ。これは、多少なりとも、ドストエフスキーの権威を政治利用したものと言えるかもしれない。
ウクライナ側の過剰反応
プーチンが直接、ドストエフスキーを政治利用したことを裏づける証拠を見つけるのは難しい。むしろ、ウクライナ側の政治的過剰反応がロシア文学の排除に動き、それがドストエフスキーへの嫌悪をもたらしているようにみえる。
2023年2月のロイター電によると、ウクライナは2022年11月までに、ソ連時代に発行されたか、ロシア語で書かれた、書籍約1900万冊を図書館から撤去した。1900万冊のうち1100万冊がロシア語書籍であった。すでに同年6月の段階で、文化情報政策省はすべての公共図書館に対して、現代ロシア文学、とりわけ侵略国家の政策を支持したとして制裁が課せられた作家や出版社の作品を棚から撤去するよう勧告を発出したという(ウクライナの情報を参照)。同じころ、「ロシアとベラルーシの作家はすべて、6年生から11年生までの学校の カリキュラムから外され 、ゴーゴリとクリミア・タタールのカリロフは、外国文学ではなく、ウクライナ文学の授業で教えられることになるかもしれない」という記事まであった。2024年3月に公開された「ル・モンド」の記事「プーシキンもドストエフスキーもトルストイももうない:ウクライナの図書館が書架を一掃」では、「ロシア人作家の書籍は、2022年の侵攻以降、ウクライナのほとんどの図書館の書棚から姿を消した。司書たちはこの決定を軽々しく下しているのではなく、むしろ愛国心から行っている」と書かれている。侵攻やロシアの優越性を支持する作家の作品を棚から撤去するよう公式の指示を受けた結果でもある。
気になる過剰反応
これらは、バカげた過剰反応にしか思えない。ただ、戦争とはこういうものだ。その昔、日本でも同じようなことがあった。ウクライナの場合、ジャーナリストという肩書のテティアナ・オガルコワと哲学者ウォロディミル・イェルモレンコがドストエフスキーの『罪と罰』の視点からロシアのウクライナ侵攻について議論した記事を読むと、あきれ果てる。
オガルコワはつぎのように話している。
「主人公のラスコーリニコフは二人の婦人を殺し、最後に捕らえられるが、ラスコーリニコフには何の描写も裁きもなく、本当の罰もない。ロシア文化における刑罰の不在と、この戦争で私たちが目にしていること、ロシアがウクライナに対して暴力やミサイルや何でも使うことができるため、私たちは不公平を目の当たりにしている。ロシアの文化には、この不処罰について非常に深いものがある。不処罰はロシア文化に非常に適したものだ。ロシア文学やドストエフスキーの中にも、その関連性があると我々は考えている。」
こうした飛躍した議論を大真面目に披歴する人を憐れむしかないのか。この発言に関連して、イェルモレンコは、「犯罪と罰のつながりを断ち切るこの傾向は、ロシア文化において豊かな歴史をもつため、非常に重要な兆候の一つなのだ」と言っている。そのうえで、「たとえば、スターリン主義の作家たちが、スターリン主義的抑圧の象徴である収容所(gulag)の建設をいかに正当化したかである」と話すのだが、どうにもウクライナ国民にとって都合のいい部分を針小棒大に拡大して議論しているだけのように思えてくる。どうにも情けないのである。
「反西洋的で民族主義的な傾向をもつドストエフスキー」は本当か
「反西洋的で民族主義的な傾向をもつドストエフスキー」というのが真実であれば、とくにウクライナ国民がドストエフスキーを嫌う理由になりうる。ただ、その前に、ドストエフスキーが生きたロシア帝国内の時代精神のようなものを知っておく必要がある。
2025年は、1825年12月に起きたデカブリストの乱からちょうど200年になる。ドストエフスキーは1821年生まれだから、この反乱の前に生を受けていた。おそらく彼の成長過程とこの乱以降のロシア帝国の変遷は関係があるに違いない。そこで、デカブリストの乱にまつわる話をごく簡単に書いておこう。
単線的に書けば、デカブリストは「最初のロシア革命家」とみなされ、ロシア帝政に対する内部対立のプロセスを開始し、その後、「デカブリストがゲルツェンを目覚めさせた」とされる。つまり、農奴解放令実現に影響を与えた「社会主義の父」アレクサンドル・ゲルツェンを喚起させ、彼につづく他の革命家たちによって継承され、最終的には「バトン」がボリシェヴィキに渡されるという、ソ連が植えつけた文脈のなかで理解されることが多い。あるいは、「デカブリストの妻たち」を通じて、並外れた忠誠心、愛情、愛する人のために苦難を厭わない姿勢を象徴する、ロシア女性のたくましさの輝かしい見本というイメージを広めた。おそらく、プーシキンが1826年12月末から1827年1月初めにかけて紡いだ有名な詩を、1827年1月初めにモスクワから流刑地の夫のもとへ旅立つ、流刑に処されたデカブリストのA・G・ムラヴィエワに託したことで、その詩にある「足枷ははずれるだろう、牢獄は崩れ落ちる――そして自由が入口で喜んであなたを迎え、兄弟たちが剣をあなたに渡すだろう」という言葉が革命家たちを勇気づけた(注1)。
いわゆる「土壌主義」をめぐって
こうした短絡的な見方を支持するわけではないが、おそらくドストエフスキーはこうした時代精神のなかで育ち、そして思考した。ゆえに、以下の記述においては、ジェームズ・スキャンラン著『思想家ドストエフスキー』(2002年)(下の写真)を参考にする。
(出所)Amazon | Dostoevsky the Thinker: A Philosophical Study | Scanlan, James P. | Modern
そこでは、有名なドストエフスキーのいわゆる「土壌主義」が解説されている。1860年にサンクトペテルブルクで文筆活動を再開すると、ドストエフスキーは弟ミハイルと共同創刊した雑誌『ヴレーミャ』(時代)において、普遍的人間的特性に対抗する国民的特性の重要性を主張する準スラヴ主義的教義を主張する。それは、ロシア語で「土壌」(почва)を意味する「ポーチヴァ」に由来する、「ポーチヴェニチェストヴォ」(почвенничество)、すなわち「土壌主義」運動と呼ばれるようになる。
スキャンランによれば(201頁)、ドストエフスキーが「土着主義」観の理論的基盤を明確にのべたのは、1862年の論文『二つの理論家陣営』における西洋主義批判のなかであった。もう一方の陣営は「スラヴ派」であり、彼らもまた同論文で批判の対象となった。西欧主義者たちは、人間の発展の多様性を無視し、民族的差異を抽象化し、個人を共通の特性に還元する「汎人類的理想」をあらゆる民族に押しつけようとしていると彼は主張した。以前の著作では、西欧主義者たちを「人間を擦り切れた15コペイカ硬貨に変えようとする」と非難していたが、「二つの陣営」では、この古びて刻印が消えた硬貨(特徴的な要素が擦り減った国家の象徴)という適切な比喩を再び用いて、個人の脱国家化に抗議した。
スキャンランは、ドストエフスキーが1849年に人間に発見していた「深い可塑性」に関連して、『二つの理論家陣営』において、その可塑性が、異なる背景や環境によって生み出される民族的多様性のなかに、いかに顕著にあらわれているかを強調している、と指摘した(注2)。さらに、ドストエフスキーは、あらゆる民族(ナロード)は、「居住する国を特徴づける特有の状況下で発展するにつれ、必然的に独自の世界観、独自の精神構造、独自の習俗、独自の社会生活の規範を形成する」と記す。「土壌主義」の背景にある植物学的な比喩を使うと、「異なる土壌は異なる植物を育み、それらは異なる果実を結ぶ」ということになる。
スキャンランは、ドストエフスキーのさらなる主張が、「制度や理想は特定の土壌の産物であるため、他の土壌には輸出できないかもしれない」というものだとのべている。「あらゆる果実は、自らの土壌、自らの気候、自らの栽培を必要とする」という主張は、「汎ヒューマニズム」の名のもとにロシアに異質な文化を押しつけようとする西洋主義者たちの誤った破壊的試みに対する攻撃の根拠となりうる。国民性は数世紀をかけて形成されるため、「容易に再構築されるものではない」というのがドストエフスキーの基本的なスタンスだ。ドストエフスキーは、「我々の大地には我々固有の、土着の何かが宿っている。それはロシアの気質と習俗の民族的・祖先的基盤に埋め込まれている。救いは土壌と民衆にあるのだ… 西洋の理想は決して我々に完全に適合し得ない」と考えていたのである。
しかし、「反西洋主義の基調とロシア文化への明らかな愛着が認められるにもかかわらず、理論そのものは、いかなる国民性にも優越的な地位を付与するという意味での、固有の排外主義的偏向を帯びてはいない」、とスキャンランは指摘している。そして、ドストエフスキーはさらに、自国の国民性の防衛と発展に注力することが、万人が望む人間の完全な可能性に到達する最善の道であると論じている。
ロシアの優位性
だが、ドストエフスキーは1862年以降、「あらゆる民族の平等な重要性」という命題に再び立ち戻ることはなかった。むしろ彼は、ロシア民族の性格が他のあらゆる民族に優越することを執拗に宣言し、その優越性によってロシアに世界史における至高の役割を割り当てるようになる。
「ポーチヴェニチェストヴォ」の原理に忠実に、ドストエフスキーはロシア人性の発展を、それを生み出した優れた土壌と結びつけた。ロシア的環境の特異な美徳の証拠として、彼は一連の歴史的論拠を提示した。そのロシア的土壌の特別な美徳を支えた背景には、ロシアが正教という形で「真の」キリスト教を保持してきたことがある、とドストエフスキーはみなす。彼はスラヴ派の見解を全面的に受け入れ、東方と西方のキリスト教の分裂はローマが普遍的交わりから意図的に離脱したことによって生じたと考えた。この解釈によれば、西方教会は次第に世俗化と物質化へと傾いていったのに対し、東方教会はキリストにおける人類の精神的結合を第一に置きつづけた。西方では、キリストは失われ、正教会のみが「キリストの神聖な姿をその純粋さにおいて完全に保存した」というのである。
「ドストエフスキーはクリミア戦争の時期に、いわゆる「キリスト教国」たる西欧諸国がイスラム教徒のトルコ側に味方したことで、西洋がキリスト教的価値観に忠実でないという明白な証拠を見出した」というスキャンランの指摘(206頁)は興味深い。ここから、ドストエフスキーはロシア人の性格がもつ独特の倫理的性質をとくに強調するようになる。彼はロシア民族をヨーロッパ人より「無限に高貴で、誠実」と呼び、「ロシアの兄弟愛がもたらす、すべての道徳的理念と目標は、国民的利他主義の雰囲気――あらゆる利己主義に優先する『共通の大義と公益への普遍的願望』――を創出する」と主張するまでになる。
こうして、ドストエフスキーは、西洋主義者は兄弟愛に基づく社会を築くことへの関心を語るが、兄弟愛というものが西洋人の性格には単純に「存在しない」ことに気づいていない、とまで書く。
「知られざる地政学」連載(122):なぜドストエフスキーはウクライナで嫌われるのか:文化をめぐる権力闘争(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)