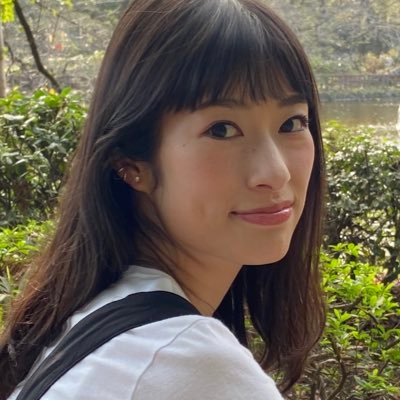「知られざる地政学」連載(122):なぜドストエフスキーはウクライナで嫌われるのか:文化をめぐる権力闘争(下)
国際「知られざる地政学」連載(122):なぜドストエフスキーはウクライナで嫌われるのか:文化をめぐる権力闘争(上)はこちら
国民性という問題
ここでドストエフスキーは、国民性(национальность)という言葉を使って、兄弟愛という感覚が当初から生来的に存在するロシア人に対して、天性としてそれをもたない西洋において、それが「再生」可能かを問う。何世紀にもわたり、ロシアの状況が兄弟愛をロシア人の「血と肉」の一部とすることを可能にしてきたため、それは生来的な意味だけでなく、土壌によって生み出された永続的な「第二の自然」という意味でも、ロシア人の「本性」の一部となっているのに対して、そうではない西洋人には、こうした性格を育むのは難しい。とくに、物質主義的で深く利己的であるとみなすユダヤ人について、ドストエフスキーは、根源的に邪悪であり、あらゆる残虐行為を犯しうる存在という立場をとった。
スキャンランがいうように、ドストエフスキーは、ロシア人もユダヤ人も「選ばれた」民と認識している。双方とも最終的には「すべてが彼らに従う」と確信している。しかしこうした普遍的な類似点にもかかわらず、ドストエフスキーは、ユダヤ人は利己的な搾取者となり人類への脅威となったと主張する一方、ロシア人は人類の幸福のみを念頭に置く利他主義者だと論じたのである。
普遍性に結びついたロシア人の優位性
ドストエフスキーは、ロシア人の国民性として、兄弟愛の精神だけでなく、彼が「普遍性」(всеобщность)と呼んだ優越性をもつロシア人こそ、救世主的使命を備えていると信じた。スキャンランは、1860年代初頭から、ドストエフスキーは「ロシア精神の「多面的な本質」を熱狂的に絶対化し、ロシアの「普遍性」という教義を、民族主義の歴史においてみられるもっとも誇大に膨らんだ国家優越性の主張の一つへと変貌させた」、と指摘している(214頁)。その結果として、「普遍性に関してドストエフスキーが惹かれたのは、ある民族集団に「第一の自然」の類いの根本的な優越性を見出したという点で、一種の生物学的に根差した民族的排外主義であったという結論は避けがたい」、とスキャンランはのべている(218頁)。伝統的な「選ばれた民」思想とは異なり、ドストエフスキーの目的論的排外主義は、ロシア民族が自らを救うためというより、人類を救うために選ばれたと考える。しかしこの立場がもつ寛大で普遍的な含意にもかかわらず、それは他の民族を貶め、大いなる計画において彼らを力のない対象として劣位と依存の立場に置くのである。
汎スラヴ主義とスラヴ人の保護者としてのロシア
ドストエフスキーの思想はさらに問題を大きなものにした。彼は道徳的模範や説得の域を超え、ロシアと他のスラヴ諸民族(ウクライナ人、ベラルーシ人、ポーランド人、チェコ人、そしてとりわけセルビア人、ブルガリア人、その他のバルカン・スラヴ人)との関係の領域へと踏み込んだのである。スキャンランによれば、1876年の『作家の日記』でドストエフスキーはこう記している。
「ロシアは、何世紀にもわたって受け継がれ、今に至るまで揺るぎなく歩んできた偉大な理念を裏切ることはできない。この理念はとりわけ、すべてのスラヴ民族の統一という理念である。」
ドストエフスキーの汎スラヴ主義的熱意の強さは、彼の生涯のほぼすべてがロシアと他のスラヴ諸民族との不安定な関係が続く時代に費やされたという状況に起因していた。その象徴的な出来事として、1830~31年のポーランド革命、 クリミア戦争(1853~56年)、第二次ポーランド革命(1863~64年)、露土戦争(1877~78年)といった出来事がある。この数十年間、ロシアはスラヴ諸民族に関わる様々な問題に絶えず巻き込まれ、そこにはスラヴ人自身だけでなく、イスラム教徒のトルコ人、正教徒のギリシャ人、そしてキリスト教徒(ただし非正教徒)である西ヨーロッパ諸国も関与し、相互に深い不信感を抱いていた。これらの紛争において、ドストエフスキーは忠実に支持した帝政政府と同様に、ロシアを異教徒や外国勢力からスラヴ人を守る守護者とみなしていた。そのため、スラヴ人の状況と人類を和解させ、統一をもたらすという壮大な使命を結びつけることは、彼にとって容易なことだったのだ。
このとき、ドストエフスキーは他のスラヴ諸民族に対する強制の必要性を認めない姿勢を示している。「ロシアは彼らの保護者であり、おそらく指導者ではあるが、支配者ではない。母ではあるが、主人ではない。仮に彼女がいつの日か彼らの主権者となるとしても、それは彼ら自身の宣言によるものであり、彼らが独立とアイデンティティを定義づけてきたあらゆるものを保持したままのことである」、というのが彼のスタンスだった。この全スラヴ人の将来の友好的な統合という彼の確信は、彼らの民族的近縁性に関する見解に基づいていた。
当時、ドストエフスキーは「大ロシア人部族」と他のスラヴ人を区別したが、通常、彼らの間の差異を曖昧にした、とスキャンランはいう。ウクライナ人とベラルーシ人については、単に別の名称のロシア人であると主張した。「ロシアの地の支配者はロシア人だけである。(大ロシア人、白ロシア人、ベラルーシナ――それはすべて同じである)」というわけだ(ドストエフスキーは当時のロシア帝国を、いかなる意味においても多民族国家とは決してみなしていなかった。彼が「タタール人」と呼んだイスラム教徒の民族は、「かつての抑圧者」および「新参者」として単に排除されていた。ユダヤ人は「国家の中の国家」であり、「国家の根源[ナーツィア]、すなわちロシアの部族」に対立する存在だった)。
「力こそが正義」
ただし、ドストエフスキーは、ロシア人とともに「偉大なるスラヴ族」の一員とみなした他のスラヴ諸民族が、とりわけ「苦難…奴隷制、そして屈辱」という共通の歴史によって結ばれていたことを意識していた。だからこそ、彼は西洋に対する屈辱を晴らすために、戦争さえも肯定するようになる。
スキャンランによれば、ドストエフスキーは皮肉にも、自らの以前の反功利主義的立場(目的が手段を正当化するという原理への非難)を逆転させるようになる(224頁)。具体的には、戦争がなければさらに多くの血が流される可能性があるからこそ、戦争は善であると彼は主張するのである。内戦を除けば、一般的に「戦争こそが、国際的な平穏を最小限の流血、最小限の悲惨、最小限の労力で達成する過程であり、少なくとも国家間の正常な関係の何らかの形が構築される過程である」と彼は記すのだ。まさにこの種の量的・結果主義的論証こそ、社会主義革命家たちから提示された際には、ドストエフスキーが倫理的根拠から断固として拒絶していたものだった。
ドストエフスキーは、「剣を一度振るう方が、無限に苦しむよりましだ」と主張し、「勝利は国家間の正常な関係の模倣を生み出す」という理由で戦争を擁護する。これは、まさに「力こそが正義」を肯定する危険な領域に迫っていると言えるだろう。もちろん、ドストエフスキーは、世界が「ロシアの理念」に平和的に従うことが原理的には可能だと考え、ヨーロッパとの戦争を公然と主張することは決してなかった。彼は、統一された東方の先頭に立つロシアが「剣を振りかざしてヨーロッパに突進したり、何かを奪い取ったりはしない」と主張した。なぜなら「ヨーロッパが再び完全に統一されてロシアに対抗する機会を得たならば、間違いなくそうしただろうから」。むしろ彼は、他の東方諸国との愛に満ちた同盟によって精神的に強化された慈悲深いロシアの姿を描いた。
それでも、ここで紹介したように、一時期のドストエフスキーの思想は、西洋からみても、非ロシアのスラヴ人からみても、受け入れがたいものであったと断じざるを得ない。
ドストエフスキーをめぐるもう一つの論文
ここからは、『ロシア史』50号(2023年)185–218頁が初出である、ジュリア・ベレスト著「F・M・ドストエフスキーのナショナリズム:歴史、歴史学、そして政治。2022年以降の文脈における古い論争」を取り上げる。ドストエフスキーの普遍的愛という哲学的メッセージと、彼の多くのジャーナリズム記事にみられる露骨な排外主義的・自国至上主義的・戦争賛美的発言との間の鮮明な対比を説明するために書かれた論文だ。
論文では、重要論文として先に紹介したスキャンラン以外に、ジョセフ・フランク著『ドストエフスキー:預言者のマント』(2002年)が紹介されている。そのなかで、フランクは、1870 年代に読者から多くの反響を呼んだドストエフスキーの日記『作家の日記』の 人気を論じるなかで、「親ウクライナ的シンパシーをもつ」マロロシア(ほぼウクライナ地域)出身の女性がドストエフスキーと文通し、彼の崇拝者として面会したことに触れ、つぎのように記述したという。
「彼女はリトル・ロシア人の性格を、その独立心と女性に対する態度を称賛した……しかしドストエフスキーは、そのような独立心の否定的な側面のみを見出した。それは共同体の家族制度の崩壊へとつながったのである。この制度は、グレート・ロシア人(ロシア人)の間では依然として広く普及していた。さらに彼は、セルビア人や小ロシア人といったスラヴ諸民族が自らの固有言語や文学を育むことは「明らかに有害」だと主張した。そうした排他的な集団主義は、大ロシア文学によって育まれる普遍的な啓蒙の業を妨げるだけであり、「そこにはすべての救い、すべての希望が宿っている」とのべた。」
こうして、ベレストは、「フランクは、ドストエフスキーの「偉大なるロシア帝国主義」と「普遍的調和と和解の理想」との間に明白な矛盾を見出し、この矛盾をドストエフスキー自身が認識できなかったと指摘する」と書いている。ここで問題になるのは、純粋な創作(小説)とジャーナリズムの間の境界線だ(注3)。フランクはこの二つの間にドストエフスキーが厳格な境界線を引いたことはなかったと主張する。だからこそ、自分のかかえている矛盾に無自覚だったとみるのである。
いずれにしても、ベレストは、これまで多くの国において、ドストエフスキーのジャーナリズム的著作にほとんど価値を見出してこなかったことを批判している。ベレストは、ドストエフスキーの『作家の日記』(1873年から1881年までの記事からなるジャーナリスティックな著作集)が同時代人に絶大な人気を博していたにもかかわらず、「ドストエフスキーのナショナリズムの性質と歴史的遺産はほとんど研究されてこなかった(あるいは、これまで見てきたように、単に覆い隠されてきた)」と書く。そのうえで、「ドストエフスキーに関する西洋文学の海全体を見渡しても、彼の民族主義的イデオロギーを包括的に論じた単行本は一冊もなく、ドストエフスキーの政治思想が当時および現代において知的・実践的に及ぼした影響については、ほとんど何も書かれていない」、とまで指摘している。
ドストエフスキーからドゥーギンへ
こうした問題意識をもつベレストは、ウクライナ問題に関する「過激主義」を理由に2014年に解雇されたモスクワ大学の元教授、アレクサンドル・ドゥーギンらがドストエフスキーから受けた思想的影響について深く検証された例はない、と主張する(注4)。
ベレストは、「ドストエフスキーはドゥーギンの知的影響の中でも特別な位置を占めており、ドゥーギンがもっとも重視しているのは彼の美学ではなく、むしろ彼の「終末論的」メッセージである」と考えている。ドゥーギンは、ウクライナで本格的な戦争がはじまった直後、2022年2月以前にロシアを支配していた文化に取って代わるべきものとして、「ドストエフスキーを中心とした文化」を挙げ、「我々は遅滞なく、ロシア文明を西側諸国と一線を画すもの・・・『ある作家の日記』に目を向けるべきだ!これこそ、我々が語り、叫び、テレビで見せるべきものだ」とのべたという。
さらに、ドゥーギンは、ドストエフスキーの「ロシア人はヨーロッパのアイデンティティを深く繊細に理解できるが、その逆は成り立たない」という主張に強く共感している。ドストエフスキー同様、彼はヨーロッパのロシア観を無知で悪意に満ちた「風刺画」に過ぎないとみなし、この見解は長年変わっていないと考えるのだ。
このようにみてくると、ベレストの批判はたしかに的を射ているようにみえる。さらに、ベレストは、プーチンの思想にもドストエフスキーの思想をみている。「特別軍事作戦」は戦争ではなく、親西欧的な「ゼレンスキーのナチス政権」から兄弟ウクライナ民族を解放する行為だと主張するプーチンの偽善的な言い分が、ロシアが西側ではなくロシアとの同盟を求めるスラヴ民族を含むすべてを再統合する運命にあるという「ドストエフスキーの思想を不気味に彷彿とさせる」というのである。
哀しい政治化という現実
ベレストは、論文の最後の部分でつぎのように書いている。
「現状では、西洋研究におけるドストエフスキーのナショナリズムへの批判は、往々にしてその研究の結論には反映されないか、あるいはドストエフスキーの文学的偉大さを強調する宣言によって慎重に和らげられるため、西洋で長年確立されてきたキリスト教的人道主義者としての彼の全体像は変わらないままである。この傾向は過去20年間にますます顕著になり、ロシア学界におけるドストエフスキー称賛の潮流と並行して進んだ。2022年にドストエフスキーをめぐる論争がソーシャルメディアに波及した際、小説家としてだけでなく公的道徳家としても称賛される彼について、西洋の一般読者がその民族主義的・反ユダヤ主義的見解をいかに知らないかが明らかになった。」
そのうえで、ベレストは「知的な誠実さ」と「政治的関心」の二つの重要性を説いている。最後の結論部分の記述はつぎの通りである。
「2022年以降の政治環境で激化したロシアの対西洋文化戦争という文脈において、一つ明らかなことがある――ドストエフスキーを「排除」することは西洋学術の核心原則に反し、まさにロシアのプロパガンダの思うつぼとなるだろう。しかしながら、ロシアが古典文学を(誤用しながらも)利用し、「退廃的な」リベラルな西洋に対する伝統的価値観の守護者としての自らの主張を裏づける手段としている現状において、彼のナショナリズム思想を穏便に処理したり、目を背けたりすることは同様に危険である。現代政治におけるマスメディアの未曾有の役割を考慮すれば、脱植民地化の視点からドストエフスキーを再評価し、この議論を専門外の人々にも身近なものとする必要性は、西洋世界にとって知的な誠実さと政治的関心の問題である。」
厳しい現実
しかし、現実は厳しい。キーウ市議会は、2025年12月18日、ロシア帝国およびソ連の政治の歴史と象徴に関連する15の施設および個別の要素を首都の公共空間から撤去する決定を支持した。そのなかには、『巨匠とマルガリータ』で名高いロシアの文筆家ミハイル・ブルガーコフ(1891-1940)に捧げられた対象物(地理的対象物、法人名、記念碑および記念標識)が含まれている。具体的には、2007年に建立されたブルガーコフのブロンズ像だ。
キーウでは、2023年7月13日のキーウ市議会の決定に基づき、キーウの公共空間から撤去すべき記念物のリストに251件が登録されている。2025年12月現在、そのうち170件以上が撤去済みだ。さらに36件は、資産管理者が撤去または修正の準備を進めている。別途、37の施設は文化遺産であるため、ウクライナ文化省の承認を得た上でしか作業を行うことができないという。
こうしたバカげた政治利用が着実に進んでいるのがいまのウクライナということになる。もちろん、ロシアもまたプーチンが中心となって、文化の政治利用が広がっている。それを助長しているのがマスメディアというオールドメディアだ。そして、この文化をめぐる権力闘争という政治舞台において、学者もまた政治に振り回されている。わかってほしいのは、こうした構造であり、権力闘争によって文化の位相が定められてきたという歴史である。それにもかかわらず、権力側は教育を通じた「洗脳」をつづけている。
たぶん、少なくともこうした「洗脳」に立ち向かうためには、ここで示したような勉強が必要なのだ。2026年もまた、勉強をつづけなければならないと強く思う。
【注】
(注1)デカブリストの乱自体を歴史的に俯瞰すると、1789年のフランス革命によって祖国を逃げ出したフランス貴族がエカテリーナ2世の治世の終わり(1796年)には、サンクトペテルブルクやモスクワなどのロシア帝国の諸都市に到達していたところから考える必要がある。この結果、19世紀のはじめには、ロシアのエリート層全体がフランス語で完璧に話し、書くことができるようになる。亡命者の教育者たちは革命の敵だったが、彼らの存在そのものが、フランス風の流行をロシアにもたらす。同時に、彼らが嫌っていた革命の思想への関心も呼び起こす。
こうした新しい時代精神のなかで、1808年6月、アレクサンドル1世がフィンランド併合の勅令を発布する。注目されるのは、皇帝が新たな臣民に、帝国では前例のない権利、すなわち自治、スウェーデン式地方自治、さらには政府と議会の中間的な存在である上院さえも与えたことだ。もちろん、西欧で進む近代化の風がロシアにも流れ込んできた証左と言えるだろう。だが、この政策はロシア貴族の間で不満をもたらす。なぜフィンランドでは自治の運営に関与しているのに、我々は自国の運営に関与できないのかというわけだ。
1812年の祖国戦争で、ロシア軍はナポレオンを打ち負かす。このとき、ロシアは「解放された地域」において、農民の農奴制がなく、都市の住民が都市の運営に参加していることを知る。こうした印象を抱いて、1815年から16年にかけて、勝利者たちは祖国に帰還し、その対照がすぐに目につくようになるのだ。ナポレオンの勝利者たちによる欧州の新たな分割条件に基づいて、ロシアはワルシャワを含む広大なポーランド領土を獲得する。そこで皇帝アレクサンドル1世は、ポーランド王国を設立し、議会(セイム)と憲法を授ける。セイムの開会式では、皇帝自らが演説を行い、しかも、自分が「征服者ではない」ことを示すため、フランス語で演説したことが知られている。
自由主義の兆候は、ロシアのエリートたちに強い影響を与えるようになる。それが、サロン的ながら不穏なサークルの誕生をもたらす。1816年3月、四つの団体の断片が「救国連合」を創設し、これが後のデカブリスト運動の発祥地となる組織となるのだ。ただ、1820年にサンクトペテルブルクでセミョーノフスキー衛兵連隊が反乱を起こす。皇帝にとって、セメノフスキー連隊が単なる衛兵ではなく、皇帝親衛隊、つまり皇帝の親衛隊だったから、アレクサンドル1世はその直接の監督下で処罰を行い、兵士たちは流刑に処され、一部の将校は裁判にかけられる。そして、「セミョーノフスキー」事件の影響を受けて、皇帝は、この事件を1820年のヨーロッパの事件(スペイン、ポルトガル、ナポリ王国での革命)の反響と捉え、それまでの自由主義的な方針を放棄し、締め付けを強化した。
デカブリストの乱自体は、1825年12月1日(西暦11月19日)、アレクサンドル1世がタガンログで死去し、その後継者をめぐるゴタゴタのなかで起きる。重要なのは、西欧での大きな変化に対するロシア帝国の対応が迫られていたという時代の雰囲気だ。
(注2)1849~1862年ころのドストエフスキーについて紹介しておきたい。1821年生まれのドストエフスキーは、23歳から24歳にかけて書いた『貧しき人々』で成功する。だが、27歳のとき、社会主義者ミハイル・ペトラシェフスキーが主宰する会の検挙に伴って、逮捕される。その後、有名な死刑執行直前で皇帝ニコライ1世の「恩赦」で流刑されるという経験をした。刑期は4年。その後もセミパラチンスクで兵役に服さなければならず、しばらくはペテルブルクへの帰還が許されなかった。
38歳になって、ようやくドストエフスキーはペテルブルグに戻る。こうして1860年初出の『死の家の記録』(シベリアの監獄生活と囚人らの人間観察)や1961年刊行の『虐げられた人々』が出る。なお、1866年には『罪と罰』が上梓される。
(注3)ドストエフスキーの小説を主眼にしながら分析している大澤真幸著『〈世界史〉の哲学 近代篇2 資本主義の父親殺し』は、大変に興味深い書物であると書いておこう。スキャンランやベレストからみれば、大澤の分析は中途半端にみえるかもしれないが、逆に、スキャンランやベレストが大澤のようにドストエフスキーの小説を深く理解していたとは思えない。
(注4)ドゥーギンについては、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』の「第2章 プーチンの復讐において」、主として陰謀論との関係で論じたことがある(45~47頁)。関心のある読者は参考にしてほしい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)