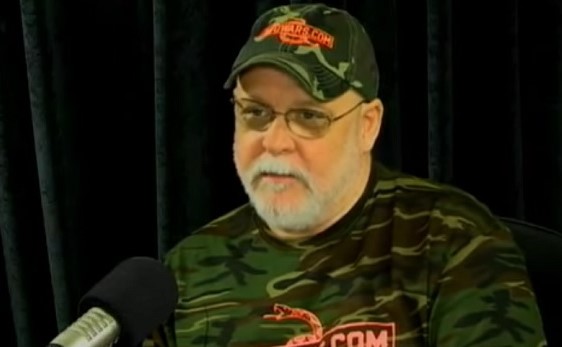第3回 Laïcité (政教分離の原則)
国際フランスには、どんな小さな村にも必ず教会がある。教会には立派なステンドグラスと繊細で且つ美しい彫刻が施されている。日曜の朝ともなると、ミサの合唱や教会の鐘が街中に鳴り響く。

しかし彼らは当然だが「God save the Queen (今となってはthe Kingである)」とは歌わないし、大統領就任時の宣誓式で聖書に手を置くことなどはない。その代わりに彼らは高らかに言うのだ。「Vive la république! Vive la France! (共和国万歳!フランス万歳!)」と。
それは「自由、平等、博愛」の精神と共にフランス革命以降、長い紆余曲折を経ながら模索してきたフランス共和国のアイデンティティーを織り成す要素のひとつであるLaïcité、政教分離に基づいている。

Illustration from 19th century.
フランス共和国憲法第1条には「フランスは不可分で、ライックで、民主的かつ社会的な共和国である。フランスは、出身、人種または宗教による区別なしに、すべての市民の法の下の平等を保障する。フランスは全ての信条を尊重する」と規定されている。
実社会においては、文言ほどフランス社会が人種や宗教の違いから来る軋轢や不平等を乗り越えられていないことは言うまでもない。またその過程においても、「人権の理想」の為に蹂躙された「人権」があったこと、植民地における「人権」はその範疇に入っていなかったことなどは忘れてはならない。
少なくともそこには、人々の生活やモラルや価値観の形成に深く浸透し、国家の内部に制度として存在していたキリスト教信仰を国家の制度から切り離し、其々の「信仰の自由」は保障しながら、フランス共和国の「不可分性」を実現するために国民に提示された普遍的価値観があり、それは今日に至るフランス共和国のアイデンティティーになっている。
アンシャン・レジームとカトリック教権主義からの脱却と共和国の模索という文脈の中で生まれたフランスのライシテだが、時代が変遷するにつれ、その性格も変容し、その矛盾も指摘されてきた。
特に移民の流入と差別、テロの頻発という社会不安の中においては、宗教と慣習やモラルが密接に結びついているイスラム教徒に対する風当たりは強く、本来であれば国家の宗教的中立性と全ての宗教の自由と平等を保障する手段であったライシテが、その宗教的中立性を個人に押し付けるような形で、逆に個人の平等や自由を制限するという事態に陥ってしまっている。
そうした風潮は、1989年のイスラム教徒の女学生のスカーフ着用を禁止する校則に関する社会的論争をはじめ、2015年の「シャルリ・エブド」やユダヤ人系食品スーパーやバタクラン劇場でのテロ事件などを背景に確実に強まっている。

Flowers and candles in front of the French embassy in Berlin as a sign of solidarity with France after the terrorist attacks in Paris at 13th of November in 2015.
2020年10月16日にパリ郊外で、フランス人の中学校教師がイスラム教徒の男に路上で首を刃物で刺され死亡した事件も記憶に新しい。
これは「表現の自由」を教える授業で同教師が、ムハンマドの風刺画を生徒に見せ(男性教師は一応クラスの生徒に風刺画を見せる事を言い、見たくない生徒へはクラスから出ていくように指示していた)、それを知ったイスラム教過激派の男に殺害されたという事件である。
私はこの時フランス人の反応を見て、やはり違和感を覚えずには居られなかったというのが本音である。
というのも、メディアも、どちらかというとリベラルな私の知人友人たちを含め、多数派の意見として聞かれたのが、「フランスはライシテの国であり、表現の自由の国である。それが嫌ならフランスから出ていけばいい。
イスラム教徒は自国の圧政や不自由が嫌でフランスに移住したのであれば、フランスの自由とライシテに従うべきだ。彼らはフランスの自由を享受しにフランスに来ておいて、フランスの自由を攻撃している」というものであった。
確かに殺人は許されない犯罪である。いかなる理由があろうともそれは正当化されるべきではないのは明白なのであるが、果たして上記のようなフランス人の主張の先に、ライシテが目指してきたはずのフランス共和国の「不可分性」が実現するのであろうかという疑問を持たずにはいられない。

Paris, France – November 18, 2015: Commemoration against terrorist attacks, on November 18th, 2015 at Republique place in Paris, France
 ラップ 聖子
ラップ 聖子
1982年、鹿児島出身。フランス在住。地元鹿児島とフランスを繋ぐ日本茶の輸入ビジネスを起業。日本茶販売とともにお茶と日本文化に関するワークショップを開催。一児の母。カナダ、オランダに留学経験があり、国際交流や語学が好きで、最近は母親になった事もありSDGsに関心を持っている。