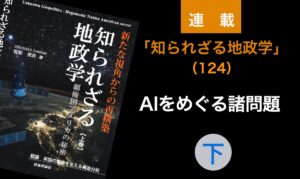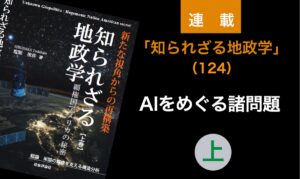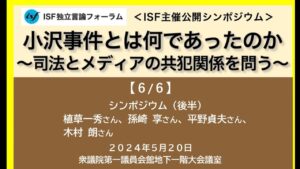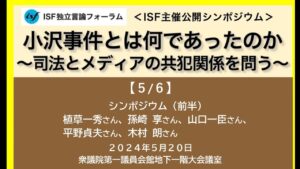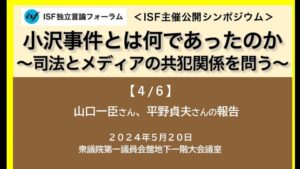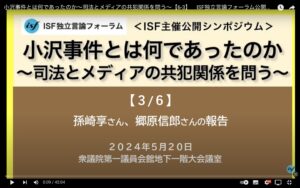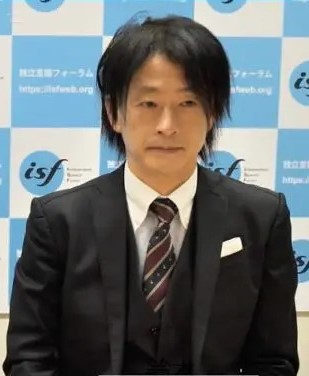第1回 déjà vu : 既視感
国際私は今、フランスのブルターニュ地方のディナンという街に居る。ここに移り住んだのは去年の5月で、もうすぐこの街での暮らしも1年になろうとしている。その前はパリに9年ほど暮らし、フランス生活もそこそこ長くなってきたところだ。慣れ親しんだパリを離れて、私は今イギリス海峡へとつながるランス川が流れる、灰色の石の建造物に囲まれた中世城塞都市に住んでいる。私をここに連れてきたわけを話そうと思う。デジャヴの話をしようと思う。
2020年の冬、凱旋門近くにある日本大使館に昨年産まれた娘のパスポートの申請をする為に私はパリに居た。当時は、19年の秋冬から猛威を振るったコロナ禍の為に、非常事態宣言が敷かれており、夜間の外出は禁止、また外出時にも許可証を常に携帯しておく必要があり、またレストランやカフェなどの文化公共施設はずっと営業停止中だった。
フランスは20年の3月からロックダウンに入り、夏のバカンス時にはロックダウンを解除、また秋にはその反動で更に感染者の波が押し寄せ、またロックダウンに入り、という事を繰り返していた。色とりどりの花々と柔らかな光に満ちた美しいパリの春を、狭いアパルトマンの中で過ごさなくてはならなかったし、毎日増える一方の感染者と重症者、死者数を伝えるニュースを見ながら、言葉にならない不安を覚えては居たけれど、それでも私も夫も、産まれたばかりの娘のお世話に奔走しながら、新しい家族を迎えた喜びと共にその時間を有意義に過ごしていた。
私にとっては、遠くに住む親の手助けも無い、異国の地での初めての出産・育児にあたって、夫がリモートワークになり、慣れない育児を夫と共に出来たことで、かなり精神的にも肉体的にも楽になったし、この期間を親子3人でゆっくり過ごせた事は私達にとって、貴重な時間になったと思う。幸い、私たちの住んでいたパリ郊外は閑静な街で、パリで増加していたコロナ禍におけるアジア人に対するヘイトクライムや差別などもあまり感じないまま過ごせた事も大きいと思う。
しかし20年のパリの薄暗い冬空の下、外出許可証を手にしながら、夫と共にベビーカーを押しながら、石畳の街を歩いている時、私はデジャヴを見たような気がしたのだ。「光の街」と謳われるパリの面影はどこにもなく、カフェやレストランの暖かい光や談笑の音も消え去り、人々の不安と怒りと鬱屈が蔓延っているような街。観光客も抱擁を交わす恋人達の影ももうどこにも見えず、ただ通りに居るのは暗い顔をして足早に過ぎ去っていくパリジャンと、その通りの横でワインボトルを片手に昼間から酔っ払うホームレス達だけ。その時、私はデジャヴを覚えたのだ。
それは、かつてどこかで見た世界大恐慌のウォール街の写真だったかもしれないし、戦後のインフレの中でパンを買うために大量のマルクを荷車で運ぶドイツ人の姿だったかもしれないし、数々の映画で描かれてきたナチス占領下のパリの暗さだったのかもしれない。パリの冬は、街灯やカフェや人々の灯す灯り無しには、一瞬にしてモノクロームになる。ただただ薄暗く厚い曇空が迫り落ちてくる。そしてそれは、これまで見てきたパリの中で圧倒的にモノクロームだった。
15年のパリ同時多発テロ事件の際にも、パリは確かにモノクロームになった。人々の疑心暗鬼と恐怖の表情がすぐに見てとれた。日本では、自衛隊の軍用車両を見ると何かしら不安な気持ちになっていた私も、あの時は通りに銃を抱えた軍人に、むしろ少しの安心感を覚えるくらいだった。
しかし、それでも通りにはまだ光があったのだ。自由と平等と博愛を信じるパリジャン達はテロの恐怖に屈せず、カフェで社交を続けていたし、芸術と音楽をこよなく愛するパリジャン達は、またミュージアムやコンサートへと足を向けた。そこにはまだ、微かな光があった。しかし、コロナ禍の20年の冬のパリには、光がどこにも見当たらなかった。ただ重く漂うモノクロームの世界。そして、思ったのだ。「パリを離れよう」。

Paris, France – November 18, 2015: Commemoration against terrorist attacks, on November 18th, 2015 at Republique place in Paris, France
それから半年後の春に転職や引っ越しを無事に済ませ、私は新天地にて、今この原稿をなんとも暗澹とした気持ちで書いている。私はパリに置いてきたはずの暗く重たいデジャヴをまたここで見ている。それというのも、今まさにロシアがウクライナに軍事侵攻をしているのだ。
 ラップ 聖子
ラップ 聖子
1982年、鹿児島出身。フランス在住。地元鹿児島とフランスを繋ぐ日本茶の輸入ビジネスを起業。日本茶販売とともにお茶と日本文化に関するワークショップを開催。一児の母。カナダ、オランダに留学経験があり、国際交流や語学が好きで、最近は母親になった事もありSDGsに関心を持っている。