
権力者たちのバトルロイヤル:第41回 もう一人の『エリザベス』
国際・エリザベス女王の“急死”
また一人、権力者が退場した。
9月8日、英国国王のエリザベス女王の訃報が届いた。享年96。高齢だったとはいえ、その急死に世界が驚いたのは、亡くなる2日前の9月6日、英国新首相となったリズ・トラスの首相任命式を行なった直後だったからであろう。

London, UK – October 21st 2014: Queen Elizabeth II framed in the window of an ornate ceremonial coach passes along the Mall in central London during a welcome ceremony and procession for a foreign dignitary
女王の死を巡って陰謀論者たちが騒ぎ出している。
7月8日、安倍晋三元首相が暗殺された。8月8日には、2年後の大統領選を目指すドナルド・トランプ前米大統領の政治生命を絶ちかねない「FBI家宅捜査」。そして9月8日が英国女王の急死。果たして偶然なのか、というわけだ。
そうした「陰謀論」をかき立てているのは、リズ・トラスのフルネームが「メアリー・エリザベス・トラス」であり、エリザベス女王のフルネームが「エリザベス・アレクサンドラ・メアリー」という点もあろう。エリザベス女王からエリザベス首相という“偶然”に色めき立つのも無理はあるまい。

英トラス前首相
少なくとも、この時期、トラスが首相となったのは偶然ではなかった。
2021年夏以降、イギリスは深刻な2つの経済危機に苦しんできた。
1つはロシアによる欧州各国へのガス供給制限の結果、天然ガスの国際価格が高騰。それによって引き起こされたエネルギークライシス(エネルギー危機)。もう一つは新型コロナのパンデミックに伴う生活支援金のばらまきによるインフレと不況のダブルパンチで起こった「コスト・オブ・リビング・クライシス(生活危機)」である。
これでイギリス経済がガタガタになったところに追い打ちをかけたのが、ロシアのウクライナ侵攻だった。イギリスのボリス・ジョンソン政権は対ロシア強硬路線を掲げてロシア産天然ガス・石油の締め出しをEU各国に同調するよう働きかけてきた。
その中心人物が外務大臣だったトラスなのだ。その強硬路線の結果、エネルギー価格はさらに高騰し、供給が追いつかなくなったイギリスでは、ガス供給会社が相次いで破綻、今夏、各家庭の冷房がきかなくなり、ホテルでシャワーから湯が出なくなるほどだった。この10月にはガス・電気が80%値上げすることも決まっており、冬の気候によっては凍死者が出ると懸念されている。

Eine Tafel zeigt steigende Energiekosten
この危機に対処できず、支持率が急落したジョンソン政権は、7月5日、財務大臣(リシ・スナク)が造反したことで倒れる。トラスは、スナクの対抗馬として登場、激しい保守党党首選を僅差で勝ち上がった。
いずれにせよ、「ロシアをソ連時代に戻す」と欧州から締め出す「逆・鉄のカーテン」を狙う対ロシア強硬派が新首相となった。ウクライナへの経済・武器支援を継続するどころか、対ロシアへの直接介入もありえる「戦争指導者」の登場に、トラスの勝利直後から「いつまで(政権は)もつのか」と、危ぶまれていたのがイギリスの実情だった。
そこに「女王の急死」である。トラスは女王「最後の宰相」であり、9月10日に戴冠したチャールズ3世の「最初の宰相」として2人の君主に忠誠を誓った。

September 16, 2022,Hong Kong.People gather next to flowers placed as a tribute outside the British Consulate in Hong Kong on following the death of Britain’s Queen Elizabeth II.
もし女王の急死がなければ、せいぜい「英国3人目の女性首相」だった扱いが、「エリザベス女王の最後の意を受け、新国王のために意を尽くす」という最高の栄誉に浴することになったのである。
こうなれば、トラスの対ロシア強硬路線もフォークランド紛争で「鉄の女」の異名をとったマーガレット・サッチャーを彷彿とさせるとばかり、国民の支持が高まる。彼女の強硬路線が国民に受け入れられる土壌が生まれていたことが理解できよう。
つまり、女王の死と新首相の登場によって、このときイギリスは「対ロシア戦争」の戦時体制へと突入しようとしていたわけだ。
・英国復活
前首相のジョンソンが「イギリスのトランプ」とすれば、トラスは日本の保守層から「イギリスの櫻井よしこ」と呼ばれている。スレンダーで知的風のルックスからは想像できないほど強烈なタカ派政治家なのだ。

Chorleywood, Hertfordshire, England, UK – October 11th 2020: Scarecrow of UK Prime Minister Boris Johnson sitting outside hair salon with sign about the Coronavirus Covid-19 lockdown
ロシアについては前述のとおり。親中だったジョンソンとは打って変わり中国に対しても「ウイグル人をジェノサイドしている」と厳しく批判を続けてきた。日米豪印の対中国包囲網・クアッドにも協力するなど、プーチンと習近平にしてみれば「最悪の英国首相」といってよかった。
さて、トラスの政治キャリアを探っていくと、興味深い事実がいくつか浮かんでくる。
もともと彼女は労働党左派の両親のもと、オックスフォード大学時代は、君主制の廃止を求める熱烈な「左翼学生活動家」だった。しかし政治活動の行き詰まりと生活の困窮からなのか、あっさり保守党に鞍替えする。その見返りに石油メジャーのロイヤル・ダッチ・シェル(現シェル)で高額収入と安定した生活を得て、保守系シンクタンクで政策実務を積み上げてきた。
そして2006年、ロンドン議会選挙で初当選。2009年、デビッド・キャメロン時代の保守党で念願の国会議員となり、その美貌もあって、各政権の目玉閣僚として長官(大臣)や次官級に抜擢されてきた。目玉閣僚の役回りをこなしながら、この10年来、確たる政治的バックボーンを築き上げていたのだろう。それが明らかになったのが、今回の保守党党首選だった。
彼女が党首選の演説で「偉大なる英国復活」の政策としてぶち上げてきたのが、「原発拡大」と「北海油田再開発」だった。簡単に言えば、ロシア産のエネルギーを欧州から完全に締め出す。
その代替エネルギーとしてイギリスが中心となって小型モジュラー原発を生産し、イギリスのみならず欧州の各都市に販売する。さらに北海油田を大規模開発して供給量を大幅に増やし、エネルギー不足の各国に販売するプランをぶち上げているのだ。

Oil platform in the UK
言うまでもないが、欧州各国のエネルギーを握れば、ブレグジット(EU離脱)で低下したプレゼンスを取り戻し、欧州の主導的立場に返り咲くことも可能となる。それだけではない。ロシアとの「冷戦」が長期化すれば小型モジュラー原発の新規開発と北海油田の大規模開発は、確実な投資案件となり、世界中から莫大な投資マネーが集まることが予想される。
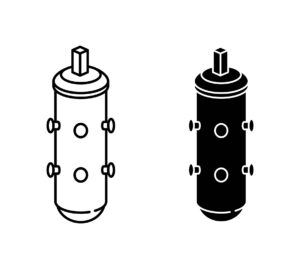
Small modular reactor icon , vector
2000年以降、完全に斜陽産業の不良債権化していた北海油田とイギリス原発ビジネスが、一転して「宝の山」となり、イギリス復活へとつながるというわけだ。
ただし、それが本当だとしても、現在進行形の不況に一般庶民はそうそう耐えられるものではない。が、「女王の死」と「新国王の戴冠」で、いま、イギリス国民は沸き立ち、一致団結している。この苦境に耐えようという機運が高まっているのである。
果たして偶然なのか、と陰謀論者ならずとも疑いたくなるのも無理はあるまい。
さて、元気だったころのエリザベス女王は、毎年、クリスマスにはバッキンガム宮殿のベランダから挨拶をするのが恒例となっていた。2年前の2020年のクリスマス、イギリス公共放送チャンネル4がエリザベス女王の挨拶映像をオンエアした。
ところが、その直後に「今の映像はディープフェイク(CG)で作った偽造です」とテロップを打った。そして、偽造映像と平行して「本物」を見比べる番組を放送したのだ。もちろん王室の許可を受けたもので、プロが画像解析しなければ一般レベルでは、もはや見分けがつかないほどの「リアルさ」が話題になった。
エリザベス女王は、このCG映像放送直後の2021年から高齢を理由に公務から半ば引退し、また新型コロナウイルスを理由に人前に出ず、その間に登場する「映像」が本物かどうか、わからなくなっていた。
そう、わかっているのは、わずか2日前に滞りなく任命式が行なわれ、「エリザベス首相」が戦争指導者という大役をこなしやすい最高のタイミングで「女王の死」が発表となったという点だけなのである。























































































































































































