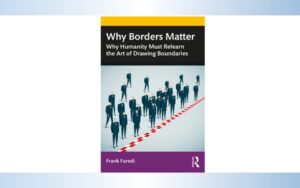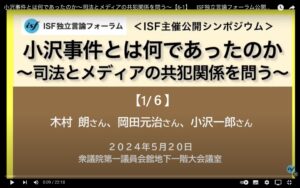第3回「一帯一路」をバイアスなく理解するために
国際私の先の小文は中国の経済戦略を米露の軍事的戦略と対比させることを本旨としていたが、その中国戦略としての「一帯一路」にも「西側」の批判が絶えない。
そして、その批判の中心はハンバントタ港整備事業に向けられており、この事業は採算もとれず、よってそもそも「債務の罠」を計画したものだったという批判である。

Map of Sri Lanka. Detail from the World Atlas. Selective Focus.
が、この批判にも色々な意味で誤解や不正確さが含まれている。ので、その問題を簡単に見るとともに、本稿では私自身が詳細に調査をした中国ラオス鉄道の建設プロジェクトについても少し簡単な紹介をしておきたい。「一帯一路」は中国外交の基本であり、この事例だけでその全体への評価が覆ってはならないと考えるからである。
・ハンバントタ港計画の構想、事前調査と実施の経過
それで、そのハンバントタ港整備事業についてであるが、まず最初に述べなければならないのは、その構想に最初に関心を示した外国政府はカナダであり、カナダ国際開発庁が2003年に1000ページにもわたる報告書を企業にまとめさせ、実現が可能との結論を出しているということである。
この構想自体は後に大統領となるラジャパクサやその息子の港湾担当大臣が最初に提出したものであるが、彼らが当時の政府になさしめた実現可能性調査(FS)ではコストが高すぎるとの結論を出しているから、当地の政府が否定したプロジェクトを復活させたのがカナダ政府ということになる。

bird view of the new developing port city project in Sri Lanka
しかも、「西側」のこのプロジェクトへの関与はまだ続く。2006年にデンマーク企業が行ったFSでも開発は可能との結論が出され、またその開発を2段階に分けて推進すべきとの具体的な提案も行っている。
つまり、第1段階ではコンテナ以外を扱う港湾を作り、その収益も利用してコンテナを扱う大型港への拡張を計るという合理的なものであった。
が、ともかく、こうして、この当初に最も強力に推進したのは西側であったということが重要である。スリランカ政府がこの計画に最終的にゴー・サインを出したのはこうした経過があったからである。
ただし、こうして計画実施が決定されたものの、スリランカ政府が融資を打診したアメリカもインドも協力を断る。そして、このために、当時のラジャパクサ大統領が複数の中国企業に働きかけを行い、よって最終的に中国ゼネコン大手の「中国港湾集団」が中国輸出入銀行の協力を取り付けて計画を実施することとなったものである。
もちろん、この際、この建設を実際に請け負うこととなった「中国港湾集団」は自分自身でもFSを行ったので、彼らの責任を追及することは可能である。
が、実のところ、この実施計画を無視したラジャパクサ大統領の指示が負債を拡大したのだということも言える。というのは、前述のように本来の実施計画は2段階に分かれていたものが、事業の完成を急ぐ大統領の指示が第1段階の状況を判断しないままの第2段階への建設の推進となったからである。
これは期待した収益を生むことなく第2段階に進んだことを意味するので、「採算性」に問題が出てくることは当然である。ともかく、こうした経過であったのである。[1]
・スリランカ政府側の問題
したがって、私はこの経過を知って思うのは、もちろん最終的なFSを行った中国企業(+中国輸出入銀行)に問題があるとは言え、事態の経過はそう簡単ではなく、いったん葬られた計画を復活させたカナダ政府やデンマーク企業、そしてさらには当時の大統領=スリランカ政府の側にも問題があったということである。

Colombo, Sri Lanka: Presidential building seen from Lotus Road – Presidential Secretariat and the Office of the Executive President, government building where all important official announcements are made and appointments of state administered – Old Parliament Building (former Legislative Council of Ceylon), British colonial architecture by Austin Woodeson, chief architect of the Public Works Department – opened in 1930 by Governor Sir Herbert Stanley.
実際、私が見ても、この計画にはそもそも無理なところがあった。というのは、スリランカ経済の中心が首都コロンボのある西部に集中し、よって港湾開発としても東部が決定的に重要であるものの(そして実際にコロンボ港の開発も進められているが)、人口の少ないハンバントタ地区の港湾を選ぶのには無理があったと思われるからである。
当時のラジャパクサ大統領にしてみれば、だからこそ発展の遅れた「地方」の開発に意味があると考えたのだろうが、これはいわば過去の日本の土建行政が採算性を無視したものとなっていたのと同様、田中角栄型の公共投資政策であったと理解せざるを得ない。
ハンバントタ港の整備を企画したのはスリランカ側であり、中国はただその要請に応じて資金提供しただけなのであるが、事業の実際はこのようにあまり褒められたものではなかったのである。

Sri Lanka and China flags together textile cloth, fabric texture
したがって、こうした問題を避けるべく中国政府の事業審査能力を向上させなければならないとの意見は強い。そして、その問題を、中国大使館との交流の機会に述べたところ、そうした審査はかなりきつくなっているとのことだった。
現在の在日本全権中国大使の孔鉉佑氏は日本に赴任する前、何と中央政府で「一帯一路」の政策決定の第一線におられたようで、そこで毎日投資プロジェクトの事前評価に携わっておられたそうである。そして、そこではいつも融資の可否を最終決定する国家発展改革委員会から拒否権を発動されたという。つまり、中国もまた融資先の厳選に心がけているということである。
が、しかし、私がここで思うのは、こうして融資の可否=事業の推進の可否を中国側に任せすぎることの問題である。というのは、当然ながら、事業の可否を決める本来の決定権はそれぞれの国民に存在すべきであって、たとえば、たとえ採算性に不安があっても国民が合意するならばそれを決める権利は融資先国民にあるからである。
実際、これからますます「超大国化」する中国に様々な決定権をゆだねるのは良いことなのだろうか。各国の政治に介入させないことの方が重要なのではないか、との考えも十分になりたつ。
この意味で、私は、これまで通り「内政不干渉」を絶対の条件とする中国の現在の外交方針の方が重要ではないかと考えている。ご検討願いたい。
 大西 広
大西 広
1956年京都府生まれ。京都大学大学院経済学研究科修了。立命館大学経済学部助教授、京都大学経済学研究科助教授、教授、慶應義塾大学経済学部教授を経て、現在、京都大学・慶應義塾大学名誉教授。経済学博士。数理マルクス経済学を主な研究テーマとしつつ、中国の少数民族問題、政治システムなども研究。主な著書・編著に、『資本主義以前の「社会主義」と資本主義後の社会主義』大月書店、『中国の少数民族問題と経済格差』京都大学学術出版会、『マルクス経済学(第3版)』慶應義塾大学出版会、『マルクス派数理政治経済学』慶應義塾大学出版会などがある。