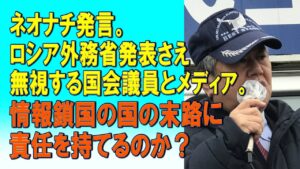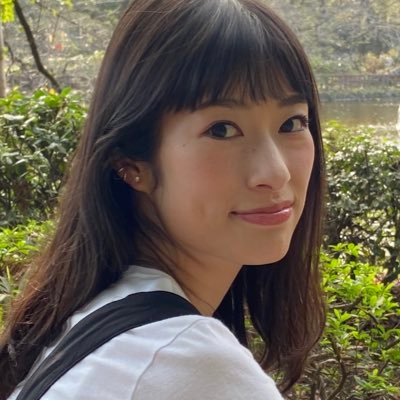第4回 犯人には同居人がいる
メディア批評&事件検証その解剖は、まだ幼い少女で、大変つらいもので、あまりにも無残な傷をもった遺体だった。その刺し傷の数は上胸部に集中し、その数は10数個で深いものであったばかりでなく、そこからうかがえる殺害の状況に普通とは様子が違うところがあった。その一つはこの被害者には性的な暴行の所見がまったく見られなかったことである。特に下半身に関しては、精液の付着はおろか、かすり傷すら見られなかった。

今市事件で茨城県警の警察官が遺体発見現場を見て描いた現場見取り図での殺害された女児の遺体状況。
もう一つは、刺し傷は前胸部の狭い部分のみに集中し、それもほぼ等しい間隔になっていたことである。この犯人は、被害者にかける思いが相当なものがあったのではないだろうか、と思った。いつもなら加害者が怒りを持って刃物を振り回すので、傷は不規則になるのが常である。しかし、この遺体の傷はあまりにも、規則的であることに驚かされた。いずれにしても現時点では容疑者が出てきていない以上は、慎重かつ丁寧に死体が訴えてくる所見を読み取ることに集中するしかなく、神経が疲れたことを今でも覚えている。
ところが、この事件の容疑者はなかなか浮上せず、捜査は難航した。犯人逮捕の兆しはなく、事件報道が細々と続いていたものの、犯人逮捕への手がかりはまったくなかったようなのである。裏では何らかの捜査が進行していたはずであった。そしてこの事件は、栃木、茨城両県警の合同捜査本部であったにもかかわらず、事件の捜査情報は茨城県警に全く入ってこないということであったので本田元教授の耳には当然、何も届いていなかった。
本田元教授は解剖を行った後、現場鑑識がほぼ終了した時期に茨城県警の捜査1課長らから遺棄現場を案内してもらったことがある。ここに栃木県側から入る方法は二つあり、北側の道から入って行く方がやや自然である。そこには「おおみや広域霊園」という看板を見て右折して、2㌔ほど行くと現場の山林に入るための左折路がある。そこからは車1台分がやっと入るだけの道であるが、そこはイノシシ狩りや鳥打ちの名所として地元の人の通行は少なくなく、決して人里離れた山林というわけではない。
当時、本田元教授が茨城県警捜査1課長に聞いたところでは、遺棄現場の山林の登り道には点々と血の跡があったことから、それが被害者の血痕であることが疑われ色めきたったが、血液検査の結果、これは人血ではないことかわかった。関係者からよく話を聞いたところ、イノシシを捕った後、腐敗しないように現場で血抜きをして運び出すときに落ちた血だという。その山道を200㍍ほど行くと途中で1回、右折して上って行く道がある。ところがそこから50㍍進むと、その道は行き止まりである。その行き止まりの道から20㍍ほど戻ったところの左手に、高さ数十㍍の木が生い茂った山林が有り、その道から山林の方に10㍍ほど降りて行った場所が遺棄現場である。
その斜度は約30度ほどのやや急坂だ。茨城県警の鑑識捜査では、道から入って斜め左方向に下がる方向に血痕が滴下しており、周囲には血だまりや血しぶきのような跡は全くなかったという。これは滴下血に過ぎず、遺体からしたたり落ちた血であるとする程度の量であるという。これは遺棄現場で遺体を犯人が抱えて降りたことを示す証拠である。発見事件からして遺棄が深夜帯と考えると、足場はやや悪かったと思われ、また遺体を抱えて運ぶにも体力が必要なことから、そこまでが限界であったと思われる。しかし、もし後一歩、先まで運べたとしたらそこから斜度が大きくなり、谷が深くなっていることから、上の道からは見えない位置に遺体が隠れた可能性があり、遺体発見は難しくなったのかもしれない。
本田元教授は、この事件は当時、大変に優秀な検視官の経歴がある鑑識課長の捜査によるものなので、信頼できると思ったという。現場は大きな通りから余り遠くなく、高くない山で、そこへ上る道幅は車1台分でしかないほどの細い道であるけれども行き止まり道だ。それを登り切ったところから、10㍍ほど下がった場所に無造作に遺棄されていたというのが現場の状況である。現場で殺害を示唆するような血しぶきや血だまりはなく、意図的に隠そうとするにしては遺棄された場所が中途半端なのだ。また同じ道を往復しなければならないことから車を見とがめられやすいため、もし犯人がそのことを知っていたらこの場所を遺棄現場としては選ばなかったであろう。
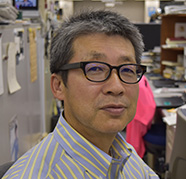 梶山天
梶山天
独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。