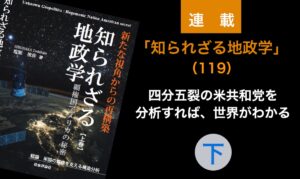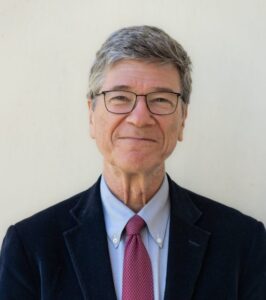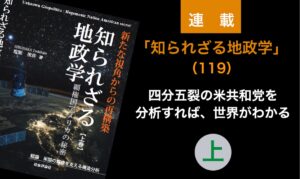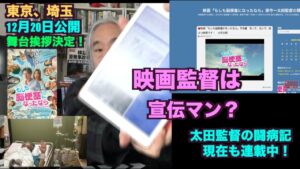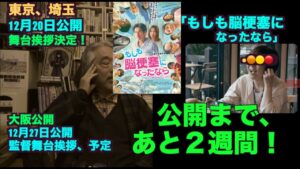ロシアによるウクライナ侵攻問題をどう見るか―哲学的認識論の見地から―(後)
国際第二のレベルはより本格的な認識論に関することであり、言葉の概念的正確さの問題である。これは実は、一般マスコミを批判する側の人びとも、同じく曖昧な言語表現をしていると思われる。それは「自由」「民主主義」「ネオコン」などに関することばの概念規定がどう正確になされているのかという問題である。
英米、ヨーロッパの西側陣営が宝のように大事にするのが、まさに「自由」であり、従来「自由主義vs.共産主義」というような対立用語が頻繁に使われた。

News headline that says “freedom”
「自由」については、「リベラル」という表現も使われるが、これは誤解のないようにいえば、「左派リベラル」「リベラル左派」ということだろう。というのも、自由には二義あって、「新自由主義」に含意される自由と、「左派リベラル」の想定する自由とがあり、両者はまったく同じではなく、左派リベラルの人が普通、新自由主義の「自由」を歓迎することはない。それは貧困と格差を生み出す自由だ。

Pyramid of three social class infographic. Vector illustration
(第一の)自由概念は、近代の資本主義の根底にある「個人の自由」であり、他人に迷惑をかけないかぎり、やりたいことをやれるという自由のことである。それは「…からの自由」として「消極的自由」といわれ、その内容は問われることはなく、とにかく外部からの制約を免れるという意味だけを重視する。
皮肉っぽく「恣意の自由」(好き勝手の自由)ともいわれ、さらに市場における(利潤追求の)自由競争と言われる際の自由であろう。だがそこでは、個人同士はばらばらで、相互に無関係とみなされている。
さて、第二の自由は「社会的自由」または「共同的自由」であり、自分個人の自由も実は他者に支えられて成り立っているということを自覚して、他者との共同と相互の承認のなかであらためて自由を考えていくというものである。それは高次元での自由であり、ヘーゲルの弁証法的自由観がまさにそれであり*13、共産主義者マルクスらの自由もそれであった。
現在の「左派リベラル」の持つ自由とは、(第一の)個人の自由への抑圧をはねのけつつ、第二の高次元の自由へと向かうものと解釈できるだろう。マルクス主義経済学者のデイヴィッド・ハーヴェイは新自由主義の(市場の)自由を批判しつつも、それを超える自由観を明確に提起できず、単に高次の「崇高な自由」があるはずだと説明したが*14、その概念的内容は以上のように規定できるだろう。
「民主主義」も曖昧な意味合いで用いられる概念である。西側の資本主義陣営こそ民主主義陣営とみなされ、彼らはこれを全体主義のロシアや旧社会主義のイデオロギーから防衛することこそ自分たちの任務と心得ていた。「民主主義」とは錦の御旗であり、だれも文句の付けようのないスローガンであった。

concept paper in hands of woman – Democraty
周知のようにそれは、古代ギリシャのデモス+クラトス(民衆の支配)に由来する。だがその内容ははっきりさせられないままに、むしろ政治的に悪用されてきた。
単に選挙で為政者を選ぶことや多数決だけが民主主義であるわけではなく、自由な議論を経て、そこで生まれた少数の意見を取り込みつつ決定することが民主主義のプロセスであり、個人と全体の調和を目指すのが、真の民主主義であろう。
また民主主義は、間接的民主主義と直接的民主主義の組み合わせによって適切に実現されるものだろう。そしてそこで実質的平等が目指されることが重要であって、それなしには、自由も民主主義も成立しないだろう。格差社会は民主主義的システムとは正反対である。米国などの民主主義陣営といわれる側が、はたしてそうした自由と民主主義を実現してきたのだろうか。
以上のような概念的重みをもつのが「民主主義」という言語表現であり、内容もはっきりさせずに、安易に政治的に利用されるべきではない。「民主主義」を振り回す者には、眉に唾を付けて臨まなければならない。
なお「全米民主主義基金(NED)」という、米国の議会が出資する民間非営利の団体があるが、世界の他国に民主主義革命を誘発する目的をもち、かつて「米中央情報局(CIA)」が非公然としてやっていたことを公然とやるものだと説明されている。
いわゆるカラー革命を世界各地で誘発し、2004年のウクライナの大統領選挙でも重要な役割を果たしたとされる。もしそうならば、こういう内政干渉的な組織が「民主主義」を名乗るのは、政治的乱用であって、いかがなものかと思われる*15。

Kiev, Ukraine – April 18, 2015: Independence Monument, Symbol of Ukraine Independence and Orange Revolution, Maidan Square Kiev Ukraine. Placard Memorials for those killed at Maidan
最後に「ネオコン」ということばを出したが、これはneoconservatism(新保守主義)の略語であり、今回のウクライナ侵攻の問題と関わって、多くの論者によってこのことばは頻繁に使用されるが、あまりはっきりと定義されて使われることがないようだ。
私自身は、ハーヴェイ『新自由主義』を翻訳した渡辺治の説明を参照して、新自由主義の存在にたいして、それに矛盾しながらも新たに補完するイデオロギーのことを新保守主義(ネオコン)だと考えていた*16。
だが、塩原の説明では、ズビグネフ・ブレジンスキーをその源流にして、ウクライナ問題で重要な役割を果たしたと思われるビクトリア・ヌーランドを念頭に置きつつも、世界を善悪二元論的な対立的構図でとらえ、単独で軍事力を行使するような立場をネオコンと呼んでいるようだ*17。
いずれにせよ、それがなぜ「新保守主義」なのか、これがいかに新自由主義と関わるのかなど、まだ不明であるので、これを使用する人は概念規定をさらに充実させてほしいと思われる。
4.ミアシャイマーの「攻撃的リアリズム」による分析
今までマスコミなどの論調や言語分析、概念分析などについて論じてきたが、それでは、ロシアによるウクライナ侵攻それ自体はどう説明されるべきか。
この点では、上記の中島も言及し、ほかにも何人かの論者が注目しているジョン・ミアシャイマーがきわめて説得的でわかりやすい議論をしているので、まずそれを紹介・検討したい*18。彼は5年間空軍に勤務したのちに、国際政治学者としてシカゴ大学に在職している。
まずミアシャイマーは、西側諸国が今回の戦争をどう見ているかについていえば、①すべての責任はプーチン大統領にある、②プーチン大統領には帝国ロシアやソ連再興を目指している、③プーチン大統領は拡大主義者であり、帝国主義者だ、④プーチン大統領はヒトラーの再来である、という4項目が妥当するという。
だがさらに、これらの説明は、実は「西側の作り話」だといっていいとされる(147頁)。これらの評価は私にはおおむね納得の行くものであり、さらに詳細な論証が求められるものだろう。まさに日本の一般マスコミは、この線に沿って記事を組み立てていたのだと実感できる。
彼の言う「攻撃的現実主義」とは、大国が無秩序になった国際社会のなかで当該地域で一番強い覇権国を志向するが、自国の勢力を脅かす他の大国を積極的に防ごうとする態度のことだと規定される。
だが、この説明は必ずしも自分には論理明瞭ではなかった。いずれにせよ、その際に大国は「自由」「民主主義」などという価値観のはいったスローガンを掲げるが、これが「リベラル覇権主義」(152頁)だと規定される。
これは同時に、「民主主義的覇権主義」とも呼べるだろう。すでに述べたように、このさいの「リベラル」「民主主義」の概念的内容が問題である。
このインタヴュー内容は説得的に理路整然と描かれている印象だったが、まず興味深いのは、彼が〔1〕プーチンに戦争遂行の責任があることは否定しないと言いつつ、〔2〕しかしながら「なぜこの戦争は起きたのか」という問いへの答えには、米国を初めとする、西側の対東欧政策が今日の危機を招いた、と二つを論理的にきちんと区分することである(〔1〕〔2〕は私が付けた)。
私の見解では、〔1〕では、プーチン氏がロシアの大統領として、自分の権限でウクライナ侵攻の命令を発したことは明らかだということをいっていると解釈される。彼がだれかに操られて軍事行動を開始したのではない限りでである。
〔2〕では、だがなぜプーチン大統領がウクライナ侵攻を開始せざるを得なかったのかは、プーチン大統領が短気だったからだとか、個人の性格に還元できない限り、ウクライナとロシアをめぐる、ある程度長い複雑な歴史的・政治的事情を探らなければ解明できないだろう。そこにこそ、社会科学的分析の生きる余地がある。

A news headline that says “Russia” in Japanese.
〔1〕のレベルの認識の正しさは単純で誰の目にも明らかである。とはいえ、ミアシャイマーが見ようとしたのは、国際法もあるのに、いきなり侵略するなんて許せないという、単なる個人の正義感のレベルの問題ではないということだろう。「たとえ世界が滅ぶとも、正義はおこなわれよ」ということでは困るということである。
〔1〕は見やすい事実だが、彼はそこであくまで「攻撃的現実主義」からの分析をおこなう。だからここでの2つの区分が意外と大事である。〔2〕のレベルの認識を〔1〕のレベルと混同しないということが重要だとみなされる。〔1〕のレベルで済むならば、〔2〕のレベルで要請される一定程度複雑な歴史的事情の考察などは不必要だろう。
〔2〕のレベルまでに至った際の結論は、いまや世界に米国、中国、ロシアという3つの大国が存在するようになったという現実認識のなかで、「現在の危機の根本的な要因」(148頁)がソ連社会主義崩壊以後のNATOの東方拡大にあったということである。
そして続いてミアシャイマーは、東方拡大の歴史的経緯とそれに対するロシアの反応を順々に展開していくが、まさにこの展開が説得的であるか否かが重要である。しかし紙数の都合で、ここではきわめて簡潔にしか述べられないので、本文を参照していただきたい。
東方拡大に関しては、1999年の第一次拡大(ポーランドなど3か国)、2004年の第二次拡大(バルト三国など7か国)のNATO加盟の状況にたいしてロシアは嫌悪し恐怖した。決定的な分岐点は、2008年のブカレストでのNATO首脳会議での宣言であり、そこでNATOは、ウクライナとジョージア(グルジア)の2国が加盟することを歓迎し、それに同意すると述べたことであった。
これには当時のブッシュ大統領が積極的だったが、メルケル首相とサルコジ大統領(当時)はここまで国境線がロシアに近づくことがロシアを強く刺激するということを憂慮した。だがそれでも米国が強引に押し切った。
ここでロシアは強く反発し、2008年ジョージアへ侵攻し、2014年クリミア半島に軍事侵攻して併合した。このときのきっかけは「マイダン革命」という、ウクライナにおける当時の合法的なヤヌコビッチ政権を打倒した反政府デモだった。

Kiev, Ukraine – December 14, 2013: Demonstrators protest on Independence Square EuroMaidan during peaceful actions against the Ukrainian president and government in Kiev, Ukraine.
さらにトランプ大統領がその後、対戦車ミサイルをウクライナに売却し、兵士の訓練をおこない、トルコもまた有効な武器であるドローンを提供した。
このウクライナの武装化は、ウクライナの「事実上のNATO加盟」(149頁)となった。2021年半ば以後、英米のNATO、ウクライナ軍がロシア周辺でしきりに軍事演習し、そこでロシアのラブロフ外相は「ロシアへの脅威が沸点に達した」と最後通告をした*19。まさにその後2022年2月24にロシアはウクライナ侵攻を開始したのである。
ミアシャイマーはここにあった米国の戦略ミスとして、行動を自分たちの視点だけでおこなっており、ロシアの視点を考慮することが欠けていたことがあったという。さらに注目すべきことに、インタヴューの最後に、西側の戦略の一つに、「カラー革命などを通じて、旧ソ連諸国を自由民主主義国家にすること」(152頁)を挙げる。
彼ははっきりと、不都合な政権を打倒して、米国流の自由と民主主義を受容する政権を作り上げることを「カラー革命」といっているのだ。これに従えば、2004年のウクライナのオレンジ革命こそ、このカラー革命であったとみなせるだろう。
そこでは、親ロシア派のヤヌコビッチが勝利したが、選挙不正があったということで市民のデモが拡大し、再投票の結果、親欧米派のユーシェンコ氏が大統領に選ばれたのである。
「カラー革命」という言葉は、いわゆる陰謀論にも近い表現かもしれないが、事実かどうか、まともに追究する余地があるだろう。そしてまさに、さきに指摘した「全米民主主義基金」こそが世界各地でこの革命を目指していたことになる*20。
ともあれ、この明快な論理展開からすると、ロシアを執拗に追い詰めたのは、米国とNATOであり、彼らの責任だということになるだろう。そしてそこに、米英など西側諸国のによる周到な世界支配の戦略と狙いがあったということになる。
そして実際、米国はかつて、自国を遠く離れて、世界各地で、ベトナム、イラク、リビア、アフガニスタンなど世界各地を侵略し、空爆し、人命を奪い、破壊してきたのである。
なるほどロシアも旧ソ連時代、アフガニスタンなどを侵略したが、それは自国領土の隣であった。それもまたもちろん許されないことであるが、米国とは事情が異なるだろう。CIA(アメリカ中央情報局)の活動を含め、こうした長期に渡る米英など西側の戦略的な軍事行動を具体的に認識しなければ、(その結果としての)今回のウクライナ侵攻の問題も十分に理解することはできないと考えられる*21。
最後に1点、次のような反論があるだろうということを記しておく。それは、ポーランドなどの東欧諸国は社会主義崩壊後、自由意志でNATOに加盟したのであって、それをロシアが制約することはできないという主張である。
ポーランドなどがNATO加盟に際してどの程度自由があったのかなかったのか私にはわからない。もしポーランド国民が自由意志でNATO加盟を選んだのならば、それは尊重されなければならないだろう。
ただし、個人の自由が万能でないように、国家のレべルでも、国際関係のなかで他国との関係は重視されるべきだという側面があるのではないか。
先に述べたように、人間関係と同様に、一国の自由と国際関係の地政学的状況とはバランスがとられる必要があるのではないかと思う。仮にこのままプーチン大統領を追い詰めて敗戦までもっていこうとすれば、被害はどんどん増え、ウクライナの国土は荒廃し、ロシアも大打撃を受けてしまい、最後に核兵器の使用ということになるかもしれない。
ここでは理性に満ちた深謀遠慮が必要ではないか。私の考えでは、ミンスク合意(2014年の議定書と2015年のより詳細なミンスク2)などを再考慮して、停戦へ持っていくべきである。
そのように考える論者は多い。また伊勢崎賢治は、日本について「緩衝国家」としての役割を期待している*22。以上不十分な記述になり、論ずべき残された課題は多いが、ここで筆をおきたい。
(脚注)
*10:少なくともドイツのkla. TVは、一方に偏らず、できるだけ客観的な情報に依拠するという姿勢を明確にもっており、日本の一般マスコミとは異なり、おおいに望ましいものである。
「ブチャの大虐殺」をめぐる矛盾 – 地平線の彼方への視線 – 日本語 | Medien-Klagemauer.TV これには日本語の字幕も付いている。
田中宇のブチャでの虐殺の批判的解説は参考となる。市民虐殺の濡れ衣をかけられるロシア (tanakanews.com)
*11:スランティングとは、「その根拠を示さずに、肯定的または否定的含蓄をもったタームを使用する」ことである。Cf. R.J.Fogelin, Understanding Arguments, Cengage Learning, New York, 1982,p.53.
*12:ウエッブ『論座』所収の清義明「ウクライナには『ネオナチ』という象がいる」https://webronza.asahi.com/national/articles/2022032200001.html?page=1
以上、上のみ。中・下もある。清はウクライナのネオナチについて、図像入りで詳細に展開する。ウクライナのネオナチ問題については、オリヴァー・ストーン製作、イゴール・ロパトノク監督「ウクライナ・オンファイア」のリアルな映画とともに、この清の説明をまず参照すべきであろう。
なおこの映画と、同じ内容を扱ったエフゲニー・アフィネフスキー監督「ウィンター・オンファイア」とを興味深く比較をしたものとして、嶋崎史崇「映画に学ぶウクライナ侵攻の前史」(『人文×社会』第6号、2022年)がある。両作品とも、いまでもインターネットで無料で見られるようだ。
*13:弁証法的自由概念の詳細については、共著『精神の哲学者 ヘーゲル』創風社、2003年所収の拙論・第一章「ヘーゲルにおける《精神》の概念とその意義」、38頁以下に詳しい。
*14:ハーヴェイ『新自由主義』渡辺治監訳、作品社、2007年、338頁。
*15:ウィキペディアより「全米民主主義基金」の項目を参照。
*16:ハーヴェイ『新自由主義』322頁以下を参照。
*17:塩原『プーチン3.0』41頁参照。
*18:ミアシャイマー「この戦争の最大の勝者は中国だ」(前掲)。以下本文中に頁数を記す。この表題の意味は、米国がウクライナに気を取られているうちに、中国を含む東アジアに力を注げなくなり、その点、かえって中国が得をしたということである。
*19:塩原は、当時のNATOとロシア側がどういう軍事行動をしたのかの事実経過を、細かく記している。塩原『プーチン3.0』18頁以下参照。なお塩原に続編『ウクライナ3.0―米国・NATOの代理戦争の裏側—』社会評論社、2022年があり、重要で詳細な事実記述に満ちているが、今回は十分に参照できなかった。
*20:「長周新聞」2022年3月17日所収の、伊勢崎賢治「ウクライナ危機に国際社会はどう向き合うべきか」では、次のようにいわれる。「僕は18年前、全米民主主義基金の代表が東京に来たとき、彼と面談したが、そのとき彼は豪語していた。『オレンジ革命は俺がやった』と――。彼らがやったことは民主化という名を借りた分断だ。…上記のことは、僕が実際に経験したことだ。」信ぴょう性のあることばではある。https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/22976
*21:ニコラス・スカウ『驚くべきCIAの世論操作』伊藤真訳、インターナショナル新書、2018年は、CIAが報道機関や映画界を偽情報、脅迫、優遇措置などの種々の手段によって操作してきたことを、赤裸々に描いている。
本書は、ハリウッドの映画界が「果てしない戦争の宣伝活動屋に進んで変身し、人道に対する犯罪の擁護者へと変貌してきたのである」(222頁)と、放映された映画の多くの実例を列挙して、そのように述べる(もちろん、そうではないすぐれた映画もたくさんある)。
私自身は今回のウクライナ侵攻のなかで、ハリウッドがいかに軍隊に協力して映像制作のプロパガンダをおこなっているのかどうかに関心をもってきたが、本書ではもちろん時期的にそこまでは描かれていない。
*22:羽場久美子らはおおむねそのように考えるが、その認識は私には、おおいに共感できるものである。羽場「アメリカの影響抜きには語れないロシアの軍事侵攻」、『マスコミ市民』22年5月号、44頁。副題に、「『ミンスク2』の時点に戻り、即時停戦を」とある。伊勢崎については、前掲のインタヴューを参照。
※以上は、季報『唯物論研究』第161号、2022年所収に掲載済み。
関連資料:ロシアによるウクライナ侵攻問題をどう見るかー哲学的認識論の見地からー(前)
〇ISF主催トーク茶話会③(2022年2月26日):鳥越俊太郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。
https://isfweb.org/recommended/page-4879/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
 島崎隆
島崎隆
一橋大学経済学部を卒業ののち、群馬県で高校教諭。現在、一橋大学社会学部名誉教授、社会学博士。ヘーゲル、マルクスらのドイツ哲学に関心をもってきたが、日本の学問研究には「哲学」が不足しているという立場から、多様な問題領域を考えてきた。著書として以下のものがある。『ヘーゲル弁証法と近代認識』『ヘーゲル用語事典』『対話の哲学ー議論・レトリック・弁証法』『ポスト・マルクス主義の思想と方法』『ウィーン発の哲学ー文化・教育・思想』『現代を読むための哲学ー宗教・文化・環境・生命・教育』『エコマルクス主義』『《オーストリア哲学》の独自性と哲学者群像』。