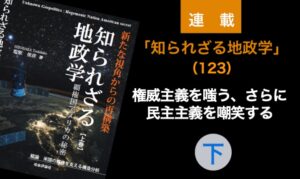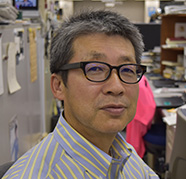「安保三文書」はこの国をどのように変えようとしているのか(後)
安保・基地問題6.空港・港湾などインフラと民間船舶・航空機の軍事利用
「安保三文書」は日本をアメリカに追従して戦争ができる国に改造するため、自衛隊や米軍の軍事活動に対する自治体や民間からの協力体制(動員体制)を作ろうとしている。「安保三文書」の軍事優先の発想が露骨に表れている。
「国家安全保障戦略」は、「総合的な防衛体制の強化の一環」として、「自衛隊・海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配備」のため、「自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化」、「自衛隊、米軍等の円滑な活動の確保」のため「民間施設等の自衛隊、米軍等の使用に関する関係者、団体との調整」を謳っている。
「有事の際の対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う。これらの取組は、地方公共団体、住民等の協力を得つつ、推進する」と特記されていることから、有事=戦時での空港・港湾のフル活用を視野に、自衛隊や米軍などの平素からの軍事利用が推進されるだろう。
これに呼応するかのように、沖縄に駐留する米海兵隊は2023年1月13日、輸送ヘリなどの軍事訓練のため、沖縄県宮古島市の下地島空港の使用届を、同空港を管理する沖縄県に提出した。

下地島空港
沖縄県は同年1月18日、米海兵隊に対し「緊急時以外の下地島空港の使用を自粛するよう強く要請」して、下地島空港の使用を認めなかった。その際、沖縄県は、1971年に当時の琉球政府と日本政府が、下地島空港の軍事利用を認めないことを合意した「屋良覚書」を示した。米海兵隊は結局、下地島空港の使用を見送る決定をした。
「屋良覚書」は、当時の琉球政府行政主席で、後に初代沖縄県知事となった屋良朝苗の名に由来している。今回、下地島空港の軍事利用を阻む根拠となったことで、「屋良覚書」の有効性があらためて確認された。

琉球政府・屋良朝苗行政主席(中央)
しかし、台湾有事で米軍嘉手納基地および普天間基地などの飛行場が、中国のミサイル攻撃を受けた場合を想定して、米軍は戦闘機や輸送機などを日本各地の民間空港に分散させることなどを考えているとみられる。
そのため米軍の意を受ける日本政府から空港や港湾を管理する自治体に対し、平素からの軍事利用に協力するよう圧力もかけられるのではないか。しかし、これら軍事利用を自治体に強いることは、地方自治への干渉、侵害にほかならない。
7.民間船舶・航空機の軍事利用と労働者の動員
「防衛力整備計画」は、「自衛隊の機動展開のための民間船舶・航空機の利用の拡大について関係機関等との連携を深める」としている。運航に従事させられる民間船舶・航空機の乗組員が戦火に巻き込まれ、死傷する危険が増す。
有事における自衛隊や米軍への自治体と民間の協力については、1999年の周辺事態法(現重要影響事態法)、2003年の武力攻撃事態法(現事態対処法)、04年の特定公共施設利用法や米軍行動円滑化法、15年の安保法制など一連の有事法制で規定されている。
これらによって、自衛隊や米軍に対する地方自治体や民間企業などによる輸送、港湾・空港業務、整備、給水、医療、通信などの分野での協力体制(兵站支援)が築かれた。
しかし、自治体や民間による協力は、罰則をともなう強制的なものではない。政府に労働者を強制動員する権限までは認められていない。それは国会での政府答弁でも明らかにされている。「安保三文書」を受けて、より協力を迫る法改正なども企てられるかもしれない。
このような動員体制の強化の動きに対して、労働者に軍事的な危険を冒してまで就労する義務はないという、業務命令の限界について法的判断を示した、1968年の「千代田丸事件最高裁判決」の意義がますます重要になってくる。
千代田丸は電電公社(現NTT)の海底ケーブル布設船だった。1956年2月に電電公社が在日米軍から日韓海底ケーブルの修理を要請され、千代田丸は長崎港からの出航を命じられた。
しかし、修理箇所は当時、韓国政府が一方的に公海上に設けた境界線(「李承晩ライン」)の向こう側だった。韓国政府は越境した日本船の撃沈・拿捕を表明し、銃砲撃も加えていた。
千代田丸乗組員は危険な業務に就きたくなかったが、仕事なので条件次第では従おうと考え、危険手当の支給などをめぐって労使交渉になった。だが同年3月5日、まだ労使交渉中なのに電電公社側は出航を命じた。労組の全電通本社支部からは「交渉が妥結しないかぎり出航に応じるな」との指令が出ていた。これを受けて乗組員は出航を拒否した。
出航拒否をめぐって、電電公社は全電通本社支部組合の三役を、公労法違反のストライキ指令を出したとして解雇した。組合側は不当解雇撤回の裁判に訴えた。1959年、東京地裁は「乗組員は危険を冒してまで就労する義務はない」という判決を下し、解雇も無効となった。電電公社側が控訴し、高裁では逆転敗訴となったが、68年に最高裁は地裁での判決を支持し、原告勝訴が確定した。
この最高裁判決の法理はいまも有効である。憲法13条(個人の尊重)、18条(苦役からの自由)、27条(勤労条件の基準)などにもとづき、軍事的な危険が伴う業務命令に労働者は従う義務はなく、業務命令拒否を理由にした解雇や差別待遇などの処分も違法だということを明らかにしている。
また、軍事的な危険が伴う業務命令でなくても、その業務が戦争協力につながる場合、労働者個人の思想・良心にもとづいて拒否する自由も、憲法19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」によって保障されている。
このように、軍事協力・戦争協力につながる業務を拒否する権利が労働者にはあることを、改めて訴えて行きたい。
「国家安全保障戦略」は、「有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制を含め、海保と自衛隊の連携・協力を不断に強化する」と謳っている。海上保安庁の軍隊化を禁じた海上保安庁法第25条を踏みにじって、海上保安庁を自衛隊の統制化に組み込み、戦争体制に動員しようと企てている。ここにも「安保三文書」の軍事優先の発想が表れている。
「防衛力整備計画」は、自衛隊と米軍が「平素からシームレスかつ効果的に活動できる」よう、基地周辺の自治体や住民の「理解及び協力をこれまで以上に獲得していく」と強調している。
ここにも地方自治への干渉、住民に対する人権侵害につながる軍事優先の発想が表れている。政府は、米軍機の騒音公害や危険な低空飛行訓練など、自治体・住民を悩ませている問題の防止に力をそそぐのではなく、日本各地での米軍・自衛隊の訓練・演習の激化を追認するのではないか。
8.学術の軍事利用と武器輸出の推進
「国家安全保障戦略」は、「安全保障分野における政府と企業・学術界との実践的な連携の強化」、「官民の高い技術力を幅広くかつ積極的に安全保障に活用」を謳っている。
そして、「総合的な防衛体制の強化に資する科学技術の研究開発の推進」のため、「防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズ」を踏まえ、「民間のイノベーションを推進し、その成果を安全保障分野において積極的に活用する」ため、「広くアカデミアを含む最先端の研究者の参画促進等に取り組む」としている。
最新兵器の開発など軍事研究に、政府の研究機関、民間企業、学術界を動員しようとする思惑がありありと見える。

Entrepreneur scientist doing research and development work on new armored electric tank in a secret base.
政府が2023年の通常国会に提出しようとしている、日本学術会議の組織改革法案(会員の選考や組織の運営に政府が介入できるようにする)に、その狙いが表れている。平和と学問の自由を重んじて、政府からの独立性を保ち、軍事研究、学術の軍事利用に反対してきた日本学術会議を、軍事研究、防衛産業(軍需産業)の振興に向けて変質させようと企図しているとみられる。
日本学術会議は会員の選考などに政府が介入しようとしていることに対し、同会議の「独立性が侵害される」として、政府に「強く再考」を求める声明を発表した。
戦前、軍国主義により学問・研究の自由が侵された歴史への反省に立つ、憲法23条「学問の自由」が脅かされている。ここにも、日本を軍事優先の社会に変えようとする「安保三文書」の本質が表れている。
「国家安全保障戦略」は、「官民の先端技術研究の成果」の「積極的な活用」による最新兵器の開発などのために、「我が国の防衛生産・技術基盤」の「強化は必要不可欠」であると強調したうえで、「持続可能な防衛産業を構築する」ため「各種取組を政府横断的に進める」と、政府の関与・支援態勢を強めるとしている。これも軍事優先の表れである。
そして、防衛産業(軍需産業)の企業の事業意欲を高めるためにも、「防衛装備移転の推進」という名の武器輸出の拡大が考えられている。「防衛装備移転三原則や運用指針」などの「制度の見直しについて検討する」という。
「防衛装備移転三原則」とは、2013年に安倍政権が閣議決定したものだ。それまでの武器輸出を禁じた「武器輸出三原則」を変え、実質的な武器輸出の解禁を認めた。「安保三文書」はそれをさらに見直して、武器輸出の販路拡大、他国との武器の共同開発を推進しようというのである。
「防衛装備移転三原則」の要旨は下記のとおりだ。
①国連安全保障理事会の決議に違反する場合や紛争当事国への防衛装備移転、すなわち武器輸出は禁止する。
②平和貢献・国際協力に資する場合、アメリカなど同盟国との国際共同開発や防衛分野の協力強化など日本の安全に資する場合、厳格審査のうえ武器輸出を認める。
③目的外使用や第三国移転については日本の事前同意を必要とするなど、適正管理が確保される場合に限って武器輸出を認める。
「安保三文書」では、「防衛装備品の移転」=武器輸出を、「我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段」と、新たに位置づけている。したがって、新たに同盟国と位置づける国やウクライナのような紛争当事国への武器輸出も、ケースバイケースで認める方向で、「防衛装備移転三原則」の見直しを図るとみられる。
そうして、武器輸出の推進のために、「政府が主導し、官民の一層の連携」のもとに、「基金を創設し、必要に応じた企業支援」をおこなうとしている。それは「防衛装備品の販路拡大を通じた、防衛産業の成長性の確保にも効果的」だと強調している(「防衛力整備計画」)。
しかし武器輸出は、世界各地で対立、紛争があり、各国が軍備増強することを前提にしている。他国の人びとが戦禍をこうむり、血を流すことが利益につながってゆく。「死の商人」と言われる所以である。
だから日本は従来、国際紛争を助長しないように、憲法9条を持つ国として武器輸出を控えてきた。ところが、それをなし崩し的に形骸化させ、平和の理念よりも防衛産業(軍需産業)や自衛隊の経済的・軍事的合理性を優先させることを、「安保三文書」は企図している。
武器の国際共同開発・生産を進めても、結局アメリカの軍需産業の主導下に日本企業が組み込まれることになるだろう。結果的に、巨大なアメリカの軍産複合体に従属するかたちで日米軍需産業の結びつきが深まる。
アメリカの軍産複合体に学術界も組み込まれた形態を、軍産学複合体ともいう。上記の「安保三文書」による学術・科学技術の軍事利用の拡大と防衛産業(軍需産業)の強化と武器輸出の推進が連動して、日本版軍産学複合体が形成されかねない。憲法9条の平和理念が形骸化され、アメリカに追従する“戦争中毒国家”になりかねない。

Defense Industry Vector Style Thin Line Icons on a 32 pixel grid with 1 pixel stroke width. Unique Style Pixel Perfect Icons can be used for infographics, mobile and web and so on.
 吉田敏浩
吉田敏浩
1957年生まれ。ジャーナリスト。著書に『「日米合同委員会」の研究』『追跡!謎の日米合同委員会』『横田空域』『密約・日米地位協定と米兵犯罪』『日米戦争同盟』『日米安保と砂川判決の黒い霧』など。