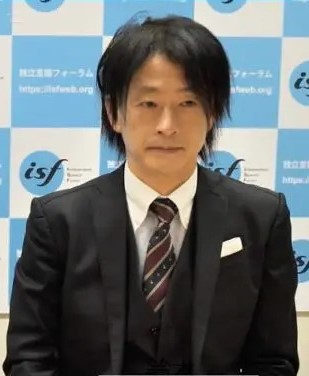ウクライナ戦争の教訓:中国のレッドラインが無視されてはならない―米国のロシアに対する仕打ちが許されたら、次に台湾をめぐる戦争が引き起こされる―
国際この1月、ロシアのウクライナ侵攻が迫るなか、駐米中国大使の崔天凱が、あからさまな警告を発した。崔は米国が台湾との関係を強化していることは、究極的に米中間の戦争に発展すると述べたのだ。
崔によると「もし台湾当局が米国に押されて独立の道を歩み続ければ、中国と米国という二つの大国が軍事的衝突に巻き込まれる」という。
一方で欧米は中国に対し、いわゆる「一匹狼外交」を展開すると批判しているが、崔はタカ派ではない。2021年7月に現在のポジションに就いて以降、崔はより良好な中米関係を求めるメッセージを送ってきた。21年8月31日の「米中関係全国委員会」(NCUSCR)に招待されて発言した際、崔は米国がとらわれている冷戦気質を警告しながら、「中米関係は相互の発展と繁栄にとってメリットがあると信じる」と語った。
崔の前述の警告は、ウクライナをめぐって米国とロシアが密な交渉を開始していた時期に発せられたが、結局戦争を防ぐことには失敗した。中国の米国に対する主要な要求は、ウクライナが決してNATOに加盟しないと確約することであったが、大統領のバイデンはそれを拒否したからだ。
ロシアのNATOに関する懸念は、ウクライナの予想される加盟だけに限られてはいない。冷戦終結以降、NATOはロシアのすぐ国境近くまで東に拡大し、ロシア南部の黒海にも部隊を目立って展開している。中国は、米国が同盟諸国を反中キャンペーンに加わるよう呼び掛けているため、太平洋においてロシアと同じく西側の軍事強化に直面している。
近年、米軍の南シナ海における活動は著しく強化されている。例えば21年に領有権紛争を抱えている南沙諸島や西沙諸島周辺における米軍機の偵察飛行は約1200回に達し、前年比で20%増となった。米海軍艦船は中国沿岸部にしばしば入り込み、ドイツやフランス、英国を含む同盟諸国も南シナ海で航行した。
こうした軍事的展開と並び米国は、南シナ海における中国と東南アジア諸国との間の領海権をめぐる論争に口を出し始めた。米国はこの海域における中国側の主張の大部分を否定し、フィリピンにもし中国とのこの海域での対立が武力衝突に発展したら、介入すると確約した。米国は東シナ海についても、中国の攻撃があったら尖閣諸島を防衛すると誓約した。
・強まる米国とNATOの中国敵視
太平洋における米国戦略の本質は、反中国の同盟構築に他ならない。昨年は米国と英国、オーストラリアがAUKUS軍事協約を締結し、オーストラリアに中国沿岸部を偵察するのに使われるであろう原子力潜水艦を供与することになった。米国は同様に、日米豪印戦略対話(Quad)を強化しようとている。
NATOですら中国を敵視し、中国に対抗するのを支援するため、太平洋諸国に注目している。20年末にNATOは中国を敵国と規定した報告書を発表し、中国からの抗議を招いた。中国は以降、NATOにアジアから手を引きよう警告している。
欧米による太平洋での軍事強化と軍事同盟形成の動きは、中国に対する挑発そのものだ。しかし中国からすればおそらくより挑発的な動きは、米国が台湾との非公式な関係強化に最近拍車をかけていることにある。
トランプ政権から米国は台湾に高官を派遣し始め、公的な接触を強めて、台湾を中国の不可分の領土と認めた1979年の外交規範を破った。この新たな方針を説明するにあたり、台湾の実質的な米国大使館である米在台協会(AIT)台北事務所副所長(当時)のレイモンド・グリーンは21年6月、米国は台湾を中国に対抗するための「好機」と見なしていると述べた。すなわち「これは米国と台湾関係の根本的変化を反映しており、米国はもはや対中国関係での『問題』ではなく、自由で開かれたインド太平洋を推進する好機である」ということのようだ。
中国と台湾・米国との緊張関係は昨年末に加熱し、台湾総統の蔡英文が、台湾に米軍が駐留している事実を認めるまでに至った。この数十年間、米国は少数の軍事訓練要員を台湾に派遣していたが、79年以降台湾当局は、この事実を公式には認めていなかった。
米国と台湾の関係について、そこでの主要な疑問はもし中国が台湾に侵攻したら米国は介入するのかどうかという点にある。これについて米国は依然、「戦略的曖昧さ」の方針を堅持しているが、何人かの米国議会のタカ派議員は変更するよう要求している。例えばヴァージニア州選出の民主党下院議員であるエレイン・リューリアは、もし中国がリスクもいとわず台湾を攻撃したら、バイデン大統領に開戦の権限を与える法律を制定するよう求めている。
・今度は台湾が米国に利用されるのか
リューリアは「バイデンが中国の台湾攻撃が起きたとしても、対応する権限を有していない点に不満を表明している。いま中国が台湾に侵攻したら、対応するために要する時間をロスするわけにはいかない。大統領は対応する権限を求めに、議会にまで出向かねばならないだろうからと述べていた」と語る。
リューリアは、中米間の戦争が勃発したら即時に核の応酬になるというという明白な事実にもかかわらず、バイデンに中国と戦う権限を与えるのは、状況を「エスカレートさせない」ために必要であると言うのだ。中国の核戦力は、米国やロシアと比較して小さくはあるが、核の応酬となれば人類を死滅させるには十分の量となる。
南シナ海における米中戦争の勃発の見通しは、この地域の米国の同盟諸国にとって重要な意味を持つ。戦争が通常型戦争に留まれば、米国本土はミサイルの来襲に直面することはない。その代わりに中国軍の怒りを買うのは太平洋諸国で、日本とオーストラリア、韓国、そしてフィリピンはすべて潜在的な攻撃目標となる。
もし中国が台湾に侵攻しても介入しない場合、米国はウクライナでやった同じ方法を取るに違いない。2月24日のロシアのウクライナ侵攻以降、米国は戦地に大量の武器を流入させ、ロシア経済の抹殺を狙う経済制裁を導入した。もし米国が中国に対する同じような代理戦争を実施するために台湾を利用するなら、中国を戦争の泥沼に沈める米帝国主義の目的のために戦い、死ぬのは台湾の国民となる。
ロシアのウクライナ侵攻の渦中で、中国が台湾を攻撃するという誇大宣伝がすさまじく盛況だ。米国のタカ派たちは、中国も台湾を攻撃するため、今回の侵攻を好機にしようとしているなどと警告している。
だが、現実はどうだろうか。もし中国が台湾を侵攻するのであれば、第二次世界大戦時の連合軍のノルマンジー上陸作戦も小さく見えるような、史上最大規模の上陸攻撃を必要とするだろう。中国はそんなコストがかかる試みに興味はないし、繰り返し平和的統一が最終目標だと述べている。
・NATO拡大の失敗がアジアで再現か
だが中国は台湾の独立がレッドラインであり、もし必要なら軍事的に対応するとも繰り返し明確にしている。今回の侵攻に先立ってロシアは10数年間もウクライナのNATO加盟がレッドラインであり、米国の高官や外交専門家も、NATOの拡大は東欧での戦争を招くだろうと警告してきた。冷戦期に旧ソビエト連邦に対抗するための「封じ込め戦略」を立案した外交官で戦略家のジョージ・ケナンも1997年に『ニューヨーク・タイムズ』紙上で、「NATO拡大は冷戦後の米国外交で最大の誤りだ」と発言したのではなかったか。
現在のCIA長官で、かつてのロシア駐米大使であったウィリアム・バーンズは、ウィキリークスが暴露した2008年2月の外交電文で「ウクライナとジョージアのNATO加盟について警告を発していた。バーンズは、次のように書いている。
ウクライナとジョージアのNATO加盟願望は、ロシアの神経を逆なでするのみならず、東欧の安定にとって深刻な懸念を生む。これをロシアが封じ込めとしてだけではなく、東欧におけるロシアの影響力を損ねようとする試みであると見なすであろう。そしてロシアは、自国の安全保障に深刻な影響を及ぼすような予測困難で統制できない結果となることを恐れている。
現地の専門家は、ウクライナのNATO加盟をめぐっては同国内のロシア系コミュニティが反対しているので分裂が生じ、暴力が伴ったり、最悪の場合内戦もありうる対立点となるのをロシアがとりわけ懸念していると伝えている。そうなったらロシアは介入すべきか否か決断せねばならなくなるが、そうした決断こそロシアが迫られたくないと望んでいることなのだ。
現在の米国の台湾政策の行きつく先は、NATO拡大がもたらした結果と同様に予測可能であろうが、それを指摘する声は乏しい。台湾での戦争は数年後に起きるものではないだろうが、もし米国がこのまま同じように進んでいくのであれば、10年後か20年後にはほとんど避けがたくなってしまう。ロシアのレッドラインは無視されたが、中国に対してはもはやそうであってはならない。さもなければ米帝国主義のために、今度はアジアの都市が戦火に包まれかねないのだ。
(翻訳:成澤宗男)
 Dave DeCampe(デイブ・デキャンプ)
Dave DeCampe(デイブ・デキャンプ)
ニューヨーク在住の国際・軍事問題ジャーナリスト。米国で最も充実したオルターナティブサイトであるAntiwar.comの編集者。ツイッターは @decampdave。