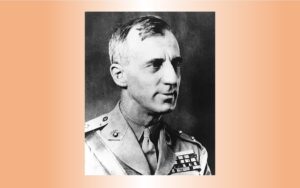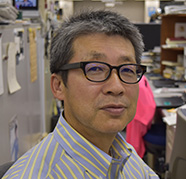戦前の〝国家警察〞が復活、警察庁「日本版FBI」を目論む警察法改正の危険
政治・国家警察の復活
先に「警察にとっての重大な方針転換」と書いたが、国家公安委員会・警察庁には、従来、犯罪捜査権限は与えられていなかった。これは、戦後改革で国家警察が否定され、地方警察が警察活動を行なうこととしたことに由来している。
ところが、今回の改正で、重大サイバー事案についての犯罪捜査が国家公安委員会・警察庁の事務と定められた。これは、戦後改革で否定された国家警察の復活であり、日本警察の「FBI化」にほかならない。しかし、それについての納得できる説明はなされていない。

View of the Metropolitan Police Building in front of Sakurada Gate in Chiyoda-ku, Tokyo
このような規定を許せば、今後、他の所掌事務についても“国家警察”に警察活動を認めることへの道筋を作ったことになるだろう。つまり、前述の法案5条4項16号に相当する規定を応用することで、国家公安委員会・警察庁の他の4つの内部部局(生活安全局・刑事局・交通局・警備局)にも警察活動を容認することができるようになり、全面的な国家警察の導入が可能となってしまうのだ。
加えて、関東管区警察局に全国的規模での重大サイバー事案に対する警察活動を認めたこともまた、国家警察の復活の象徴にほかならない。
地方機関である管区警察局は、一切の警察活動は認められていない。これを認めれば、警察庁の管轄下にある機関が警察活動を行なう、すなわち警察庁そのものが警察活動を行なったことと同視できる。まさに国家警察の復活なのだ。
ところで、刑事訴訟法193条は、「検察官の司法警察職員に対する指示・指揮」を認めている。この検察官とは、司法警察職員が捜査活動を行なう区域を管轄する検察官である。
今回の改正では、関東管区警察局のサイバー特別捜査隊が捜査を行なう。それも、管区を超えて全国に管轄権を持つことになる。その場合、刑事訴訟法193条1項の「一般的指揮・指示」は、どこの検察官が出すのであろうか。
全国を管轄する検察官は、最高検察庁所属の者のみであり、高等検察庁や地方検察庁の検察官ではないはずである。果たして、最高検の検察官が指示・指揮するのであろうか。
これは、刑事訴訟法における検察官と警察官の関係において、重大な問題である。しかし、どのように対処するのか明確にされていない。
今回の法案の提案理由として、2月2日の所信表明で二之湯国家公安委員長は「外国治安機関等との協力を進め、警察の対処能力の強化」と述べた。しかしこれは、警察庁に警察活動を認める根拠とはならない。わざわざ警察庁に警察活動を認めなくてもできることであり、立法理由にはならない。
一方、すでに国際的な組織犯罪への取組みについて、警察庁は国際協力を扱っているが、それについての警察活動は、同庁は認められていない。
また、その他の理由・背景として二之湯氏が挙げたことも、警察庁が担当しなければならない理由とはならない。現在実施されているサイバー攻撃特別捜査隊にその任務を委ねれば十分ではないか。
現在の日本と同様、都道府県警察にのみ警察活動を認める警察体制をとる国に、ドイツがある。
ドイツは連邦国家であり、州警察が警察活動の中心である。連邦警察の活動は、①連邦と州警察や外国の捜査当局との間の合同捜査の調整を行なうこと②すべての重要な犯罪とその犯人のインターポールのデータベースを管理し、犯罪情報の収集と解析を行なうこと③テロ・過激派・スパイ活動・経済犯罪の事件の捜査を行なうことである。サイバー犯罪の捜査は州警察の担当であり、連邦警察の役割ではない。
ドイツのように、「外国治安機関との協力」を新設されるサイバー警察局が行なえばよいのであり、そこに捜査権限を与える必要はない。警察の肥大化を招くだけである。
・警察国家へ向けての序章
繰り返せば、今回の法改正の構造から、国家公安委員会・警察庁の他の所掌事務についても、警察活動を容認することは、比較的に容易であろう。つまり、すべての内部部局の所掌事務について、法案5条4項16号に相当する規定を設ければ、“国家警察”による警察活動は認められてしまうのだ。
このことを国際的なテロ活動について考えてみよう。
警察庁刑事局について、警察法23条2項は、組織犯罪対策部の所掌事務として、①国際的な犯罪捜査に関すること、②国際刑事警察機構との連絡に関することを認めている。ここで、すでに警察庁で国際協力は行なわれている。その例が、国際組織犯罪である。今回の改正で、今後、国際組織犯罪についても、警察庁に警察活動を認めることになるだろう。
これを認めてしまえば、警察庁の思惑で社会が動かされてしまうことになる。
捜査機関の国際協力について、ある事例を紹介しよう。
アメリカのメディア「テックランチ」(21年11月2日付)は、「ユーロポール(欧州刑事警察機構)が19年のランサムウェア攻撃を実行したサイバー犯罪者たちを拘束」として、次の記事を配信した(以下、要約)。
〈ユーロポールとそのパートナーである各国の法執行機関は、19年以降、71カ国で1800以上の被害を出した一連のランサムウェア攻撃の背後にある組織的なサイバー犯罪者のネットワークを壊滅させた。
ユーロポールは2年間の調査を経て、12人の個人をターゲットとした家宅捜索をウクライナとスイスで行なったと、10月29日に発表。同機関は、これらの個人が逮捕または起訴されたかどうかについては言及していない。
この組織が使用したランサムウェアの一つは「ロッカーゴーガ」で、19年3月にノルウェーのアルミニウム生産企業である「ノルスク・ハイドロ」への攻撃で使用されたものと同じ種類。サイバー攻撃により、二大陸にまたがる同社の工場は約1週間の生産停止を余儀なくされ、5000万ドル(約57億円) 以上の損害を被った。 ノルウェーの国家犯罪捜査機関は、今回の捜査対象となった個人がノルスク・ハイドロへの攻撃に責任があることを確認したと述べている。(中略)ユーロポールは、今回の捜索で5万2000ドル(約600万円)の現金と5台の高級車を押収したと述べている。
「これらの容疑者のほとんどは、異なる管轄区域で注目を集めている複数の事件で捜査されているため、価値の高いターゲットと考えられている」「ターゲットとなった容疑者たちは、これらの専門的で高度に組織化された犯罪組織で、それぞれ異なる役割を担っていた」
ユーロポールによると、今回の作戦にはノルウェー・フランス・イギリス・スイス・ドイツ・ウクライナ・オランダ・アメリカの法執行機関が参加し、10月26日には50人以上の外国人捜査官が、サイバー犯罪者を目標としてウクライナに派遣されていた。〉
ここでどのような捜査が行なわれ、どんな解決策が取られたのかは不明だが、かなり強硬な手段がとられたことが記事から想像できる。
今後、法案に従って日本がサイバー犯罪についての国際協力を進めるとすれば、それは、情報共有にとどまるものではない。実際の捜査を共同することになるのではないか。すなわち、国家警察の復活と国際化である。絶対に許されてはならない。
(「紙の爆弾」2022年4月号より)