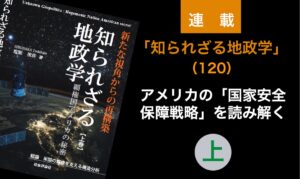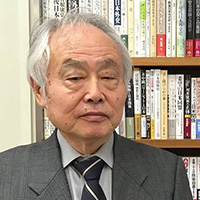評論「映画に学ぶウクライナ侵攻の前史―特に『ウクライナ・オン・ファイヤー』と『リヴィーリング・ウクライナ』を巡って」(1)
映画・書籍の紹介・批評はじめに:対抗言論の活性化と複眼的視点の獲得のために
2022年2月24日に開始され、世界中に大きな影響を及ぼしているロシアによるウクライナ侵攻。ヨーロッパ(とその外部であるロシアとの境界地域)で起きた本格的な戦争であるが故に欧米メディアによって他の紛争より増幅されて報道され、その傾向が日本にも波及している傾向は否めない。エチオピア、イエメンやシリア等での深刻な人道危機はここまで注目されておらず、差別ではないかという指摘もある[1]。しかしこの戦争が将来、冷戦終結後の画期をなす大事件として回顧されることは確かだろう。テレビやSNSで映し出されるミサイル攻撃や、廃墟となった街、困窮する避難民の様子は、私達日本人にも衝撃を与えている。日本政府も対ロシア制裁に加わり、国会では非難決議を圧倒的多数で可決し、防弾チョッキや「民生用」ドローン等をウクライナ政府に提供し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を国会でのオンライン演説に招き出席した議員の大多数が絶賛する等して、間接的に紛争当事国となっているという見方もできるだろう。
本稿の問題意識は、2013~14年にウクライナで、一般に親ロシア派と目されていたヤヌコヴィッチ政権が打倒された「(ユーロ)マイダン革命」もしくは「尊厳の革命」を正統な市民革命とみなすか、それとも非合法な「クーデター」として評価するかで、この戦争の見え方はかなり変わってくる、ということである。この戦争がどのような結末を迎えるのか、本稿執筆中の2022年5月の時点では、まだ見通せない。衝撃的で悲惨な戦争の映像に注意を奪われるのは当然であり、直接的被害者たる(国内避難民も含めた)避難民らに連帯し、最大限の人道支援を行うのは世界共通の義務でもあるだろう。だがそれと同時に、今回の戦争の歴史的背景と原因への省察を深めることが不可欠ではないだろうか。残念ながらこうした要素が、現在の日本では一般的には十分に知られていないと痛感していることこそ、非力を顧みず、私が映画評論の形で問題提起をする所以である。
具体的な題材としては、今次のウクライナ戦争の背景をより深く理解するために重要であると考えられるドキュメンタリー映画3点を取り上げる。折しも2年以上続く新型コロナウイルス禍の最中である。外に出かけづらくなった人々が自宅で過ごす「ステイホーム」の選択肢の一つとして、動画視聴が益々盛んになっている。職業や専門分野にかかわらず、多くの人々が廉価にまたは無料で、知識を広げ、認識を深めるための格好の入り口だといえよう。
まずは本稿の構成を示しておこう。
第1節では、まずはネットフリックス作品『ウィンター・オン・ファイヤー ウクライナ 自由への戦い』(以下『ウィンター~』を、親欧米派ウクライナ人の見方を代表する作品として紹介する。
第2節では、オリヴァー・ストーン氏がプロデューサーを務めた『ウクライナ・オン・ファイヤー』(以下『ウクライナ~』を、ロシア寄りのウクライナ人の視点に主として立脚するものとみなしながらも、分析しつつ吟味する。中心になるのは、米国によるマイダン革命への介入という問題である。
第3節では、両作品を比較した上で、『ウクライナ~』がインターネット上で削除されたり、検索しづらくなったりしている問題を、表現の自由や民主的討論の問題という視点から論じる。
第4節では、『ウクライナ~』の続編といえる『リヴィーリング・ウクライナ』を検証しつつ分析する。とりわけ経済を含む米国によるウクライナへの干渉政策の描写と、今日のウクライナ戦争を予見したかのような先見性に注目する。
第5節では、ストーン氏のウクライナ作品に投げ付けられることもある「陰謀論」という言葉の含意と、ウクライナでの戦争が日本にとって持つ潜在的意味を考察して本稿を閉じる[2]。
歴史を振り返ってみると、自由・平等・博愛の理想を謳ったフランス革命がナポレオンによる侵略戦争へと変質し、史上初の社会主義革命たるロシア革命に内戦や日本を含む各国のシベリア出兵(と一般には呼ばれる実質的干渉戦争)、ウクライナとロシア・ソ連による戦争(1917~21年)等が続いたことがわかる。このように、革命と戦争はあたかも兄弟姉妹であるかのように、深く関わってきた。本稿でこれから検討していくように、米国の介入により決定的な力を得たとされるマイダン革命(およびそれに対する反応として続いたといえるウクライナ東部・ドンバス地方での内戦)を遠因としてウクライナ戦争が誘発されたという見方が、それなりの根拠を持って可能だといえると仮定しよう[3]。もしそうだとしたら、かつてハンナ・アーレントがウラジミール・レーニンを引いて20世紀の特徴とした「戦争と革命」の時代はいまだ終わっていないのでは、と問い直す余地があるのかもしれない[4]。
特にストーン氏のウクライナ作品は、ウクライナ侵攻に関しては、日本では「支配言説への懐疑は蚊の羽音より弱い」とも酷評される水準の「対抗言論」への関心を呼び覚まし、以て一方的ではない真に民主的な討論の活性化に貢献することが期待される[5]。日本語での本格的評論が管見の限り見当たらないことも、本稿執筆の動機の一つである[6]。
もし人文社会系の教養に少しでも実践的意味があるとすれば、それは次のようなものではないか。例えば、直接的に自国のものではないとはいえ、今回の戦争のような非常事態的状況においても、冷静に歴史的経緯を回顧しつつ、思想史的知見も応用しながら、あえて根拠ある異論を提示することによって、より公平で包括的な議論にささやかな貢献をすること。換言すれば、特定の局面において圧倒的に優勢な見解または「常識」に対して、その正当性を部分的には承認しつつも、果たしてそれだけが唯一のものか、他のより深い見方もありうるのではないか、とあえてしつこく「水を差」すことにより、健全な懐疑の精神を育てること。そしてそのようにして、多数派に熟慮と再考を促してやまない「反時代的考察」を、嫌われ者になることも厭わず敢行し続けることであろう。
奇遇にも、ウクライナ侵攻と重なる時期に、戦争を主題とする二つのアニメーション作品が放送、上映された。一つは世界的に有名な『進撃の巨人』(NHK総合、原作は諫山創氏の同名の漫画で、2021年に完結)のファイナルシーズン第2部である。戦時下のウクライナでも原作漫画は人気を集めている、という報告もある[7]。巨人に変身する能力を持つ民族が、別の民族のさしがねにより、二手に分かれて戦わされるという設定が特色であり、人種差別の問題に真剣に向き合う作品でもある[8]。一方が先制攻撃を受けたと思っていたら、他方にとってはそれは過去の攻撃への反撃だったことが判明するという展開も、加害と被害が交錯しがちな戦争について示唆を与えてくれる。
もう一つは各地の映画館で第3期が上映され、遥かな未来における(啓蒙)専制的帝国と(堕落した)民主国家の宇宙戦争を描く『銀河英雄伝説Die Neue These』である(原作は田中芳樹氏の長編小説『銀河英雄伝説』、徳間書店、1987年に完結)。これらの作品に共通する卓越した設定は、一つの戦争という出来事を、対立する両陣営の視点からの二つの物語として提示した手法であると私は思う[9]。国民一人ひとりに主権者としての責任を求める民主主義理念の尊さを認めながらも、現実に存在する民主国家が他国への先制攻撃や無用な挑発、民間人虐殺にすら手を染めるさまも容赦なく描く後者の作品は、主人公を両陣営に1人ずつ置いている。現代日本を代表する文化の一つとなっているともいえる漫画・アニメーション作品で取り入れられている視点の複眼性が、現実の出来事を見るにあたっても、もっと必要なのではないか、ということが本稿のもう一つの問題提起である。
ウクライナの主な地名はキエフ/キーウ、ルガンスク/ルハンスク、ハリコフ/ハルキウ等、ロシア語・ウクライナ語両方の地名を持つことが知られるが、これは一つの出来事や事象が複数の見方や記憶の仕方をもたらすことの象徴ではないだろうか。
いずれにせよ、ストーン氏プロデュースによる両ウクライナ作品は、一見すると衝撃的な内容故に問題作であることは間違いない。そのため、オープンソース・インテリジェンス(インターネット上等にある信頼に値する公開情報との突き合わせ)およびファクトチェックの手法を用いて、適宜コメントも加えながら、できる限り検証していく。
なお当然ではあるが、本稿の目的が、今回の侵攻を正当化することではなく、その背景をより深くかつ多面的に知ることや、民主的討論を推進すること、ならびに表現・言論の自由への理解を深めることにあることを、念のためお断りしておきたい。
第1節 ネットフリックス作品『ウィンター・オン・ファイヤー』 (2015年)
まず知名度が相対的に高いと考えられる作品から始めよう。それは大手動画配信サイト―本稿第3節で問題にするプラットフォーマーの一つと見ることもできる―ネットフリックス自身が製作に関わったドキュメンタリー作品『ウィンター~』である。ネットフリックスでは日本語字幕版が視聴でき、ウクライナ侵攻開始後、ネットフリックスはユーチューブで英語字幕版を無料公開している。
監督は1972年生まれ、ロシア出身で米国在住のエフゲニー・アフィネフスキー氏。他にシリア難民の運命を扱った2017年の”Cries From Syria”等の作品があり、オスカー賞やエミー賞の候補になったこともある[10]。
この作品では、マイダン革命は、次のように描写される。2013年11月21日に、キエフ/キーウの独立広場で、ウクライナとEUとの連携協定締結を求める人々によるデモが始まる。当時、腐敗等の問題もあって国民に不人気だったヤヌコヴィッチ政権は、この協定を検討した上で取り下げ、ロシアとの連携強化を目指した。当初は学生を中心に、聖職者や医師等、様々な職業の人々が平和的なデモ活動を繰り広げていた。「国民は西へ、ヤヌコヴィッチは東へ」「僕らはヨーロッパ市民だ」といった印象的スローガンも見られる。人気歌手も応援に駆け付け、祭りのような明るい雰囲気だったことが映像からは窺える。
ところが当初は平和裏に行われていた抗議活動が、途中からウクライナ内務省の特殊部隊「ベルクト」等との衝突に発展する。負傷したデモ参加者の救護に当たった赤十字職員すら攻撃にさらされたという告発がなされる。途中で不可解な法改正が行われ、デモでのヘルメット着用が禁止された結果、鍋をかぶって抗議する人々の姿が印象に残る。取材を受けた市民によって、ベルクト側がゴム弾のみならず実弾すら用いて攻撃していたと断定される。デモ隊も火炎瓶―今回のロシアとの戦争でも広く使われている武器である―を投げて反撃し、双方の犠牲者が増えていく。退役軍人が「広場防衛隊」を訓練していた、といった背景も明かされる。
デモ参加者らは、①政治犯釈放②議会と大統領で権力のバランスを取ること③大統領選を実施することを要求し、その実現をデモ解散の条件とする。残念ながら、デモ隊と政府は一致点を見いだせず、革命支持者らが拠り所としていた労働組合会館が警察に攻撃され炎上する等、危機はエスカレートしていく。翌14年になってもこういった「諸問題」は解決せず犠牲者は増えていく。誰が先制攻撃して始まったか判然としない本格的銃撃戦の後、ついに一部の活動家らは大統領に辞任を要求、さもなくば攻撃すると警告する。その結果、大統領は2月27日までにはロシアに亡命し、映画では、ウクライナ国会で、革命支持派の思しき男性が、大統領は「憲法の規定にない手順」で辞職した、と宣言する。最終的には、93日間の闘争で、125人死亡、65人不明、1890人負傷という結果となったとされる。その後発足した新政権は、3月にEUとの連携協定に署名し、革命支持派の勝利に終わったことが示される。
この作品“だけ”を鑑賞した者は、恐らくその殆どが、ヨーロッパの一員となるべく立ち上がった市民たちが強権的政権による暴力的弾圧に負けず粘り強く抗議し続け、遂に権力者打倒という目的を達成した感動的な革命の物語として受け取るであろう。実際、例えば猪瀬直樹氏は、「とんでもない傑作」と絶賛し、現在の戦争にもつながるウクライナ人の「命をかけても圧政と戦う強いメンタル」を称えてやまない[11]。これはごく自然な反応であろう。
[1] エチオピア出身のテドロス・アダノムWHO事務局長の発言である。https://www.bbc.com/news/world-61101732
[2] なお本稿の構成については、ただでさえ『ウィンター~』の記述より『ウクライナ~』の記述がずっと長いのに、その上後者の実質的な続編である『リヴィーリング・ウクライナ』も第4節で詳しく扱うのは不平等ではないのか、といった批判がありうるかもしれない。だが日本で流通している情報全体を見れば、『ウィンター~』のような親欧米的見方が圧倒的に優勢であるのは明らかなので、その全体的不平等を是正する目的があることをご理解いただきたい。例えば『ウィンター~』を配信している大手プラットフォーマーたるネットフリックスについては、ストーン氏とロパトノク氏のウクライナ作品を対象としていない一方で、ゼレンスキー大統領の俳優としての出世作『国民の僕』は「人気の作品」として大きく扱っている。意図的ではないかもしれないが、結果的に偏っていることは否めない。特にストーン氏の両ウクライナ作品は、本稿で言及するように、非難を浴び、排除されることすらある作品であるため、私が詳しく検証したいという事情もある。
[3] マイダン革命と「今日のウクライナの惨状」の間に「直接の因果関係」を看取するのは私の勝手な独断でも独創でもなく、一部の専門家によっても認知されていることだ。松里公孝「未完の国民、コンテスタブルな国家」(『世界 臨時増刊号 ウクライナ侵略戦争』、2022年5月、52頁)。
[4] アーレントの”On Revolution”のドイツ語版からの邦訳である『革命論』(森一郎訳、みすず書房、2022年、1頁)を参照。ただし序論の訳注2によると、レーニンの言葉の出典は不詳とのことである(同423頁)。
[5] 松里公孝、前掲論文、42頁。
[6] 英語でも、私が検索した限りでは、ストーン氏による「独裁者へのおもねり」を非難する次のような記事が目立ち、冷静に検証した評論はなかなか見出せないようである。James Kirchick, “Oliver Stone’s Latest Dictator Suckup”, Daily Beast, April 14, 2017.
https://www.thedailybeast.com/oliver-stones-latest-dictator-suckup
[7] 「ウクライナで、ロシアで、いま何がおきているのか」(『月刊創』2022年5月号、創出版、14-15頁)。
[8] それに対して、ロシアを人食い巨人に準えるようなありがちな見方が皮相的であることは、原作全体の趣旨を踏まえれば、容易に理解できることであろう。
[9] 実写映画でこうした複眼的視点を追求した連作として、例えばクリント・イーストウッド監督の『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』を挙げることができる。
[10] この監督についての情報は、映画専門サイトIMDbに依拠している。https://www.imdb.com/name/nm1017958/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
[11] 「ウクライナ情勢は、Netflix『ウィンター・オン・ファイヤー』を見てから語れ
徹夜で見た猪瀬直樹がウクライナ関連映画を一気にレビュー(後編)」(『現代ビジネス』2022年3月26日配信)を参照。https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93743?page=2
三枝成彰氏の「ウクライナの『自由を求める民衆の闘い』を描いたドキュメンタリー」(『日刊ゲンダイデジタル』、2022年5月14日配信)も、『ウィンター~』だけを論じて称賛する点では、猪瀬氏と同じ傾向にある。https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/305152
私としては、『ウクライナ~』も見てから語れ、と補足したいところである。
第2節 オリヴァー・ストーン作品『ウクライナ・オン・ファイヤー』(2016年)
こちらの作品は知名度は低いが、そのエクゼクティヴ・プロデューサーはかの有名なオリヴァー・ストーン氏である。自らも従軍したベトナム戦争の悲惨さを訴えて世界的名声を博した『プラトーン』(1986年、アカデミー賞作品賞等受賞)。ケネディ大統領暗殺の謎に迫った『JFK』(1991年)。教科書では語られない祖国の知られざる歴史の発掘に挑んだ長編ドキュメンタリーシリーズ『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』(2012年)。アメリカ情報機関の機密を暴き、ロシアに亡命した諜報員・コンピューター技術者エドワード・スノーデン氏を取り上げた『スノーデン』(2016年)。まさに現代の米国を代表する反骨の社会派監督が、1968年に旧ソ連時代のウクライナに生まれたイゴール・ロパトノク(Igor Lopatonok)監督と組み[1]、自らインタビュアーとして出演もしているのが本作『『ウクライナ~』である。
近現代ウクライナの歩みと国内対立の問題
この作品では、まずヨーロッパとロシアの狭間にある西から東の通り道に位置するウクライナの過去が回顧される。それは、ポーランド、ロシア、オーストリア、ドイツ等常に「外来」勢力に支配され、ソ連崩壊まで統一国家となることがなかった、と総括されるものだ。第2次世界大戦中には、ソ連から独立するためという目的もあったが、歴史的に西欧との繫がりが強いウクライナ西部出身者を中心とするナチ親衛隊SSガリツィエンや、ウクライナ民族主義者同盟(OUN)がナチス・ドイツと協力した。OUNの最も有名な指導者の一人が反ユダヤ主義者・反共主義者として知られたステパン・バンデラ(Stepan Bandera, 1909~59 年)である[2]。2004年の「オレンジ革命」で成立した親欧米のユーシェンコ政権が、10年にバンデラを国民の英雄として表彰し、国際的物議を醸したこともある 。一方にとっての「英雄」が、他方にとっての「罪人」であることは、歴史的に見て珍しくないことだろう。
戦時下のウクライナでは、ドイツ軍とウクライナ民兵が協力し、何万人ものポーランド人やユダヤ人が殺害された歴史が紹介される[3]。より大きな問題として提示されるのは、こういった過激な民族主義的組織に連なっていた人々が、戦後もいわば米国の対ソ連戦略のコマとして利用され続けてきたことだ。例えば最も残忍なOUN指導者の一人として知られたミュコラ・レベド(Mykola Lebed、1909~98年)は、戦後処罰されることなく米国へ亡命し、CIAの協力者・反共活動家であり続けた[4]。
こうした公文書の保存・ネット公開についての米国の積極性は、近年公文書の改竄や破棄が問題になった国としては、見習うべきところが多いといえよう。たとえそこに記録されている内容がしばしばおぞましいものであるにしても。
これに関して私が補足しておくと、そもそも第1次世界大戦の末期には、ドイツやオーストリアも支援した「ウクライナ国民共和国」と、ソ連との間に戦争が発生したという事実も振り返っておきたい。ドイツがその後西部戦線で敗北し連合国に降伏したため、同共和国の独立を認めたブレスト=リトフスク条約は破棄され、同共和国は最終的にソ連に併合されたのである[5]。さらに約100年遡るナポレオン軍のロシア侵攻に際して既に、フランス側の一部にウクライナに傀儡国家を打ち立てるという構想があり、フランス軍を支持したウクライナ人も存在したという記録が残っているとされる[6]。ポーランド出身の米国人政治学者・政治家のズビグネフ・ブレジンスキーの「ウクライナなしには、ソ連はユーラシアの帝国であることをやめてしまう」という地政学的視点からの名言は、日本でも既にある程度人口に膾炙していると思われる[7]。そしてその政治的含意は、西側勢力によるロシア牽制・弱体化策として約200年前から事実上実践されており、現在の状況はその延長線上にあるとみることができるのではないか。この政策は、ウクライナ民族に元々内在する東西対立を利用していたといえる。こうした話題と関連して、ウクライナのNATO加盟問題を、キューバ危機に準える人は多いようだ。だがそれに加えて、第1次世界大戦中にドイツが、当時内乱状態にあったメキシコ(および日本)を味方に引き入れ米国と戦わせようと画策した故事も想起しておくのは、ロシアにとっての脅威感を推察する類比としてより有効であろう。周知の通り、メキシコはこの剣呑極まりない勧誘に応じることはなかった。にもかかわらず、こういった離間工作が露見したことが、有名なドイツによる無制限潜水艦作戦よりも、米国参戦の決定的要因になったとされているからである[8]。米国が「敵の敵は味方」という論理で、各地の右派的、宗教的、または民族主義的、軍政勢力と手を結んできたことは、歴史上よく知られている。ソ連に抵抗したアフガニスタン等のアルカイダ、チリの社会党系のアジェンデ政権を打倒したピノチェト派、北朝鮮に対抗した韓国の朴正煕軍事政権、フィデル・カストロらに倒されたキューバのバティスタ政権等、枚挙に暇がない。
本題に戻ると、ストーン氏とロパトノク監督の見立ては、こういった米国による露骨な介入が、特にウクライナでは近年まで続いているということだ。
ヤヌコヴィッチ・元ウクライナ大統領の視点と証言
この作品の中で大きな部分を占めるのが、マイダン革命で退陣したヴィクトル・ヤヌコヴィッチ元大統領へのストーン氏によるインタビューである。同氏は東部ドネツク州出身で、東部を地盤とする地域党の党首だった。ユーシェンコ政権では首相も務め、2010年には親欧米派のユリア・ティモシェンコ元首相に勝利して大統領に就任していた[9]。ヤヌコヴィッチ氏は大統領就任後にバンデラへの英雄称号授与を取り消した。一般に親ロシア派とみられているが、実際にはEUとも連携協定を目指していた。このように、境界国家として、東西の大勢力の間で絶妙なバランスを保つことが、現代ウクライナの生き方でもあったといえよう[10]。
注目すべきは、ヤヌコヴィッチ氏がEUとの協定を敬遠した理由である。EUとの協定は、当時ウクライナが支援を受けていたIMFによる要求をのむことが抱き合わせになっていた。それは、電気代・ガス代等の料金の大幅な値上げ等、国民に対する重い負担を含んでいた。さらには、ロシアとの取引を事実上制限することも条件とされた。こうしたウクライナ国民にとって不利になる条項が含まれていたため、元大統領はEUとの協定を延期し、むしろロシアとの協力強化に舵を切ったのだ、と主張する[11]。
この決断を直接的なきっかけとして起こったのが、キエフ/キーウの独立広場で始まった抗議活動だ。ストーン氏は、Consortium Newsという独立系米メディアのジャーナリスト、ロバート・パリー氏(Robert Parry)を主な取材対象者として、米国がマイダン革命で果たしていた役割を「革命のレシピ」として告発する[12]。
「革命のレシピ」とは
レシピの第1はNGOを通した資金提供である。全米民主主義基金(National Endowment for Democracy)を最も顕著な事例とするNGOが事実上、かつてのCIAの代わりとなり、標的とする国において、活動家、ジャーナリスト、企業への資金提供と訓練を通じて、しばしば当事国の利益に反する形で、アメリカ外交の利益に資する活動をさせているとされる[13]。
レシピの第2はメディアである。資金提供を受け設立された三つのテレビ局が、独立広場でのデモを支持し、ウクライナの人々に参加を呼び掛けたとされる。当初は平和的だった抗議活動だが、「右派セクター」等の極右勢力が紛れ込み、警官隊への先制攻撃を仕掛けたさまが、証拠映像つきで示される。ちなみにこの右派セクターは、他ならぬ米国務省が、「ユダヤ人やオリガルヒにではなく、ウクライナ人に属するウクライナ」の復興を目指すという反ユダヤ的傾向を憂慮していた団体である[14]。
作中で名指しされているテレビ局の一つにhromadske tvがある。私自身、作品中で提示されている同社の2013年の決算書の中で、オランダ大使館、アメリカ大使館、およびハンガリー出身の米投資家ジョージ・ソロス氏が設立した「ルネサンス財団」が約250万フリヴニャの寄付をしていることを確認した(1フリヴニャは通貨取引を行えるサイトIFC Marketsによると、2022年5月27日現在約4.6円である)[15]。ソロス氏が、ウクライナに財団を設立し、「現在までの出来事で重要な役割を担った」と語る映像も示される。
レシピの第3はテクニックである。デモに参加した人々の一部の実態は、上記の米国系NGOにより訓練されており、平和的な抗議活動を一瞬にして暴力的なものに変える能力を持つとされる。明快なスローガン連呼により群衆を一体化、熱狂させる技術は、2000年代にジョージアのバラ革命、ウクライナのオレンジ革命をはじめ旧ソ連圏等で連続した「カラー革命」に共通してみられるという。
ロシアでは批判的なメディアに対し「外国の代理人」という屈辱的なレッテルが貼られることはよく知られている。だがウクライナに関しては、外国からの資金を受けて露骨で暴力的な反政府活動が行われたのなら、この不名誉なレッテルが当てはまってしまう側面もあるのでは、と問うに値するだろう。
マイダン革命の核心へ
こうした知識を前提としてみると、「自由への戦い」として描かれたマイダン革命が、全く別の位相の下で現れることになる。
まず、故ジョン・マケイン米上院議員(共和党)、ウクライナ移民の子孫で民主党系のネオコン政治家として知られるヴィクトリア・ヌーランド(Victoria Nuland)国務次官補(2022年5月現在はバイデン政権の国務次官)ら米国の有力者らが、独立広場を訪れ、参加者らを公然と激励していたことが映像で明かされる。なぜ(当時欧米も正当性を概ね認めた)選挙で選ばれた政権を打倒するための活動を、外国の政治家が応援するのか、とヤヌコヴィッチ元大統領も首をかしげる。私達もまた、この状況の特異性を、日本に置き換えて考えてみる必要があると私は思う。また、いったいどの国で政府庁舎の占拠が許されるだろうか、と実際に起こった事件について嘆く。この時点で元大統領は知る由もない皮肉なことだが、2021年1月に、大統領選挙の結果を認めないトランプ派の人々が米連邦議会を襲撃して世界に衝撃を与えたのは周知の通りである。
ヌーランド氏に関しては、大きなスキャンダルも発覚している。何と彼女が、当時の駐ウクライナ米大使だったジェフリー・パイエット(Geoffrey Pyatt)氏と、革命後のウクライナの新政権の人事について、(後に実際に首相に就任した)アルセニー・ヤツェヌーク(Arseny Yatseniuk)氏は「経済に関する経験や、統治能力がある人物だ」等と具体的人名を挙げて相談していた通話音声が、リークにより明るみに出たことである。しかもヌーランド氏はこの通話の中で、EUを極めて下品な言葉で罵倒しており、その件で後に謝罪に追い込まれている。この事実から、米国の幹部らがこの革命に深く関与していたことは、否定し難いといわざるをえない[16]。
『ウィンター~』の項でも説明した通り、元来平和的だった抗議活動は徐々に暴力的になっていくが、最初の銃撃は、デモ隊が占拠していた音楽院の建物からだったという証言がなされる。さらに、革命運動の「司令官」を名乗っていた「人民運動」の指導者アンドレイ・パルビイ(Andriy Parubiy)氏が、「近日中に要求が実現されなければ、実力を行使する」と堂々と宣言する動画が提示される。ちなみにこのパルビイ氏は「ウクライナ社会国家主義党」(後の自由党)の創設者の一人であり、米誌「ザ・ネーション」も「ネオナチ」として問題視していた人物である[17]。
暴力はますます悪化し、過激派として国際的に知られる覆面をかぶった「右派セクター」の人々は政府庁舎を占拠し、野党と大統領との休戦合意にも応じず、結局はヤヌコヴィッチ氏退陣を求め続ける。映画では、同元大統領は暗殺未遂事件すらあったと証言し、最終的にロシアへと亡命した経緯が語られる。国会で弾劾手続きが上程されるが、賛成数が憲法の規定による全議員の4分の3に達しなかった場面が映像で示される。大統領の退陣または事実上の追放が、『ウィンター~』と『ウクライナ~』という両方の対照的作品で、正規の手続きを経ていなかったという認識で一致していることは大きな意味を持つであろう。
にもかかわらず米国務省は新政権を承認する。事後的に振り返ると、いまだに西側の盟主を自任する米国による承認という行為自体が、「クーデター」疑惑を払拭し、国際的な正統性を付与したという意味で、最大の支援だったといえるのかもしれない。新政権成立に対し、いずれもロシア系住民が多いウクライナ東部とクリミアの住民らで激しく反発する者が出る。特にクリミアでは、親ロシア派住民らが、キエフ/キーウの新政権を承認することを拒否する。親ロシア派が地方政府を占拠し、新自治政府が立ち上がる。一般に「併合」と表現されている出来事だが、米国側の調査でも、住民投票では96.77%がロシアとの合邦に賛成だったという事実が紹介される(ただし、ロシア軍が駐在する状況の中での投票であるので、不当な圧力になったのでは、という欧米メディアからの疑問も紹介されている)。
「オデッサの悲劇」と「自国民への戦争」という衝撃
翻ってキエフ/キーウの新政権の状況だが、欧米や国連からは歓迎され、ヌーランド米国務次官補自身の言葉で、米国がウクライナ「支援」—事実上は体制転換の助長―の為に50億ドルも投資してきたと語られる。ヤヌコヴィッチ政権の公約だった、東部ウクライナでのロシア語の第2公用語化は、ウクライナ・ナショナリストらの強い要求もあって反故にされる。東部ではデモが発生し、新政権派との衝突も発生。当時から正統性が疑われた新政権への猛烈な反発もあって、今日のウクライナ侵攻で主要戦場になっている東部のドネツクとルガンスク/ルハンスクに「人民共和国」が成立したのも、この頃である。戦闘はますます過激化し、ヤヌコヴィッチ元大統領は作中で、当時のアレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行は「自国民への戦争」もしくは「虐殺」を始めた、と糾弾する。2014年5月、南部のオデッサ/オデーサでキエフの新政権へのデモが発生したが、参加者らが建物に逃げ込んだところ、新政権支持者に火炎瓶を投げ込まれた結果、多くの焼死者が出た衝撃的な映像が示される。当時のロイター通信の報道によると、死者は少なくとも42人に上った[18]。これがいわゆる「オデッサの悲劇」である。やはり米国が支援したとされるバラ革命によって政権に就き、後に職権乱用等で祖国を追われた親欧米・反ロシアのミハイル・サーカシュヴィリ元ジョージア大統領が、ウクライナ国籍を得て、また米国から大規模な財政支援を受けた上で、オデッサ/オデーサ州知事に据えられたという珍事も紹介される。
以上が本作品の概要である。最後にナレーターは、主要メディアによる情報操作に気付き、身を守るよう、視聴者に呼び掛けて締めくくる。
[1] ロパトノク監督の情報はhttps://www.imdb.com/name/nm3153020/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
による。同監督のウクライナ関連作品としては、他に”The Everlasting Present – Ukraine: 30 Years of InDependence” (2021)がある。Dが大文字になっているのは、誤植ではなく、独立国でありながら外部に依存している実態を示唆していると思われる。同監督の作品は、動画サイトRumbleで視聴できる。
[2] ただしバンデラは、41年にウクライナ独立宣言をしてからは、ナチス・ドイツにより投獄されていた上、バンデラ派は戦争末期には敗色濃厚になったドイツ軍と戦闘していた時期もあり、事情は複雑である。バンデラが創立したOUNは日本では一般に知られていないと思われるが、1930年代には、当時の日本軍が極東に逃れたOUN活動家らと満州で対ソ連戦略のために連携していたという研究は興味深い(黒川祐次『物語 ウクライナの歴史』、中央公論新社、2002年、218-220頁)。
[3] バンデラ派によるポーランド人に対する「ジェノサイド」を告発する次の資料が詳しい。”1943 Volhynian Massacres – Truth and Remembrance”
https://nawolyniu.pl/ksiazki/pliki/1943ang.pdf
[4] これについては、私自身、ストーン氏が参照しているCIAの開示資料”To Catch a Nazi”で確
認した。https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000201220002-6.pdf
[5] http://www.encyclopediaofukraine.com/ のUkrainian National RepublicおよびUkrainian-Soviet Warの項目を参照。一時西部リヴィウを中心に分立し、介入してきたポーランドと戦火を交えた「西ウクライナ国民共和国」も含めた当時の経緯については、黒川祐次、前掲書、第6章が参考になる。
[6]http://www.encyclopediaofukraine.com/ のNapoleon BonaparteおよびNapoleonideの項目を参照。
このインターネット事典については、本稿付録を参照。
[7] “Without Ukraine, Russia ceases to be a Eurasian empire. “(Brzezinski, Z., The Grand Chessboard. American Strategy and Its Geopolitical Imperatives, Basic Books, 1997, p, 45.邦訳は山崎洋一訳『ブレジンスキーの世界はこう動く 21世紀の地政戦略ゲーム』、日本経済新聞社、1998年、68頁だが、拙訳とはニュアンスが少し異なる。)
[8] いわゆる「ツィンメルマン電報事件」を中心とした当時の経緯を活写したのが、バーバラ・W・タックマンの『決定的瞬間―暗号が世界を変えた 』(筑摩書房、 2008年)である。
[9] 「現代外国人名録2016」を参考にしている。https://kotobank.jp/word/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%20%E3%83%A4%E3%83%8C%E3%82%B3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%81-1687696
[10] 黒川祐次、前掲書、255頁でも、「ロシアとアメリカの間のバランスを巧みにとってその安全保障を確保」するウクライナの高い外交能力が評価されている。
[11] こうしたヤヌコヴィッチ元大統領の主張を裏付ける第三者からの資料として、オークランド研究所のフレデリック・ムーソー(Frédéric Mousseau)氏の論考”What Do the World Bank and IMF Have to Do with the Ukraine Conflict?”を参照。
https://ourworld.unu.edu/en/what-do-the-world-bank-and-imf-have-to-do-with-the-ukraine-conflict (Our Worldは国連大学が運営するサイトである)
この文書によると、IMFからの貸し付けは170億ドルで、ロシアからの貸し付けは150億ドルだったが、後者には天然ガスの33%引きが付帯していた。さらにEUとの協定には、ウクライナでこれまで許可されていなかった遺伝子組み換え食品の解禁、モンサント等のグローバル企業を受け入れる新自由主義的な規制緩和策等も含まれていた。さらにIMFによる緊縮財政策は、47~66%の所得税増税、50%のガス料金値上げ等を含んでいた。IMF・世界銀行によるこうした条件を見る限りだが、元大統領がEUとの協定よりロシアとの連携を優先したことは、二大勢力を両天秤にかけた上での冷静な熟慮の結果だと思われる。エコノミスト・日本大使館専門調査員として長年ウクライナに滞在した西谷公明氏も、IMFが要求した緊縮財政政策やEUとの連携協定がウクライナにとって著しく不利だったこと、ヤヌコヴィッチ元大統領はロシアとEUとの間で均衡を保とうとしていたことを指摘している。「誰にウクライナが救えるか 友ユーシェンコへの手紙」、『世界』2014年5月号、岩波書店、117-123頁を参照。
[12] パリー氏は2018年に死去したが、Consortium Newsは、今日のウクライナ戦争についても、有益な情報を提供し続けている。
https://consortiumnews.com/category/international/ukraine/
[13] 全米民主基金は、1983年にレーガン政権の下で設立され、90カ国以上で活動しているという。https://www.ned.org/about-the-national-endowment-for-democracy/
「明るいCIA」としての同基金による「民主化」支援が、「米国のための民主化であって、その国々にとっての民主化ではなかった」と告発するのは、紛争調停者として名高い伊勢崎賢治氏である。『長周新聞』「ウクライナ危機に国際社会はどう向き合うべきか 緩衝国家・日本も迫られる平和構築の課題 東京外国語大学教授・伊勢崎賢治氏に聞く」、2022年3月17日。https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/22976
[14] https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/
[15] https://www.ifcmarkets.com/ja/currency-converter/uah-jpy
https://hromadske.ua/finreports/fin_zvit_2013+(ENG).pdf
なおルネサンス財団は、現在はThe Open Society Foundations というより大きな財団の一部となっており、ウクライナだけで2019年には780万米ドルの予算を持っている。 https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/the-open-society-foundations-in-ukraine
[16] “US apology after EU Ukraine insult”(https://www.bbc.com/news/av/world-europe-26089672、2014年2月7日)。
[17]Lev Golinkin: Neo-Nazis and the Far Right Are On the March in Ukraine
https://www.thenation.com/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/
(2019年2月22日)
[18] “Dozens killed in Ukraine fighting and fire; OSCE monitors freed”(2014年5月4日)
▼▽▼▽▼▽
本稿はオリヴァー・ストーン氏のウクライナ作品を中心に据えた評論であり、『人文×社会』第6号、2022年6月号、49-86頁からの転載です。ウクライナでの戦争にも触れていますが、当然ながら戦争勃発当初の情報に基づいています。この戦争についての私のより新しい見解は、近刊の拙著『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(本の泉社)をご覧ください。ご感想やご質問は以下のメールアドレスにお送りください。elpis_eleutheria@yahoo.co.jp
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
●ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 嶋崎史崇
嶋崎史崇
独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki