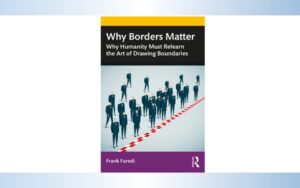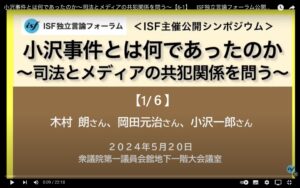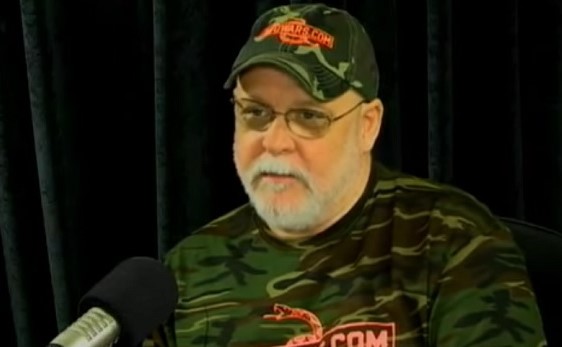第24回 一審は「弁護過誤」、控訴審は「裁判官不在」
メディア批評&事件検証足利事件の犯人として菅家利和さんが17年余り投獄された悲劇は、単なる裁判官たちの勘違いではなかった。裁判に新しく導入された「DNA型鑑定」という犯人を遺伝子を利用して証拠として裏付ける手法を一審、控訴審の裁判官たちが何も学ばずに裁判に臨んだ結果だった。
特に控訴審では、被告本人が法廷でDNA型鑑定のやり直し、まさに再鑑定をしてくれと叫んだ。しかし、裁判官たちはそれを無視した。真相を暴くチャンスを裁判官自ら葬ってしまったのだ。これが真実を見つける裁判と言えるのか。もし裁判官たちが鑑定のやり直しを命じていたら、控訴審で冤罪が明らかになったはずだ。まさに裁判官たちの怠慢という「悪夢」としか言いようがない。
そもそも警察庁の科学警察研究所(科警研)の見切り発車のDNA型鑑定に警察、検察、そして報道、最後の砦であるはずの裁判所は、「専門家が言うのだから間違いない」と何の根拠もなくこれを絶賛して信じてしまったのだ。しかも鑑定を学ぶことせずにだから、怠慢としか言いようがない。これが日本の裁判の現実なのだ。
裁判官人生の中で約30件もの無罪判決を出し、証拠に厳しい裁判官として検察に恐れられた木谷明元裁判官は、こう鋭いまなざしで一連の裁判を見つめていた。人によって心に響くものが違うかもしれない。私には一審は「弁護過誤」、控訴審は「裁判官不在」と聞こえた。
《一審裁判は、弁護士が科警研のDNA型鑑定と自白を妄信し、被告とされた菅家利和さんが犯人であることを疑わなかった。そのために捜査段階で自白していた菅家さんから、「やっていない」という真実の弁解を引き出すことができず、初公判から事実を認めるにまかせてしまった。捜査段階で接見した弁護士は菅家さんに「(迷宮入りの福島万弥ちゃん、長谷部有美ちゃんの2事件を含め)3件のうち1件もやっていないということはないんだろうね」などと語りかけたため、菅家さんは弁護人に真相を話せなくなったとされている。
さらに菅家さんが第6回公判で事実を争い出した後も、弁護士は、これを契機に弁解に耳を傾けることなく、むしろ否認供述を撤回させようとした。弁護人がついている被告人が公判廷で控訴事実を認めた場合、裁判所の有罪心証はそれだけで、決定的に固まってしまう場合が多い。一審における弁護士は、本件について誤った裁判を導く上で、決定的に重要な役割を果たしてしまったと言われてもやむを得ない。
被疑者・被告人は、厳しい取り調べを受けると、弁護人に対しても心を閉ざしてしまうことがあるから弁護人が被疑者らから真実を聴きだすことは、必ずしも容易なことではない。しかし、被告人の人権の擁護者であり、唯一の味方である弁護人は、被疑者・被告人からなんとしても真実の声を聴きだそうと努力する義務がある。弁護士は明らかにその義務を怠ったと言われてもやむを得ない。
検察については、1992年12月22日の一審の第6回公判で初めて否認に転じると、森川大司検事は閉廷後の拘置所まで出向いて菅家さんを追及し、「法廷で述べたことは真実ではない」と認めさせた。菅家さんは、この時点で被疑者ではなく、すでに「検察官と対等な立場の当事者である被告人」であったのであるから、検察官と言えども、こういう形で被告人を取り調べて追及することは許されない》と木谷元裁判感は厳しく指摘する。
さらに《裁判所に対しては、弁護人さえ、信じなかった被告人の弁解を裁判所に信用せよと求めることには難しい面もある。しかし「無辜(無実の者)を処罰しない」ことは、裁判所の最大の使命である。本件において第1審公判の終盤に至ってではあるが、菅家さんが事実を根本的に争い出したのであるから、裁判所としては、その弁解を真摯に受け止め、真相の解明に乗り出すべきであった。
特に被告人・弁護人が本格的に争い出した控訴審以降再審請求審までの裁判所が、菅家さんの弁解に全く耳を貸さなかったのは、なんとしても残念なことであった。
控訴審(東京高裁)は、佐藤博史弁護士が本格的に事実を争い出した以上、菅家さんが一審公判途中まで事実を認めていたとしても、その自白の信用性を慎重に検討するべきであった。
菅家さんの捜査段階での自白は、重要な点で変遷するだけでなく、客観的証拠とも矛盾する点があり、秘密の暴露もなかった。
また一審判決が重視したDNA型鑑定の出現頻度は、当初の1000人中1.2人から、サンプル数の増加した控訴審段階では、1000人中8.3人とされたことからも明らかなように、サンプル数の増加とともに出現頻度も増加する傾向があった(その後さらに1000人中35.8人と大幅に増加した)。このことからすると、少なくとも控訴審裁判所は、当初のDNA型鑑定に頼りきることに疑問を感じ、いっそう慎重な審理を遂げるべきであった。
この段階において菅家さんは、「DNA型鑑定は誤りだ。もう一度鑑定をやり直して欲しい」と主張していたのである。しかし、科警研のDNA型鑑定を妄信する控訴審裁判所は、自白調書の問題点を軽視してしまった》。

控訴審で弁護団が出廷した技官からDNA型鑑定の欠陥を証言させたにもかかわらず、控訴を棄却した東京高裁の高木俊夫裁判長
私は冒頭から「裁判官不在」と控訴審の東京高裁(高木俊夫裁判長、岡村稔裁判官、長谷川憲一裁判官)を痛烈に批判した。本来ならこの控訴審で冤罪を食い止めるチャンスがあったからだ。人の人生を裁判次第で変える重大な任務に就きながら、DNA型鑑定という新たな証拠手法を学びもせずに審理に臨み、判決をする裁判官の姿勢は資質に欠けると言わざるを得ない。これが中立な立場の裁判なのか、呆れてしまう。
控訴審が始まったのは、94年4月28日。初公判から菅家さんは無罪を主張した。もともと一審は、92年2月13日に始まり、同年末には日本DNA多型研究会の第1回学術集会で信州大学法医学教室の本田克也助手(当時)のグループが足利事件で使われた科警研によるMCT118型鑑定法の問題点を指摘していたのだ。

日本大学医学部法医学教室の押田茂實教授らのもとでDNA型鑑定実習を受ける佐藤博史弁護士ら日弁連の弁護士たち
しかも一審とは違って控訴審では、日本大学医学部の押田茂實教授(当時)のもとでDNA型鑑定の実習を受けた佐藤弁護士を中心とした新たな弁護団が編成され、出廷した科警研の技官たちが行った鑑定が果たして今でも信用に足るかどうか、徹底的に問うた。
弁護団は技官に「123塩基ラダーで示されている型が正しい繰り返す回数を表す型ではなかったということが分かった」と旧マーカーが正しい物差しの役目をはたしていないことを認めさせ、その時その欠陥に気づかなかったのか、と重ねて追及。技官は123ラダーによって出た数値は「結果としては(アレリックよりも)多少低め(数字が小さい)に出ていますけれど」と数値の誤差を認めさせた。技官はそれでも「当時、世界中の人で気がついた人はいなかったんじゃないかと思います」と証言したが、前述したが信州大の本田助手が欠陥を発見、警告していたのだ。技官らはその後何ら検証もしなかったことには触れなかった。
弁護団はずばり法廷で問題の鑑定の核心部分を技官から引き出した。「新しく導入したアレリックラダーは、塩基組成がMCT118部位の対立遺伝子である各アリルのそれぞれに対応するバンドを集めたものだ。この新マーカーは、同部位の塩基組成と同じもので構成されている。しかし、旧マーカーの123ラダーでは、基準である塩基組成が異なっているのに、それによる誤差が生じうることに気づかずに鑑定を行った」と。
さらに弁護団は「つまり、分からない部分があったまま、MCT118部位の分析をされてきたということになるわけでしょう」と鋭く追及。これに技官は「なにごとも基準というものは、最初は分からないもので始めまして、それでだんだん分かるものに変わってくると思うんですけども」と苦しい答えを主張したが、実際にはこの時点でも、旧マーカーの基準となる塩基組成は不明のままだった。
さらにもう一つ重大なことを法廷で明らかにした。科警研の鑑定における異動識別の判定は、電気泳動させたバンドパターンを写真撮影し、その画像を、本当かどうか分からないが、写真ではなく、特殊な解析装置で読み取って行っていたという。「それを記録したフィルムはどうしたのですか」と追及すると技官は「画像(フィルム)自体の保存はされていません」と重要なデータであるにもかかわらず、最初から保存しなかったことも白日の下に晒した。
こうして科警研によるDNA型鑑定の重大な問題の数々を弁護団は、法廷で認めさせた。裁判での手ごたえを感じた。だから主任弁護人の佐藤弁護士は、控訴審判決を翌日に控えた96年5月8日、東京拘置所に足を運び、笑顔で菅家さんと面会した。無罪判決への自信がそうさせたのだろう。自然と言葉が出た。「絶対無罪判決になると思う。釈放されたら、何をしたい?」。明日が待ちどおしかった。
控訴審判決の日が来た。「一審判決の事実認定に誤りはない」高木裁判長が下した結論は控訴棄却。裁判長が判決文を読み終えた直後、「自分はやっていません」。菅家さんの上ずった声が法廷に響いた。「あなたには残念だけれども、認められない」。高木裁判長はそう答え、閉廷を告げた。
もし控訴審段階で、DNA型再鑑定が実現されていたら、菅家さんが早期に釈放されるだけでなく、足利事件の公訴時効も成立せずに再捜査が可能になったかもしれない。控訴審裁判の誤判はとてつもなく大きい。
高木裁判長は2008年に病死した。在職中に足利事件だけでなく、懲役が確定したネパール人ゴビンダ・プラサド・マイナリさんが東京高裁に再審請求中の「東電OL殺害事件」をめぐり、東京高裁の裁判長として一審の東京地裁の無罪判決を破棄、無期懲役とし、2度も冤罪を作った。また無期懲役で服役し、仮釈放された石川一雄さんが東京高裁に第三次再審請求中の「狭山事件」でも、同高裁の第2次再審請求審の裁判長として請求を棄却している。こんな裁判官が07年に春の叙勲で瑞宝重光章とは、日本はやはり狂っている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
●ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
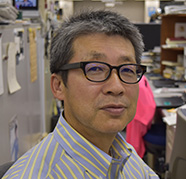 梶山天
梶山天
独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。