
アーレントと戦争の問題
国際政治一 戦争、政治、宗教 ――― ある違和感から
本日は、「戦争と宗教」というシンポジウムのテーマ設定を最広義に解して、「宗教哲学会という場で戦争について語り合う」という意味に受け止めさせていただきます[1]。他のお二人の実質的なご提題と比べ、場違いな話になるのは確実ですが、混ぜっ返しの話が一つくらいあってもいいのではないかと開き直っています。
というのも、私は、現代の政治的状況をめぐる議論において「戦争と宗教」が結びつけられていること自体に、強い違和感をおぼえるからです。
戦争とは、政治の領域での問題事象であり、この世の事柄です。戦争が現代人にとって重大な事象であるのは確かですが、この世を超えたものを志向する宗教を、この世的なものの極致のような戦争と直接結びつけて論ずるのは、スジが違うと思うのです。
――と、私としては宗教のためにと思って政教分離を強調したいのですが、伝統的二分法を振り回すと反発を招きそうですので、まずは時事的な話題から入ります。
2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻が報じられたとき、「今どき戦争が起きるなんて信じられない! なぜそんなことが起きたのか?」といった声が上がりました。「今の時代に戦争などあるはずがない」といった思い込みがそこにあるとすれば、それは21世紀の現実からして的外れです。
皆さんご存じのように、2001年9月11日のテロ事件のあと、アメリカ軍は無限の正義の御旗を掲げてアフガニスタンに侵攻しました。2021年に完全撤退するまで20年近くに及んだこの泥沼の戦いは、やはり19年間にわたったベトナム戦争と同じく、米軍の敗北で終わりました。アフガニスタンの人びとにとってタリバン政権のほうが米軍支配などよりましだったようです。2003年にはアメリカ軍はイラクに軍事進攻し、敵の大将を絞首刑にしたあとも居座り続け、2011年にやっと引き下がりました。めちゃめちゃにされたイラクの内政は今日なお混迷を続けています。アメリカが大義名分としていたイラクの大量破壊兵器は見つかりませんでした。自分たちにとって目障りな国だからと戦争を仕掛け、破壊行為をやり散らかしたことは、これはもう21世紀の戦争犯罪と言うほかありません。
現代世界の政治力学によって引き起こされているこうした戦争を、特定の宗教思想との関連で説明するのは、それこそ戦争犯罪に加担するようなものです。冷戦の終結後アメリカが一人勝ちを誇る時代に、その地球支配に対抗するには何かしら大義名分がなくてはならず、それが既成宗教の名の下に語られたりするのですが、その対抗勢力はあくまで政治的な性格のものであり、この世的に理解すべきです。そういった対立の構図を宗教がらみの話にして一般化するのは、問題を見誤らせる隠蔽工作と言われても仕方ありません。
ロシアのウクライナ侵攻にびっくりして、その背景にはきっと宗教的対立があるに違いないなどと憶測する前に、ウクライナを舞台として一体何が起こっているのか冷静に見つめることのほうが、よほど重要です。
これについては、少なくとも、2014年に――これまたアメリカに巧妙に誘導されて――起きた「マイダン革命」と呼ばれる反ロシア派のクーデタと、それ以後のウクライナ情勢を押さえなければなりません[2]。ロシア系の人びとの居住するウクライナ東部のドンバス地方が分離独立を宣言し、それをウクライナ政府が武力で制圧しようとし、ロシアとしては堪忍袋の緒が切れたという事情があるのです。そもそも、ウクライナがNATOに加盟し米軍の支配下に入れば、ロシアがどれほどの脅威と感じるかは、ちょっと想像力を働かせれば分かることです。われわれにそれが分からなくなっているのは、米軍の軍事支配にとっくに組み込まれてその脅威を感じないようにさせられているからです。複雑怪奇なウクライナ情勢については、しかし私はこれ以上語る資格を持っていません。
世の人はそれほどヒマ人ではないので、もっと単純に考えます。そしてテレビや新聞など大手マスコミの報道を真に受けて、ロシアは卑劣だ、プーチンは悪の独裁者だと決めつけます。その根底にあるのは、「ロシアに攻撃されているウクライナはかわいそう。善良なウクライナ人を蹂躙しているプーチンは邪悪だ。ゆえに、ロシア=悪、ウクライナ=善」という図式です。これは、ニーチェがルサンチマンの回路として暴き出した弱者道徳の見本のようなものです。不幸なウクライナ人を救え、との善意の声が地上にこだまし、第三次世界大戦を引き起こしかねないほどの危なっかしい大統領が、そのどさくさに英雄視されるありさまです。幼稚な勧善懲悪的決めつけは、政治的には百害あって一利なしです。アーレントが『革命論』で示したように、政治の世界に同情は禁物なのです[3]。
もちろん、ロシアとウクライナの交戦が続くのも、百害あって一利なしです。すみやかな停戦が望ましいのは言うまでもありません。それを阻んでいるのは何か。ロシアとウクラナとの衝突を望んでいる勢力が、事態をいよいよ泥沼化させているのではないか。そう問い直すことのほうが先決です。反ロ・親ウの一方的立場にこれ以上加担するのは、逆効果です。長年築かれてきた日露関係もズタズタにされてしまいました。隣国との関係が破綻すれば――アメリカは大喜びでしょうが――北方領土問題をはじめとして日本がどれほどのものを失うか、冷静に見積もるべきでしょう。
プーチン政権は戦争に行き詰まって早晩倒れるだろう、そうすればロシアは民主化して世界平和が実現するだろう、など幻想もはなはだしいのです。2010年末から連鎖反応的に起きた「アラブの春」は、中東の国々を混乱に陥れました。民主化と称されるものが、内戦という名の地獄に導くのです。革命はたんなる政変やクーデタとは違います。体制が覆されることで以前よりもっと劣悪な状態に陥ることのほうが多いのです。人民に自分たちの国をどう立て直すかの合意と協和がないかぎり、迷走は必至です。権威の失墜と権力の喪失は暴力の連鎖を招くのみ、とは『革命論』でアーレントが警鐘を鳴らすところです。
停戦に向けての名案は、容易に見出せそうにありません。民主主義対権威主義といった子ども騙しの善悪二元論に安住している者に、そんな超難問がどうして解けるでしょうか。われわれにできることは、どこに問題の本質があるかを、頭を冷やして熟考することのみです。もちろんそれは政治哲学的省察であっても、宗教哲学的思弁ではないはずです。
そのためにも現代の文脈からいったん離れ、少し遠目で眺めてみることが肝要です。以下では、アーレントが戦争について省察している二つのテクストから示唆を得て、現代における哲学的戦争論の可能性を遠望したいと思います。
二 核時代の戦争問題――『革命論』序論から
さきに、「なぜ戦争が起きてしまったのか?」というありがちな反応にふれました。そこには、「今の時代に戦争など起こるはずがないのに」という聞き捨てならない思い込みが聞きとれます。「いつ人類は戦争を卒業したのか?」と聞き返したくなります。
20世紀という「戦争と革命の世紀」は過ぎても、アメリカは世界各地に軍事拠点をもち、戦争を次々に引き起こしています。その好戦性が問題にされないのは不思議です[4]。それどころか、アメリカ軍がウクライナを援護すべく参戦しないことを、意外に思う人さえいます。あたかも、アメリカが地上を軍事的に制圧しているのが当然であるかのように。
しかしその一方で、戦争はもう時代遅れだと、われわれ現代人がどこかで感じているのも事実です。その違和感からわれわれは、戦争が起こる原因として、つい宗教を想定したくなるほどです。イスラム教や東方教会の伝統からすればほとんど濡れ衣なのに、です。
考えてみれば、神の死後にどうしてそんなに宗教戦争が起こるのか、いぶかしく思います。これに対しては、いや、神はまだ死んでいない、ニーチェの言葉はやはり間違いだった、と反応する向きもあるでしょう。しかしその前に再確認すべきことがあります。ニーチェが「神は死んだ」と最初に記した『愉しい学問』には、何と書いてあったか。
ニーチェは、神の死後、何千年にもわたって「神の影」が人類を悩まし続けるだろう、と述べています[5]。それが、断片108番「新たな戦い」の言わんとするところでした。
だとすれば、こう理解できそうです。――神の死後にも人類は、遺影のような「神の影」に付き纏われ、それに翻弄されたあげく戦争を懲りずに繰り返しているのだ、と。
とはいえ、「神は死んだ」という診断は、なにも宗教にのみ関わるものではありません。上で強調した通り、現代の戦争を宗教に引きつけて理解したつもりになるのも的外れです。そこでニーチェにあやかりつつ、ここで別の補助線を引いてみることにします。ニーチェの言葉「神は死んだ」になぞらえて、私は「戦争の神は死んだ」と言いたいのです。
この「戦争の神の死」という時代認識を、私は、ニーチェ解釈[6]のみならず、ハイデガー解釈[7]やアーレント解釈[8]でも提起しましたが、ほとんど何の反響もないので、ここでもう一度繰り返させていただきます。
まず、神が死んだからといって安心するのは早いのです。神の死後、何千年にもわたって人類は、神の影に取り憑かれることだろう、とニーチェは予言しました。神の死は、過去の事柄ではなく、今後しつこく人類にとって大問題であり続けるだろう、と。
それと同じく、私が「戦争の神は死んだ」と言うとき、だからといって人類は戦争から解放されたなどと言いたいわけではありません。その逆です。戦争の神の死後はじめて「戦争の神の影」との戦いの火ぶたが切って落とされたのです。
それにしても、戦争の神はどうして死んだのか。そう訊かれることでしょう。これについては、私はアーレント『革命論』の序論「戦争と革命」から多大な示唆を与えられました[9]。この序論にはアーレントの戦争論が披瀝されています。
人類は古来、「戦(いくさ)」というものに積極的意義を飽かず見出してきました。軍神の崇拝から英霊の顕彰まで、発明には事欠きませんでした。しかし、20世紀に核兵器という最終絶滅手段を手に入れたことによって、人類は戦争を意義づけることが総じてできなくなりました。そういう意味で、戦争は決定的に時代遅れとなったのです。これが、「戦争の神は死んだ」という言葉で私が言い表わそうとするものです。
ロシアのウクライナ侵攻が報じられて、今どき戦争が起こるなんて意外だ、という反応が多かったのも、これに由来します。しかし、この地上で戦争はべつに終わっていません。戦争の神は死んでも、いやだからこそ、戦争の神の影はドス黒く残存しています。人類は戦争ときれいさっぱり縁を切ったどころか、最終絶滅戦争が執行猶予のまま仮想戦争ゲームにうつつを抜かす人類史のエポックがようやく始まったのです。
のみならず、戦争は各地で依然として頻発しています。それが飛び火して人類自滅戦争がいつ勃発するかもしれず、そうなることには何の意味も見出せないままに、戦争はダラダラ続いています。第二次世界大戦後の朝鮮戦争しかり、幾度もの中東戦争しかり、ベトナム戦争しかり、湾岸戦争しかりです。
「神が死んでやれやれ」と解放感に浸っている場合ではないのと同じく、「戦争の神が死んでくれて本当によかった」と喜び合ってはいられないのです。人類が賢くも平和に目覚めて戦争を放棄するに至ったのでは毛頭なく、戦争にのめり込んで軍事技術があまりに発展しすぎて自滅しそうになったから、だから戦争にうつつを抜かすことが不本意にもできなくなったというだけなのですから。
しかしだからといって、原子爆弾の爆発の以前と以後とで時代が隔絶してしまったことを忘れるべきではありません。
核テクノロジーとの何千年にもわたるであろう濃密な付き合いが始まったのが、1945年8月でした。ロシアがウクライナの原子力発電所を占拠したと衝撃的に報じられたり、ロシア大統領が核攻撃の可能性もあるとチラつかせたと喧伝されたりするのは、まさに「戦争の神の影」におののく時代だからこそなのです。
核兵器の暴発と核反応器の暴走の危険と隣り合わせに生きていることを、われわれは改めて実感しました。だとすれば、何千年も続く核時代にふさわしい、したたかな知恵というものがあってよいでしょう。そこで、話は急に飛ぶようですが、私はこう思うのです。核時代に生まれた平和憲法をいかに活かすかという「活憲」の創意工夫が試されている、と。
新しい始まりは、いつまでも古くならず、将来的であり続けます。国の根本を定めた憲法が古くなったからそのつど時代に合わせてマイナーチェンジすればよい、と思うのは愚かです。しかしだからといって、護憲教条主義的な思考停止は御免蒙りたいと願っています。求められているのは、積極的な意味での憲法批判です。そして、批判吟味に耐えた憲法からその可能性を引き出して平和を戦いとろうとする戦略的思考です。憲法は賞味期限切れであるどころか、革命的な新しい始まりをひらく力を秘めているのです。
そう私は確信していると、『アーレントと革命の哲学』に記しましたが、戦争の神の死に関しては、もう一つ考えなければならないことがあることに気づきます。
絶滅戦争の様相を呈した第二次世界大戦の最終段階で原子爆弾が開発され、かつ実用されたことで、戦争の神は死んだ――これが、戦争の神の死という出来事の内実なのですが、戦争の神が死んだことをなんとしても認めようとしない国が一つあります。原爆を日本に投下した当事国です。
絶滅戦争が戦われた地上では「軍神」は軒並み消え失せたはずでした。しかし、自分たちが落とした原子爆弾の威力で第二次世界大戦を終わらせ、最終的に勝利を収めたのだ、と堅く信じている国では、戦争の威光はいまだに健在です[10]。戦争の神を葬り去っておきながら、それを絶対認めたがらない国が、戦争に前のめりなのは腑に落ちる話です。
惨敗を重ね、無条件降伏要求を突きつけられた大日本帝国は、たとえ国全体が焦土に帰そうとも国体は死守しなければと信じ込んでいましたから、無条件降伏はできない相談でした。しかし、参戦してきたソ連に攻め込まれて共和制にさせられることだけは避けたいと考え、その前に、まだしも交渉の余地のありそうなアメリカを相手として降伏に踏み切ったのです。アメリカとしても、天皇制をどうすべきか考えをめぐらせたすえ、占領政策を円滑に進めるには好都合だと分かったので、天皇をその地位に居残らせました。
そうした相互取引が簡略化されて、原爆が戦争を終わらせた、という神話が出来上がったのです。また、同じ事態を敗戦国に都合よく簡略化すれば、天皇が英断で戦争を終わらせた、となります。降伏後には天皇制維持を認めてもらったうえに、共産主義の影響を殺ぐうえで占領軍を当てにした、天皇を中心とする被占領国は、米軍の傘下に入ってその庇護を受けることを選んだのでした――沖縄を犠牲に捧げて、です。
占領時代に制定された日本国憲法は、戦力不保持を謳う一方で、アメリカ軍という強大な軍隊の存在には触れていません。米軍は占領時代が終わっても日本からいっこうに引き上げず(最長とされるアフガニスタン駐留でも20年足らずで撤兵したのにです)、東アジアの軍事的緊張をせっせと作り出してはみずからのプレゼンスを正当化してきました。米軍の居残りが長すぎて――日本各地にあった米軍基地を沖縄に集中させたことも一因です――大多数の日本人は事態の異常さを気にも留めなくなってしまいました。
自衛隊は違憲かという議論はあっても、在日米軍が平和憲法に抵触するかは、砂川事件の伊達判決後、問われなくなりました。天皇の上に日米安全保障条約(と日米地位協定と密約)が君臨している戦後体制と一体となってきたのが、日本国憲法だったのです。
ロシアが千島列島の返還交渉に応じる気がないのは、かりに日本に返還すれば、アメリカがそこを軍事拠点とするに違いないと疑っているからです。そして、そう疑われるのも無理はありません。それに、そうでなくとも日本列島は米軍の前哨基地なのです。
東アジアでは米日韓の軍事的一体化が進み、中国との緊張が高まっています。それと同じくヨーロッパでは、冷戦後に大義名分を失ったはずのNATOが我が物顔で居座り、勢力を拡大し続けています。もちろんこのことは、ロシアに対する公然たる挑発となっています。アメリカ中心の軍事同盟が、ソ連消滅後もロシアに敵対姿勢を露わにし、東欧にロシア包囲網を張りめぐらせていることが、問題の根本にあるのです。ロシアが、隣り合わせのウクライナまでNATOに加わるのは絶対困ると思うこと自体は、覇権主義的とは必ずしも言えません。勢力拡張にいそしんでいるのはアメリカのほうです。ウクライナ問題の本質は冷戦後のNATOの跳梁跋扈にある、と見るのが公平な見方というものでしょう。
東アジアにしろ、東ヨーロッパにしろ、アメリカは対抗勢力――今日ではとりわけ中国とロシアですが、かつては大日本帝国もそうでした――を煽って、それぞれの地域で対立を激化させては、自勢力圏における米軍常駐と軍備増強要求を正当化し続けているのです。今日の日本は、その恰好の餌食になり、ぐうの音も出なくなっています。
アメリカの支配圏の拡大はなんら咎められず、そのアメリカと対立する国の悪辣さばかり強調されるのは、明らかにバランスを逸しています。あたかも、唯一の超大国アメリカと張り合う大国があってはならない、とでも言わんばかりです。しかし、唯一の超大国による世界一元支配ほど危ういものはありません。
アメリカが自国の利益拡大をねらって巧妙に立ち回るのは、国際政治の常というものでしょう。むしろ問題はその政策を、平和志向の民主主義国の善意や正義だと勘違いすることのほうです。国益がぶつかり合い、駆け引きが演じられるのが外交です。大義と利害のひしめく場で多元的な力が干渉し合い、しのぎを削っている状態こそ健全なのです。
ロシアや中国やその他の国々がアメリカと張り合うこと自体は、独立国家として当然のことです。反米勢力は消えてなくなるのが望ましいなどと言えるはずもないのです。人類にとってもアメリカ自身にとっても、です。日本やドイツもアメリカと対等に渡り合うことをめざすべきでしょう――いやしくも独立国家であろうとするのであれば。
続いて、張り合いを重んずるアーレントの戦争論に、急ぎ目を転じましょう。
三 アーレントの戦争論――『政治とは何だろうか』の戦争問題
アーレントが『革命論』の序論で披露した戦争論と近い関係にあるのが、『政治とは何だろうかWas ist Politik?』中の「戦争問題Die Kriegsfrage」草稿です。
『政治とは何だろうか』[11]は、ドイツのピーパー社から『政治入門Einführung in die Politik』という書の執筆を依頼されたアーレントが、『人間の条件』(『活動的生』)と『革命について』(『革命論』)を刊行した間の期間に、この両主著に跨がる内容を述べたもので、結局公刊されずにとどまった遺稿です。その中心をなす二つの草稿「第一章 政治の意味」、「第二章 戦争問題」は、前後に公刊された二つの主著にそれぞれ深く関連しており、アーレント政治哲学概論の趣のあるテクストです。「政治の意味」が、『活動的生』エッセンスの感があるのに対して、「戦争問題」で展開されている戦争論は、『革命論』序論よりずっと規模が大きく、『革命論』の本論でも論じられていない内容を相当含んでいます。
『政治とは何だろうか』の全体を貫く問題意識は明瞭です。つまり、全体主義と原子爆弾という二つの「われわれの時代の政治的根本経験」(WP, 30)がそれです。その過酷な経験を通して、現代では「今さら政治に意味などあるのか」(WP, 28)という問いが避けられなくなっているというのです。アーレントはこの状況をあえて逆手にとって、「政治の意味とは自由である」(WP, 28)と言い切り、いわば自由の政治哲学を企てるのです。
『活動的生』の「ポリス的なもの」の真珠採りの解釈学の再説ともなっている、その「政治の意味」論をここで追うことはできませんが、注目すべきは、アーレントが現代人の根本経験として、全体主義と並んで原子爆弾を挙げている点です。ナチズムに典型な全体主義の問題にこだわり続けたことで知られるアーレントですが、彼女なりに原子力の問題をもう一つの重要テーマとしていたことが分かります[12]。そして、20世紀のこの二大テーマに通底する「戦争問題」として浮上してくるのが、「絶滅戦争」なのです。じつに、「現代人を脅かしている絶滅戦争の政治的意義を省察すること」(WP, 91)こそ、『政治入門』後半の「第二章 戦争問題」の賭金にほかなりません。
では、アーレントは「絶滅戦争Vernichtungskrieg」をどう理解しているのでしょうか。定義らしきものを探すと、次の説明が見出されます。
ここで〔=交戦国政府間で平和条約が結ばれて戦争が終わるのではもはやなく、勝利によってもたらされるのが敵国の国家的絶滅、いやそれどころか物理的絶滅だという場合に〕むしろ問題となるのは、交渉の対象にはもちろんなりえないこと、つまり一つの国や一つの民族の実存そのものである。この段階になると戦争はもはや、敵対する国の共存を所与として前提して、国家間に生ずる紛争を暴力によって調停することのみを求めたりはしなくなる。この段階ではじめて戦争は、政治の手段であることを本当にやめてしまい、絶滅戦争と化して、政治的なものによって定められた限界を突き破り、かくして政治的なものそれ自身を絶滅させ始めるのである。(WP, 87)
一国たとえばソ連、一民族たとえばユダヤ人を絶滅させることが、それ自身目的となるのが「絶滅戦争」、別名「全体戦争totaler Krieg」[13]です。つまり「絶滅戦争は、全体主義体制に適合する唯一の戦争」(WP, 87)なのです。ところが、全体主義国はその流儀を相手方の非全体主義国にも強いるので、全体主義的方式を相手国も引き受けざるをえなくなります。絶滅戦争を仕掛ける相手と戦うことは、絶滅戦争の流儀で戦うことになるのです。
とはいえ、この地上で国家が敵国の絶滅をもっぱらめざして戦争を繰り広げることには、どうしても人的、物的な限界がありました。「人類史上最大の惨戦」[14]と称される「独ソ戦」にしても、絶滅というまがまがしい形容に現実が完全に沿うには――ソ連の兵士と人民の多大な犠牲の下に――まだ至りませんでした。
絶滅戦争が現実味をおびて人類に立ち現われたのは、第二次世界大戦中の二通りの「絶滅手段」の発明によってでした。一つは無条件降伏要求、もう一つは原子爆弾です。
ヒトラーのドイツとの戦争に臨んでアメリカ大統領ルーズベルトがあみ出したのは、「無条件降伏の要求」(WP, 86)でした[15]。それは、いかなる交渉も譲歩も拒否し、もっぱら相手国の「虚無化Vernichtung」をめざすものでした。敵国を無に帰したうえで「浄化」し別の国に作り直すことに、戦争の大義が見出されたのです(戦争によって他国に革命もどきを起こすというおせっかい方式がこれ以後定着します)。これによりドイツは、国家壊滅に行き着くまで降伏できなくなりました。妥協を許さないその方式は、国体護持を第一義とする日本にも、容赦なく適用されました。それによって何が起こったか。無条件降伏要求に猛反発し、死に物狂いで徹底抗戦するという狂気が、引き出されたのです。日本が戦争末期に、いわば一億総玉砕の自滅戦法にまで追い詰められた理由は、ここにあります[16]。
絶滅方式の玉突き的連鎖は、無条件降伏要求に到り着いただけではありませんでした。ナチ・ドイツに先んじるためにはやむをえないという名目で開発の始まった核分裂エネルギー利用は、全体主義型の絶滅戦争に対抗するそれ自身、絶滅戦争用の超-兵器でした。しかもその殲滅兵器が、「帝国主義的」でこそあれ「全体主義的」とは言い難かった日本――とアーレントは述べています(vgl. WP, 87)――に対して、実戦で使用されたのです。
全体主義と無条件降伏と原子爆弾は、絶滅戦争の時代に一連の現象として立ち現われてきたことが分かります。ちなみに、全体主義の特徴としてアーレントが『全体主義の起源』でつとに挙げたのは、「絶滅収容所Vernichtungslager」でした。原子力発電所とはもう一つの「虚無化(フェアニヒトゥング)基地(スラーガー)」だ、と私は述べたことがあります[17]。現代世界を理解するうえでの最重要語の一つは、「絶滅・虚無化Vernichtung」なのです[18]。
絶滅戦争という極端な戦争観は、平和志向のわれわれ現代人には縁遠いものであるかに見えて、第二次世界大戦以降のわれわれの発想を規定し続けています。極悪の支配者に導かれて戦争を引き起こした国は、体制を覆して国全体を総入れ替えするに限る、とわれわれが思い込んでいるとすれば、それは勝者による虚無化的介入を理想としているのです。敗戦国日本がかつてそうされたように。
さて最後に、アーレントの『政治入門』にもう少し学びましょう。アーレントが古代ローマの知恵から引き出す視点は、絶滅戦争的発想から脱却するうえでの重要な示唆を与えてくれるからです。
アーレントによれば、絶滅戦争は「政治のうちにいかなる場所も占めてはならない」(WP, 105)。なぜか。アーレントはこう説明を続けます。
あるものが、感覚的なものの世界と同様、歴史的-政治的なものの世界のうちで現実的であるのは、当のものがあらゆる側面から示され、知覚されうる場合だけである。これが正しいとすれば、現実一般を可能にし、現実が存続することを保証するためには、人間や民族の複数性ならびに立場の複数性がつねに必要である。言いかえれば、世界が成立するのは、複数の遠近法(ペルスペクティーフェ)が存在することによってのみである。世界はそのつど、世界の物があれこれの視点から多様に眺められたその秩序としてのみ存在する。(WP, 105)
絶滅戦争を批判するために持ち出されるこの考察は、アーレント独自の現象学的存在論にもとづいています。存在するとは現われることであり、その場合、現われは、多様な観点から見られるものでなければならない。何かが現実的(リアル)であるとは、単一の視点にではなく、複数の視点にそれぞれ異なって現われるということである。逆に、たった一人にしか映じない世界というのは、無きに等しい。それゆえ、観点の複数性を消去し、唯一の観点しか認めないのは、世界そのものを消滅させるに等しいのだ、と[19]。
世界は複数の視点から眺められるときにこそ現実的に存在するのであり、単数の視点からしか眺められなくなるとき、世界はもはや現実性を失う。――この複数性の思考をアーレントは、あえて古代ローマから引き出そうとします[20]。古代ローマと言えば「ローマ帝国」、そしてその連想で「帝国主義」しか思い浮かべられない貧弱な想像力とは異なり、ここで引き合いに出されるのは、トロイア戦争という太古の絶滅戦争――「絶滅戦争の原型」(WP, 91)――を逃れて、アエネーアスに率いられイタリアの地に都市を創設したローマ人です。ギリシア人に対する対抗勢力として古代世界を豊かなものとしたローマ人は、「降伏者を容赦するparcere subiectis」(WP, 115)という、殲滅型ギリシア人には望むべくもなかった徳を発揮し、戦争のあとで――相手を殲滅することなく――和平を結んで、かつての敵と友好関係に入り、平和共存することができたのです。
これと異なるのが、冷戦後のアメリカ勢力圏拡大路線(別名グローバル化)です。
東西陣営が第三次世界大戦の勃発に怯えつつ核戦力を誇示して対峙し合うという時代が終結した冷戦後の世界。それは、多様なものの共存の時代であるはずだ、とわれわれは想像していました。ところが、戦後に温存された絶滅戦争の発想はいつまで経っても精算されず、仮想敵国が次々に作り出されては、その邪悪さが喧伝され、その体制崩壊が正当化されます。第二次大戦以来われわれの習い性となった、敵を根絶しなければ気がすまない共存拒否的発想こそ、いちばん危ういのであり、現代世界の軍事的緊張を高めているのです。正義の御旗を独善的に振りかざすその偏狭ぶりたるや、アメリカに対抗する勢力の存在をひとしなみに悪と決めつける愚かしさです。
気がつくと、アメリカの新保守主義者の頭脳の中のみならず、東アジアに住むわれわれの脳天気なイメージの中でも、北朝鮮はもとより、ロシアや中国にも「悪の帝国」のレッテルが貼られているありさまです。あたかも、北朝鮮王朝はもちろん、現ロシアも現中国も崩壊してアメリカの一強支配が貫徹する東亜新秩序こそ、めざすべき理想郷であるかのように。しかしその遠大な理想の実現のためには、現にある隣国を虚無化しなければならないことには、心優しい平和愛好者たちは思いを致すということがありません。
ついでに言えば、平和憲法の精神を鼓吹し、口を開けば戦争絶対反対を念仏のように唱える平和主義者の発想も、絶滅戦争という極端な戦争観によって規定されているように思えてなりません。ひょっとすると、平和憲法の戦争全否定の論理にも、全か無かの二者択一を迫るがごとき危うさがあるのでは、と一度疑ってみたほうがよいでしょう。
だいいち、日本国のいったいどこが平和国家なのでしょうか。これだけの軍事要塞列島が。米軍(とその基地)とその二軍(つまり自衛隊とその基地)がひしめいている国の憲法が、戦力不保持を唱えているのは、どう見てもお笑いぐさです。世界有数の軍事費を「防衛費」などと取り繕う真似を、いつまで続ける気なのでしょうか。在日米軍の駐留費を思いやりたっぷりに払わされていることは、違憲ではないのでしょうか。
最後に、繰り返しになりますが、東アジア諸国間の緊張を高めている元凶は、ロシアでも中国でもなく、米軍のプレゼンスです。このことを、現代日本で戦争について省察しようとする者は直視しなければなりません。現代における哲学的戦争論の可能性もそこからはじめて摑みとられることでしょう。(了)
▼▽▼注釈▽▼▽
[1] 本稿は、2023年3月25日に京都大学文学部で行なわれた宗教哲学会第15回学術大会のシンポジウム「戦争と宗教」の提題用原稿の再現である(当日のシンポジウムでは、時間の関係で原稿の最初と最後の読み上げをスキップした)。提題者は森のほか、高橋沙奈美氏(九州大学)と芦名定道氏(関西学院大学)、コメンテーターは氣多雅子氏(京都大学)、司会・趣旨説明は秋富克哉氏(京都工芸繊維大学)であった。
[2] 「マイダン革命」に関しては、オリヴァー・ストーン監督のドキュメンタリー「ウクライナ・オン・ファイア」(https://www.youtube.com/watch?v=pSDZpw1EZsQ&t=92s)は必見。続編「リヴィーリング・ウクライナ」(https://youtu.be/1yUQKLiIoFA)もある。どちらも日本語字幕付き。ストーンや親ロシア派の主張がそのまま真実というわけではもちろんないが、現在量的に圧倒している欧米側およびウクライナ政府側の情報を相対化する解毒剤のような機能は果たしうるであろう――とは、情報提供してくれた嶋崎史崇氏の見解。
[3] 拙訳ハンナ・アーレント『革命論』みすず書房、2022年、第二章「社会問題」を参照。
[4] 2023年3月19日の新聞報道によると、国際刑事裁判所(ICC)はプーチンに戦争犯罪の容疑で逮捕状を出したという。しかしアメリカは、世界各地で犯してきた戦争犯罪を追及される恐れがあるため、ロシアやウクライナと同じくICCにそもそも加盟していない。
[5] 「新たな戦い。――仏陀の死後、なお数百年もの間、ある洞窟に仏陀の影が映っていたという――巨大な恐るべき影が。神は死んだ。だが、人の世の常として、おそらく、さらに何千年もの間、神の影の映ずる洞窟が存在することだろう。――ということは、われわれは――われわれは、神の影にすら打ち勝たねばならないのだ。」(拙訳ニーチェ『愉しい学問』講談社学術文庫、191頁)
[6] 拙論「学問と生――ニーチェに学んで戦いを生きる」(『理想』第705号、理想社、2021年2月、所収)。
[7] 拙著『核時代のテクノロジー論――ハイデガー『技術とは何だろうか』を読み直す』現代書館、2020年、第5章。
[8] 拙著『アーレントと革命の哲学――『革命論』を読む』みすず書房、2022年。
[9] 『アーレントと革命の哲学』の序論を参照。以下の記述はこれに基づく。
[10] アメリカほどではないにしろ、独ソ戦という絶滅戦争を戦い抜いたロシアでも、戦争の神の死は十分認知されていない。中国を含む第二次世界大戦の勝者――連合国つまり国際連合安全保障理事会常任理事国――の間では事情は似たり寄ったりなのである。
[11] Hannah Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus Nachlaß, hrsg. von Ursula Lutz, Piper, 1993, Ungekürzte Taschenbuchausgabe, 2002. 本書をWPと略記。邦訳は、ハンナ・アーレント『政治とは何か』佐藤和夫訳、岩波書店、2004年。このドイツ語テクストの英訳が、アーレント遺稿集『政治の約束』に収録されている。Hannah Arendt, The Promise of Politics, ed. by Jerome Kohn, Schocken Books, 2005. この英訳からの重訳が、ハンナ・アレント『政治の約束』高橋勇夫、2008年、ちくま学芸文庫、2018年、である。
[12] 『政治入門』における原子力問題の究明については、拙著『死を超えるもの――3・11以後の哲学の可能性』(東京大学出版会、2013年)の第9章「アーレントと原子力の問題Ⅱ――戦争論への寄与」で論じたことがある。
[13] 「総力戦」の時代が開幕したのは第一次世界大戦においてだが、ここでの「全体戦争」は、全体主義の登場と結びつけて理解すべきものである。
[14] 大木毅『独ソ戦――絶滅戦争の惨禍』岩波新書2019年、iv頁。
[15] 吉田一彦『無条件降伏は戦争をどう変えたか』PHP新書、2005年、参照。
[16] 日本がアメリカの無条件降伏要求によって追い詰められていったありさまについては、ケネス・B・パイル『アメリカの世紀と日本――黒船から安倍政権まで』(原著2018年)、山岡由美訳、みすず書房、2020年、が啓発的である。
[17] 前掲『死を超えるもの』第9章、255頁。
[18] ハイデガーが戦後の技術論で「虚無化」を思索の事柄に据えたのも、絶滅戦争の時代における省察と言うべきものであり、政治哲学の裏返しと解することができよう。
[19] アーレントの現象学的存在論のこの基本テーゼは、たとえば『活動的生』第7節末尾に見出される――「共通世界は、それがわずか一つの位相のもとで見られるとき、消失する。共通世界がそもそも存在するのは、その遠近法が多様である場合だけだからである」(拙訳アーレント『活動的生』みすず書房、2015年、72頁)。鷲田清一が『朝日新聞』2023年3月1日朝刊の「折々のことば」でこの箇所を引いてくれたとき、本提題の趣旨に沿って考えていたかは不明だが、タイムリーだと少なくとも私は感じた。
[20] 古典古代を引き合いに出すだけで、奴隷制を擁護するつもりかと難詰されかねないが、視点の複数性がもたらすリアリティは、さまざまな事例に則して確証されうる。たとえば、第二次大戦後ほどなく書かれたヘレン・ミアーズ『アメリカの鏡・日本』(伊藤延司訳、角川ソフィア文庫、2015年、原著1948年)は、戦後に支配的になった見方とは異なる日米関係観を明確に打ち出しており、敗戦国の記憶喪失の回復に資するものがある。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
・ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
・ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
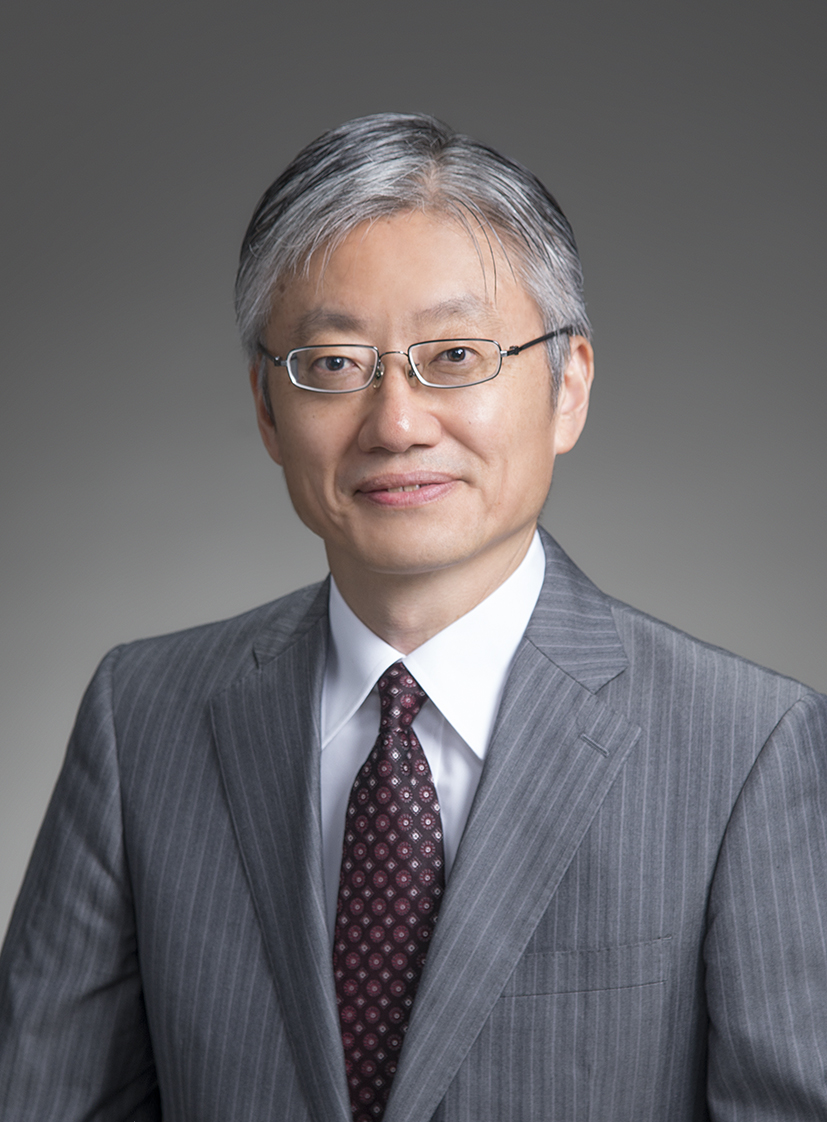 森一郎
森一郎
1962年生まれ。東北大学大学院情報科学研究科教授。著書に『死と誕生』、『死を超えるもの』(以上、東京大学出版会)、『世代問題の再燃』(明石書店)、『現代の危機と哲学』(放送大学教育振興会)、『ハイデガーと哲学の可能性』(法政大学出版局)、『核時代のテクノロジー論』(現代書館)、『ポリスへの愛』(風行社)、『アーレントと革命の哲学』(みすず書房)。訳書にアーレント『活動的生』、『革命論』(以上、みすず書房)等。

























































































































































































