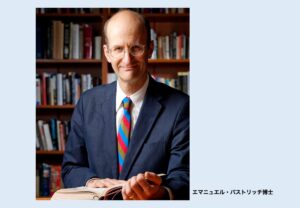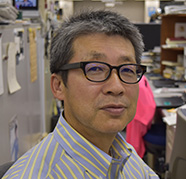第8回 ノーベル賞受賞化学者の素晴らしき人生!/書評「ストックホルムへの廻り道」(大村智著)
映画・書籍の紹介・批評
2015年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士
2015年にノーベル生理学・医学賞(詳細は評文末尾※1)を受賞した大村智博士(1935年~、北里大学特別栄誉教授、女子美術大学名誉理事長、経歴詳細は評文末尾※2)の「ストックホルムへの廻り道」(日本経済新聞出版社、2017年)を読んだ。
同書は、2016年8月1日から31日までのひと月間にわたって日本経済新聞に連載された「私の履歴書」シリーズの一環(大村智編)だが、大幅加筆訂正後出版の運びとなったものだ。

冒頭は、2015年10月5日のノーベル賞発表の日から始まり、ストックホルムでの授賞式に至るまでのてんやわんや、事後講演や取材に飛び回るお祭り騒ぎに等しい日々が回顧される。
ノーベル賞学者の自伝ともいうべき本書は第2章で、生い立ちに遡り、1935年山梨県北巨摩郡神山村(現韮崎市)の裕福な農家の長男として生まれ育ったこと、自然豊かな環境でサッカーや卓球、スキーにのめり込む活発な少年期を送り、地元の国立大学(山梨大学学芸学部自然科学科)に進学、58年卒業後は定時制高校(東京都立墨田工業高等学校)の教諭として勤務、その傍ら勉学に励み、63年東京理科大学大学院理学研究科博士過程を修了、そして「研究者と一緒になりたい」という格好の伴侶を得て所帯を持つ。65年北里研究所に入所し、東京大学薬学部博士号取得後は、米コネティカット州ミドルタウンにあるウエスレーヤン大学の客員研究教授として招聘され、夫人同伴で渡米する。73年帰国し、75年北里大学薬学部教授に就任、以後紆余曲折がありながらも40年以上にわたって研究に打ち込む様が、私のような門外漢にも研究者人生の一端が窺え、興味深かった。
著者の錚々たる経歴には目を見張らされるが(末尾の23ページにわたる年譜、数々の博士号並びに内外の受賞歴・医薬発見、各大学教授・外国のアカデミー会員・役職兼任、多数の叙勲等)、反面型破りで気骨のある、権力に阿ない素顔もかいま見える。
他人が見つけた物質の構造決定より「物取り」、自らが土壌から化合物を見つけ出しその性質や活性を調べるという逆転の発想、なぜなら微生物は無駄なものは作らないからとい理念こそが、ノーベル賞に繋がったことに唸らされる(ノーベル賞は微生物と一緒に取ったとの感謝も忘れない著者だ)。
しかも、研究のみならず、スポーツもよくし(若いときはスキー=数々の優勝歴あり、40歳頃からゴルフ)、絵画や陶芸にも造詣が深く(1997年から14年間女子美術大学学長を務め、現韮崎大村美館館長=2007年開設、女性画家中心の2000点に及ぶコレクションを寄贈)、北里研究所・大学・病院の経営面でも産学共同による特許料(米メルク社から総額200億円余)で立て直しと手腕を発揮、八面六臂の活躍だ。
「一期一会」を座右の銘とするように各界と培った人脈の厚さが、今ある成功へと導いたことがわかり、人生の訓としても読める良書になっている。
「黄金のトライアングル」、健康管理・一期一会・研究推進(社会貢献)の3原則がモットーで、美術やスポーツの趣味をはじめ、良き縁に恵まれてのバランスのとれた研究生活こそが、成功に繋がり、人生の糧になったことがあとがきで、締めくくられている。ノーベル賞受賞者ならではの人生哲学で、自らのモラルともいうべき心得、人生訓は圧巻だ。
もうひとつ、特筆に値するのは2000年に亡くなった文子夫人の存在た。陰に陽に研究者の夫を支えた献身、内助の功こそが順風満帆ばかりでなかった研究生活を支えたことが随所に窺え、愛惜の情が滲み出ている。ノーベル賞受賞後の記者会見で、開口一番「心の中で家内に報告しました」と答えたのには、今は亡き妻への自然に漏れ出る感謝の念からだった。
文子夫人は生前、時に倹約を強いられる生活にも不平ひとつこぼさず、「あなたはノーベル賞をとる人だから」と鼓舞し、研究生活に専念させてくれたと回顧し、今この場にあったなら、どんなにか喜んだだろうと、ノーベル賞は妻に捧げたいとの偽らざる本音がぽろりと漏れ出たものだろう。
アメリカでの留学時代、ホームパーティで手料理をふるい、研究者仲間をもてなしてくれたことを振り返り、妻のサポートあってこそ長い廻り道ながらこの日の栄光に繋がったと、感無量だったに違いない。
なお、題名の「ストックホルム」の暗示するところは、目をかけてくれた薬学者(野口照久=1924- 2011)に鼓舞された「ストックホルムを目指せ」、つまり研究者として至高の目標「ノーベル賞」を指すこと、廻り道とはそこに至るまでの道のりが山あり谷ありで平坦でなかったことを意味するのを、最後に付け加えておく。
○脚注
※1.ノーベル賞の受賞理由は、線虫の寄生によって引き起こされる感染症の新たな治療法に関する発見=イベルメクチンによる。1975年静岡県伊東市から採取した放線菌を、米メルク社と共同開発し、抗寄生虫活性物質・エバーメクチンを開発、その後これを改良したイベルメクチンを開発し、40年後に研究業績が認められ、ノーベル賞を受賞したわけだが、川奈のゴルフ場の土壌から取られた菌だったことを見ても、趣味と実益(研究)が結びついた発見ともいえ、いかにも大村博士らしい。
なお、大村室の研究グループはこれまでに約200種類、成分にすると500近くの新規化合物を発見し、そのうち25種が医薬、動物薬、農薬、研究用試薬として実用化されている。
※2.大村 智(おおむら さとし、1935年(昭和10年)7月12日- )は、日本の化学者(天然物化学)。北里大学特別栄誉教授、東京理科大学特別栄誉博士、薬学博士(東京大学)、理学博士(東京理科大学)。2015年ノーベル生理学・医学賞受賞。
土壌に生息する微生物がつくる化学物質の中から役に立つものを探し出す研究を45年以上行い、微生物の大規模な培養や有機化合物の特性評価を行う独自の方法を確立した。
以下、詳細はこちら
☆トピックス/インドでコロナに効いたイベルメクチン
パンデミック下私が隔離生活を送ったインドでは(2020~2021年)、大村博士が発明した抗寄生虫薬・イベルメクチンが、新型コロナウイルスにも効き目のある特効薬として大いに寄与したものだ。
2020年4月から、銀座新聞ニュースに「インド発コロナ観戦記」を連載しだした私は、2021年5月デルタ株大爆発でインドが世界ワーストの危機に陥った際、イベルメクチンがいかに死者急減に貢献したかを伝えたが、その際にいろいろ調べて発明者が日本人であると知ったときは、驚いたものである。お膝元の日本はいったい、何をやっているのだろうと思った。我が同胞が発明した特効薬が手の届くそばにあるのに、やれワクチンだ、新薬開発だと、神輿をあげて、安価な既存薬に目を向けないことに不思議な驚きとも怒りともつかぬものを覚えた。巨大な利害が絡むゆえの黙殺とわかったが、人命優先ではないかともどかしかった。
ノーベル賞受賞のミラクル薬が、パンデミック下口にしたり文字にするのもタブーとされるような事態に陥ったことは残念だが(ある意味、これだけの偉業を成し遂げた人物だから、毀誉褒貶は付き物だろう)、そのことでイベルメクチンの価値が落ちたわけでなく、むしろ抗寄生虫薬としてのみならず、オーバーオールに使える可能性も提示したわけで(マラリアや結核に効くとの論文もある)、免疫強化に役立つ同薬の今後に期待したい。
*アフリカでブヨが媒介する線虫によって引き起こされる感染症、悪くすると失明に至る病気、河川盲目症(オンコセルカ)に
卓効を示したイベルメクチン(製品名はメクチザン=1987年、年1度の服薬を無償供与し1億2千万人を救済)が、今回同書を読んでフィラリアにも効くことを知った。インドで、象皮病(リンパ系フィラリア症)患者に何人か遭遇したことがあるが、足が太く腫れ上がって象の皮のようになる風土病だが、治療薬として処方されていたことを改めて、知ったわけだ。
パンデミック時も、現地でイベルメクチンは入手可能で、薬局で購入したムンバイ(西のマハラシュトラ州都、全土でワーストのコロナ被害)在留邦人もいたようだが、インドでは偽薬も広く出回っているため、時勢が時勢だけに、私自身は購入を控えた。
インドでは、パンデミック勃発初期からイベルメクチンは使われていたが、最も効力を発揮したのは、2021年5月のデルタ暴発時である。
〇外伝/ノーベル賞受賞博士のオリジナル帽
大村智博士の被られているお帽子がずっと気になっていた。インドの初代首相・ネルーが愛用していた帽子(インドの独立運動の象徴で、マハトマ・ガンジーが創案したガンジーキャップ)に似ているように思ったからである。ネットで調べて茶人帽、別名利休帽と言い、千利休が被っていた帽子であることがわかったが、上記「ストックホルムの廻り道」の10~11ページに、大村博士自らの筆になるご自慢の愛用帽についての説明がある。
曰く、冷房で薄くなった頭髪が冷えるため、最初は婦人帽のつばを切って使われていたこと、その後プレゼントされるようになり、ノーベル賞受賞後の山梨県名誉市民(韮崎市名誉市民の称号は2000年)の式典で山梨県知事から、本絹の利休帽を贈られたとの由、以来色違いで10セット揃え、おしゃれを楽しんでおられるらしい。
とてもよくお似合いで、今では博士のトレードマークともなっておられるようだ。
*「ストックホルムへの廻り道」は、知人の寺島隆吉さん(岐阜大学名誉教授)にご紹介いただきました。寺島先生は、「コロナ騒ぎ謎解き物語」全3巻(あすなろ社、2021年)で、イベルメクチン擁護論を展開、大村智博士とは面談されるなどの交流を持ってらっしゃいます(特に第3巻の「ワクチンで死ぬか、イベルメクチンで生きるか」は、大村美術館から50冊の注文があったそうです)。寺島先生主宰の「翻訳グループ」の研究者メンバーの来夏セミナーは、大村美術館に隣接する、大村博士の生家を解体復元した蛍雪寮(養蚕農家や土蔵を活かした瀟洒な造りの登録有形文化財建造物、韮崎大村記念公園内)で行われる由、大村館長の鶴の一声で許可が降りたそうです。
*以下は、銀座新聞ニュースに掲載された「コロナ騒ぎ謎解き物語」全3巻(寺島隆吉著)の拙書評(本文下コラム)です。
https://ginzanews.net/?page_id=59251
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催公開シンポジウム:東アジアの危機と日本・沖縄の平和
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 モハンティ三智江
モハンティ三智江
作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。