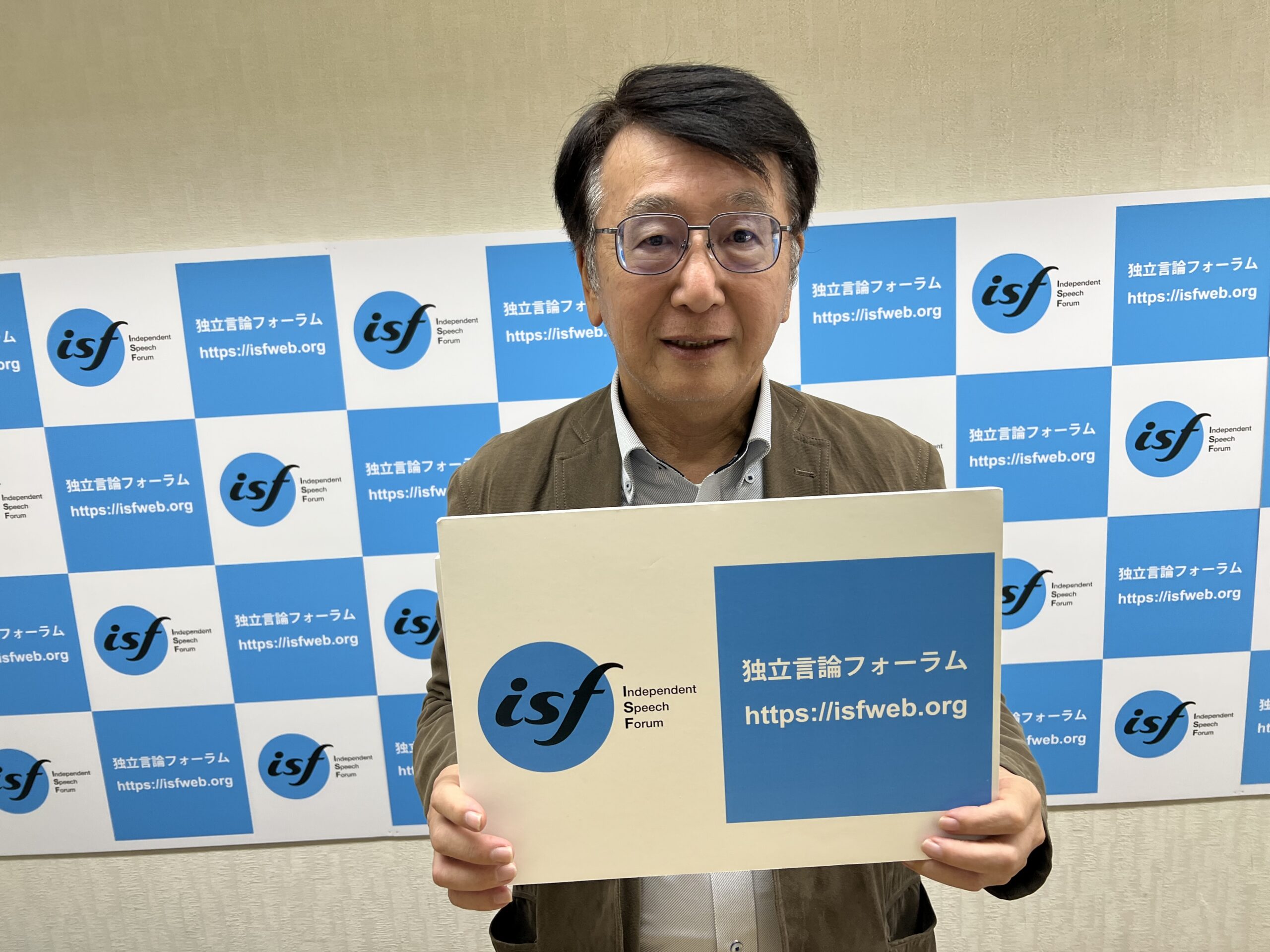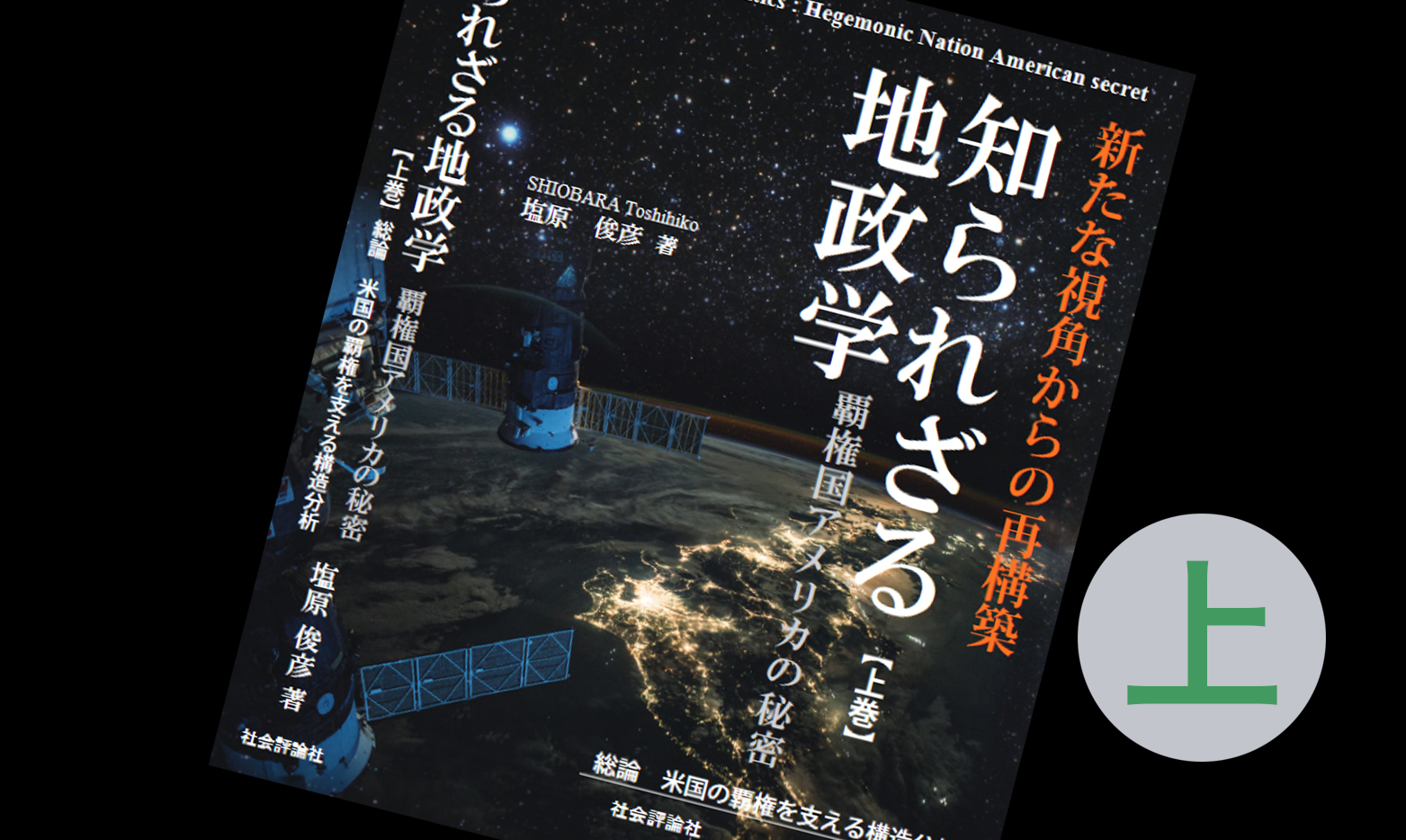
「知られざる地政学」連載(1) 「教える-学ぶ」立場からみた地政学の誕生(上)
映画・書籍の紹介・批評国際
ようやく400字換算で2000枚ほどの拙著『知られざる地政学:覇権国アメリカの秘密』(上下巻)を脱稿した。2023年10月以降、社会評論社から逐次刊行される。そこで、これから週に一度くらいのペースで、このサイトにおいて、同じタイトルの連載を公開する。この本に書いたこと、あるいは紙幅の関係で書けなかったことを率直に語りたいと思う。
「教える-学ぶ」と「語る-聞く」
大著(分量だけはたしかに多い)を書き上げて思うことは、これからはこの本をもとにして、「教える-学ぶ」立場から発信し、実際に「教える」ことにも挑戦したいということだ。この立場の表明は、その昔、柄谷行人が『探究Ⅰ』において書いたことに対応している。
要するに、「自省」という自己対話には、「他者」が存在せず、あるいは、他者が自分と同質であることが前提とされている。そこでの対話は「語る-聞く」のレベルにとどまっている。わかりやすくいえば、「プラトンの弁証法は対話の体裁をとっているけれども、対話ではない。そこには他者がいない」。いわば、同じ土俵が最初から前提とされ、自分が語れば、相手はその意味内容を理解して聞いてくれることが最初から用意されているのだ。
近代化は、この自己対話による自省を通じて、個人とか個人の自由意志といったものを育んだ。このレベルであっても、個人の自由意志を自覚的にもてるようになれば、少なくとも自分らしい人生を営むことが可能となるだろう。だが、そのとき、自分の考えたことは万人にも通じると信じてしまいがちになる。地政学においては、覇権国アメリカの言い分はすべて正しいという独我論がまかり通るようになる。
だが、本当は、言葉も価値観も通用しない他者を想定して、こうした他者にも通じる普遍的な価値観を求めながら、世界秩序に考える新しい視角に立った地政学が必要なのだ。
自省力の不足
残念ながら、21世紀になっても、自省する訓練を受けないまま、ただ他者に同調することによってのみ何となくアイデンティティを感じて生きる人が増えているのではないか。ここで思い出すのは、2002年2月、札幌の喫茶店での大澤真幸との会話である(詳しくは拙著『ビジネス・エシックス』[講談社現代新書、2003年]の「あとがき」を参照)。彼は、「近頃の学生は自省力が足りない」と指摘した。自己対話ができなければ、自分自身を磨くこともできない。薄っぺらで皮相な人々が自分の無能を知らぬまま、それでいてSNSで発信したがる。
いま、事態は20年前よりもずっと悪化している。「語る-聞く」レベルの自省力は衰え、もはやTikTokで同調するだけの「集団白痴化現象」が起きているように感じる。実は、私の本はこうした人々に向けて書いたものではない。「語る-聞く」レベルにも達していない人はそもそも、『知られざる地政学』を読破することはできないだろう。
そうなると、残されるのは、多少なりとも、自省力を鍛えた人ということになる。だが、「語る-聞く」というレベルでは、『知られざる地政学』は書かれていない。「教える-学ぶ」という立場から書かれている。だからこそ、ブックカバーに「新たな視角からの再構築」と書かれているわけだ。新たな視角とは、「教える-学ぶ」立場から考察したことを意味している。
アイデンティティという問題
それでは、「教える-学ぶ」立場とは具体的にどんなことを意味しているのか。それを理解してもらうためには、補助線が必要だ。
フランシス・フクヤマは、2018年にIdentity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentmentを上梓した。同一性(アイデンティティ)とは、何かと何かの一致を意味している。社会化の過程で特定の社会集団と同一化した結果形成された、特定の社会集団に属するという人の経験や、他の個人や集団との違いに関する考え方、行動パターン、価値観などがアイデンティティをかたちづくる。アイデンティティは、個人の自己決定と自己認識の中心的な側面のひとつであり、変化する状況において自分自身でありつづけることを助け、自分を取り巻く世界と自尊心を評価する基準を提供する。
問題は、たった一人では生きていけない人間はこのアイデンティティを他者の承認によって感じ取るところにある。だが、このときの他者は、本当は真の他者ではない。すでに説明したように、同じ共同体、地域、国家のような限られた空間を前提にした「仲間意識」が広がるのである。そして、そんななかでも承認欲求は存在しつづける。
地政学でいえば、これまでの地政学研究は米国の価値観、あるいは西欧の価値観、あるいはキリスト教の価値観を前提に行われてきた。そこには、非キリスト教的アジアの価値観をもった他者はいない(私が書いた『復讐としてのウクライナ戦争』には、キリスト教文明に対する決別の意味が込められている)。
つまり、真の他者を前提としているわけではないから、これまでの地政学は独我論的でまったく普遍性のない思い込みのようなものを育んできた。独我論の典型はナショナリズムだろう。つまり、インチキがはびこってきた。あるいは、外見が違うとか、言葉が話せないといった差異だけを突出させた差別が公然化するようになる。
残念ながら、同じ穴に住む貉はこのインチキになかなか気づかない。「語る-聞く」のレベルにとどまっているかぎり、まったく別の他者の評価や判断を知り、自分で咀嚼し、再解釈するところまで至らないのだ。拙著『知られざる地政学』において使った言葉でいえば、「とまどえる群れ」はせいぜい、「語る-聞く」のレベルにとどまっているために、その閉ざされた空間内において実に騙されやすい。
「有名人」について
この限られた空間内で「語る-聞く」のレベルにとどまっていると、どんな事態になるかを、有名人を例にして説明してみよう。
有名人は、ある共同体、ある地域、ある国において、多くの人に名前や顔などが知られている人物を意味している。有名人ではない人を「一般人」と呼ぶことにすると、一般人は有名人を何となく知っているという理由から、その有名人に親近感をいだくようになる。言葉も通じないような他者としてではなく、自分たちの「仲間」のような感情をもつ。ゆえに、有名人と一般人の間には、「語る-聞く」レベルの関係が築かれるともいえよう。
有名人の側も、自分が一般人に知られていることを意識するようになると、自分の存在がすでに承認されているとの誤解から、自意識過剰になったりもする。いずれにしても、この「有名人-一般人」の関係には、他者が存在せず、「語る-聞く」というレベルの独我論的世界(自分の考えは万人に通用するとの見方)が広がりやすい、とくに過度の同調性を特徴とする日本ではそうだ。
わかりやすくいえば、たとえ大谷翔平という有名人であっても、ロシアに行けば、ほぼだれも知らないだろう。そのとき大谷に他者に出合うことになり、「語る-聞く」といったレベルの立場ではいられない。
※(下)に続く
※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。
https://isfweb.org/recommended/page-4879/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
○ISF主催公開シンポジウム:差し迫る食料危機~日本の飢餓は回避できるのか?
○ISF主催トーク茶話会:藤田幸久さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。