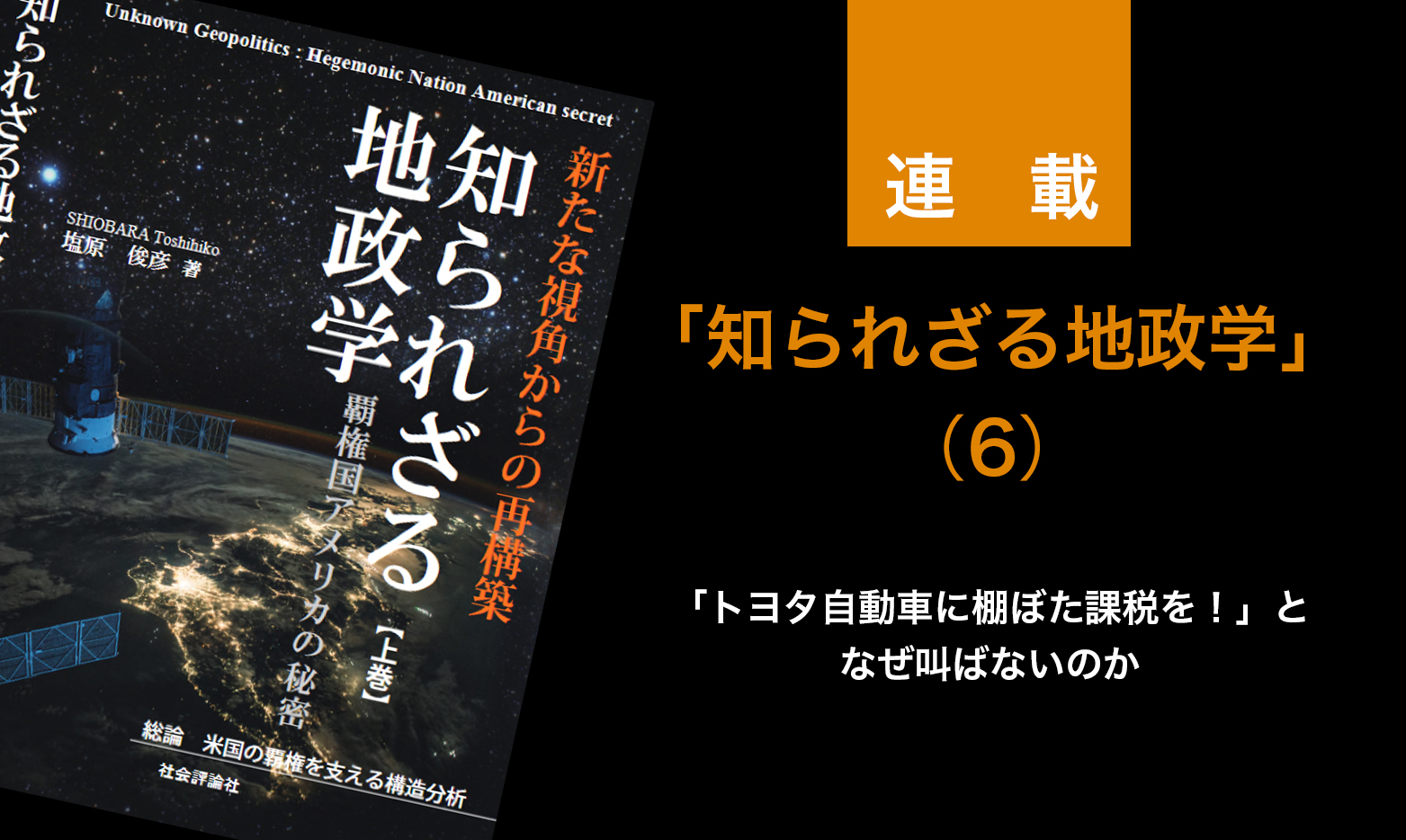
「知られざる地政学」連載(6)「トヨタ自動車に棚ぼた課税を!」となぜ叫ばないのか
映画・書籍の紹介・批評国際
いま、地政学上の最大の関心事の一つは、テック・ジャイアンツと呼ばれる、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット(グーグル)、メタ・プラットフォームズ(フェイスブック)、ネットフリックスなどの超国家企業への課税問題である。
この問題については、拙著『知られざる地政学』では、紙幅の関係から割愛せざるをえなかった。そこで、ここでこの問題について簡単に論じてみよう。
WTOの関税モラトリアム
世界貿易における電子商取引の重要性の高まりを受け、世界貿易機関(WTO)加盟国は1998年5月20日、世界的な電子商取引に関する宣言を採択する。そのには、「加盟国は電子通信に関税を課さないという現在の慣行を継続する」とする、いわゆる「モラトリアム」も盛り込まれた。「electronic transmissions」(電子通信)という言葉が定義されないまま、ソフトウェア、電子メール、テキストメッセージからデジタル音楽、映画、ビデオゲーム、付加製造用の設計図まで、あらゆるものを包含するものが関税を課されない状態がWTO閣僚会議(MC)で2年ごとに延長されつづけてきた。
モラトリアムの背後には、米国のテック・ジャイアンツを優遇し、そのビジネスを世界に普及させることで米国の影響力を拡大しようとする覇権国アメリカの圧力があった。
このモラトリアムは決して恒久的なものとして認められたわけではない。にもかかわらず、現在、2024年2月に開催されるMC13まで有効である。インド、インドネシア、南アフリカなど一部の加盟国は、財政収入の課税ベース決定における政策的余地を拡大し、国内産業を支援し、その他の規制目的を追求するために、モラトリアムを再考すべきであると主張している。他方で、EUやG7諸国などの他の加盟国は、影響を受ける産業における貿易政策の不確実性を減らすために、恒久的なモラトリアムが必要であると主張してきた。
OECDの提案
しかし、自社のサービスやデバイスを通じて世界中のユーザーにソフトウェア、サービス、コンピューターゲーム、音楽、映画を提供するビジネスは大規模となり、多国籍企業が異なる国の税制間のギャップやミスマッチを利用することによる国内の税源浸食と利益移転(BEPS)が大問題となってきた。いわゆる「デジタル・タックス」をどう課税すべきかが問われるようになるのだ。
そこで、拙著『サイバー空間における覇権争奪』でも指摘したように、2015年の段階で経済協力開発機構(OECD)租税委員会の「税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画」の主要課題の一つとして、経済のデジタル化への各国の徴税協力が認識されるようになり、2017年3月、G20財務相会議はOECDに対してBEPSの枠内で課税にとってのデジタル化の意味合いについての報告書を2018年4月までに作成するように命じる。こうして世界共通のデジタル・タックス課税のための協議が本格化するようになる。
OECDは、BEPSの慣行により、各国は毎年1000億~2400億ドルの歳入損失を被っており、これは世界の法人所得税収の4~10%に相当すると見積もっている。だからこそ、OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組みでは、135を超える国・地域が協力して、租税回避に取り組み、国際的な租税規則の一貫性を高め、より透明性の高い租税環境を確保し、経済のデジタル化から生じる租税上の課題に対処しようとしてきた。
2023年7月11日、OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework on BEPS)の138の加盟国は、これまでの重要な進展を認識し、各国・法域が国際税制の歴史的な大改革を進めることを可能にする成果声明に合意するに至る。
その内容は、「二つの柱による解決策」に合意するものだ。第一の柱は、多国間条約(MLC)で、その締約国が、一定の収益と収益性の閾値を満たし、かつ、これらの締約国の市場との関連性が定義されている多国籍企業の残余利益の定義された一部に関して、国内課税権を行使することを認めるものだ。MLCは2023年末までに署名式が開催される予定で、その目的は、各法域で適用される国内協議、立法、行政プロセスを経て、2025年にMLCを発効させることにある。
第二の柱に基づくグローバルミニマム税は、多国籍企業(MNE)がどこで事業を行うかにかかわらず、各法域において15%の実効ミニマム税率で課税されることを保証し、公平な競争条件を確保するものである。課税対象ルール(STTR)がグループ内の利子、ロイヤルティ、その他の定義されたグループ内の支払い(対象所得)に適用される。対象となる所得のリストには、グループ内サービスに対するすべての支払いが含まれる。対象となる所得の項目が、居住地法域においてSTTRの最低税率である9%を下回る名目法人税率が適用され、条約によりその所得が発生する法域がその所得に課税できる税率が制限されている場合、STTRはその法域に対し、9%と居住地法域の名目法人税率との差額を上限とする税率で課税することを認めている。STTRを実施する多国間文書は、2023年10月2日から署名を受け付ける。
この合意は、地理上の政治ではなく、経済に注目する、いわゆる地経学上の大きな一歩であり、注目に値する。
注目される2024年2月以降
これに加えて関心の的となっているのは、2024年2月に開催されるWTO閣僚会議(MC13)の行方である。WTOの加盟国(164カ国)がいわゆる電子送金(デジタル商品、サービス、役務)に対して関税などを課すことが認められる可能性があるからだ。ただし、これに対して、国際通貨基金(IMF)は、途上国は適切なペース で関税を引き下げるべきであるとの立場に立つ。関税のような差別的措置と付加価値税(VAT)のような広範な非差別的措置を比較して、IMFは、「世界全体では、現在の税率でデジタル化された貿易から得られる付加価値税の潜在的な歳入額は、潜在的な関税収入よりも150%高く、すべての所得水準の国グループにおいてほぼ同程度かそれ以上である」と主張している。
広がる「棚ぼた税」
こうした世界的な税制の動きを知れば、2022年の石油・ガス価格の高騰で起こった世界的な「棚ぼた税」導入の動きについても知らなければならない(英語では、風が吹くことで果実を得られることにたとえて、想定外の利益をwindfallと呼び、それに対する税金をwindfall taxという)。2022年9月30日、欧州連合(EU)理事会は、(主にプーチンのウクライナ戦争による)エネルギー価格の高騰に直面している家庭や企業を救済する資金を得るために、化石燃料企業に対してEU全体で風前の灯火となる利益税を課すことに合意したのである。税制専門機関の情報によると、この税金(EU用語では「連帯拠出金」)は、各国の税制にもよるが、2022年および/または2023年から、2018年以降の年間平均課税利益の20%増を超える課税利益に対して、少なくとも33%の税率で計算される。EUは、この政策により約1400億ユーロの税収が見込まれると予想している。
日本の輸出企業に「棚ぼた課税」せよ
これと同じ発想に立って、日本で考えられる「棚ぼた」、すなわちwindfallといえば、予想外の円安・ドル高による輸出企業の利益であろう。わかりやすくいえば、トヨタ自動車は自動車やその部品を海外に販売するだけで、ドルで支払われる売上高がドル高によって円でみると何もしなくてもどんどん膨らみ、より多くの円建て収益をあげたのである。これを放置しておいていいのだろうか。
輸出品に対しては、世界中の慣行として、国内で課された付加価値税が輸出企業に還付される。日本の場合、消費税の還付となる。「2021年度 トヨタなど輸出大企業20社に 円安で増大 消費税還付1.7兆円超 中小業者は悲鳴」という2022年10月24日付の報道によると、22年3月期の輸出還付金の合計額は、およそ6兆6000億円にのぼる。各社別の推定値は下表のとおりだ。

(出所)https://www.zenshoren.or.jp/2022/10/24/post-20731
こうした輸出に伴う消費税の還付金の3割でも半分でも、還付を停止すれば、それを円安に苦しむ人々向けに活用できる。きわめて簡単なことである。2024年3月までに、法律を改正し、2023年度の輸出に伴う消費税還付金の一部を止め、円安対策費として利用することはできないのか。2022年から議論をしていれば、実現できたかもしれないと思うと、国会議員の不勉強を批判したくなる。
たとえば、ロシアでは、急激なルーブル安で石油や天然ガスの会社が輸出に伴うwindfall利益を得ることになる。ゆえに、ロシアではすぐにその超過利潤への課税が政策課題となる。多くの場合、輸出税をかけて棚ぼた利益の一部を吸収するのが当然となっている。
経済学では、標準を上回る利益を超過利潤と呼び、「レント」ともいう。このレント部分に対して超過利潤税、すなわちレント課税をするというのは当然の考え方だ。何もしていないのに、つまり、正当な理由なく得た利益について、それらを税を通じて集め、社会全体に再配分してシェアするのである。
議論をする重要性
私は、「棚ぼた税」が主要マスメディアで議論されたり、国会で審議されたりした事例を知らない。れいわ新撰組は、「消費税ゼロ」と叫ぶ前に、こうした問題をしっかりと国会の場で問題提起すべきなのだ。立憲民主党も、もっと国際情勢をしっかり勉強し、機動的な対応ができるようにすべきだろう。日本共産党も、柔軟な頭脳と明晰な分析力を鍛える必要があるだろう。
野党よ。「トヨタ自動車に棚ぼた税を!」となぜいえない。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)がある。

























































































































































































