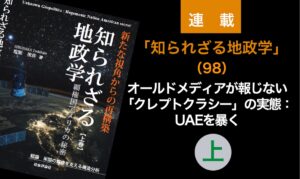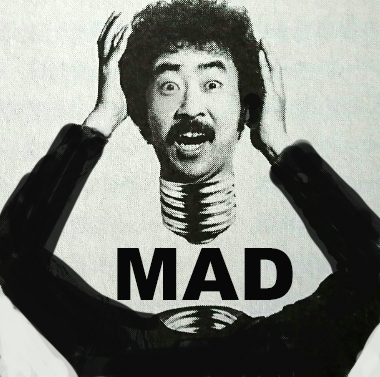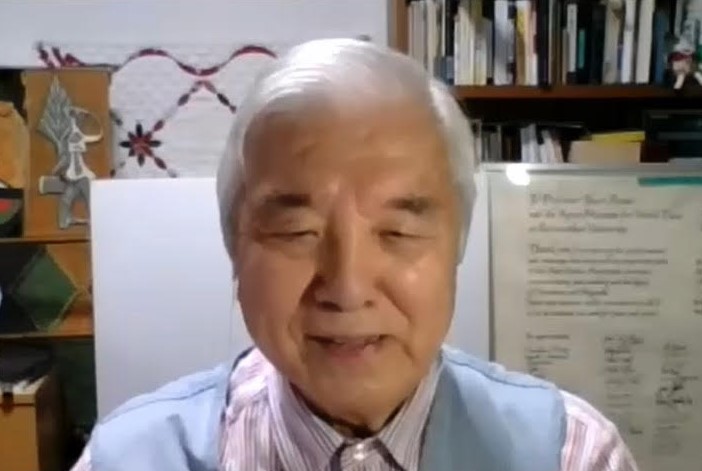〈海峡両岸論〉李克強急逝で見せたおろかな報道 政治大混乱に期待するメディア
国際「李克強氏死去、しぼむ中国『改革派』」[i]「第2の天安門事件となる懸念」[ii] 中国の李克強前首相が10月27日、心臓発作のため68歳で急逝(写真 李氏急逝を一面トップで報じる人民日報紙)した記事のタイトルだ。これに暗殺説[iii]まで飛ぶ「おろか」な報道をみるにつけ、中国の不安定と混乱に期待するメディアの対中姿勢が浮き彫りになる。李氏の遺体は11月2日荼毘(だび)に付されたが、大混乱は起きなかった。中国指導者の死が政治的大混乱につながる条件を分析しながら、習近平総書記に権力が集中する中国共産党の特殊な統治構造を考える
素早い情報公開の背景は?
李氏急逝を聞いて頭をよぎったのは、周恩来首相(1976年)と胡耀邦総書記(1989年)の死去が、中国の民主化運動(第1次、第2次天安門事件)の引き金になったことだ。元共産党リーダーの死が、一党独裁を揺るがす要因にならないかを分析するのは、チャイナ・ウォッチャーの「習性」でもある。
しかし「第2の天安門事件となる懸念」と踏み込むには根拠が必要。1989年6月の天安門事件の際、筆者が北京で取材した経験を踏まえて分析すれば、李急逝が習近平一強体制の安定を損なう可能性は低いという見立てに落ち着く。共産党統治に内在する論理と、国際政治秩序の急転からその理由を読み解きたい。
共産党当局は今回、李急逝が習一強批判や社会の不安定につながらないよう、素早く手を打った。香港英字紙「サウスチャイナ・モーニングポスト」の急逝翌日(10月28日)の報道がそれを物語る。記事は、李氏は静養中の上海にある党幹部用施設「東郊賓館」で、水泳の最中に心臓発作を起こし、近くの上海中医薬大付属曙光病院に搬送された。死去が確認された後、遺体は27日に北京に運ばれた、と詳細に伝えた。
同紙によると、李氏はかつて冠動脈のバイパス手術を受けたという。急死をめぐる「ウワサ」が独り歩きしないよう、党中央が香港紙を使って詳細な情報を開示したのだ。
当局側が神経質になったのは、国内総生産(GDP)の3割を占める不動産の深刻な不況に加え、デフレ懸念や青年層の高失業率という「経済三重苦」がある。経済発展は共産党独裁の「正当性」を保証する最大要因だ。だから経済不振は統治の不安定化を招きかねない。
さらにちょうど一年前、若者が白紙を掲げ共産党と習批判のスローガンを叫び、ゼロコロナ政策に反対する「白紙デモ」の勃発も、鮮明な記憶として残っていたはずだ。

「中央分裂」など3条件
では李急逝は、周恩来と胡耀邦死去後に起きた反中央行動の引き金になる条件はあるのだろうか。筆者はその条件として ①政策・路線をめぐり党中央が分裂 ②主流派から批判された「被害者」 ③大衆的な人気-の3条件を挙げたい。中でも「中央の分裂」は共産党の一党独裁の崩壊につながりかねないから、詳細な分析が必要だ。
周恩来の場合はこの3条件をすべて満たしている。中国は当時、文化大革命の末期にあたり、体力・知力とも衰えた毛沢東主席に代わって毛沢東夫人の江青氏ら「4人組」が実権を握り、党中央主流派を形成していた。
「4人組」は、モンゴルで墜落死(1971年)した林彪副主席と、文革の終息と経済建設を主張する周を「孔子」にみたてて批判する「批林批孔」運動を1973年に開始。周は批判の矢面に立たされた「被害者」だった。同時に、周は毛沢東以上の大衆的声望があり、3条件のすべてが当てはまる。
では1989年4月に心臓病で死去した胡耀邦(写真 1989年4月天安門広場の人民英雄記念碑に設けられた胡氏を悼む肖像写真と花輪)の場合はどうか。胡は1986年末に起きた民主化要求の学生デモを「積極的に支持」したとして、主流派を形成する鄧小平ら長老に批判され、1987年1月総書記を解任された。③の「大衆的人気」について言えば、民主化要求の学生から絶大な支持があり、やはり三条件を満たしている。
路線対立あったのか
問題は李克強が、3条件に当てはまるかどうか、中でも①の「党中央の分裂」があったかどうかが最大論点になる。冒頭紹介した記事は、李急逝について「共産党内で市場機能を重視する『改革派』の退潮を改めて印象づけた」と書く。
さすがに李を改革派とは断定せずに、「いわゆる」を意味するカギかっこを付けて、慎重な表現にとどめている。「習氏との確執」や「政策をめぐる分裂」の明確な証拠に乏しいためであろう。
李が習総書記に次ぐナンバー2になったのは、2012年の第18回党大会。習はスタート時から、中国がもはや高度成長は望めず、安定成長が「新常態」になる、との認識を明らかにしていた。李もまたこの認識枠組みの中で、経済運営に当たってきた。
具体的な経済政策をめぐって意見対立することはあったと想像出来るにしても、中央が分裂するような対立関係にあったとは考えにくい。
ワシントンコンセンサスの終焉
李は、市場の論理に基づく経済改革を進めた朱鎔基元首相に近いとされてきた。しかしその路線は、中国が高度成長を遂げた時代の話だ。米国の一極支配を支えてきた「ワシントンコンセンサス」の終焉というパラダイム転換が進む中で、李に「市場機能重視の改革派」のレッテルを貼るのは時代の変化という相対化が必要だ。
ワシントンコンセンサスとは、レーガン・サッチャー時代の1980年代に始まる「小さな政府」「規制緩和」「市場原理」「民営化」「民主化」を世界に波及させることによって米一極支配を貫徹させようとするイデオロギーだ。
しかし2008年のリーマンショックは、金融レバレッジ(梃子)商品の開発によって、架空の金融需要を再生産する金融資本主義の限界をさらけ出した。ワシントンコンセンサスの中で急成長を遂げた中国は、この時4兆人民元の資本を市場に投入し、世界経済を下支えした。ワシントンコンセンサス延命に協力したのだ。
国家と巨大ITの綱引き
しかしこのモデルの敵は「内」にあった。トランプ政権の登場と、足掛け3年にわたるコロナ禍が、このモデル崩壊を決定づける。トランプは「アメリカ第1」を押し出し、国際通貨基金(IMF)と世界銀行による自由貿易体制と、国際協調という「ワシントンコンセンサス」を否定し、自ら崩し始めたのだった。
続いてコロナ禍は、世界中に国境を復活させグローバル化に歯止めをかけ、国家の機能と役割を復権させた。[iv]一方、IT革命とAI技術の飛躍的進歩は、米国でGAFA (Google、Apple、Facebook、 Amazon)という巨大プラットフォーマーを生み出し、彼らは国家を超える力を持ち始めた。
中国でも「アリババ」の馬雲(ジャック・マー)氏の政府批判発言を機に、習政権がIT業界締め付けを開始する。このやり方は、習が進める国有経済の成長と民営経済の衰退を意味する「国進民退」の象徴的手法として欧米は批判する。だが、李が締め付けに異議を唱え、党内に路線対立が生じたという情報はない。
いま世界では「ワシントンコンセンサス」の崩壊によって復権した国家と「巨大プラットフォーマー」による激しい綱引きが展開されている。「ワシントンコンセンサス」に代わって「ペキンコンセンサス」や「チャイナスタンダード」という新モデルがあるわけではない。
習氏に対抗する勢力ない
李急逝に話を戻す。不動産不況を招いた責任は、習だけでなく李も免れない。西側では、「国進民退」に批判的だが、李がどこまで「国進民退」に抵抗したのかも、定かではない。「経済三重苦」の治療方法をめぐって共産党中央が分裂しているという情報もない。
こうしてみれば、指導者の死が大混乱の引き金になる条件として挙げた「中央の分裂」は存在しないとみるべきだろう。李は一身に権力を集中させる習氏の敵ではない。
李は、2022年の第20回党大会ではまだ67歳であり、「暗黙のルール」の「68歳定年」に届かないまま引退したことに同情は集まった。しかしだからと言って、②の主流派に批判された「被害者」とまで言いきれないだろう。李は有能な経済政策のエリートではあっても、③の「大衆的な人気」があったかどうかは疑問だ。
③条件を当てはめて分析すれば、李急逝が共産党の一党独裁の不安定化につながる可能性は低いという結論が導き出される。習一強支配の強化に反対する声が中国にあるのは事実だ。だが、李急逝が政治的混乱に発展するという見立ては、習独裁への「当てこすり」に期待する、メディアのシナリオに基づいている。
習一強体制の安定度について言うなら①中国民衆が体制転覆を望む兆候はない、②中流階級は党の政策の最大の受益者であり反旗を翻さない、③党最高指導部から、習氏グループ以外は排除され、習氏に対抗する勢力はいない―を挙げれば十分だろう。

皇帝型秩序など3秩序複合体
李氏急逝をめぐるおろかな報道ぶりは、われわれの対中観の在り方を問い直している。われわれは中国の政治・経済・社会を欧米や日本と同一視し、欧米のモノサシから中国を「異質な専制国家」と見做す。中国を「マルクス・レーニン主義」から一面的に判断すると、実相を見失う。
ここで、中国共産党による一党独裁統治を①皇帝型秩序②国民国家秩序③マルクス・レーニン主義秩序-の複合的構造で成立しているという仮説を立てたい。
歴史的にみると、中国は「一強」の皇帝権力下で安定してきた。異質な民族、文化、習慣を取り込む「多元共存」の世界である。中国は異なる民族・地縁・言語・宗教という異質集団の集合体だから分裂の危機が常にある。台湾問題や新疆ウイグルをみればうなずける。
習が共産党の長期戦略として「中華民族の偉大な復興」の旗を立てたことは、皇帝秩序の歴史を肯定的にとらえる思考と矛盾しない。一方、米一極支配の終焉と多極化する世界秩序という新パラダイムでは、多極間の共通ルールが必要である。それが、共産党が国際関係で強調する「国連中心主義」「国際法」など、国民国家の関係を支える法的秩序だ。
さらに、レーニン(写真=ロシア・ブォルゴグラードにある高さ57メートルのレーニンの世界最大の銅像 ロシアエクスプレスHP)やスターリンらカリスマ指導者を頂く中央権力集中型のマルクス・レーニン主義は、皇帝型秩序と親和性がある。その秩序を共産党組織に内在化させることによって、習氏を支えるブレーン[v]は、皇帝型秩序と国民国家との矛盾・相克の答えを見出したのではないか。
習一極支配はこの3秩序から成り立っており、中国の「安定と実利」にとって役に立つ秩序を選びつつ、政権運営しているというのが筆者の仮説だ。国家統治のあり方に定式はない。「進化論」を俗論的に解釈して、人類社会も一直線に進化してきたし、深化するとみることこそ、歴史的な事実を無視した俗論である。他者に「異質な専制国家」のレッテルを貼るほど、我々の統治は完全でも成熟もしていない。(了)
* * *
[i] https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM273B30X21C23A0000000/)
[ii] https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/77654
[iii] http://taiwannokoe.com/ml/lists/lt.php?tid=KYj4WCHb7CC/PAUJtc1dqSK1t0Bjhb93sQTC1pPISO4YaroaW9KySpgE1LsTjfNh)
[iv] 岡田充「海峡両岸論」第113号「強権政府待望する時代が始まった
五輪を全てに優先した安倍失政」https://okadakaikyouryouganron.weebly.com/28023237772000123736355421/113-202043)
[v] 岡田充「習近平思想」を作った男——中国トップ・ブレーンの王滬寧氏とは何者か」
https://www.businessinsider.jp/post-106611)
* * *
岡田充の海峡両岸論 第156号 2023・11・12発行からの転載です。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ISF主催公開シンポジウム:WHOパンデミック条約の狙いと背景~差し迫る人類的危機~
● ISF主催トーク茶話会:小林興起さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 岡田充
岡田充
共同通信客員論説委員。1972年共同通信社入社、香港、モスクワ、台北各支局長、編集委員などを経て、拓殖大客員教授、桜美林大非常勤講師などを歴任。専門は東アジア国際政治。著書に「中国と台湾 対立と共存の両岸関係」「尖閣諸島問題 領土ナショナリズムの魔力」「米中冷戦の落とし穴」など。「21世紀中国総研」で「海峡両岸論」http://www.21ccs.jp/ryougan_okada/index.html を連載中。