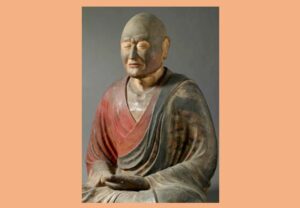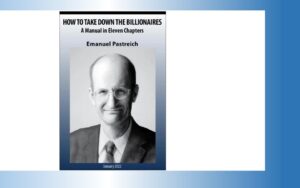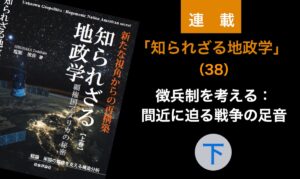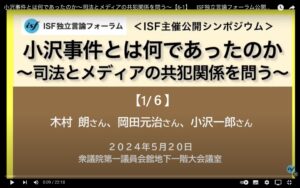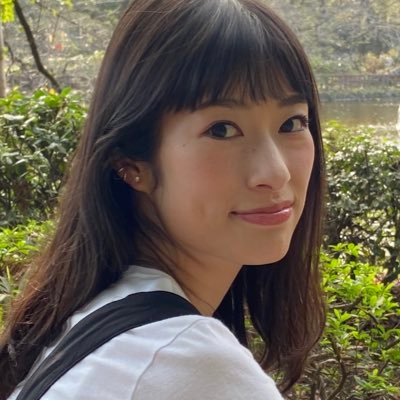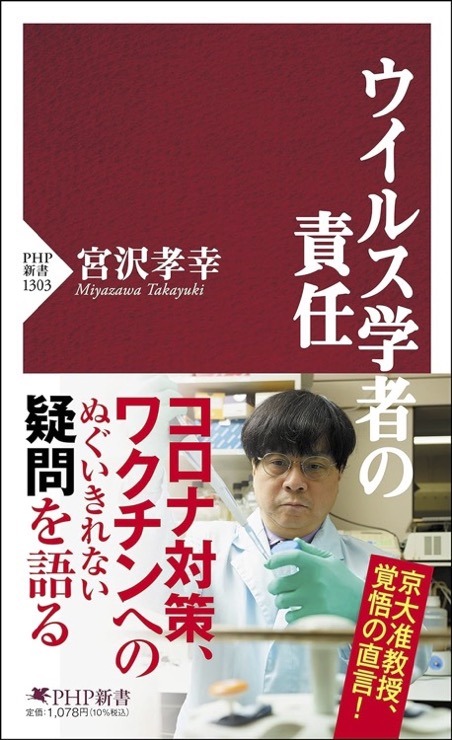
【書評】宮沢孝幸『ウイルス学者の責任』 ―理系分野でも、対米従属の打破と日本独自の道の模索が必要(下)
映画・書籍の紹介・批評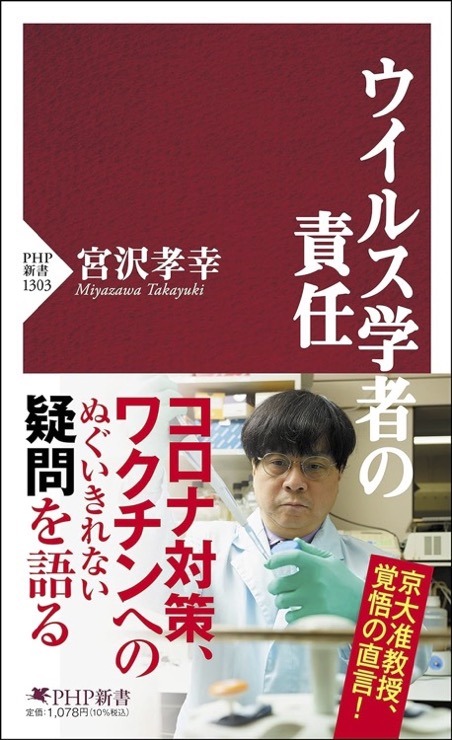
【書評】宮沢孝幸『ウイルス学者の責任』 ―理系分野でも、対米従属の打破と日本独自の道の模索が必要(上)はこちら
第2章 ワクチンを打てば解決するのか?
宮沢氏はコロナワクチンに対して、早くから慎重な意見を唱えてきたことで知られます。まずワクチンが開発できるウイルスとできないウイルスの区別がなされ、前者は「一度感染して回復したら、もう二度と感染しない」(78頁)種類のものとされます。さて新型コロナはどちらの種類だったでしょうか。
コロナワクチンが遺伝子に関わる新規技術を用いていることは、既に知られています。「生物やウイルスが、タンパク質を合成するための設計図がDNA」で、RNAはタンパク質合成の「手順書」であり、その手順書をタンパク質合成工場のリボゾームに運ぶのがmRNA、という説明はわかりやすいものです(82頁)。
日本でも膨大な数と種類のコロナワクチンに関する副反応疑いの有害事象が報告されています。著者は本書執筆時点ではその効果の評価を見極めるのは早い、という慎重な判断をしています(87頁)。けれども、ワクチン接種が実施された21~22年に、非常に大きな超過死亡が観測されたのは、気になるところです。宮沢氏はスコットランドのデータを用いて30~40代でワクチン以外に明確な要因が見当たらない心疾患が増えていることに注目し、この世代はワクチン接種不要だった、と結論づけます(90頁)。本来であれば、全世代一律の接種推奨ではなく、このような集団ごとの細かい分別が必要だったはずです。しかも接種者の大半は、ワクチンなしでもコロナに感染しなかったはずなので、「ごく稀な犠牲は仕方がない」(91頁)という―私から見ると全体主義的で非人道的な―考え方が否定されるのはもっともです。
そもそも日本人は未知の「ファクターX」によって、欧米に比べて新型コロナに対して有利だったとされています。宮沢氏が、従来型コロナウイルスなどへの感染により、感染や重症化を防ぐ細胞性免疫が、新型コロナに対しても「交差免疫」として働いていたからではないか(94頁)、という仮説を立てているのは重要です。
mRNAワクチンは遺伝子技術を用いていますので、気になるのが世代を超えた影響です。一般にはありえないとされていますが、ファイザーワクチンの成分が血中にも流れていることは、ファイザーも認めています。つまり血液から胎盤を通して成分が母体から胎児に取り込まれ、特に新型コロナウイルスと共通するワクチンの成分であるスパイクタンパクにより、胎児が悪影響を受ける恐れがあるとされます。さらには、そのスパイクタンパクが胎児の血中を流れていると、新型コロナに対する「免疫寛容」が誘発され、正常な免疫反応が起こらなくなる可能性もある、とされます。「理論的に考えられるリスクに対しては、実験してそれが起こりえないことを証明する義務はある」と宮沢氏は主張します(102頁以下)。こういった起こり得るリスクに先行的に対応する予防原則的な考え方が乏しく、確実な因果関係が立証されるまでは安全と仮定、という楽天主義で突き進んだのが、日本の実情ではないでしょうか。
こうした潜在的リスクにもかかわらず、日本では妊婦へのコロナワクチン接種が推奨されました。しかもその理由として、一般の医療機関がコロナ陽性になった妊婦を受け入れていないから、という事情が挙げられることがあるのは、私から見ると本末転倒そのものです。宮沢氏は反対に、コロナ陽性者でも一般の医療機関で受け入れられるようにすればよいと提言しています(以上107頁)。私も医療体制の不備により、世代を超えた犠牲者が誘発されかねない現状の体制には問題があると思います。
第3章 ウイルスRNA混入事件
第3章は、新型コロナ禍以前にも、宮沢氏が薬品会社や規制機関と闘ってきた、という事実の記録です。きっかけは、日本赤十字の職員から、輸血用血液にウイルスが混入しているかどうかの検査を依頼されたことでした。実際に外国では、マウス白血病関連のXMRVというウイルスが、癌等の原因になる、という報告が出ていました(118頁)。宮沢氏が調べたところ、血液自体にウイルスはありませんでしたが、何とウイルスを検出するための試薬の方に微量のXMRVが混入していたことが判明しました(122頁)。試薬会社の日本支社は過ちを認めましたが、米国本社は情報公開に応じませんでした。驚かされるのは、米国立衛生研究所(NIH)は、混入の事実を2年も前に把握していたのに、見て見ぬふりをしていた、という実態です(123頁以下)。宮沢氏は論文を執筆して社名を公開するという形で抵抗し、一定の成果を上げました。「製薬会社・試薬会社、アメリカの行政機関、有名科学雑誌などが束になれば、茶番でも何でも通ってしまうのが実情」(125頁)という述懐からは、コロナ禍でも問題になったこうした巨大な「医産複合体」(Medical Industrial Complex)の恣意性と権力性が垣間見える、と私は思います。イヌ用ワクチンへのネコ関連ウイルスの混入事件を調べた結果、宮沢氏は厳密な「検査を義務づけるには、一度大きな被害が起こらないと無理」とも推測しています。ここに(命よりも)「製造コストを重視」(144頁)することの恐ろしさが表れている、と私は感じています。「ワクチンメーカーや製薬会社の影響を受けない、中立的な第三者機関」(150頁)創設は、困難かもしれませんが、本来必須でしょう。
第4章 今市事件―獣医学者としての責任
ISF副編集長の梶山天氏も連載で度々取り上げている冤罪疑惑問題である、2005年の今市事件。実はこの事件の解明にも、宮沢氏は協力していました。この事件では小学1年の女児が殺害されましたが、物証は被告人が飼っていたネコの毛と、被害者に付着していたネコの毛のミトコンドリアの種類が一致する、ということだけでした。検察側鑑定人は同じ種類のネコという解析結果を出していましたが、弁護側から獣医師としてネコの生態にも詳しい宮沢氏が鑑定を依頼されたわけです。宮沢氏はミトコンドリアの種類が一致しても、同一のネコ個体とはいえないと反論しました。裁判の過程で、検察側鑑定人が恣意的にも、一部のデータを裁判所に出していなかったことも明らかになりました。こうした宮沢氏の努力もあり、ネコの毛の証拠能力は否定されましたが、被告が母に宛てた「こんなことになってごめんなさい」といった手紙を根拠として、有罪・無期懲役とされてしまいました―殺害を認める文言は一言もなかったのですが(152-162頁)。
司法のこうした頑迷さもあって、被告にとって芳しい結果は出ませんでした。けれども、何の見返りもなく、苦労ばかり多くても、「社会の要請に応え、社会から期待されている役割を果たす意思を示してこそ、本当の研究者といえるのでは」(166頁)という姿勢は、現状のような蛸壺化(行き過ぎた専門化)の時代にこそ、学ぶべきものであると私は思います。
第5章 研究者として大切なこと
第5章では、現状の科学研究の問題点について語られます。日本の科学研究の低調ぶりが指摘されて久しいのは、周知の通りです。宮沢氏は5年等の長期の研究計画を立て、それに従って実行する「プロジェクト研究」制度に問題がある、と見ます。当初の年毎の計画書から逸脱したことをすると、予算の目的外使用、といった非難を受けます。けれども著者は自身の長年の経験から、実はほとんどの発見は偶然・予想外から、と証言します(170-176頁)。本書に出ている言葉ではありませんが、偶然の機会を生かす力としてのセレンディピティーが大事、と言ってもいいでしょう。
もう一つ宮沢氏が問題視するのは、日本の科学研究が『ネイチャー』『サイエンス』といった欧米の権威に追随し過ぎ、ということです。こうした欧米系の学術雑誌には欧米人の価値観が深く反映されており、ウナギの新しいウイルスの発見が、食材としてのウナギの価値を軽視する欧米では評価されなかった、という実例が紹介されます。(192頁以下)。新型コロナにしても、日本人は既述の通り欧米ほどの脅威にさらされていなかったのに、未知のmRNAワクチン接種等、欧米と同様の対策が実施されました。「欧米の価値観に縛られるよりも、むしろ、欧米人が考えないことを研究したほうがいい」(196頁)という提言は、原子力や遺伝子操作といった欧米由来の科学技術が行き詰まりを見せる中、日本人が目指すべき道を指し示しているようにも見えます。ISFが掲げる対米従属打破にも呼応する理系分野の考え方だと思います。宮沢氏が推しているわけではありませんが、コロナおよびワクチン後遺症対策として一部で注目されているイベルメクチンや、ナットウキナーゼも日本の産物であることも強調しておきたいです。
第6章 私はなぜウイルス研究者になったのか
終章に当たる第6章では、ベテラン世代といえる著者が、これまでの研究者人生を振り返ります。宮沢氏は関西のご出身ですが、大学・大学院時代は東京大学で学びました。意外なのは、食料問題に興味があったため第1志望とした植物学科にも、第2志望の農芸化学科にも競争で進学できなかった結果、畜産獣医学科に入ったことです(201頁)。しかし、こうした元来必ずしも積極的に選んだわけではない道が、恩師にも恵まれたこともあり、今日のウイルス学者・宮沢氏を生んだわけですから、人生何が幸いするか、わからないものです。
もちろん、博士課程飛び級に始まる彼の輝かしい業績は、年に363日を研究室で過ごしたことすらあった(214頁)、という超人的努力と、科学への愛の賜物でもあるでしょう。英国留学を経て、人手不足に悩んだ帯広畜産大学時代など、あまり恵まれない時期もあったそうです。それでも、ネコのウイルス・免疫の研究では「ニャーベル賞」に値する研究をした、と自負するのは、「にゃんこ先生」としてネット上で人気を集める著者ならではです(225頁)。
現在の京都大学に落ち着いてからは、悪しき「ウイルスに感染した」のではなく良き「ウイルスを取り込んだ」といった逆転の発想(「関西ではアホが正義」、227頁)を許す自由な環境が気に入っていたようです。にもかかわらず、冒頭で触れたような、不本意な退職を迎える次第になったのは、残念でなりません。著者の生き方は、人生には四面楚歌になっても闘わなければならない時がある、ということを教えてくれます。特殊な才能や環境に恵まれた人ならば尚更であり、それが社会への責任を果たすということなのだ、ということも。
おわりに
以上が本書の大雑把な概要です。多岐にわたる著作ですので、割愛したところも多くあります。専門研究者としての業績にはならないにもかかわらず、著者が多くの一般向け著作を公表していることは、社会貢献として大いに尊敬すべきことだと考えます。それどころか宮沢氏は、学会で訪れた仙台市で、オミクロン株人工説について自らチラシを配りながら、町の人々に「日本を守ろう」と訴えるという行動にさえ出ており、外国メディアで記事になったほどです。
Jefferey Jaxen : BREAKING: Top Japanese Virologist Warns of Manufactured Omicron Strain, in: The High Wire.
2023年9月28日。
宮沢氏ほど慎重な正統派の研究者が、そこまで異例の行動に出ざるを得ないほどの非常事態が出来しています。このことを広く自覚していただければ、本稿の目的は達成されたと思います。本書の続編ともみなしうる『ウイルス学者の絶望』(PHP研究所、2023年2月)は、コロナワクチンに対して、より厳しい視線を向けていますので、併せてお読みになり、著者の危機感を共有していただければ幸いです。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 嶋崎史崇
嶋崎史崇
独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki